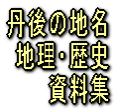 |
伊佐津川
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
伊佐津川の地誌↑お花見頃の伊佐津川河口の付近 《伊佐津川の概要》 舞鶴市の中央部。西舞鶴市街地の東部を流れる川。 旧伊佐津川がどのような流路をしていたかについては多くの研究がある。 現在の明倫小学校のあるあたり、お城の本丸あたりは、市街地の中ではなぜか少し高いが、その南側が低く、この南側(笠水神社から駅)のあたり一帯はかつては大沼地ではなかったかと思われるのであるが、ここに旧伊佐津川や旧池内川、高野川が流れ込んでいたと思われる。 高野川を西に寄せ、池内・真倉の両川を一つにして東に寄せ、城と城下の地を整備したとされる。 現在の土木重機があっても一気にできるような工事量ではなく、何代にもわたって何年にもわたって整備されていったと思われる。 一本松地蔵の伝説や九枠橋とか切山とかいった名があるが、そうした難工事の折のものと言われる。 伊佐津というのは今の西舞鶴駅やバザールタウンのあるあたりの地名だが、津というのだから、かつてはこのあたりの川口に湊があったものと思われ、海はこのあたりまで侵入していたものだろう。 伊佐津川の主な歴史記録《舞鶴史話》(昭和29年) 〈 京極高知がこの地方に残した事蹟は伊佐津川の瀬替であります。この頃伊佐津川の支流池内川は七日市公文の東を流れて淡島神社と笠水神社との中間を流れ、真倉川は十倉と京田と七日市の間を北流して笠水神社の南で高野川に合流し、その辺一たいを沼にして今の円隆寺の東方を浸しつゝ北流して舞鶴湾に注いでいたのを現今の如く高知が改修したのであります。なお高知が池内真倉両川尻を改修した際境谷を貫流せしめたから川の左岸には新たに一聚落ができこれに伊佐津の名を附したといわれています。 《舞鶴市史》 〈 綾部市の於与岐町に発して当市を北流し、字万願寺付近で池内川を合わせて北流をつづけ、字下安久において舞鶴西湾に注ぐ。全長一万六、九一○メートル。かつては上流地域の名を用いて真倉川と称し池内川とは別流していたといわれ、池内川と真倉川にはさまった地域は、この両川によって生じた氾濫原で、上河原、西河原などの小字名が残り、昔の有様を示している。この氾濫原の中ほどを京街道が通じていた。 天正七年(一五七九)、丹後国の守護一色氏および国人層を平定し、その翌年、主君織田信長から同国を与えられた細川藤孝は、一五八○年代に田辺城を築造し、また、城の北西部に町屋建てをし通城下町とした。この時、後世「伊佐津川の瀬替」といわれる大土木事業が行われた。当時、城地の南東部では伊佐津辺に大沼があり、真倉川と池内川とが北流して注いでいたが、藤孝は築城に際し両川の沼への流路を断ち、これらを一流にして新川(伊佐津川)に瀬替えし、城の東部を舞鶴湾へ導いた。こうして、城郭および城下町への浸水を防止するとともに、城西部の高野川と合わせ、伊佐津川を田辺城東西の総堀にして同城の堅固化を策したのである。なお、細川氏移封のあと入国した京極氏の時代にも、瀬替えの補強・整備工事が続行されたようである。また、瀬替えにより境谷村内は新川が流れて集落が分割されたため、川左岸部は分村して伊佐津村が誕生した。 田辺築城と城下町の建設に当たっての大土木事業の一つに、いわゆる伊佐津川の瀬替があった。これは「丹後国加佐郡旧語集」に、 城ノ南東ハ深き沼二而丹波川 池内川 伊佐津川堤を築 両川を一流にして沼江の流を留 惣堀を附られし由 伊佐津村ハ境谷村一在成し村中を割 川を堀 天神山の出先八間切川筋立る由 伊佐津村の在名其節たるよしとあるごとく、城地南東の深沼へ流入していた丹波川(真倉川)と池内川とを、沼への流路を断つために、両川を合流させて新しく開削した総堀(伊佐津川)へ瀬替した工事である。 現在の伊佐津川の上流、真倉川と池内川とはそれぞれの谷口部において、その流路が、谷間での流路方向そのままに京田・七日市地区の平坦地中央へ進むのでなく、中央より標高の高い、両地区東側山麓に方向を変へて合流している地形的不自然さや、伊佐津川下流右岸に位置する倉谷・上安久・下安久において、同川対岸(左岸)にもわずかながら各地区の地籍が存在する境界上の不可解さは、右の瀬替施工を証明している。すなわち、瀬替によって、前者は人為的に流路が変更されたということであり、後者は各地区の西端ないし南西端部分が河川敷となり、その余り地が左岸部に残った結果である。 ところで、伊佐津川瀬替年代について、「丹後旧語集」は「京極高知公伊佐津川堤をば築」と、京極氏(慶長六年丹後入国)の時代の事績としている。しかしながら、慶長五年の田辺籠城において、その絵図では、城西方の高野川とともに、東方に「二ツ橋」の架かった伊佐津川を示す河川が描かれており、また、細川氏の家臣で籠城に参加した、北村甚太郎(のち宮村出雲と改名)の著述する「丹後田辺籠城之覚書」(成立、寛永後期か)には、七月二十一日の城南方での銃撃戦況を報じるなかに、「二ツ橋といふ大河あり 其川上にいさつと申在所在(略) 上林 日置 加藤ハ川はたの土手之上より立はなしに被打候 我等兄弟ハ川の瀬ハ常々案内者なれハ川下より渡り越へ各より壱町ばかり罷出 兄弟かわりかわり能つもり打申候」(「永青文庫」)と記された部分があり、伊佐津川は土手や浅瀬もある大河として表現されている。 右のことから伊佐津川の瀬替は、その後、京極氏が大掛かりな築堤やその他の附加工事を実施したことはあったとしても、細川時代の施工と推定して間違いなく、というよりも、築城と城下町建設のためには、瀬替が不可欠の工事であったということである。すなわち、現在の十倉・京田・七日市・公文名・境谷(伊佐津川左岸部分)・伊佐津・引土地区内各地点の標高差からみて、瀬替前の真倉川と池内川の流路は、現府道布敷・公文名線を挟んで、前者は西側、後者は東側を走っていたこと、この両川が流入した城南東方向の沼地は伊佐津小字深田・菰池付近であったこと、そしてさらに、沼水の流路は、同じく西舞鶴市街地内各地点の標高差から、おおよそ現JR西舞鶴駅から真名井通り・本町方向であって、沼の増水状況によっては、高野川右岸一帯は遊水池化したこと、などが推測されるからである。 勿論、伊佐津川瀬替は、上掲「丹後国加佐郡旧語集」が記すごとく、田辺城西側の高野川に対する、東側の総堀を設ける軍事的目的があったことは言うまでもないが、同城南東の沼地から城および城下町への沼水の進行を防止するための大土木事業でもあったのである。 なお、現在、「大手川」さしてその名残りをとどめている田辺城内南西部の外郭の外堀は、籠城図にも描かれている細川時代以来の堀であるが、この堀の役割は城郭防御だけでなく、伊佐津川瀬替によってもなお真倉・池内両川旧流路の伏流水が、池内川扇状地末端の湧水とも合わさって、城・城下町、特に低地の町内へ進行するのを集水して高野川へ導いた排水路であった。ちなみに、大手川の水流をさかのぼっていくと、伊佐津小字深田・菰池周辺を通って公文名から七日市。京田に到達する。 こうして、田辺築城および城下町の建設は、現西舞鶴地域平野部の東西を北流して舞鶴湾に注ぐ二河川の一つ、伊佐津川という人造川を誕生させて、当地域に地勢上の大変貌をもたらしたのである。 《まいづる田辺 道しるべ》 〈 伊佐津川を語る時忘れてならないのは、今より凡そ四百年前、細川藤孝侯の時代より京極高知侯の頃にかけて伊佐津川瀬替の大工事が施工され、今日の舞鶴市の発展の礎となったことである。 この瀬替について加佐郡旧語集に、 「城の南東ハ深き沼ニ而丹波川(真倉川)、池内川、伊佐津川堤を築、両川を一流にして沼江の流を留、惣堀(外堀)を附られし由、伊佐津村ハ境谷村一在(村)成し、村中を割、川を堀天神山の出先八間切、川筋立る由、伊佐津村の在名其節たるよし、橋二ケ所」 又丹後旧語集によると、 「京極高知、伊佐津川堤を築」 と記している。(一六〇一から一六二二) 中世以前に市内を流れていた真倉川、池内川を細川藤孝侯は城の惣堀として、一流にすべく伊佐津川の瀬替の難工事が行われた。 この工事は今迄通説として京極高知侯が施工せし如く伝えられて来たが、最近の調査・研究によると、この瀬替工事は相当長い歳月を要した工事であったことが推測され、おそらく細川藤孝侯の時に総堀工事に着手し、京極高知侯の時に完成されたのが正しいのではないかと見直されつつあると聞く。 処で、伊佐津川瀬替後橋が初めて架設されたのはいつ頃であったか定かでないが、古い記録として旧語集の中で伊佐津川に 「橋二ケ所、前代板橋二而高欄有し先御代後破損掛直し其の時より土橋に成。土橋(二ツ橋)下の松縄手(ハリノ木縄手ならん)之通に有洪水に流れ其ノ後不掛」 これによると瀬替後早い時期に、二ケ所に橋が架設されたことが知れる。 この内の一ケ所は現ニツ橋辺りと比定され、今一つの橋は、二ツ橋より下流、JR橋りょう辺りに架設されていたものと推察される。 この橋について、享保十二年(一七二七)に書かれた丹後国田辺図の中に、現JR橋りょう辺りに橋の絵が書かれており、 「□□□橋古道」 と説明が付せられている。 これによると享保頃再度橋が架設されていたのか。説明通りこの橋は、若狭街道へ出る古い道であったことが窺われる。 二ツの橋名が初めて見えるのは、慶長五年(一六○○)の田辺籠城記の中に出てくる、 「慶長五年七月二十一日、三刀屋四兵衛外七名(氏名略ス)此者共、ニツ橋という大河あり、其の川上に伊佐津と申在所在」 というもの。今一つ、 「同年八月中頃より敵衆東西(東は大内、西は大橋辺り)に石火矢を仕懸被申候、東之方はニツ橋川端に柵を結び堤を小楯に取」。 この記録によって慶長五年頃には既に二ツ橋が有ったことが判り、橋はこれより以前から架設されていたことが推測される。 伊佐津川が瀬替されてから凡そ四百年、その間幾度となく大洪水が発生し其の都度伊佐津川は氾濫し、堤は決壊、橋は流失して城下まで大被害をもたらしている。 これ等往時の伊佐津川の大洪水と其の後の河川改修、ニツ橋の架替状況等について知り得た範囲内で年代順に記述して見た。 ○天正八年~元和八年(1580~一六二二) 細川藤孝侯より京極高知侯に至る間に伊佐津川瀬替工事が施行されたであろうと推測されている。 ニツ橋が初めて架設された年代は定かでないが瀬替後最初に板橋が架設され、次に高欄の橋に架け替えられ、その後土橋が架設されている。 二ツ橋の架設と同じ頃下流ハリノ木縄手通りに橋が架設されていたが、度々の洪水で流失し、その後は架設されなかった。この橋は若狭街道の古道であったと推測されている。 ○慶長五年七月二十一日( 一六〇〇) 田辺籠城記の中にニツ橋の橋名が初めて見える。 ○寛永二十年(一六四三)八月 大出水あり田辺城下に浸水、寺内町大橋快菱屋で地上二尺三寸(○・六六メートル)あり。 ○慶安三年(一六五○)七月二十九日 洪水田辺城内外に浸水。 ○延宝九年(一六八一) 七月九日 大洪水により伊佐津川倉谷前堤三十八間(約六十八メー トル)欠壊。 ○享保二十年(一七三五)六月二十一日 大洪水伊佐津川決壊し、城下内外に浸水。京口、職人町辺りで地上七、八尺(約二・四メートル)に及ぶ。郡中で人四百人死す。この洪水でニツ橋流失せしも、その後架設の記録見当たらず。 ○元文三年(一七三八)七月二十日 夜八ツ(午前二時)より田辺大水。 ○寛保三年(一七四三) 伊佐津と大橋に普請人足が出る。 ○延享元年(一七四四)二月 伊佐津川普請人足出る。 ○延享三年(一七四六)四月 安久川埋りしに付砂渫の為町中へ人足壱千人被仰付。 ○寛延二巳(一七四九)三月八日 安久川町中へ壱千人人足被仰付。 ○寛延三年四月二十五日~五月三日、五月六日~七日 伊佐津川新天神山をかけて上安岩測(相生橋辺り)まで十五間通り川端広被仰付人足弐千人。 ○天明七年(一七八七)六月 ニツ橋掛替。 ○寛政四年(一七九二)六月 大内橋の修繕人足総町中より五百人出る。 ○文化五年(一八○八)七月十日 ニツ橋木橋に架替、渡り初を行う。 橋長サニ十九間(五十二メートル)、橋巾二間(三・六メートル)。 左右石垣を築いて従来の亀甲畳を取り除く。 ○文化九年(一八一二)五月 伊佐津川川浚。 ○文化十年(一八一三)二月十五日 伊佐津川川渡人足千五百人被仰付。 ○天保三年(一八三二)七月四日 大内ニツ橋江営請に付仰付、伊佐津村、引土村、公文名村より人足三十五人出る。 ○天保十三年(一八四二)六月二十四日 町中より二ツ橋掛替人足弐千参百人出る。 九月十三日に竣工。 ○嘉永四年(一八五一) 九月一日 二ツ橋懸替、架設棟梁善兵衛、掛り治三郎、吉兵衛。 ○明治二十九年(一八九六)八月三十日 大暴風により市内大半浸水、明倫校で床上五尺(一・ 五メートル)に達す。 由良川筋では水量三十尺(九メートル)に達し死者三百四拾壱人出る。 ○昭和十年(一九三五)六月四日 二ツ橋架換される。 『舞鶴地方史研究』(60.3) (地図も) 〈 … 四 「丹後旧語集」、「丹後国加佐郡旧語集」が記している、田辺城の南東にあって、真倉川と池内川とが流れ込んでいたとされる大きな深沼の所在場所を、同城本丸跡(現西舞鶴公園)の南東、伊佐津付近と仮定して、両川の旧流路を、昭和四十三年舞鶴市作成の地図(二、五○○分ノー)に記載されている西舞鶴地域平坦部各地点の標高を参考に推測してみたい。 旧両川が各谷口部から平坦部中央(京田・七日市)へ流出、大沼へ向って進行したと仮定する伊佐津方向上における各地点の標高を見るとき、その多くが道路上で測定されているが、道路は田畑に比べ総体的に高く、両者の高低差は、例えば、橋梁や堤防道路などの取り合い部分を除き、旧街道である現府道布敷・公文名線で○~三○センチメートル、第二次世界大戦中に産業道路と称して新設された現国道二七号線では、かなり嵩上げが行われた模様で六○~一五○センチメートルもあって(一九八九年一二月測定)、これらの標高が西舞鶴地域平坦部の起伏を正確に示していないので、道路上の標高は可能な限り、その近辺の田畑との高低差から推算した田畑の標高に読み替えた上で、各標高を比較検討すると旧両川流路の大凡の方向を推測することが可能である。 すなわち、旧「真倉川」は図①の太線矢印で示すごとくに、山崎橋辺から池内川扇状地のために西側山麓寄りへ押しやられて、京田の集落から城南中学校方向へと北西に進み、次いで大和紡績工場前付近から北東方向に流れを変える。そして、流入先である田辺城南東の大きい深沼は、西舞鶴公園(同城本丸跡)の南々東ないし南の「伊佐津 小字深田」および「同 小字菰池」辺りに存在したと、その小字名からして推定し得よう。なお、京田の小字名「中川」は、池内川と京田川の中間を流れていた真倉川の名残りであろうか。 一方、旧「池内川」も同じく図①の太線矢印のように、九枠橋の上手から同川扇状地中央を七日市の集落方向へと北西に進み、次いで扇状地末端を北東に曲って境谷地内(境谷の伊佐津川左岸部分)に入ると再び北西方向を取り、伊佐津の「深田・菰池」へ注いだと推測できる。 そして、同川が扇状地末端で流路を北東に転じた七日市地内では、その左岸に河原が出来、また、その一部に市も立ったらしく、小字名に「上河原」、「西河原」、「市ノ上」、「市中」、「市ノ前」などがあって、かつての流路の所在とその右(北東)転を傍証してくれる。 最後に、伊佐津の小字「深田・菰池」付近と推定した田辺城南東大沼の溜水の進行方向について見ておきたい。「深田・菰池」以北の西舞鶴地域平坦部における各地点の標高は図②のとおりであるが、これらの高低差から判断して、大沼の水はJR西舞鶴駅南側構内を経て真名井通りの西側を北進したと推測され(図②の太線矢印方向)、さらに沼の増水状況によっては西舞鶴公園一帯へも浸水していったであろう。つまり、伊佐津川の瀬替え前において、高野川以東の現西舞鶴市街区域は、大沼へ流入する旧真倉川と旧池内川との遊水池的場所となっていたと考えられ、このような地勢の処を城および城下町の敷地化するためには、両川の流路を変更して同処への浸水を阻止し、用地の造成を図らなければならなかったであろう。 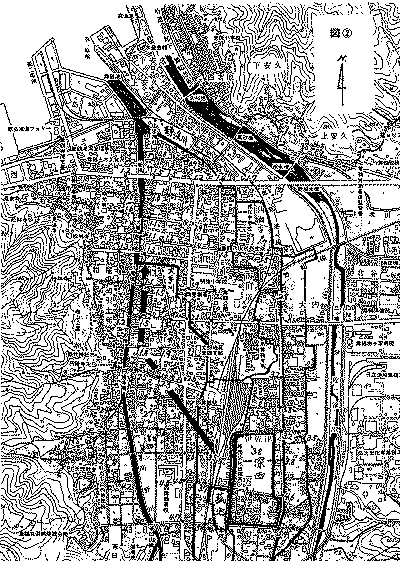 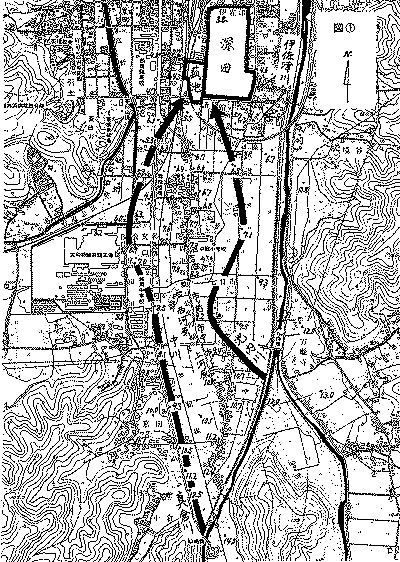 『市史編纂だより』(51.8) 〈 専門委員 野村 幸男 舞鶴西地区が地方中心都市として誕生したのは、細川幽斎がこの地に城を築いた時からである。彼がこの地に城を築く以前、丹後の中心は、竹野川の下流地域、峯山付近、更にまた中世には国府の置かれた府中であり、舞鶴西地区は湾奥に臨む一寒村であり、最初は女布の下森神社付近、ついで愛岩山、倉谷の山麓にそれぞれ数十戸の家屋が存在するに過ぎなかったと考えられる。 幽斎がこの地に築城を決定したのは、 (1)一色氏の勢力が残存する宮津、峯山の地を避けた。 (2)この地が比較的京都に近く、信長の下知に応じやすかったこと。 (3)領下である丹後一円との連絡は、海路により確保することが出来たこと。 などがあげられよう。 この平地城の築造により、この他は武士のほかに商人も多く集まり、丹後における軍事、政治、経済の中心都市に変貌したのである。かくて舞鶴西地区にも新しい城下町が出来あがり、周知の如く関ヶ原合戦の際にはこの城によって、石田方の15.000の軍勢を防いだのである。 ついで細川氏の移封後、慶長6年(1601年)京極高知かこの城に入った。彼は元和6年(1620年)宮津に新城を築くのであるが、主として舞鶴に本拠を置き、約20年間当地方の治政に意を法いだ。すなわち (1)慶長7年全領の検地を行った。 (2)伊佐津川の瀬替えを行い、池内川、真倉川の治水を行った。 (3)伊佐津川の瀬替えにより、城の南部の湿地が消滅したので、この地に濠及び土塁を築いて総堀をもった舞鶴城を完成せしめた。 これらはいずれも大事業ではあるが、特に伊佐津川の瀬替えは、まれにみる大土木工事であり、城及び城下の発展に対する京極氏の並々ならぬ意図がうかがわれ、かつまた、12万3千石という財力がこれを可能にさせたのではないだろうか。 私は鶴城の復元を試みる中て、伊佐津川の源流である池内川、真倉川の旧河道をさぐってみた。 加佐郡誌によれば、「池内川、真倉川、高野川は其の川尻現今の如きものではなくて、池内川は七日市、公文名の東を流れて、淡島神社と笠水神社との中間を少しく西に偏り、真倉川は十倉と京田と七日市との間を北に流れ、笠水神社の少し南手で、女布と高野由里との中間を東流して来た高野川と合して一面の沼となり、緩かに笠水神社の西を洗って北流、池内川と合し、更に広い沼池を作った上、今の圓隆寺裏の東方を浸して、舞鶴湾に注いでいた」とある。 私は舞鶴市役所版「3000分の一の地形図」、舞鶴市史編さん室編「字、町名、小字名一覧表」をもとに、七日市の歴史愛好家福田五郎氏、梅垣半治氏のご教示を得て、池内川、真倉川の旧河道を次のように整理した。 旧池内川は、同地域を西南流して、現在の伊佐津川を越え、西舞鶴変電所東南隅に あるオブロ池に出て北流、布敷公文名線に沿い、字名では六反田掛止りを過るのであるが、掛止り(中筋小学校東南300メートル)付近に、長さ2メートル位の橋脚に使われていた材木が発見された。これは高野方面から松尾寺に至る巡礼街道がここで池内川に出合い、ここに架けられた橋の跡であるといわれている。ここから北流して、公国寺東方50メートルの辺に出るが、掛止りからここ迄の間は地下水が非常に高く、井戸を堀れば、清水がとうとうとわき出て来る。ここから東北に流れを替え、西舞鶴高校の西南隅で高野川に合する。 旧真倉川は、現在の川より、もつと山崎神社の近くを流れ(これは古い池の跡から推察される)京街道に沿って少しく蛇行しながら北に進んでいる。この付近に、十倉、京田、七日市、三部落の境界線が通っているが、この境界線が旧河道と一致するものと考えられる。次いで現在の鉄道線路に沿って北流、字西河原(城南中学校 校門東方50メートル付近)で鉄道と交叉し、ここで線路を横切り、以後はその西側を北流、笠水神社のすぐ西側を通り、ここから西北流して、茶臼山の東側で高野川と合流していた。 旧池内川、真倉川にはさまった地域は、自然地理の上でいう氾濫原で、そこには、上河原、中河原、西河原などの字名があり、昔の有様を示しているようである。旧河道近くは地下水が高い。氾濫原の中央部には、昔は旧京街道の一部であり、現在は布敷、七日市線が通っており、比較的高燥で、古くから、ここを中心に交易が行われ、七日市と名づけられたのである。市に関係のある中市、前市の字名もある。 高野川は昔から、ほぼ現在の場所を流れていたが、茶臼山以北においては、池内川、真倉川よりにすなわち今の河道よりやや東側を流れていたようである。 以上が、舞鶴西地区を流れていた池内川、真倉川、高野川の昔の姿の概略である。 さて、細川氏に続いて、丹後の地を領した京極高知は、舞鶴城以南の洪水防止と、沼池の農耕化を企て、池内川、真倉川の治水に着手したのであるが、瀬替えの事業は先ず真倉川をその谷口で北々東に流し、秋葉山の山脚を切断して、河道を直線に直した。次いで池内川を南に寄せ、旧河道より約100メートル南で真倉川と合流させ、この合流点をほぼ中央にして約300メートルにわたり、巨大な石で枠を作って、二つの河の激流をせきとめたのである。この工事は伊佐津川瀬替えの中て最も困難な作業であった。このことは舞鶴市史「各説編」第五節「一本松地蔵」の伝説によっても推察することが出来よう。 更に新しい河川の北流を阻止する山脚は二カ所において切り崩さオL、境谷付近では山麓が約100メートル程も削り取られている。 かくして京極高知の時に、舞鶴の湾奥、平野の南部を荒れ回っていた両河川は、平野、東端に押しやられ、洪水はやわらげられ、湿地は美田や良好な住宅地伊佐津として変貌する端緒が築きあげられたのである。 《中筋のむかしと今》 〈 伊佐津の林田修一氏(平成十四年十二月、一○二歳でなくなられた)が明治二十九年八月三十一日におきた伊佐津川大水害の状況を記録されているので紹介する。 明治二十九年八月三十一日(陰暦七月二十二日)即ち俗に云う二百十日の前日朝より大暴風雨となり、午後五時頃より更に一層甚だしく激甚を極む。 直ちに父は(当時二十六歳)堤防の決壊を心配し、荒れ狂う大暴風雨の中を伊佐津川の氾濫の状況を検ずるに、既に堤防の上を濁流が溢れ、今にも堤防流失の危険。言語にする由もなし。よって見返る間もなく大声で危険の急報を告げつつ家にたどりつき、取るものも取らず一刻も早く家内一同を引き連れ、堤防の下流へ取り敢えず避難すると共に、近所の人々にも急を告げ最早是非一刻の猶予も許されず。 然るところ家財に執着のありたる人々は為に人命を失いたる者多し。堤防の決壊の箇所は境谷出口の橋のところより北へ約一丁余の間が忽ち崩れ流失、為に夜間の事の対策を施す術もなく山なす濁流に悉く後片づけもなく、その周辺の家屋は云うに及ばず屋敷までも大河と化したもの、この周辺に居住する人々は一瞬にして、先祖伝来の住居・田畑を悉く失い、その戸数は二十二戸死者は実に二十三名を算し、その惨状は言語に絶するところとなり。以上のごとき惨状を残して伊佐津を川とかへ分断する。 為に民家は南北に分断川氾濫の為交通もままならず言葉さえ交わす事不能につき、大きな障子に大害して用を交わす状態なり。 漸く災害当日より五~六日を経過して水かさも減りたるを以て字内男子は総動員して死者の捜索に従事するなり。 [「伊佐津川大災害状況略記」より]).  『舞鶴の民話1』 〈 伊佐津川の瀬替えが行なわれたのは藩主京極高知の頃である。 池内川は七日市、公文名の東を流れ伊佐津の粟島神社と公文名の笠水神社のほほ中間を流れる、真倉川は十倉、京田と七日市の間を北へ流れて笠水神社の南側で高野川と合している。 その辺一帯は葦のはえた沼になっていた。一度大雨が降ると川ははんらんして一面の泥海と化し、家屋を流し、又床上浸水し田辺城まで泥水が広がった。 そこで田辺藩では真倉川、池内川の流れを万願寺から伊佐津川の東側り、吉原から舞鶴湾に注ぐよう伊佐津川の瀬替えの計画を立てた。 そのころ博学で名の通っていた庄屋山口長左エ門に作業奉行を命じて築堤工事をするように命じた。長左エ門は難工事であるので引受けることを渋ったが、多くの人の難きを目の前に見ているので引受けることにした。 長左エ門には年ごろの美しい娘があった。娘は毎日昼前になると工事場で動く父親に弁当や茶菓を運んだ。工事には地元をはじめ、遠く丹後、若狭方面からかりだされた人夫が百数十人も動いていた。 奉行の美しい痕のことは、たちまち彼らの評判となった。娘かやってくる頃になると工事かはかどらなかった。その上襲ってきた洪水に、ようやく築きかけた堤防も根こそぎ流れるなど工事はおくれるばかりであった。娘にいいよるものもあったが、見むきもしなかった。 藩の役人は工事場にやってくる娘のたたりではないか、昔から橋の難工事には人柱をうずめることがあるという。長左エ門は夜おそくまで、工事の見廻り、用材の調べなどしていた。 藩の役人の命で、三日月のうすぐらい夜、父親が工事現場でケガをした報せで、家へ。藩よりかごがさしむけられ、娘はそれに乗って、工事場の河原に連れてきた。かごをおりるや、一たちで娘を斬り殺し川に流した。 その後皆んなは仕事に精をだした。長左エ門は悲しみにたえて仕事を続けた。まもなく川の瀬替は完成した。しかし誰いうとなく、新しい川に悲しそうな姿の娘の亡霊が夜になると河原でみかける。 村人たちは川の瀬替に犠牲になった娘の霊をなぐさめるため、堤防のねきに石地蔵をまつり、一本の松を植えて、ねんごろにまつった。 いつしかこの松が大きくなり、遠くから眺められるようになった。伊佐津川は大きな流れとなり、村の人の水害を防いだ。 今もこの地蔵さんは川の流れを見つめている。 関連項目平成30年7月の豪雨直後の様子 |
資料編の索引
「一本松地蔵」という紙芝居の一部。 舞鶴平安レディースというグループが作られたそうで、私の同級生・岡本敏雄氏が持ってきて下さった。勝手に使わせてもらってもいいのかどうかわからないが、私の机の上に置いておくだけではもったいないので、紹介ということで、絵の一部だけてすが… 伝説のストーリーは、このページの下にあります。 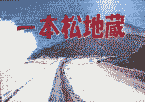 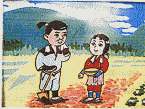 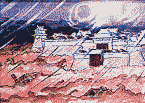 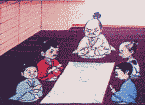     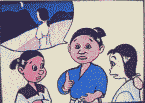 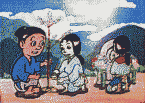 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2008-2018 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||