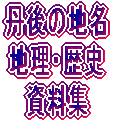 |
菅(すげ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅の概要《菅の概要》 鱒留川の下流域で国道312号から分かれて峰山市街地へ愛宕山丘陵を越す網野街道の菅峠の両側である。 菅は、戦国期に見える地名で、「丹後御檀家帳」に「一 すけの里 御屋かた様御内藤田右京亮殿」と見える。里村紹巴の「天橋立紀行」永禄12年7月4日条に「四日には菅とは城まで入道殿御下山」とある。 寛永の初め頃、愛宕社石段下を切り通して、参勤交代の本街道を菅峠の旧道から峯山町の出町へ結び、峯山の表玄関が菅峠口に移る。これにより菅峠への松縄手(菅村地内)が峯山の町続き町として市街地化していき、明治初年、この地域が光明寺町として峯山町に組み入れられていた。 菅村は、江戸期〜明治22年の村名。はじめ宮津藩領、元和8年からは峰山藩領。明治4年峰山県、豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年吉原村の大字となる。 菅は、明治22年〜現在の大字名。はじめ吉原村、昭和30年からは峰山町の大字。平成16年から京丹後市の大字。 《菅の人口・世帯数》 1237・446 《主な社寺など》 小字沖波(おきなみ)の弥生前〜中期の遺跡、鱒留川を挟んだ対岸、途中ヶ丘遺跡との関係が考えられる。 鱒留川の左岸に面した舌状の微高台地上にある弥生前期でも古い形式の土器を中心とした遺跡。昭和22年、地元民が弥生前期の壷形土器(ほぼ完形)を発見した。その後、瓦土の採土や耕作によって多くの弥生式土器および土器片が発見されている。同45年には建設工事に伴い畿内第一様式に比定される弥生式土器多数の出土があった。とくに頸部に箆削り突帯や沈線を施す壷が注目された。未調査。突帯文土器か、縄文晩期の土器にはそうしたものがあって、弥生直前のもの、水田稲作寸前時代。  網野街道と鱒留川の交差地点の南、川のたもとに久津方神社(履掛明神)がある、旅人の交通安全の神として草履を供える風習があった。履掛明神の旧社地は現在地の南方、小字古川付近で「大門先」の地名が残る。またその西の大河原には峯山藩の仕置場があったという。 『峰山郷土志』 〈 宝暦三年(『峯山明細記』) 三尺社履掛明神、上屋 一間半四面、境内 長三十間幅十四間程、祭礼 九月十五日で、峯山田町の神子内膳(今城の妻)を雇って神事を勤めたという。支配は常泉寺で、社料米として四斗成りの田が字宮がきにあった。 明治二年『峯山旧記』によると、昔は川裾の由、疫病除の神であったといっている。 久津方の旧社地は、現在地の南方字古川の付近で、「大門先(だいもさき)」の地名も残っているし、神輿をのせたという石もあった。古老の話によると、久次村の真奈井神社の例祭と同日の祭りで、真奈井の神與の御旅所であったという。真奈井がもし、苗代境の神所段にあったとしても、ここまでは約四キロ近い距離となる。 また、「履掛」とは、日本三ヵ所の一つで、旅人が足を痛めないよう、この神前の流れで足を洗い、鞋をはきかえ、古わらじを社前に供えて旅の安全を祈ったうえで、再び旅立って行ったともいう。 社の西を大河原といい、峯山藩のお仕置場があったのはここで、西園寺鎮撫総督を出迎えたのは、長岡村境の古川であったというから、この社のわずか東方に当たる。また、参覲交代の藩主の送迎もこの付近であったろう。 明治十二年『届書』によると「社 三尺四面、上屋 八尺四面、境内 五畝、境外 一反二畝十歩……」とある。 明治十七年『府・神社明細帳』には「社殿 一間半四面、境内 八四五坪…」とだけあり、上屋は記載されていない。 久津方神社は、今も一般に「くつかけさん」と呼ばれている。震災の被害はなかった。 現在、社は本殿五尺四面、上屋十尺四面、拝殿十三尺に十六尺、境内社地八百四十五坪(実測八百九十五坪)である。… 探すがどこにあるのかわからない、泉の金刀比羅神社の脇から遊歩道があって愛宕山の頂上まで行ける、山の名からしてこの頂上に神社はあるのではなかろうか、と考え行ってはみたが、神社はないし途中の案内板にも何もない↓地図には書かれているが、実際はもうないのではなかろうか。  『峰山郷土志』 〈 カラナシは、韓穴師(カラアナシ)の転訛ではなかろうか、韓鍛冶(カラカヌチ)かも、物部系の倭鍛冶と異なっていて彼らは天目一箇神を祀るといわれ、片目の魚伝説が隣の新治にある。ウッソーと思われるかも知れないが、スガとかスゲは天日槍の子孫の名にもよく出てきて、日槍族由縁の地名で、川砂鉄と関係があろうといわれる。もっとも有名な場所は鳥取県日野町上菅(かみすげ)の都合山たたら跡だろうか、この遺跡は江戸期のもので古代のものではないが、下層には古い時代までさかのぼれるものがまだ眠っているいるかも知れない、地名から考えればたぶんさかのぼるのではなかろうか。  常泉寺は愛宕山丘陵南の山腹にある。寛永9年創建、もと曹洞宗竜献寺末、元禄8年転宗。寺宝に白隠筆の山号の額がある。 江戸時代、当寺の鎮守社に履掛明神(現・久津方神社)があった。 『峰山郷土志』 〈 宝暦三年(『峯山明細記』) 松雲山、常泉寺、境内屋敷 長二十二間幅十四間、寺 四間に八間、座敷 一間半に二間、薬師堂 一間半四面、撞鐘なし、山畑 六間に十五間程、山林間数知りがたく……。 『村誌』 正保申年 開基 罷庵和尚、境内 東西二十四間南北二十九間、面積 二一二坪 正保元年(一六四四)は寛永九年を去る十二年後で、後光明天皇の時代となる。確実な資料があればともかく、『峯山旧記』の寛永九年ではあるまいか。寺宝として、白隠筆の「山号の額」がある。 八重椿−「境内に数百年を経たりといふ八重椿の老木あり。周囲八尺、稀有のものとす」と「中郡一斑峰山案内』にある。この名木は、その後白蟻に害され、震災後切りとられた。 昭和二年三月七日、震災被害、全、半壊である。 … 《交通》 《産業》 菅の主な歴史記録「丹後国御檀家帳」〈 (朱書) 「さま」 御屋かた様御内 一すけの里 藤田右京亮殿 かうおや かうおや そうはた 志やう村弥兵衛尉殿 かちや太郎左衛門殿 五郎右衛門殿 中西又次郎殿 彦 八 ど の 孫 左 衛 門 殿 助 左 衛 門 殿 (朱書) 「二」 中の弥五郎殿 『丹哥府志』 〈 【履掛大明神】(祭九月十五日) 【松雲山常泉寺】(禅宗) 【付録】(愛宕大権現) 『峰山郷土志』 〈 下菅の前面の耕地は、その名にふさわしい沼沢地帯で、浮橋(あゆび板を敷いて)をかけて通行したというから、干拓して現在の良田に仕立てるまでには、長年月の努力と非凡な科学的才能が必要であったろう。峯山藩の手で行なわれた耕地整理も、その主なものの一例である。 しかし下菅を開眼したのは、何といっても初代高通で、峯山支封されてまもない寛永元年(一六二四)の頃、菅の愛宕石段下を切り通して、参覲交代の本街道を、菅峠(旧道)から出町へ結んだことである。これによって、いままで長岡村金田から上菅を経て、新治村はずれに出るか、あるいは、三軒屋に迂回して、新治の村中を通って、安村田地を横切り(新治道)、峯山の出町の馬場先に入る峯山本街道、すなわち峯山の表玄関が、菅峠口に移動したわけで、交通上からは全く便利になったわけである。この本街道にそった履掛明神の西の河原に、峯山藩のお仕置場(刑場)があった。 菅の小字一覧菅 上り達 アザ谷 井原 因幡岩 一町田 打明 大川原 沖波 刈止 上稲木 上中稲木 上泉長 上川原 上東 北山 岸ノ下 消山分 胡麻谷 小長谷 五反田 泊屋窪 山王谷 星 細見 三石分 下川原 新助屋敷 下深田 四反田 下稲木 十名 松谷 下東 摺鉢 ?(クサカンムリに毛)内 菅ケ谷 菅村 菅峠 竹返り 立通 大門崎 丹波井根 寺ノ谷 照畠ケ 堂畷 堂ノ上 峠ノ谷 中東 畷下 畷田 中深田 莱切原 長町 長谷 長谷口 中坪 泉長 中嶋 入田 墓ノ下 墓ノ段 深田 藤ノ木 樋ノ口 百町 堀川 松原 丸山ノ下 前田 宮垣 宮分 ヨト川原 早稲田 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『峰山郷土志』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2013 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||