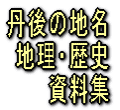 |
三宅郷(みやけごう)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三宅郷の概要《三宅郷の概要》加佐郡内の郷。『丹後風土記残欠』に記載があり、『和名類聚抄』には記載がない。 残欠は、高橋郷と大内郷の間に、「三宅郷 今依前用」と記している。 高橋郷と大内郷は白鳥山で接しており、南側は何鹿郡で、これら両郷の北側にあったのではないかと思われる。 また残欠は神名帳に「河辺坐三宅社」が見えて、河辺のあたりではなかろうかと推測される。 本文では「河辺坐三宅社 以下三行虫食」とある。『和名類聚抄』には記載がないので早く失われて、志楽郷に併合されたのではなかろうか。ほかには何も記録が残らない。 三宅とは、一般に「古代大和朝廷の直轄領」とされ大和勢力が直接開発したものや、地方豪族が贖罪のために貢進した屯倉がある。管理は貢進した豪族がそのまま行い、地方豪族に貢納物を課する課税地区としての性格の濃いものであったと見られているという。 安閑紀の「丹波国蘇斯岐屯倉」がこの郷に当たるものかどうかは不明。 何が課税の対象となったかは、ここなら塩や金属でなかったかと思われる。 加佐郡式内社に三宅神社があるのではあるが、この社の比定が定まっていない。一説には河辺八幡神社とし、また一説には北吸の三宅神社とする。丹哥府志は喜多の宮崎神社を比定する。また西方寺の猪蔵神社境内にも三宅神社がある。「室尾山観音寺神名帳」は、従二位三宅明神と正三位三宅明神を記している。加佐郡内には少なくとも三宅社は二社あったと思われるのである。 三宅郷の主な歴史記録《丹後風土記残欠》〈 《加佐郡誌》 〈 三宅郷は、今の東大浦村河辺川流域の称であらう、と思はれる。何となれば、丹後風土記に「河辺に座せる三宅神社云々」の文字が見えているから、斯う憶測しても差支へなかろうといふのである。 関連項目 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||