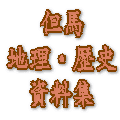 |
畑(はた)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畑の概要《畑の概要》 兵庫県豊岡市但東町の一番下流に位置する。 中世のはた村は、文明10年(1478)八月吉日付播磨国広峯神社(姫路市)の但馬国檀那村付注文に「一はたの二郎衛門」、同14年八月一〇日付の丹後・但馬両国檀那村付注文に「但馬国いつしの郡内河内之はた村一ゑん」とみえる。次に天文(1532-55)から永禄(1558一70)頃の山名祐豊の奉行人の一人であった徳丸盛長から夜久主計助に宛てた書状写に「畑村」の村名がみえる。正保(1644-四八)頃成立の国絵図に村名がみえる。 畑村は、江戸期~明泊22年の村。出石郡のうち。山名氏政滅亡後天正13年まで青木勘兵衛、同年から前野長康が領した。文禄4年からは出石藩領。明治22年合橋村の大字となる。 畑は、明治22年~現在の大字名。はじめ合橋村、昭和31年からは但東町の大字。平成17(2005)年より豊岡市の大字となる。 《畑の人口・世帯数》 81・33 《畑の主な社寺など》  国道482号に「赤坂」という全但バスのバス停がある。このあたりにあった古墳。土が赤い。 今はモンゴル館に移されている。   赤坂古墳群第一号墳の復元
『但東町誌』赤坂古墳は豊岡市但東町畑字大野山にあった横穴式石室で、付近には二、三号墳があり、三基からなる群集墳です。発掘調査の結果、南北十二メートル、東西十メートルの楕円形をした小型の円墳であることがわかりました。 石室は遺体を納めた部分と出入り用の通路からできており、古墳時代末期の七世紀半ばから後半にかけて築かれました。全長七・九メートル、奥壁幅一・九メートル、奥壁高さ一・九二メートルです。 石室内部からは、金属製品として鉄刀、鉄鏃などの武具、馬具、装飾品として金の耳環が出土し、当地方における古墳の終末を考える上で重要な資料を提示しました。 発掘調査 平成十五年十月~十二月 移設復元 平成十六年一月~三月 赤坂古墳群一、二、三号 赤坂道路下にある一号古墳で、平田猛羅古墳と同時代(六〇〇)頃と思われる。二、三号は大曲り突出部の尾根山頂にある。  神木の銀杏の大木がある。出石藩主仙石氏の崇敬が厚く、同氏は毎年米五升を献じ、参勤交代の途上に参拝したという。 兵庫県神社庁のHPに、 「三柱神社 主祭神 倉稲魂神 配祀神 保食神 稚皇産霊神 祭記事 八朔祭りは8月末に地区の人々総出で祭儀を行ない、終了後直会をする。 由緒 創立年月不詳 江戸時代三宝荒神と仰ぎ又、八大荒神ともいい藩主仙石氏の崇敬社にして毎年9月28日の例祭には献米5升あり又、参勤交替の途上藩主自ら参拝せり。 明治6年(1873)10月村社に列せらる」とある。 古くは村奥に上鍛冶(福田家)・下鍛冶(不明)の両家があり、掘削工具などを作っていたといわれる。三柱神社は鍜冶の神様のようである。 ふつう三柱神社は、和銅四年二月初午、秦伊呂具が伊奈利山に三峰に三柱の神を祀ったことが始まり、あるいはカマドの中の三つの石を祀ったものとか、稲荷社と同じような農業の豊穣の神様。三宝荒神は日本仏教の仏様。  『但東町誌』 東覺寺 (畑)
眞言宗 高野派 (正智院末) 本尊 聖観音 由緒 長享年中創建 光尊開基 本堂 方六間三尺 庫裡 桁行六間三尺 梁行五間 鐘楼堂 方九尺七寸 境内地 三百三十四坪 官有地第四種 擅徒 四百十三人 境内佛堂 一宇 庚申堂 本尊 青面金剛 由緒 不詳 建物 方一間 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 畑の主な歴史記録畑の伝説『但東町の民話と伝説』うちわ耳の法印さん(畑)
むかし、畑の東覚寺に、それはそれは大きな耳をした法印さんがおられました。 耳が大きい人は賢いと言いますが、村の者が人の悪口でも言おうものなら、「おかねさんや、きのうは嫁の悪口を言うとったのう。嫁いびりは、ようないで。」といった具合で、愚知をこぼしてもたちまち、法印さんの耳にはちゃんと聞こえておりました。 そんなことで、村の者は法印さんのことを「千里眼のうちわ耳の法印さん。」と呼んで尊敬しておりました。また、村の者は人の悪口を言わないように心掛けておりました。 その法印さんについて、こんなエピソードが伝わっています。 真言宗の僧侶は、頭髪を剃らなければなりませんが、法印さんの髪そりを引受けていたのが寺男の源太という者で、このあたりでは剃刀を使えば右に出る者がないという、めっぽう腕のたつ男でした。 その日も法印さんの髪そりが始まりました。 「だいぶ伸びておるので、骨が折れるかも知れんのう。」 「はい はい、心得ております。大丈夫でございますよ、法印さん。」 本堂の前の縁先にござを敷いて、あぐらをかいて髪を剃ってもらっている法印さん。着物の袖を、たすきできりりとしぼり、剃刀を使っていく源太、庭先では、つゆ雨があじさいをぬらし始めておりました。ジョリジョリ、剃り落としていく後に、それこそ青々した坊主頭が広がっていきます。法印さんは、すべてを源太にまかせ切って、目をとし、瞑想に入っておられるようでした。 ところが、ちょうど六分くらい剃った頃でしょうか、どうしたことか、源太の心に--法印さん、村の者から賢い人だ、偉いお方だ。と、言われていなさるが、この剃刀でグイッと喉をかき切ったら、法印さんは死んでしまいなるがなあ。--源太の一存で殺すことも出来る、そんな思いが浮かんで来ました。 「いけない、いけないことだ。」 源太は思わず手を休め、その思いを呑み込むように大きく息をすると、また、ジョリジョリと髪を剃っていきました。 でも、なぜか思うまいとしても、打ち消そうとしても、またしても「この剃刀で……。」という思いが、頭を持ち上げてくるのです。--と、源太は、一瞬手元が狂ったように思いました。その瞬間、あの大きな法印さんのうちわ耳が、ピクッと動いて、 「おい、源太。いま、お前さん何を考えていなすった。」 ハツとたじろぐ源太に、強い語気の法印さんの言葉が跳ね返りました。 「いや、別に何も考えておりませぬが。」 「嘘を申すな、ちゃんとわかる。その剃刀でこのわしを殺すことも出来る--そう思ったであろう。」 かくそうとすればする程、見抜いていく法印さんの鋭い透視。 これには、源太も弱ってしまいました。 「えろう、すまんことでした。どうしたわけか、きょうは、思いもかけない悪い心が出て来まして、はずかしゅうて、はずかしゅうて。」 「いやいや、はずかしいことはない。はずかしいのは嘘をつくことじゃ、自分の心をごまかすことじゃ。」 そう言うと、法印さんは、人間の在り方を求める曼陀羅の世界について、こんこんと話をされました。 その話が終る頃、法印さんの髪そりも、やっと終りました。 その後、源太はますます修業に励んだので、「寺男の源太さんは、人間もよう出来とる。腕もよし、ほんに剃刀使いの名人だ。」と、言われるようになりました。 それにしても、源太の心の迷いが、どうして法印さんにわかったのでしょう。 貸し牛の涙(畑)
むかし、畑の村中を通って、丹波の「貸し牛」が行ききしていました。 「貸し牛」というのは「鞍下牛」のことで、毎年、六方田んぼの田植え準備の為、見るからにたくましいこってい牛(牡牛)が、丹波から貸し出されておりました。 但東町を通るのは、丹波から西谷-河本-畑-水石-寺坂-鯵山峠-出石といった道順で、和屋の谷からも出石へ入りました。 いずれにしても、川原町の「藤六」という茶店で、牛の受け渡しをするのが習わしになっていました。 仕事が終って牛が丹波へ帰る日を「大あげ」といって、出石の町は大そう賑わいました。 ある年の「大あげ」のこと。例年のように水石村の道を「貸し牛」が帰ってきました。 六月とはいえ、梅雨も一休みして、はるぜみの声が一しきり聞こえる、照りつけのきびしい日でありました。 「牛が帰ってくるぞ--。」 牛の姿を見た水石村の人々が連れを誘って道ばたに集まってきました。 牛の背中には暑さを凌ぐ為の、ござや米のあき俵が掛けられ、お礼の酒や、町で買った雑貨などがいっぱい積まれ、追子達は一様に風呂敷づつみを腰に巻いたり、けさ掛けにして大事そうに身につけていました。包みの中は、「貸し牛」の労銀でしょうか。-と、どうしたのでしょう。一頭だけ、列から遅れている牛がおりました。見る限りでは黒ぴかりする、ガッチリした牛で、どこが悪いとも思えません。 ところが、その牛が村人の前にきた時、 「あれえ、あの牛、泣いとる。涙を出しとる。」 と、言う者がありました。小さな声でしたが、なぜか村人は、電気にでもうたれたように、一斉に牛の顔を見ました。 でも、牛の目は少しうるんでいるようですが泣いているようには見えませんでした。牛がうつ向いて歩いているので、よく見えなかったのかも知れません。 一方、その追子はというと、お酒に酔っているのか、足がふらつき、牛にもたれかかるように歩いています。牛の労銀は入るし、つい気が緩んで、出石の茶店でお酒を飲み過ぎたのかも知れません。畑村の峠にかかる頃は、その追子は連れからずいぶんと離れておりました。 それから、二~三時間もたった頃でしょうか。 「大変だ!誰かきて下され!追子が牛にやられとるで!」 大声で叫びながら、転がるように一人の男が駆け下りてきました。 異変が伝わった畑村では、上を下への大騒動です。惣代さんを先頭に村の者が峠へ行くと、男が言ったように、腹わたがはみ出て血まみれになった追子が横だわって死んでいました。 そばの木の枝には、切り裂かれた風呂敷ずつみがひっかかり、あたりに金が散らばっていて、余りの様子に村の者は思わず目をそむけました。死んでいたのは、遅れて峠へ向かったあの追子でした。 追子を殺した牛は、近くの山に入って草を食べていました。 「追子が峠で一服しとってな。お酒を飲んでいるうちに、木にくくりつけた綱がほどけて、暑さのせえもあって、牛が暴れたらしい。」 「追子をしとったのは牛の親方で、それが酒好きで、牛の働いた労銀は、大方飲み代に使ってしまうし、牛が恨んで親方をつき殺した。」 思わくや尾ひれがついて、この話はたちまち村中の大評判になりました。-それにしても、何と恐ろしい話ではないでしょうか。 その後、世の中の移り変わりと共に、峠の道を通る人もなくなって、「貸し牛」の話も、遠いむかしの話となりました。 床尾の天狗(畑)
むかしのこと。-畑村の人々が、その日もつつましく野良仕事に励んでいました。と、にわかに「サーツ、サーツ。」と、聞き慣れない、まことに奇妙な音がして、スーツと消えて行きました。 「あれ! 何の音だ!」 「風の音?………」 「木の葉が揺れとらん。」 「そうだ、うちわだ!うちわであおぐ、あの音だ!」 「ほんと、うちわだ。」 「う-ん、ごっついうちわだぞ。」 子供達が空に向かって叫んでいます。村の大人達も驚いて、仕事の手を休めて空を見ました。しかし、その日は別に変わった話も伝わらず暮れて行きました。 ところがその晩、平助の子供の四つになる平太が帰ってこないということで、大さわぎとなりました。 近所の者も手分けして、そこらじゅうくまなく探しましたが見つからず、夕闇がせまってくるし、途方にくれていると、畑村の千里眼といわれている、ばあ様がやって来て、何やらブツブツ念じながら申しました。 「平太がいないらしいが、どうやら天狗のようだ。あの時、妙な音がしたであろう。確かにあれは床尾の天狗だ。平太は山の方にさらわれている、明日探しなさい。」 これを聞いた近所の者は、まっ青になってふるえあがりました。-恐ろしや、恐ろしや。このご時世に天狗様が現われて、しかも、子供をさらっていくなんて-でも、怖がってばかりいる場合ではありません。平太が殺されたりしたら大変です。近所の者は夜明けを待って、山の方を探す相談をして別れていきました。 あくる朝になりました。鳴り物入りだと天狗も逃げるだろう。平太にも聞こえるだろう。と、三柱神社の大太鼓に寺の鉦。家々からは鍋や釜、たらいまで持ち出して、「平太をかえせ、平太をかえせ。」と、村中総出で床屋の谷々に入っていきました。 そして、三日目になって、やっと平太を見つけることが出来ました。平太の家の者も、村の者もホッとしました。 不思議なことに平太の見つかった場所は、今まで何回も探した場所で、村の者は狐にでもつままれたように首をかしげる程でした。それに、平太は山の中を歩き回った形跡もなく、着物も乱れていませんし、かすり傷一つありません。恐ろしいことをされていると想像して怖がっていた村人達は、きれいな草の上にちょこりんと立っている平太を見て変な気持ちになりました。 それから後も同じような出来事が、床尾山麓の村々に起こりましたが、天狗にさらわれた子供が帰って来て、「天狗にご馳走をしてもらった。おはぎをよばれた。お菓子をもらった。天狗の鼻が高かった。天狗と一緒に空を翔んだ。」などと、得意になって話すので、村の大人達は、天狗は思ったよりやさしい者に違いないと思うようになりました。居心地がよかったのか、天狗の所から一週間も帰ってこない子供もいました。 “天狗にさらわれると賢うなる” そんな話も出るようになって、大人の中には、真剣、天狗にさらわれて見たいと思って、山中の岩の上に座って、じっと待っていたけど、腹は減るし、天狗はこんし、どうしょうもなかった。-とか。どうも、ずる賢い大人達は、天狗も相手にしなかったようです。 その後、天狗にさらわれた話も、姿を見たという話も聞きませんが、天狗は謎を秘めたまま、山の奥へ引越していったのではないでしょうか。 畑村の不浄の池(畑)
〈1.池が濁る〉 先祖の鍛冶太兵衛さんの頃は、大勢の鍛冶職人がいまして、なかなかの繁盛ぶりでしたが、後代なるにつれ農業のやり方も変わってきて、むかしのような農具の作り方では間に合わなくなって、鎚打つひびきもだんだんと絶え、その主人の頃は、広い屋敷もひっそりしておりました。 お家柄ですので女中さんを狂ませておりましたが、主人は口ぐせのようにその女中さんに言い聞かせておりました。 「あの池を女子がまたいだらあかんで、女子がまたいだら、えらいことになるでなあ。」 少し呑気な主人でしたが、代々伝わる「不浄の池」の言い伝えだけは、しっかりと受け継いでおりました。 春のことでした。その年も、京の都からこちらにはないという人きな佗助椿が、赤い花をいっぱいつけて、屋敷の池の面に美しい姿を映しておりました。 そんなある日、女中さんが陽気に誘われて庭の方へ出てきました。しばらく池を見つめていましたが、やがて、 「え-い!どうなるか知りませんが、二度ためしてやりまひょう。旦那さんは、言い伝えだ、何んだかんだと言いんさるけど……。」 と言うと、よせばよいのに、つい、ピョンピョンと池を渡ってしまいました。 さあてどうなるか、女中さんは胸に手をあて、じっと池の面を見ておりました。と、どうでしょう。ジワジワと池の水が濁ってくるではありませんか。佗助椿の花影がすっかり消えて、ついに濁り水が渦を巻き出しました。 さすがおてんばの女中さんも、これには大びっくり、 「大変だ!大変ですがな、旦那さ-ん。」 と、すっとん狂な声を張りあげ、家の中に駆け込みました。 あわてて主人が池の方へ行って見ると、ほんとうに池が濁って渦をまいているので、「う-ん。やっぱり、言い伝えの通りじゃ。おそろしや、おそろしや。」 と言って、真つ青になりました。 〈2.桑の葉が落ちる〉 「かんじゃ」の身内に、それはそれは賢いおかみさんがありました。鍛冶屋の先祖が天日槍に刀を献上した話や、出石のお殿様が畑村にこられた話など、昔の言い伝えをよく覚えていて、誰かれなしに話しかける、語り部のようなおかみさんでした。「不浄の池」のこともよく聞かされていたので、池の悪口は絶対に言うまいと常日頃心掛けておりました。 すでに、本家の鍛冶屋の建物も朽ち果て、屋敷あとは桑畑に変わっておりました。--その日、おかみさんはケタツにあがって桑の葉をこいておりました。 はじめのうちは、小唄を唄いながら気楽にやっておりましたが、つい忙しいやら、えらいやらで、言ってはならない「不浄の池」の悪口を言ってしまいました。 「もう、こんな池ども何の値打ちもありゃあせんわ。人はめずらしげえ言いなはるか、掃除するだっけだ。あんな、きったなげな池ども……。」 言ったあと、すぐ気がついたわかみさん、「しまった。」と言うと、口に手をあててふたをしました。が、後の祭り、何と、おかみさんの愚知にこたえるように、桑の葉がヒラヒラ、ヒラヒラと落ち出しました。 さあ大変なことになりました。桑の葉は、まるで雨が降るように、パラパラ、バラバラ、だんだんと大きな音をたでながら、あっという間に一枚残らず落ちてしまいました。 気を失ったようにうずくまっていたおかみさんが、我に返って見ると、片手でケタツにしがみつき、一方の手は口をしっかり押さえて、ガタガタ、ガタガタふるえておりました。 このショックで、しっかり者のおかみさんも、まる三日寝込んでしまいました。 後になって落ち着いてから、「こやあもんだ、もう言わん。池の悪口は絶対に言わん。」と、身内の者に話したそうです。 〈3.あやしげな老人に出合った話〉 「かんじゃ」の身内になる男が、京の町を歩いておりますと、何やらあやしげな老人が男の前でで立ち止まりました。 男もしかたなく立ち止まると、老人は、さらに近づいてきて、男の顔をしげしげとのぞき込みますので、男は気しょくが悪くなって 「何んですい。どうかしましたか。」 と尋ねると、老人は、 「あんたもなあ、あれだ。先祖や、いわれのある所を大切になさらんと、あきまへんなあ。あんたとこには池がありますなあ。あんまり掃除をなさらんと、あんたも、うだつがあがらんようになりますぞ。」 と言いました。 男は恐ろしいことを言う老人が何故、畑村のことを知っているのか不審に思ったので、 「怖いこと言われますが、あんた、畑いうところを知っておられますんか。池がある言われますが……。」 と、問いただしますと、 「いやな、畑いう所は知りまへんが、あんたの顔を見たら、ようわかります。それに神木が揺らいどりますえ。」 と、老人の答えが返ってきました。 畑村にきたこともない、まして、「不浄の池」も「神木」も見たことちない見ず知らずの老人に、こんなことを聞かされた男は、気味が悪くなって、そそくさとその場を去りました。 男は、気になって仕方かおりません。早速、田舎へ帰ると畑村を訪れて、「不浄の池」の掃除をすると地酒を供えて、丁寧におはらいをして清めました。 今でも「不浄の池」の掃除をするのは「かんじゃ」の身内の男がするものと決められています。水のない空池となっておりますが、「誤テ不浄ノ事アル時ハ忽ニシテ濁テ其験顕然也」という古文書の言葉は、生き続け受け継がれているわけです。 「枯らさんように……。」と、おかみさんから言い聞かされた「佗助椿」は、もうなくなりましたが、椿が毎年赤い花を咲かせて、「かんじゃ」一族のしあわせを見守っているといいます。 畑の小字一覧『兵庫県小字名集Ⅱ但馬編』【畑】(はた) 堂ノ上(どうのかみ)、トクショウ(とくしょう)、堂ノ下(どうのしも)、下垣(しもがき)、井ノ上(いのうえ)、岡ノ下(おかのした)、岡ノ畑(おかのはた)、段ノ岡(だんのおか)、水口(みずぐち)、畑ヶ中(はたけなか)、系谷(けいだに)、向垣(むかいがき)、鍛冶屋(かじや)、中ノ前(なかのまえ)、尾花(おばな)、的場(まとば)、西縄手(にしなわて)、尾崎(おざき)、東(ひがし)、伯母ケ坂(おばがさか)、大目義(おおめぎ)、岡田(おかだ)、寺外(てらがい)、家の奥(いえのおく)、下ノ谷(しものたに)、七阪(しちさか)、屋敷(やしき)、崩レ(くずれ)、山ノ口(やまのくち)、岩花(いわはな)、小峠(ことうげ)、光明寺口(こうみょうじぐち)、山ノ口(やまのくち)、下坪(したつぼ)、畑田(はただ)、長外(おさがい)、畑ヶ坪(はたがつぼ)、ハイアガリ(はいあがり)、曲り(まがり)、山根(やまね)、畦高(あぜだか)、ミヤノ(みやの)、大門(だいもん)、番中(ばんなか)、三反田(さんだんだ)、岸ケ下(きしがした)、石砂(いさご)、立長(たておさ)、祭田(まつりでん)、石ヶ坪(いしがつぼ)、柳ヶ坪(やなぎがつぼ)、野尻向(のじりむかい)、赤坂(あかさか)、井ノ口(いのくち)、大野(おおの)、下谷(しものたに)、茶ケ谷(ちゃがたに)、鍛冶屋谷(かじやだに)、細坂(ほそざか)、床尾(とこのお)、段ノ奥(だんのおく)、段ノ中(だんのなか)、深山(ふかやま)、大野山(おおのやま) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||