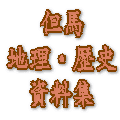 |
東中(ひがしなか)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東中の概要《東中の概要》 明治初年に東中村と改称したもので、それ以前は中村といった。正保(1644-48)頃成立の国絵図に村名がみえる。 円山川支流出石川最上流域に位置する。県道山東大江線(63号線)沿いに人家が散在。 東中村は、明治初年~明治22年の村。出石郡のうち。明治初年中村が改称して成立。同22年高橋村の大字となる。 東中は、明治22年~現在の大字名。はじめ高橋村、昭和31年からは但東町の大字。平成17(2005)年より豊岡市の大字となる。 《東中の人口・世帯数》 54・21 《東中の主な社寺など》  新宮川に沿って奥ヘ入っていくと、どんつきに鎮座する。(大きな車で入ると180度転回が難しい)。前の谷川が禁漁の川なのであろう。魚の姿はない。 その案内板に↑ 禁漁区の由来
村上天皇の康保年間(九六四-九六八)勅使大宮吉光殿、薬王寺牛頭天王社へ下向の時、紀州熊野明神を当村新宮谷へ勧請せらる。文禄四年(一五九五」の頃、出石藩主小出大和守吉政公の時、小坂東中両村氏子となる。往古より川魚を捕らぬ習わしあり、その起源、新宮谷川の神池より鯉の流失にはじまるとも云う。 以来村民挙げて神魚とし乙保護に努め江戸時代の天明五年(一七八五)の頃、出石藩主仙石越前守久道公、村民の美挙をたたえ、殺生禁止の公札を下す。 往時は渓流に手をつけるとモツ、ヤマガワコイ、時にはナマズ、ウナギまで群れをつくって集まり、手をつつき飯器を洗えばおどつてその中に入り、水も汲めぬ有様で訪れるものは、その奇観に驚いて、その理由を聞かぬものはなかつたという。 久畑尋常高等小学校編、昭和六年発行『但馬読本』に拠る 平成十五年一月一日東中ふるさと委員会 当地は初め薬王寺村の牛頭天王社(現大生部兵主神社)が氏神であったが、文禄四年同社の氏子から離れ、小坂村とともに当新宮神社を創立したと伝えている。 かつて新宮神社の氏子は神池に神魚を放ち守っていたが、大水害で神池が流失し神魚も流れた。そこで新宮川一帯は禁漁区と申し合せたが、大正11年内務省指定となり現在に至るという。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 東中の主な歴史記録東中の伝説『但東町の民話と伝説』魚をとらぬふしぎな村(東中)
唐草模様の大きなよろしき包みを背負った一人の商人が、小坂峠を越して久畑の方に向かっていました。大事な商談で約束の時間にはどうしても間に合わせたかったので、道中休みもとらずに一心に歩いていたのです。峠を下りて何とか間に合うことがわかり、少し歩をゆるめ汗をぬぐいました。初夏の山なみは緑色にむせ返り、陽はようしゃなく照りつけます。山ぞいの道をぐるっとまわると、小さな集落がみえてきました。東中です。右手を流れている川はその集落にぐっと近づき、左側の山側から流れてきた川と一つになってのどかなせせらぎの音さえ聞こえてきました。川面をのぞいていた旅人は、川底の小石がひとつひとつみえるほどに澄んでいるその渓流に、疲れて熱くほてった足をつけてみたくなりました。 土手を下り、わらじ毎水の中へ足をつけ、「ああ、ええ気持ちじゃ、ごくらくじや」と水中で足を動かしました。ゆらゆらと水面がゆれ、「中の小石までゆれとるわ」と水中をのぞきこんで旅人は、わが目を疑いました。川はいつのまにか真紅となり、ゆれていたのは小石ではなく無数の魚だつたのです。モツ、山河、鯉などの雄鰭は夏になると紅く変色するということを旅人はあとで知りましたが、もっと驚いたことにその魚たちは、水を動かせば動かすほど群をなして集まってくるのです。手をつければ手をつつき、足を動かせば足に寄り集い、その愛らしさといったらありません。いつのまにか、その村の子ども達が旅人のまわりに集まっていました。 「かわいいだろう」 「ようけ おるだろ」 と口々にいいながら、そっと手を水の中にさし入れています。旅人は 「ええな、なんぼでも魚かおるし、逃げれへんし、川魚がようけ食えるな。」というと、年かさの子どもがきっとなって旅人に言いました。 「この魚はな、神様のお使いじゃ、この魚を食ったらバチがあたるでだれもとったらあかんのじゃ」 「そうじゃ」「そうじゃ」と幼い子たちまで口をそろえます。 旅人は、そっと足を上げ立ちにがりました。だんだん少なくなっていく魚を追いかけまわしている自分の村の子どもや大人たちの様子を思い浮かべながら、 「そうか、そうか、ほら魚がはねた、よろこんどるんだな」 と、子どもの頭をなでました。こうまで川魚が人になれた不思議さが旅人には今わかり、今日の商談はうまくいくぞと勇んで歩き出しました。 東中の小字一覧『兵庫県小字名集Ⅱ但馬編』【東中】(ひがしなか) 下中(しもなか)、清水垣(しみずがき)、新宮谷(しんぐうだに)、大津へ(おおつへ)、後ヶ谷(うしろがだに)、滝ノ下(たきのした)、早谷(わさだに)、竹ノ後(たけのご)、坂又(さかまた)、天ヶ谷(あまがだに)、岡ノ後(おかのご)、山根(やまね)、小早谷(こわさだに)、大早谷(おおわさだに) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||