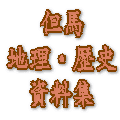 |
河本(こうもと)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河本の概要《河本の概要》 出合市場から但東夜久野線(県道56号)で南下し、日殿村の南、河本川の流域に位置する。文明10年(1478)八月吉日付播磨国広峯神社(姫路市)の但馬国檀那村付注文に「一かう本」「一かう本之こしろ衛門」とみえる。正保(1644-48)頃成立の国絵図に村名がみえる。 河本村は、江戸期~明治22年の村。出石郡のうち。山名氏政滅亡後天正13年まで青木勘兵衛、同年から前野長康が領した。文禄4年からは出石藩領。明治22年合橋村の大字となる。 河本は、明治22年~現在の大字名。はじめ合橋村,昭和31年からは但東町の大字。平成17(2005)年より豊岡市の大字となる。 《河本の人口・世帯数》 74・29 《河本の主な社寺など》  県道56・但東夜久野線沿いに鎮座。式内社(九条家本では毛谷神社に作る)。 埴安神・稲倉魂命ほかを祀る。社伝によるとかつては河本川の上流、天谷村地内に鎮座していたが、洪水で現社地に流されたという。宇賀大明神社ともみえ、当村および西谷村・天谷村が氏子で、本沢寺(現高野山真言宗)が別当寺を勤めている。文化14年(1817)に本殿を修復した(社蔵棟札)。 『但東町誌』 延長三年(925)四月に綴られた但馬世継記の記事を正しいものとすれば、…
手谷神社 祭神 大彦命 村社 手谷神社
鎮座地 合橋村河本字宮谷 〔出石郡神社系譜傳〕 出石郡手谷村 〔但馬神社重寶記〕 佐々木庄河本村 〔但馬國神社燈明記〕 高橋郷高橋在 〔特選神名牒〕 河本村字岡田(出石郡合橋村大字河本) 〔神祗志料〕 今天谷河本村にあり 祭神 埴安神 ○調書ニハ宇賀御魂神大彦命ヲモ記ス 由緒 (イ)總説 文武天皇四年の創立と傳へ元天谷村に垂跡せられしかば天谷神社と稱すべきを中古洪水の爲め流されて其止まりし處に宮殿を造營するに至り手谷と改稱すと云ふ又神名は稻倉魂命の頭字を取りて宇賀大明神と稱し亦同神を豊岡毘賣命と云ふを以て岡宮或は岡大明神とも稱せり延喜式の制小社に列し文化十四年本殿を修復し明治六年十月村社に列せらる (ロ)社名祭神 〔出石郡神社系譜傳〕手谷神社 祭神 大彦命 〔但馬國神社燈明記〕手谷神社 祭紳 大彦命 異説 〔但馬神社重寶記〕手谷大明神 祭神 高橋臣之祖大彦命 (ハ)創立 〔國司文書〕手谷者丘名也 祀高橋臣之祖大彦命奉禰之手谷神社 〔但馬故事記〕人皇四十二代文武天皇庚子四年秋十月以考元天皇之皇子大彦命之裔高橋臣義成爲出石郡司高橋臣義成祀大彦命於手谷丘稱手谷神社 〔但馬祕鍵抄〕高橋郷 高橋臣義成食封之地故名高橋高橋本郷 高橋臣住于此地天眞宗豊祖父天皇御宇庚子四年十月出石郡大領正八位下高橋臣義成祀其祀大彦命於手谷丘謂之手谷神社 〔但馬世継記〕高橋郷 高橋所謂處高橋臣此地ニ住故負名也手谷ノ里 手谷者丘名也高橋臣在此祀其祖大彦命於手谷丘謂之手谷神社 (ニ)沿革 〔延喜式 巻十 神名式下 但馬國同一百卅一座 大十八座 小一百十三座 出石郡廿三座 大九座 小十四座 手谷神社 〔特選神名牒〕 手谷神社 祭神 埴安神 〔神祗志村〕手谷神社 宇賀明神といふ 神社明細帳 神社道志流倍 〔本殿修復棟札 ○文化十四年〕 奉修復棟上宇賀大明神社 本願別當 本澤寺 文化十四年丁丑十一月十二日 現主 寂舜 大工渡銀札四百五十匁小挽 百三十二 但シ寺養之 棟上八拾匁ニ而寺かまひO外略 〔神饌幣帛料供進神社指定年月〕大正四年十月二十六日 境内 二百九十七坪 ○調書ニハ二百九十三坪ト記ス 官有地 營造物 本殿 柿葺流造六坪 本殿覆 六坪 拜殿 柿葺入母屋造三坪 境内神社 松尾神社(大己貴尊)稻荷神社(保食神) 祭日 例祭 十月十二日 寶物及貴重品 一本殿修復棟札文化十四年 一枚 一鏡 二面 氏子 百二十戸 『校補但馬考』 録曰、天多爾と訓へし、○考曰、雀岐庄天谷に坐す、池臣曰、河本村宇賀明神と云ふ是なり、○按するに、本社は天谷河本西谷三村の産土神なり、盖天谷はてだににて本村なり、河本は神許(カウモト)にて社の所在地なり、○考証曰、祭神埴安神 録曰祭神詳ならす、 按するに、本国養父郡に手谷神社あり、又按するに、但馬神社の推究に就ては、一箇の注意せさろへからさることあり、そは本社の如き、てだに神社と稱するも、天谷村にあらすして河本村にあり、日出神社の如き、ひで神社と稱するも、日殿村にあらすして南尾村にあり、其他氣多郡賣布御殿の如き、禰布村にあらすして石立村にあり、美含郡阿古谷神社の如き、阿金谷村にあらすして轟村にあるの類なり、盖天谷河本の如き、もとー村にして天谷村と稱せしに、人口の繁殖するに從ひ所謂出村をなし、本村は依然天谷村と稱するに拘らす、出村は神社所在の地なるを以て新に神許(カウモト)の名を冠し、轉して河本となりたるものならん、其他の神名村名も、盖之に類するものならん、國中往々神名村名の符合せさるものあるか故に、特に記して参考に供す、  本沢寺の裏山に出石郡西国八十八ケ所の第88番札所があり、境内に八十八ケ所が配置される。 『但東町誌』 本澤寺 (河本)
眞言宗 高野派 (正智院末) 本 尊 阿彌陀佛 由 緒 不詳 堂 宇 桁行十間三尺 梁行五間三尺 経 蔵 方一間三尺 鐘楼堂 方一間三尺 境内地 二百廿三坪 官有地第四種 檀 徒 二百六人 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 河本の主な歴史記録河本の伝説『但東町の民話と伝説』河本城悲話(河本)
むかし、但馬の各地に山城や砦が築かれた時代に、河本にも河本城が築かれていました。 河本の字松尾から左手奥に一きわ高くそびえる山の頂がその場所で、眼下に丹波へ通じる街道があり、但馬丹波へ出入りする要衡として守りを固めていました。 いまも残っている本丸、姫がなる、的場、城堂、小屋がなる--などの地名から、当時かなり整った城であったことがわかります。城主は河本氏ということですが、「お殿様と呼んでいたとも伝えています。 その城にまつわる、こんな話が残っています。 時代はずっと下って、城跡だけが残り、村人達の間からお城の話も遠のいた頃でした。 村の男が城跡の下の谷に入って炭焼きをしておりました。炭がまに木をつめ、口だきをしているうちに、男はうとうとと眠ってしまいました。………と、どこからともなく、「水をくれ! 水を……。」と、うめき声が聞こえてきます。男が声のする方を見ると、額や顔はいうに及ばず、からだ中に刀きずを受け、血まみれとなって倒れている武士達が、谷のあちこちから腕をさしのべ水を求めてうごめいているではありませんか。何十本、いや何百本もありましょうか。粗末な装束を身にまとった者、鎧姿の者。時々「ウオッ」と鬨の声も聞こえてきました。 あまりの様子に驚いていると、男はハツと目が覚めました。男はびっしょり汗をかいていました。夢を見ていたのです。--この話を伝え聞いた村人達は、河本城の合戦で死んだ武士の怨霊が、いまだに谷にさまよっているのだと恐れ、その谷を悪戦と呼ぶようになりました。 当時、国の中央では政治の実権をめぐり、争いが起きて、それが地方へも波及し、地方の豪族、郷士達が入り乱れて争うという有様で、河本城もその渦中へ巻き込まれていきました。天谷側の水源を念入りに調べるやら、城堂から、武器や兵糧をかっぎあげるやらで戦いに備えて万全の準備をしておりました。 ところが、いざ戦が始まると相手の軍勢が意外に大軍で、つぎからつぎへと攻め登るものですから、河本勢もだんだんと追いつめられ苦戦をしいられました。特に炭焼きの男が夢を見た谷では熾烈な攻防が繰り返され、血気盛んな河本勢の若い武士達が、城を渡してなるものかと、討って出たりしましたので、敵味方に死傷者続出、忽にして、阿鼻叫喚の修羅場となりました。 しかし、剛の者を擁した河本勢も数には勝てず、ついに城を後にすることになりました。 残った河本勢はそれこそ満身創痍、満足に歩ける者も数人しがなく、こぼれ刃のやいばを杖に、地を這い天を仰ぎ、無念の涙をよりしぼりつつ、間道を通って天谷側の寺の奥へと落ちのびて行きました。 ところが、そこにも追手が迫っていて、城主の奥方が敵の射た矢にあたって、痛恨の死を逐げました。残った武士達も、生きて敵のやい刃にかかるより、潔く自分で命を断とうといって、腹を切って自決しました。 戦乱の時代とはいえ、この様子を見た村の人々は、常ならぬうつし世のかなしみをいたく感じたことでありましょう。 なくなった奥方の墓だ、といわれている碑が、西谷にありますが、別のものだと言う人もあり定かではありません。河本城の戸をゆずり受けたという「お城戸」と呼ぶ、屋号の家も残っています。 いずれにしても河本城の悲話は、これからも語り継がれていきましょうが、もう城跡もすっかり生い茂り、悪戦の谷からも何の便りも聞かれなくなりました。山頂を渡る風が、四季折々の歌を、昔を偲ぶかのように奏でています。 河本の小字一覧『兵庫県小字名集Ⅱ但馬編』【河本】(こうもと) 砂田(すなだ)、石ヶ坪(いしがつぼ)、畑ヶ中(はたけなか)、ロクロ(ろくろ)、蛇食(じゃぐい)、千本垣(せんぼんがき)、月谷(つきたに)、峠ノ下(とうげのした)、峠(とうげ)、長坂(ながさか)、後カイチ(うしろかいち)、奥畑(おくはた)、岩ヶ下(いわがした)、渕ヶ谷(ふちがたに)、岩吹(いわぶき)、小広田(こひろた)、大広田(おおひろた)、奥ノ田(おくのた)、松尾(まつお)、中川原(なかがわら)、貝ノ原(かいのはら)、岡田(おかだ)、ヲサ田(おさだ)、宮ノ谷(みやのたに)、宮谷口(みやだにぐち)、出合河原(であいかわら)、井上(いがみ)、上砂田(かみすなだ)、冥加谷(みょうがだに)、森谷(もりたに) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||