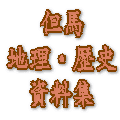 |
小坂(こざこ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小坂の概要《小坂の概要》 出石川の最上流域、ここを源流としている。当地から南西方に向かう山道は小坂峠(直見峠)を越えて丹波国天田郡直見村(福知山市夜久野町)に通じている。主要県道山東大江線が通り小坂峠で夜久野町に通ずる。今でもなかなかの難所。正保(1644-48)頃成立の国絵図に村名がみえる。大光寺の地名があり天台宗寺院であったが焼失し、今は大門口・経小屋・寺屋敷の地名が残る。 小坂村は、江戸期~明治22年の村。但馬国出石郡のうち。山名氏政滅亡後天正13年まで青木勘兵衛、同年から前野長康が領した。文禄4年からは出石藩領。鎮守は隣村の中村にある新宮神社。寺院は浄土真宗乗専寺。明治22年高橋村の大字となる。 小坂は、明治22年~現在の大字名。はじめ高橋村、昭和31年からは但東町の大字。平成17(2005)年より豊岡市の大字となる。 《小坂の人口・世帯数》 41・18 《小坂の主な社寺など》  つまらぬところで、写してもらうほどのものでもありませんが、とかおっしゃっていたが、いやいやなかなかのお寺で、 片野荘小坂には覚如門弟乗専が一院をつくり、のちに乗専寺と呼ばれたが、但馬地方では早い時期にできた浄土真宗の寺院であろうといわれ、十一面観音立像は町文化財となっている。 真宗出雲路派本山 『但東町誌』 小坂の乗専寺
浄土真宗は鎌倉の初期親鸞上人が拓いた仏教で、一向宗とも呼ばれ農山村に広まった。有名な一向一揆はこの宗教の影響が大きかった。(笠原一雄著「一向一揆」)福井市の興宗寺は但馬行如を開基としており、その開幕には但馬人が深いかかわりをもっていたことが知られる。現存の但馬真宗教団は本願寺派、興正寺派、出雲寺派の三派が主となっており、豊岡の光妙寺は本則寺を、生野の金蔵寺、出石の福成寺は興正寺を、但東町の乗専寺(小坂)は出雲路寺を本寺と仰いでいる。 但東町小坂の乗専寺は小坂峠を経て丹波との交渉の深い土地に建てられた。 開祖乗専は丹波の長田野の六人部の生れといわれ、覚如に傾倒して丹波の寺を本願寺に寄進した。覚如の筆頭の門弟で、大和の国で死んだと伝えられているが、故郷は長田野に近いところにあり、大和に行く以前、小坂の五兵衛の許に乗専の姉が嫁いでいたので、姉の許で晩年を過すべく一寺を建立し乗専寺と名づけたといわれている。しかし乗専は大和にと旅立ち観応二年(一三五一)大和で死んだ。しかし今もその寺はこの但東町の小さい山村の集落に残っているのである。(石川松蔵著「但馬史」三巻)町内の古い寺の一つである。 竜峰山 乘専寺 (小坂)
正應二巳丑年七月(六八五年前)乘専と申す僧、天台宗の僧にて親鸞聖人の弟子となり、法名乘専を許されたが、聖人の歿後、故郷へ歸り(現在福知山市長田野の生れと伝ふ)草菴を建立す。その後火災により焼失し、貞享三年九月本堂再建す。棟札に小出備前守代官林浅右衛門等の記名あり。 本尊 阿弥陀佛立像 (延寶七暦末) 眞宗 本願寺派 境内地 二九七坪 檀家 百一戸 平安時代の作と伝える木造十一面観音像(像高170センチ)を祀る。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 小坂の主な歴史記録小坂の伝説『但東町の民話と伝説』大光寺の平家残党(小坂)
むかし、小坂村大光谷にあった大門の前に、二の腕から斬り落された武者や、目を矢で射抜かれれた雑兵など約二百余の将兵が、あえぎあえぎ辿りつきました。 門番は、もう腰も抜かさんばかりの驚きようでしたが、首領らしい武者が、静かに馬を降りて歩みより、 「大光寺の慈尊大僧正さまに、安芸の矢野五郎、十郎兄弟が、一の谷から落ちて来たと伝えてくれい。 いやなに、相国清盛さま御在世の頃、京の東寺にお住いになっていた平家縁りの大僧正さまじゃ、吾等をよく御存知、案ずることはない。疾く行け」 と言いましたので、門番も不安はぬぐえないまでも、大僧正さまのお叱りを受けることは、よもあるまいと思い、雪の道を寺まで数十町、息せききって駈け登りました。 「おお、安芸の五郎、十郎が来たと言うのか、早よう人数を集めて出迎えよ、深手の者は里で治療し、歩ける者は寺まで案内せよ」 大僧正さまは、ことの外お喜びのようすで、こんな安芸の一党を宿坊にお引き取りになりましたので、寺内は急に大世帯になりましたが、皆の顔色はさえず、屋島に逃れた平家の安否ばかり気づかっていました。 ところが、首領の五郎、十郎が瀬戸内に放っていた小者の報告によると、平家はまたも屋島で敗れ、壇の浦に向かったと伝えましたし、文冶元年四月にもなると、安徳帝は二位の尼に抱かれて西海に入水され、平家一門も、後を追って悉く自害し果てたという悲報も伝えられるようになりました。 それに、平家の残党狩りは予想外にきびしく、九州、四国でも、近畿でも、どんな山奥までも源氏の追手がかけられているとも報告されましたので、寺内の人々の気持ちは日に日に暗く沈んでゆくばかりでした。 そうこうするうちにも、関東武者五百余が、丹波路から大光寺に向けて近づいているという情報も入るようになりましたので、五郎、十郎は寺に難のかかるのを恐れ、丹波境の峠まで打って出て、斬り死にしたいとも申し出ましたが、「拙僧とて平家縁りの者じゃ、追手があれば寺と共に果てるまでよ。」と、大僧正さまはすでに覚悟なさっているという口振りでした。 大光寺攻めの戦いは、大門を焼いて才谷から登る軍勢三百と、久畑から佐々木谷に出て、裏から寺を攻める軍勢二百による戦闘で開始されました。寄せ手は一斉に弓を射かけて敵のひるむのを待ち、その隙にじりじりと山を登るという戦法をとりましたが、源氏の中にも元気な者がいて、才谷から経小屋に登って火を放ちましたので、火はやがて、寺屋敷にも飛び火して、さしもの大寺も、つぎっぎに紅蓮の炎に包まれてしまいました。 「五郎、十郎、もはや逃れる先は祖父谷のみぞ、天谷から唐川越えで丹後に逃れよ」 大僧正さまはそう言い残すと、今にも焼け崩れんとする金堂の中に、身を投じておしまいになりました。 「ああ、大僧正さま吾等も」 と後を追わんとする五郎、十郎を押し留めたのは、家の子郎党数名の者たちで、「後を追うては大僧正さまの御心に背きます。早く祖父谷へ」と促しますので、大光寺に心を引かれつつも天谷に逃れ、円城寺峠から峰山を経て丹後半島の木子、駒倉の山中に逃げこみました。 しかし、源氏の追手はついにこの山中にまでも及ぶことになり、矢野五郎、十郎の率いる安芸の一党も、とうとうこの地で降伏することになりました。 そして、武器は取り上げられましたものの、幸わい生命だけは助けられましたので帰農し、永くこの山の中に住むことになったと伝えられます。今日では、この平家村に住む人はたいへん少なくなりましたが、それでも五郎、十郎を先祖の首領として仰ぎ、唯一の遺品として、赤旗一流を大切に保存しております。 小坂の小字一覧『兵庫県小字名集Ⅱ但馬編』【小坂】(こざか) 石才(いっさい)、向谷(むかいだに)、大光寺(だいこうじ)、道ノ下(みちのした)、熊地(くまぢ)、上ノ山(うえのやま)、田中(たなか)、堂ノ上(どうのうえ)、直見峠(のうみとうげ)、茗荷谷(みょうがだに)、寿子峠(すごとうげ)、森ノ上(もりのうえ)、杉谷(すぎたに)、金谷(かなだに)、中地薮(なかぢやぶ)、渡り瀬(わたりせ)、岡田(おかだ)、大蔵谷(おおくらだに)、小蔵谷(こくらだに)、向岡田(むかいおかだ)、棒田(ぼうだ)、嶋川原(しまがわら)、追田(おえだ)、早谷(わさだに)、芹原(せりはら)、蔵谷(くらだに) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||