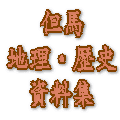 |
栗尾(くりお)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗尾の概要《栗尾の概要》 平田村の上流側に位置し、集落は出石川の右岸、 中世は、雀岐庄東方(領家方)の一村であった。弘安8年(1285)の但馬国太田文作成当時、当村の領家職は坊門俊輔の子俊親がもっていたとみられるが、俊親は元亨2年(1322)に出家しており、跡はその子親輔が継いだ。ところが親輔は建武3年(延元元年、1336)後醍醐天皇に従って大和国吉野に参向したので、親輔の領家職は没収された。貞和2年(1346)11月27日、光厳上皇の院宣によって、栗尾村領家職は勘解由小路兼綱に与えられた。親輔が「参南山之間」建武以来領家職が没収されたこと、貞和年中に兼綱が拝領したことは、のち応安4年(1371)3月6日付の兼綱の一子仲光宛譲状土代に記している。同土代には、次いで当村は「予母儀方相伝由緒之地也」と記している。兼綱(予)の母は坊門俊輔の女で、俊輔には輔能・俊親・清忠3人の男子があった。兼綱譲状土代の一文と、太田文の雀岐庄東方の注記「領家尾張三位入道」(坊門俊輔か)、「子息三人」を併せ考え、以上の当村領家職の相伝が推定される。坊門親輔の大和国吉野参向についてはとくに史料はないが、親輔の叔父清忠は後醍醐天皇の側近として著名で、天皇とともに吉野に入っている。親輔も同行したのであろうという。 貞和の頃当村の公文は当麻三郎左衛門尉と志津田彦三郎入道で、2人は但馬国大高山凶徒(南朝方)与同輩で、所領は没収され、その跡は貞和4年12月27日付の足利尊氏下文(案)によって他の所職とともに門真左衛門尉寂意に与えられ、同5年5月28日付で栗尾村下地などが寂意代快尊に打渡された。このとき長年の御家人でかつは「本所領下職人」であった明覚は、志津田入道を扶持して違乱に及んだようである。そこで領家から提訴され、明覚は観応元年(1350)6月日付の陳状(案)を残しており、このなかにも訴状中の「栗尾・平田公文職名田畠」の文書が引用されている。しかし明覚の陳状は前欠で、訴訟の内容は明確さを欠き、提訴した領家がだれなのかもはっきりしない。前掲兼綱の譲状土代は、当村の項でさらに続けて「仍雖為少所、可執心」と記している。当村は勘解由小路家(のち広橋家)領としては長く維持されることはなかったようで、大永6年(1526)6月日の広橋家知行目録には、当村は消えている。寛正3年(1462)7月22日、将軍足利義政は「大納言佐房」雑掌の申請によって、当村と楽前北庄(日高町)の臨時課役・宇護役・段銭人夫以下諸公事を免除して守護不入の地とし、管領・守護によって施行・遵行されているが、文書は後世の写で、大納言佐房は「公卿補任」には所見しない。誤写があるようという。 栗尾村は、江戸期~明治22年の村。出石郡のうち。山名氏政滅亡後天正13年まで青木勘兵衛、同年から前野長康が領した。文禄4年からは出石藩領。明治22年高橋村の大字となる。 栗尾は、明治22年~現在の大字名。はじめ高橋村、昭和31年からは但東町の大字。 平成17(2005)年より豊岡市の大字となる。 《栗尾の人口・世帯数》 124・47 《栗尾の主な社寺など》 栗尾や平田は古墳が多い(みな10mほどの円墳、横穴式。6~7世紀か)。  ヒダチ神社とも呼ばれるそう。一般にヒダルとかシダラとか呼ばれる神と思われる。 当社は城崎郡日和山(豊岡市)から勧請したものといわれ、出石藩主小出英安が太刀一口を献上、小出氏ののちに出石藩主となった仙石氏や豊岡藩主京極氏は参勤交代の途上必ず参拝したと伝え、祭神は多遲麻比多訶神という。 「 もともとはシャンとした神であったが、シャンとして民衆の神であったが故に権力への阿諛追従を拒み、いくらたべても満足することがなく、最も劣れる餓鬼とか(権力側から)いわれ、おとしめられてきた神であった。フシダラ権力側が何と言おうとも、地元民からみれば、立派な態度を貫いたシダラ民衆神である。  集落の一番奥で、道路が獣除けのため封鎖されていて、近づけない。奥に鳥居が見えるのがそうかと思われる。大正14年(1925)清滝大神宮社(東妙見宮)の境内から甕2・鏡1・銅製経筒1・古銭(宋銭)12と土器片が出土したという。  『但東町誌』 石室山 松禪寺 (栗尾)
天文年間(四四〇年前) 来翁祖諄和尚の開基にして、天寧寺派にして寛文三年山頂より現在地に移転す。その後一一世陽岩恵春和尚のとき、嘉永五年、妙心寺派となり、現在一五世、英洲瑞峯和尚となる。 本尊 地蔵菩薩 鐘の銘に曰く 高楼新立厳整禪叢 前住妙心現住天寧萬休叟誌 敲苗昏月鳴明焼風煩悩 守寺宗標首座 夢破菩提心通萬靈佛 平安城住大橡藤原氏次作 慶衆若圓融満耳功徳在 寛文三龍集癸卯小春朔日 不聞中洪音不竭壽同 当所 理左衛門 原左衛門 弌空 松禅寺は天文年間(1532-55)禅慶の開山といい、本尊は木彫一木造、像高120センチの地蔵菩薩。 同寺に伝わる木造薬師如来坐像は高さ121センチ、藤原期のもので県指定文化財。ほかに同時期のものと思われる多聞天・増長天・阿修羅の各像があるそう。 境内の薬師堂↓  境内の案内板↓ 薬師さんが祀られているということは、金属があったのでなかろうか。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 栗尾の主な歴史記録栗尾の伝説『但東町の民話と伝説』いつのころからか、栗尾の日和山に霊験あらたかな日足神社と呼ばれるお宮さんがあって、村人たちの厚い信仰を受けていました。郷路岳のふもと、こんもりとしたその森はとこまでも静かで美しく、ひんやりとした冷気は身もひきしまる思いでした。登り口には細い丸太が敷かれ、老人でも子どもでもたやすく登れるようにしてありましたし、境内も草が抜かれ、村の人たちがどんなにこの神様をありがたく思い、手厚くお祭りしていたかがよくわかるのでした。 そのころ、このあたりの道は京に通じる道として重要な役目を果たしていましたが、ある時出石のお殿様が京に上られることになり、行列が栗尾にさしかかりました。幾人ものおつきのあとに、たてがみもつややかな立派な馬がいて、馬上には一目で大名とわかるお殿様が手綱をにぎっておられました。村人たちはひれふしながらこの行列の様子をチラリチラリとみておりました。ところが行列が日和山の下の道までくると、お殿様の馬が突然暴れだしてお殿様は振り落とされてしまいました。ピタリと止まったお殿様の馬は、そこから先は一歩も動こうとしません。 「ええい、進まぬか!」 とお殿様は手綱を力まかせにひっぱりました。こともあろうに村人たちの面前でこのような醜態を演じ、お殿様は権威を挽回しようと必死でした。しかし、どんなに進む合図をしても、どんなにいっしょうけんめいひっぱっても馬は動きません。いっも骨身惜しまず世話をして一番なれているはずの馬子がひっぱっても馬はびくともせず、そのたびにお殿様は振り落とされました。 「何とかならんのか。この馬を手なづける者はおらんのか。」 とお殿様は大声でわめかれます。わけのわからない突発の事態に、祈祷師を頼んでおがんでもらうことになりました。 祈祷師は 「これは日和山のお宮さんのたたりです。このたたりを解くには、手厚くお祭りしなければなりません。」 と言いました。出石のお殿様は短気でした。それに、こんなことは今までになかったのでよけい頭にきていました。 「何がたたりじや。城主にたてつく者はたとえ神でも容赦はせぬ。即刻、山の上から下ろしてしまえ!」 と、大変なご立腹でした。もうこうなればお殿様にはさからえません。お宮さんはとうとう、下の道に下されてしまいました。 ところが、それからというもの、出石のお殿様の周辺はゴタゴタともめ事が起きはじめ、とうとう世にいう仙石騒動にまで広がりました。 再び祈祷を頼まれた祈祷師は、 「やはり、これは日足神社のたたりにまちがいありません。すぐに立派な刀を献納して、お許しを乞うてください。」 と、再度お殿様に、申し上げました。 さすがのお殿様も、今度ばかりは祈祷師の言葉に従うほかなく、立派な刀を納めました。それ以降、騒ぎもおさまり村にも平穏なくらしが戻ったといいます。 秋になると村人たちは、家内安全、五穀豊穣の祈りをこめて、毎年盛人なお祭りを欠かしません。 湯町のお薬師さん(栗尾)
むかし、栗尾村に湯町という所があり、そこには小さな森があって、その森の中の御堂には等身大のお薬師さんと十二神将と呼ばれる神々がお祀りしてありました。 そして、この森のすぐ近くの岩の間からは、昼も夜も絶えることなく熱いお湯が流れ出していましたので、村人は五、六人は入浴できるぐらいの岩風呂を造り、雨や雪をしのぐために、その岩風呂をすっぽりと包む小屋を建てていました。 こんなことで、田畑からの帰りにこの温泉につかって行く人もたくさんありましたし、リュウマチや神経痛によく効くという評判がたっていましたので、丹波や丹後からも湯治客があり、付近の農家に宿をとって、コンロで自炊しながら、毎日、ここに来ては湯につかる人も少なくありませんでした。 この栗尾村に住む藤太じいさんも、毎夕この湯町に出かけ、お薬師さんにお参りしては湯につかって帰るのを日課にしていましたがある日、いつものように湯町に行こうとしていると、だれか息せききって走って来るものがあります。 「おい、どうしたのじゃ」 「何を呑気なことを言うていなさる。湯町のお薬師さんも神様たちも姿が見えなくなったのじゃ」 半信半疑のじいさんは、小首をかしげながら湯町まで小走りにかけて行きましたが、恐る恐る中をのぞき込んで叫びました。 「おっ、こりゃあどうしたことじゃ」 「お薬師さんはどこに行きなすったのじゃ」 これを聞いた村人たちは、必死になってあたりを捜し始めました。 男も女も、村中総出で草を分け、森の中から付近の山の中まで、何度も何度も捜し回りましたが、やはり、お薬師さんも神様たちの姿も見当りませんでした。 ところが、それから数日経ったある日のことです。 「おーい、たいへんだ!」 「湯町の湯が出なくなったぞ!」 森の方から村の若衆の叫ぶ声が聞こえてくると、村中の騒ぎはいっそう大きくなって、みんな湯町の野天風呂の所に走って行きました。 それにしてもいったいどうしたというのでしょうか。昨日までの湯は滴も流れていないのです。 「これは何のたたりじゃ」 「お薬師さんを捜さにゃ、お湯は出るようにならんぞ」 村人は、また一生懸命お薬師さんを捜し始めましたが、どんなに捜してみても、それっきり、湯町のお薬師さんや十二神将は見当らなかったと言われます。 しかし、それから数年経ってからのことです。 「わしは、湯島(城崎)に行ってきたんじゃが、驚いたことに湯町のお薬師さんや神様がちゃんと湯島にお祀りしてあるのじゃ、だれが持って行ったのかのう。お薬師さんか湯町はいやじゃと言うて逃げなすったのかのう。それにしても、湯島には湯が出て、ええ温泉場になっとるぞえ」と話す者がありました。 村人は不思議に思いましたが、湯島に行った人が帰ってくると、必ず同じ話をして聞かせますのでそのうちに、だれもこの話を信じるようになりました。 それからどれはどの月日、星霜を経たでしょうか。村の奥の山中に大きなお寺が建立され、村人の願いで、大きな薬師如来像数基も祀られることになりましたが、栗尾村には再び熱い湯の湧き出ることはありませんでした。 そして、今日、松禅寺に残る薬師如来像は、このときに造られたものといわれ、山の御堂にお祀りされていたものであるといわれています。 栗尾の小字一覧『兵庫県小字名集Ⅱ但馬編』【栗尾】(くりお) 谷山(たにやま)、大戸(おおと)、下川原(しもがわら)、平山(ひらやま)、中坪(なかつぼ)、下坪(したつぼ)、宮ノシモ(みやのしも)、二ノ切(にのきれ)、竹ガウト(たけがうと)、セバト(せばと)、宮ノ上(みやのうえ)、ハサコ(はっさこ)、百合が花(ゆりがはな)、堂ノ本(どうもと)、竹ガハナ(たけがはな)、上山根(かみやまね)、岩原(いわはら)、柴地(しばぢ)、ヲサ(おさ)、中島(なかじま)、本城(ほんじょ)、シモク山(しもくやま)、登尾(のぼりお)、隠レ尾(かくれお)、土橋(つちばし)、小屋川(こやがわ)、梅ヶ谷(うめがたに)、治郎ケ谷(じろがたに)、大ナル(おおなる)、水越(みずこし)、クズレ(くずれ)、郷布(ごうぬの)、新戸口(しんどぐち)、高尾(たかお)、寺谷(てらだに)、宮ノ向(みやのむこう)、岡(おか)、萱野口(かやのぐち)、萓野(かやの)、ヒジサコ(ひじさこ)、登り立(のぼりたて)、棚田(たなだ)、赤頭(あかがしら)、野田(のだ)、供養木(くようぎ)、伯耆崎(ほうきさき)、下道(したみち)、宮ノ向(みやのむこう)、川原(かわら)、ナワテ(なわて)、神子谷口(みこだにぐち)、反田(たんだ)、釈迦堂(しゃかどう)、泉貝(いずみがい)、柴原貝(しばらがい)、鴻ノ巣(こうのす)、上川原(かみがわら)、柴山(しばやま)、平石(ひらいし)、貝田(かいた)、林ヶ谷口(はやしがだにぐち)、中ノ谷(なかのたに)、大谷(おおたに)、向山(むかいやま)、貝田峠(かいたとうげ)、婆谷(ばばたに)、寺谷(てらだに)、ヒシロ(ひしろ)、切畑(きりはた)、郷路(ごうろ) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||