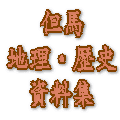 |
西野々(にしのの)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西野々の概要《西野々の概要》 西野々は、太田の北、少し高いところあり、東は高竜寺村、西は木村と境している。 幕府領の太田市場村・木村と隣接し、境界決定が難しい。寛延元年(1748)、わら谷事件では木村の百姓が倉見領である当村わら谷の道を切り崩したことから、寛延元年当村総代が訴状を送り、木村庄屋が回答書などで応酬し、同3年寺社奉行大岡忠相による裁許で当村が勝訴している。 西野々村は、江戸期~明治22年の村名。但馬国出石郡のうち。山名氏政滅亡後天正13年まで青木勘兵衛、同年から前野長康が領した。文禄4年出石藩領。寛文6年からは旗本小出氏の知行。明治22年資母村の大字となる。 西野々は、明治22年~現在の大字名。はじめ資母村、昭和31年からは但東町の大字。平成17年より豊岡市の大字となる。  西野々側から太田側を見る。今は立派な自動車道↑がついているが、以前はこの道路の突き当たりに見える山を越えて太田と通じていたという。学校へ行くにも大変だったという。この山に愛宕神社があるので、愛宕峠といったのであろうか。上の写真で言えば左側(東側)へちょっと(100mばかり)迂回すればよいではないかと思えるようなことなのだが、何かそうできない事情があったものか、現代人には理解不能な道が結構あるものだが、昭和7年にここにトンネルが掘られた、たった全長22m、幅4mのトンネルだったが、無駄な労力が省かれ、熊と会うこともなくなった。 そのトンネルが今も残っているという。集落へ入る道、手前の道でも、次の道でも入って、川に出るので、その川沿いの道を下ればいいようなのだが、その道にはワンちゃんがいて、吠えるぞという顔して道の真ん中に座ってござるった、行けなかった。 《西野々の人口・世帯数》 38・14 《西野々の主な社寺など》  集落の東に大きな円墳のような円い山に鎮座。 『資母村誌』 若宮神社
西野々村字宮山に在り村社、祭神正哉吾勝克速日天忍穂耳命。 天照太神の皇子にして太神。命を愛して太子となし遂に豊葦原中国を治めしむ、尊初天降らんとするに際し當時大己貴尊出雲を中心として四隣に威を振へるが故に中途より還り状を太神に具す、太神因りて高皇産霊神等に議し天穂日尊、天稚彦等を遣はして之を圖らしむ、意の如くならざりしを以て更に建御雷神、經津主神を遣はし漸く大己貴命及其部属を征服することを得たり、是に於て忍穂耳尊更に降臨し給ふべかりしも皇子瓊々杵尊既に誕生ましませるが故に己れに代りて皇子を遣はさん事を太神に請ひ其許を得て天孫遂に日向に降臨し給へり。『日本書紀、古事記参照』 神體 衣冠束帯の立像手に玉を持つ。 神體厨子銘記天保五年未七月上旬願主村中、奉彫刻佛師山口庄太郎、日域名諸工七條西宮方深秘職正流庄屋七郎兵衛外。 創立年不詳 寛延元年再建、明治六年十月村社格加列、明治二十七年十月上屋再建。 本殿奥桁記 寛延元年戌霜月吉日棟梁畑山村平井九左衛門藤原昌勝 一札 奉建立當社鎮守若宮大明神 御位皇増益、天長地久、我身亦自常護是人、村家氏子敬白、于時寛延戊辰霜月大吉祥九一日御地頭小出織部様御代官伊藤政右衛門様御支配の時齊神道管隕上吉日殿門人祭主當若宮大明神神巫女朝日和泉庄屋太井七郎兵術勝辰 一神鏡臺記 寛延元年戊辰霜月廿一日 奉進上松井長左術門 一高麗狗二對一對の背に午の元祿十五庄屋七郎兵衛 境内社 稻荷神社 一燈寵一對 文政十一年九月 宮田預一石三斗ありしも賣却し唯宮田の字を存す 境内坪數 百八坪外に七畝四歩明治三十八年編入 氏子數 二十八戸 祭日 十月八日 《交通》 《産業》 『資母村史』 鑛坑の跡 西野々村字本谷にあり、金屋の字を存し愛宕山裏に金屑石多く出づ太田村にも金屋、吹屋、イモヂカエ、トギダ等の字を存す、往昔鉱石發掘し鍛練せしものならん虫生村字向金山坂野字轟にも鑛坑あり。
《姓氏・人物》 西野々の主な歴史記録西野々の伝説『但東町の民話と伝説』小屋谷砦の戦い(西野々)
むかし、木村の大将軍館に目を引きつらせたような五人の武者が、さも大事件が起こったという様子でやって来ました。 「お館さまはおいでか。われらは御鳥羽上皇さまのお使いでまかり越した。火急の使者が来たとお伝え下され。」頭らしい一人が、少しの時間も無駄にはできぬと言うた様子で門番に言いました。 門番も使いの内容は判りませんが、この五人の武者を見ているとただ事でないことはよく判りますので、ころがるようにこの事を奥に伝えました。「お館さまが直々にお会いになるそうじゃ。庭までお入りなされ。」 使者は、募府の配下のくせに院の使いを軽く扱うのかと言うた様子で奥庭に進みましたが、館の主が来てもひざまづかず「都の三上皇さまと共に各地の武将が蜂起し、今や倒幕の挙兵が進んでいる。貴殿も速やかに但馬の官軍に合流し、京を目指して上られるよう。」と言いながら、懐中に入れてあった院からの書状を渡しました。 館の主は後に但馬守護職となる太田昌明であり、頼朝の叔父・源行家の首を取った豪の者ですから、こんな使者の口上にうろたえるような男ではありません。勿論、頭の中では幕府が勝つか院が勝つかの読みが走ったと思いますが、昌明はすぐに幕府に利ありと判断し、「この者たち、世を乱す無法者である。すぐこの場にて斬り捨てい!」と命じました。使者は丁重なもてなしがあると思って来たのに、斬り捨てるとは何事と思い「昌明、正気の沙汰か。今、院に御味方せずば後悔するぞ!」とわめきましたが、昌明の手下に組み伏せられ、その場で首を討たれてしまいました。 怒ったのはこの事を聞いた但馬の官軍であります。京に上る土産に昌明の首を持って行こうと数百の軍勢を集めて昌明の館にドッと押し寄せて来ました。昌明は大将軍館ではとても防ぎきれないと思い、急ぎ西野々の奥にある丹後境の嶮峻、小屋谷砦に移り防戦しました。 この砦は西野々部落から約一㎞ほど登ったところにある急坂の砦で、ちょうど谷と谷の分かれるその真中に聳える絶壁の砦ですから、攻めるに難しく守るに易い天然の要衝であります。 武具を着ているだけでも重いのに、その上、刀や槍を持ちこの山坂を登って行くのですから、もうそれだけでも息たえだえであります。それが登りつめて今一歩となると上から石や木材が落ちて来るのですから、攻め手はたまったものではありません。武者も石も木材も地煙をあげて谷に転落して行くのですから、戦死者は日増しに増えていきますし、骨折や打撲に苦しむ者も続出します。 こんな戦力低下のあせりに追い討ちをかけるように京都から届けられた報せは、北条義時の幕府軍一五万が都に上り、三上皇は捕らえられ挙兵は完全に失敗したということでありました。但馬の官軍はこれで戦う目標を失い、あっという間に四散してしまいました。 これは承久の変での但馬での出来事ですが、いち早く幕府支持にふみきった昌明は、その忠節ぶりが認められ但馬守護職という要職につくことになります。また、この時に焼かれた大将軍館はそのまま放置し梓野の南、堀ノ内の高台に大きく新しい館を新築します。そして、この事件で太田氏の勢力範囲は太田荘から但馬全域に拡がることとなったのです。 西野々の小字一覧『兵庫県小字名集Ⅱ但馬編』【西野々】(にしのの) 休石(やすみいし)、石田(いしだ)、宮田(みやだ)、地蔵ノ前(ぢぞうのまえ)、立て田(たてだ)、ゴウノノ(ごうのの)、中田(なかだ)、栗町(くりまち)、ヒガシ(ひがし)、中島(なかじま)、井上ミ(いがみ)、札場(ふだば)、クゴ(くご)、棚田(たなだ)、金谷(かなや)、丁田(ちょうだ)、浦ノ谷(うらのたに)、ワラ(わらだに)、小谷(こだに)、ヲバガ谷(おばがだに)、九右工門田(くえもんだ)、長尾(ながお)、平山(ひらやま)、岡ノ後(おかのうしろ)、一ノ瀬(いちのせ)、漆谷(うるしだに)、梨ノ段(なしのだん)、本谷(ほんたに)、峠谷(とうげたに)、細谷(ほそたに)、城山(しろやま)、ボウズ森(ぼうずもり)、宮山(みややま) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||