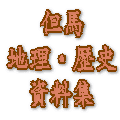 |
大河内(おおごうち)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大河内の概要《大河内の概要》 大河内は久畑の東にあって、薬王寺川の左岸に注ぐ大河内川の流域山間を占め、出石・福知山道(国道426号)が通る。この道は山道に入って 大河内村は、江戸期~明治22年の村。但馬国出石郡のうち。山名氏政滅亡後天正13年まで青木勘兵衛、同年から前野長康が領した。文禄4年からは出石藩領。明治22年高橋村の大字となる。 大河内は、明治22年~現在の大字名。はじめ高橋村、昭和31年からは但東町の大字。平成17(2005)年より豊岡市の大字となる。 《大河内の人口・世帯数》 50・22 《大河内の主な社寺など》   当寺は荒廃していたが、文禄4年(1595)に堂宇を回復し、のち小出秀政の四男で、出石城下吉祥寺三世嫩佐を招請して中興開山としたという。安永2年(1773)堂宇を焼失し、のち復興。天保2年住職となった本秀は「正法眼蔵」の研究者として有名。慶応2年(1866)同寺に寺子屋が開設されたという。 『但東町誌』 笛岡山 楽音寺 (大河内)
記録が乏しく、寺暦は明らかでないが、大河内に、隣接の薬王寺部落の鎭守兵主神社に六つの坊があり、当時もその一坊だったといわれている。その荒廃していたのを三六六年前の文録四年五月、便喜善方首座が復興して曹洞宗に改めた。 その後吟海善龍首座から安山広禪首座に傳へ、出石町吉祥寺を本寺とし同寺三世祐山和尚を勧請して開山とした。二世天宗和尚のとき平僧地から法地に昇格し中興となったが、当寺の最功労者である九世本秀和尚は、正法限藏の研究家として知られ、眼蔵注釈書はその寺宝として保存されている。また本秀和尚は仏具を調達し境内を整備するなど多くの足跡を残した。本堂の屋根付え・山門納屋の改築は前注透嶺和尚のとき完工した。 檀家 百二十五戸 《交通》 「登尾峠」という峠はあちこちにあるが、トオと呼んだのではないかと思われる、トオとはタワで、稜線がタワンで低くなっている場所という。 アリラン・アリラン・アラリヨ、アリラン・トウゲ・ノモカンダ゜… と聞こえる。トウゲではなくコゲらしいが、聞いていると、日本語とまったく同じでトウゲである。トウゲは朝鮮語か。 今はトンネルだが、昔の峠道は「はなはだけハしき峠也、別して下り卅丁けハし」とあって、但馬側がけハしいとある。 国道9号の福知山市野花で分かれて、出石街道を北上すると、ここへやって来る。 近世初期、豊臣秀吉の弟・羽柴秀長が豊岡・出石付近を一円支配したことにより、福知山-佐々木谷-登尾峠-久畑-出石-豊岡の出石街道が改修、整備されたという。近世には峠下の上佐々木の小野原には本陣・旅籠が営まれていたという。 福知山藩日記(島原市猛島神社蔵)寛文7年(1667)8月12日条に「御国廻衆御通ニ付(中略)、福地山より佐々木上り尾峠迄、道掃除申付候ニ付而、奉行ニ御歩行衆道割候而奉行申付出候事」とあり、14日条には「上佐々木村上り尾峠迄道見分並上佐々木村御国廻衆御宿出来、為見分八右街門・九郎左衛門・七郎右衛門罷越事」とみえる。 また「丹波志」に「佐々木村ヨリ但馬国久畑市場村マテ、壱里拾四丁三十間、牛馬道、但シ上リ尾峠国境杭迄二十四丁四十間、国境上り尾峠峰疆、左右山並尾鏡、峰疆三国嶽峰疆道、境ハ上リ尾峠峰ニ杭有之」とあり、文化3年(1806)刊「但州湯島道中独案内」の小野原の項に「一の宮より一り」として「のぼりをの坂又のばりりやうくだり竜ともいふ、はなはだけハしき峠也、別して下り卅丁けハし、峠ハ丹波但馬のさかい也、右に大江山の峯みゆる、一丁ほと下りて若狭の二子山(青葉山)見ゆる、又五六丁下りて夜泣の松と云あり、此松を削りて、夜なきする子の家にて火ニとほせば夜なきやむといふなり」とみえる。 江戸時代までの登尾峠は小野原から西北の谷底の道をまっすぐに谷頭へ上っていたが、明治中期以後は小野原からやや北へ上って、三国山の西の山腹の下部を蛇行しながら山頂の鞍部、現在の登尾峠(約455メートル)に達し、蛇行を重ねなが大河内へ下り、久畑に達するようになった。 《産業》  黒毛和牛の超ブランド品・ 但馬牛といってもいろいろ蔓がある。ツルというのは血統で、優れた1頭の牛の血統のみを引き継いでいる純血種のことである。 当地の稲木場吉左衛門は寛永年間(1624-44)に但馬牛のなかでも最も優秀な品種の一つとされる黒毛和牛(稲木場蔓牛)を産出した。その後は世襲でその純系を維持し、この牛の飼育を一帯に広めた。同牛発祥の地の記念碑がある。 当地あたりの農業は地形上、山田や山畑が多く、生産性は極めて低かった。田畑といっても3分の2以上が下々田もしくは下田で、上田は全体の1割にも満たない。山畑では焼畑栽培が行われ、蕎麦・大豆・小豆・コンニャクが生産された。 稲木場吉左衛門は、肢蹄・気力の強い長命な黒毛和牛を生み出し、以後世襲で純系を維持し、いなきばつる牛として当地方に広めた。但馬牛の中で、最も優秀な品種の1つとされている。大河内村に隣接する薬王寺村(上の写真で言えば、先の三叉路を右ヘ行ったところ)の大生部兵主神社は、古来牛馬の守護神として崇められ、例祭には牛市が立った。 今の日本の黒毛和牛は100%但馬牛で、但馬ツルの子牛を、各地で育てた牛であるという。もともとは食べるための牛ではなく、役牛であった。 『但東町誌』 (2)和牛と「つる牛」
(イ)但馬牛 但馬牛は丹波牛より名早く「種牛は内国にて但馬に限る」といわれたが、とくに有名となったものは元禄の頃からといわれている。いわゆる純系の「蔓牛」は美方郡を中心に「治部蔓」「黒田蔓」「源兵衛蔓」「稗飯蔓」等のつる牛が産出されるようになった。(窪田五郎著「日本牛史」昭和一五年三月刊) 但東町では昔から「牛」のことを「べこ」といっていた。これは単なる方言でなくてアイヌ語の「貨幣」ということで、昔から牛が米と共に物々交換に用いられ、貨幣の役割を果したことを示しているといわれている。後世貨幣を作るとき、鋳貨に牛の頭を鋳し、これを「ペコ」といったことからきたという説もある。 和牛のうち最初に但馬牛が有名となっだのは「輓牛」としてで、速度は遅かっかが牽引力強く、足が早く古代の御所車引きに珍重されたことは前述の通りである。元禄の頃から但馬牛が有名になった理由は「歩様頗る早く、性質柔順、(中畧)使用に便なるによれり」といわれていた。牛は峠等の坂道も平気で上り、庶民の山地坂道等、道の悪いところで物を運び、牛車を牽くに用いられたといえる。すなわち一般商品の交易、輸送の増大と共に、和牛の背による輸送、車による搬入搬出の増大が、但馬牛の名を高くしたものと思われる。 牛車を使うものは七~八才以上に限り、輓き方などを「仕込む」時期は、春秋を第一とし、夏は不良とされた。また牛耕の場合と同様、「仕込」さえ終れば但馬牛は賢こく、オーと呼べば止り、シッと云えば歩み出し、チョッチョッと云えば左へ曲り、手綱を引けば右に曲る(但馬牛は鼻木をつけ、一本の手綱を右側につけるを常としていたため)ことを覚えた。手綱は三ひろ半(約三m)を一本を用い、牛があばれ出す時は、その手綱をゆるめで波形に振れば綱の波動が牛の鼻に当り、牛は怖気を生じ、柔順となるため需要が多くなったものとみられている。しかし道路がつくられ山道や峠道が車を引いて通れる近代的道路に代わり、多くの物資の大量迅速な輸送時代となると、牛は次第に馬に代るようになっていったといえる。 (ロ)いなきば蔓牛(つるうし) 但東町の和牛飼育は労力集約的で昼間放牧、夜間舎飼という家族的な労頭飼育により、優秀系頭の和牛のみが飼育された。それは繁殖地の持徴である優秀高価な「仔取り」のためで、まさに芸術品とも思われるような体形の整っだ系統牛の繁殖に努力が傾中された。「いなきば蔓牛」は但馬における前記「治部」「黒田」「源兵衛」「稗飯」蔓牛等と共に、最も優秀な純系統種であった。 いなきば蔓牛等但馬の和牛が「小牛産物」として最も有名になってくるのは、元禄(一六八八)以降といわれているが、この名称の起源は、大河内村で相当な稲木場をもっていた稲木場吉左衛門の飼育にかかる系統牛という意味と思われる。稲木場は稲を干す稲架を意味し、その広さは水田面積の広さを意味しているから、相当の本百姓であったと思われる。稲木場吉左衛門は寛永年間の人で、良い牛を飼養し、世襲で純系の和牛を生産してきたので、この人の姓をとって「いなきばつる牛」というようになったといわれている。この家系は明治年間にも襲名して続いており、次の文書が残っている。 明治六年宮城災上献金人名御届出 一金一二銭 稲木場吉佐衛門 他一二名 この屋敷は現在「松ノ木」部落にあり、現在は畑地となっている。(杉山政之助「いなきばつる牛物語」) (ハ)牛の市場 大生部兵主神社は別名を「薬王寺牛頭天王社」ともいい、古来牛、馬の守護神として知られ、近隣但馬、丹後、丹波の畜産農家の信仰の厚い神社であった。このことは但馬を中心として畜産とくに牛飼い(主として和牛)の地であったことと、当時なお獣医学が発達せず、牛馬の病気、出産分娩の無事は「神頼み」より他なかったことを示しているものであった。またこの牛馬信仰に伴って、「牛市」も開かれ、この山奥の神社であるので、常設の市場でなく、例祭等の日「牛市」が開かれることになっており三丹各地から牛が集った。しかし神社の境内は今も見られるように狭いので、社前の田畑を氏子立合の上「牛繋場」に定めた。これに対し雲原村(現、福知山市)総代から、銀十匁が届けられ、その請取証文が残っている。 覚 一金拾匁 右其御村天王様へ御参詣の節牛繋として鳥居より東側五間に八間の処差出申候右銀子たしかに受納仕り以上 承応三甲子年一一月 薬王寺村 喜 太 夫 大河内村 三郎右衛門 右 氏子 惣代 雲原村惣代 三右衛門 殿 承慶三年は一六五四年のことであり、右の銀一〇匁は、承応三年の米価が、一石三九匁(「歴代諸物価一覧」)であったことをみても、相当な金額であったことが知られる。 《姓氏・人物》 大河内の主な歴史記録大河内の伝説『但東町の民話と伝説』いなきば蔓牛の話(大河内)
大治五年(一一三〇)崇徳天皇八年に京都三十三間堂を建立して、千体の観世音像を安置する工事が行なわれました。何しろ堂の長さ六十四間五尺(約一一七米)、本堂の柱間が三十三もあるのですから、材木を集めるのが大変でした。なかでも棟木は大きくてりっぱなものをと全国に呼びかけられ、集まったたくさんの候補の中から、但馬高柳村の柳の大木が一番ふさわしいとえらばれました。高柳という地名が示す通り、樹令何百年というこの大木は、それはりっぱなものでした。大勢の人がかかって苦心の末切り倒されましたが、あまりに大きすぎて運ぶことができません。 「このあたりで、もっと力の強い馬か牛はおらんのか。」 とさいさいたずねられ、たくさんの牛馬や、力持ちの男たちが何回となく挑戦しましたが、みんな途中でへこたれてしまってお役人たちは困ってしまいました。こんなことでは、決められた日までに京まで運ぶ見通しがたちません。さんざん探しまわったあげく、世話人の一人が、少し東の方に力といい、賢さといい、根気強さといいどの牛にも負けない強い牛がいるそうだという話を聞きつけました。ものは試しと探しあて連れてきたので役人たちはたいそう喜びました。うわさの通りみた目にも毛並といい、骨格といい、並はずれてりっぱな牛でした。当地の強い牛たち何百頭の先頭に立ち、進めの会図を聞くやいなや、この牛はひと声「ウオーツ」とうなり声をあげました。見物の人々の胸の奥までひびくずっしりと重い声でした。おどろいたことに、あとに続くたくさんの牛たちが、このうなり声に和して同じように声を出し、ゆっくり一歩をふみ出しました。さしもの大木がミシッと動くと、話を聞いてかけつけた大勢の見物の人々から感嘆の声があがりました。「ウォーツ」「ウォーツ」とかけ合いの声と共に力は一つになって重い木をひっぱっていきました。無事に京に到着したことはいうまでもありません。 この建物は、翌年天承元年に無事完成し、長承元年(一一三二)三月十三日、三十三間堂の落慶供養に鳥羽上皇が臨御されたと伝えられています。 先頭にたってこの建造物の棟木を引いた牛が、のちにいういなきば蔓牛でした。大河内部落に稲木場古左ヱ門という豪農があって、良牛を飼育し、家の前に稲木場(稲の天日乾燥場)を作っていたことからこの名がついたもので、その子孫を世にいなきば蔓牛と称しました。この牛は、あしが強く、気力もあり、子どももよく産まれます。その上、長生きするところから田畑をたがやしたり、子孫を増やすために郡内にひろめられました。 蛇と鎌 (大河内)
このお話は、昔むかし山仕事の好きな働き者の男が、登尾峠付近で怖い体験をしたお話です。男の名は、昔のことではっきりしませんので、仮に「与作」としておきましょう。 その日は、朝から強烈な夏の太陽が照りつけ、暑い一日になりそうでしたが、働き者の与作は、夏は暑いのが当然だと思っていましたから、暑さなどちっとも気にせず、女房の手弁当を持って、山へ出かけて行きました。 蝉しぐれの中を歩いて行くと、しばらく来ない間に道端の草がずい分大きくなり、両側から道におおいかぶさるようになって、歩ける部分かせまくなっておりました。与作は吹き出す汗を拭りながら、草いきれの中を進んでおりますと、道を丸太ン棒がふさいでいるではありませんか。 「だれだ、こんなところに丸太ン棒を置いたやつは。じゃまだな。エエイ!」と、思いきりその丸太ン棒を蹴ったとたん、草むらがザワザワと揺れて、身の丈ほどもあろうかと思われる大蛇が、ニューと首をもたげて、カーツと口を開けたのです。 与作は、心臓が飛び出さんばかりに、びっくりしました。 「あっ、わっ、わっわっ。」 と、恐ろしさで言葉にもならず、逃げようにも足がすくんで動くことができません。どうやら、汗が目に入り、大蛇を丸太ン棒と見まちがえたらしいのです。 大蛇は赤い口から、チロチロ、チロチロと長い舌を出しながら、あたりの草をなど倒し与作の周囲をぐるっと囲みました。蛇には、まぶたがないので、まばたきをすることがありません。その恐ろしい目で、ジッと与作を見ております。 与作は生きたここちがしませんでした。一瞬、汗も引き、蝉しぐれも聞こえず、時間も止まったかのようでした。ドキン、ドキン、と早鐘のように脈を打つ自分の心臓の音が、あたりの静寂を破つて聞こえるばかりでした。 大蛇は、恐ろしさで動けない与作に、ジリジリとにじみ寄り、足の方からぐるぐると巻きはじめました。まず、獲物を絞め殺してから食べるつもりなのでしょう。巻いている力に序々に強さが加わってきます。 与作は、だんだん苦しくなり思わず目を閉じました。すると今朝出がけに見送ってくれた女房のまあるい顔が浮かびましたが、ぐるぐる巻きにされている今、逃がれる方法などあるはずがありません。 「こんなことで死にたくない!だけど、あゝ苦しい!もうこれまでだ。」 と、気が遠くなりかけたその時、急に体が楽になったので、与作は、 「とうとうわしは死んでしまったんだ。」 そう思い、おそるおそる目を開けました。 と、どうでしょう。大蛇が五つほどに切れて与作の周りに転がっており、切り口から真赤な血が吹き出しているではありませんか。 与作は、何か起きたのかさっぱりわかりませんでしたが、しばらくして「はっ!」と気付き、そおっと腰に手を当てました。与作の腰には、今朝女房が渡してくれた鎌がしっかりとさしてあり、思い切り絞めつけた大蛇はその鎌で自分自身をバラバラに切るはめになってしまったのです。 鎌のおかげで命びろいした与作は、すぐさま家に帰り、女房や村の者達にこの体験を話して聞かせました。するとある古老が、 「そのとおりじゃ。山に行く時は必ず鎌を腰にさして行くんじゃ。大蛇から逃げられないと思ったら腰を巻かせれば、鎌が蛇を切ってくれる。まだあるぞ。大蛇を叩く時は、しなる木で叩くことじゃ。硬い木で思いきり叩くと折れることかおるのでかえって危険じゃ。」 村の者は皆、なるほどと思い、与作の恐ろしい体験から、山で大蛇に出合った時の身の守り方を学んだのです。そしてこの教えは、その後もずっと語り継がれたということです。 ひだる腹(大河内)
とてもお腹がすいていることを「ひだるい」とか「ひだる腹とか言います。それに関するむかしむかしのお話です。 旧京街道を通り、久畑から福知山に行くのに登尾峠という大きな峠があります。この峠を歩いて越すには、たいへん時間がかかりました。だから峠を越す時は、決して夜道にならぬよう、またひだる腹で旅をせぬよう、みんな心掛けたものです。 ところが、ここに一人、たいへん心掛けの悪い男がおりました。 ある日、男は福知山で買い物をして峠のあたりまで帰ってきましたが、ちょうど頂上付近で日がとっぷりと暮れてしまいました。その上、お昼ごはんを食べてから何も口にしていなかったので、お腹もすいていました。 「あゝ、腹がへったなあ。こげんなことなら何か食う物を買っとくんじゃった。それにこんなにはよう暗うなるとは思わなんだ。まあ仕方がない。この峠さえ越せばもうちょっとのしんぼうだで、がんばって歩かにや。」 男は一人ごとを言いながら星の明かりをたよりに空腹をがまんして帰りを急ぎました。すると前方に、何やらボーと灯が見えてきました。 「おっ、だれか迎えに来てくれたんだな。おおい、わしだ。ここにおるぞ!」 男は帰りの遅い自分を心配した家族が、迎えに来てくれたものとばかり思い、灯に向かって叫びながら急いで歩きました。 でも不思議なことに、歩いても歩いても灯に近づけません。石につまずいて転んだり、道ばたの木で引っかいたりしながら、それでも灯に向かって一生懸命歩きました。 「おおい。わしだ。たのむから、そこにじっとしていてくれ。」 男はもう必死です。とてもお腹も空き、それこそ、お腹の皮と背中の皮がくっつきそうです。それに行けども行けども灯に近づけません。男は泣きべそをかいていました。それまで感じなかった背中の荷物も何やら、急に重たくなってきました。急いでいた足もやがてふらふらになり、とうとうその場に倒れ込んでしまいました。 ところが、男の家では、おかみさんが、すっかり夜がふけたのにまだ帰ってこない亭主を心配して待っておりました。 やがて一番どりが鳴くと、長くなが-く感じられた夜が白んできました。殆んど寝つかれなかったおかみさんは、あたたかいおにぎりと、熱いお茶を持って、急いで峠へ向かいました。 ハアハア言いながら頂上付近までやって来ると、何やら道ばたに転がっています。近づいて見ると、何と亭主ではありませんか。着物はボロボロ、手足は引っかき傷だらけ、それはそれはものすごい様相です。おかみさんはびっくりして。 「あんた、あんた!しっかりして!。」 と亭主を揺り動かしました。自分を呼ぶ声にやがて気のついた男は、自分がなぜこんなところにいるのか、どういう状態なのかさっぱりわからず、しばらくきょとんとしていましたが、起き上がろうとした時の体中の痛みで、そこが峠の頂上付近であることに気付きました。 そして、おかみさんの差し出すおにぎりをむさぼるように食べ、暖かいお茶を飲み、少しずつ元気を取りもどすと同時に、昨夜のことを少しずつ思い出しました。 男はどうやら、何時間もの間、山の中を歩きまわっていたらしいのです。あの「灯」は一体何だったのでしょう。峠を越す時の注意を怠ったばかりに、男はとんだ目にあってしまいました。買い物の荷物はなくなってしまいましたが、おかみさんは亭上が命びろいしたことだけで、もう充分でした。 その後も越す時の注意を怠って旅した者は、この男と同じような目にあったということです。 勅使さまの恋(大河内)
むかし、南谷村(大河内)に萩女と呼ばれる美しくて気立てのやさしい娘がいました。父親はこのあたりの名主で、南谷に大きな屋敷を構えていましたが、男の子がなく、この萩女だけを頼りにだいじにだいじに育てました。村の人も萩女さまには三国一の花婿が来るぞえと噂しましたし、ここらには萩女さまの婿殿になるような男はいねえ、都の方のお方か何かでねえとのうとも言いました。 ところが、康保元年(九六三)春のことです。但馬守重信の奏聞により、薬王寺の大祭に京から勅使がお下りになるというお達しが届きました。こんな草深い里に、天皇さまのお使いがお越しになるというのですから、もう加悦、雲原、久畑谷一帯の人々は大びっくりで、村の主だった人々は、来る日も来る夜も勅使さまをどうおもてなしするかということで相談を重ねました。そして、やっとお泊りは南谷村の名主さまのお屋敷と決り、お給仕は萩女さまにお願いしようということになりました。 こうして、名主屋敷の改造や、萩女さまのお手伝いをする近くの村々から選ばれた娘さんたちの行儀見習が終る頃に、とうとう勅使さま下向の日がやって来ました。 案じていた空は一点の雲もなく晴れ上り、薬王寺の本堂には真新しい五色の緞張が張りめぐらされて目も覚めるようです。また、境内には吹き流しが三流四流風になびき、山門前の参道はきれいに掃き清められていました。 そして、勅使さまが輿をお降りになるあたりには、緋の衣に中啓を持った大僧正さまを先頭に、社僧袮宣、三丹の名主などが、それぞれ正装でお出迎えに立ちました。それに、下座の村人は峠のふもとからずっと並んでお待ちしていますし、木に登って遠くから見物するやじ馬なども合わせると、ゆうに千人に余る盛大なお出迎になりました。 こんな人々の中を、若者八人がきの輿に乗った青年勅使大宮吉光さまの行列が静かに御到着になりましたが、山門前でお出迎えの萩女さまに、しばし目をお止めになったことに気付いた者は一人もいませんでした。 しかし、祭礼の当日まで二日間の有余がありましたので、萩女さまの御案内で、薬王寺の周辺から護摩ケ成のあたりまでも、肩を並べて御散歩になっているお姿を見かけた者はたくさんありました。 吉光さまは、お祭りの当日、衣冠束帯の正装で勅使の大役を無事おすませになり、自らも天王社領として田地四町六反五十歩を寄進し、ほっとした面持ちで南谷の宿舎にお帰りになりましたが、翌日は一日だけ休息しすぐ京にお発ちにならねばならない日程になっておりました。お帰りの日は、萩女さまも雲原に越す峠の頂までお見送りになりましたが、いよいよお別れという時、吉光さまは輿を降りて萩女さまに近づき、何か二百三言お話になりました。勿論、誰の耳にも何も聞えませんでしたが連れの者の話すには、萩女さまは目に涙を浮べていらっしゃったということでした。 それから三ヶ月程経ったある日のことです。村人は萩女さまの花婿が決ったという報せと、それも相手が勅使大宮吉光さまと聞いて二度びっくりをしました。 御結婚の儀式は、都の貴族であり、河内の国司である吉光さまの父君も御参列になって盛大に催されましたが、生涯をこの地で終わることに決心なさった吉光さまは生まれ故郷である河内の名に大の一字を加え、南谷村を大河内村とお改めになったと伝えられます。 また、大河内の旧家桑垣家の祖は桑垣権之守と言いますが、代々大河内の名主を勤めたいという録もありますので、萩女さまは桑垣家の娘であったのかも知れません。 人の住むところには必らず恋があり、いつの時代にも人間はいろいろなロマンスの花を咲かせますが、平安の恋ということになるとリアルな感じが薄らぎ、楽しく、清潔でほほえましくさえあります。 大河内の小字一覧『兵庫県小字名集Ⅱ但馬編』【大河内】(おおこうち) 岶垣(さこがい)、吉田(よしだ)、苅又(かりまた)、五位田(ごいでん)、仏田(ふっだ)、松木(まつのき)、西ヶ谷(にしがだに)、岶ノ谷(さこのたに)、向ケ谷(むかいがたに)、小谷(こだに)、親谷(おやだに)、峠谷(とうげだに)、落(おとし)、赤毛(あかけ)、桑垣(くわがい)、寺谷(てらたに)、京田(きょうでん)、恋神(こいがみ)、能谷(のうだに)、百合(ゆり)、西門(にしかど)、炭釜(すみがま)、千原(ちはら)、稲ヶ谷(いねがたに)、河ノ辺(こうのべ)、與登(よと)、伊吹山(いぶきやま)、西ヶ谷(にしがたに)、小富士(こふじ)、三国嶽(みくにだけ)、登尾(のぼりお) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||