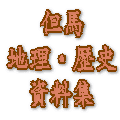 |
佐田(さだ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐田の概要《佐田の概要》 栗尾村の上流に位置し、集落は出石川の両岸にある。出石・福知山道(旧・京街道・国道426号)が通る。 佐田村は、江戸期~明治22年の村。但馬国出石郡のうち。山名氏政滅亡後天正13年まで青木勘兵衛、同年から前野長康が領した。文禄4年からは出石藩領。鎮守は久畑村の一宮神社。明治22年高橋村の大字となる。 佐田は、明治22年~現在の大字名。はじめ高橋村、昭和30年からは但東町の大字。平成17(2005)年より豊岡市の大字となる。  旧街道の一里塚跡の石碑↑  「吉成寺址碑」と「南無阿弥陀仏…」とある石碑。たぶん「村継場」の跡ではなかろうか。碑の文字が読めない。 《佐田の人口・世帯数》 42・20 《佐田の主な社寺など》 『但東町誌』 縄文土器片と出土品
写真は昭和四七年佐田亀谷土取場より発見された縄文土器片である。縄文早期(約七〇〇〇年前)のものと思われ、但東町で始めて発見されたものである。発見場所は県道より四〇〇m入った谷あいの赤土層で、木炭片や焼土の層が見られるので堅穴を掘って生活していたのかも知れない。まだ農耕を知らず木の実の採取や狩猟で暮していた時代であろうと思われる。なお、この土器片は但東町民俗資料館に保存されている。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 佐田の主な歴史記録佐田の伝説『但東町の民話と伝説』心谷の悲恋物語(佐田)
佐田から佐々木に越す峠の谷は、「こころ谷」と言うロマンチックな名がついておりますが、これはその名にまつわる悲しい恋の物語です。 昔むかし、京の都に、ある若い公家が住んでおり、彼はたいそう立派な風采をしていたので、都の娘たちの中には思いを寄せる者も多くございました。 ある日のこと、公家は都大路で一人の娘に道をたずねました。ふり向いた娘は、「どきっ」としました。きりっとした口元、やさしくほほえみかける瞳、ひとめで公家を好きになってしまったのです。 それからの娘は、病に取りつかれたように公家を恋いこがれる毎日に変わりました。用もないのに都大路に出て公家の通るのを待つこともございました。 公家は、娘がやさしく会釈してくれるので少し心に止めはしましたが、自分のまわりに群がってくる多くの娘だちと同じくらいにしか思っていませんでした。 少し涼しくなったある初秋のことです。但馬の佐々木庄に、たいへん高貴な方をお祀りした神社があり、その秋祭りの祭礼に、若い公家が勅使として代参することが決まりました。 娘はそのうわさを耳にすると、何となく不安にかられました。公家が佐々木庄から都へは二度と帰って来ないような気がしたのです。娘は思いあまったある日、都大路で公家に自分の思いを打ち明け、一緒に佐々木庄に連れて行ってくださいと懇願しました。 娘の告白を聞いて、公家はたいそう驚きました。都大路で出逢う娘から、まさか恋心を打ち明けられるとは夢にも思っていなかったからです。それに勅使として代参する地に、娘を連れて一緒に行くなどできるはずがありません。娘の心を傷つけないよう、必ず帰って来るからと言ってその場を取りつくろい、数日後のある秋晴れの朝、公家は佐々木庄へ向けて都をあとにしました。 娘は、公家の言葉を信じて待つことにしましたが、日が経つにつれ、恋心はつのる一方です。そしてとうとうある日、公家の後を追って旅立って行きました。 娘の一人旅は、並たいていのものではありませんでした。大きな峠をいくっも越さねばならず、足には豆ができて血がにじむこともありましたが、公家恋しさのあまり、痛さも辛さも、また恐さも忘れて歩き通しました。 やがて片野庄にたどり着きました。ここまで来れば、佐々木庄は峠を一つだけ越せば、もう目と鼻の先なのです。でも娘は、公家に迷惑をかけてきらわれたくなかったので、これより先へ進むことはできませんでした。はやる心を押さえながら、近くの大将軍塚で待つことにしたのです。 一日過ぎ、二日経ち、そして十日経ちました。娘は毎日、谷から峠を見上げて公家を待ちましたが、いっこうに公家の帰って来る様子はありません。 ところで、都の娘が峠の向こうで自分の帰りを待っていることなどつゆ知らぬ公家は、神社の境内にある「なんじゃもんじゃの木」にさわれば、直ちに恋人ができるという話を聞き、ためしにさわってみました。するとどうでしょう。祭礼に巫女として上っていた美しい村の娘を、たちまち好きになってしまったのです。そして、都の娘のことは、すっかり忘れてしまい、村の娘と結婚して佐々木庄へ住むことに決まってしまいました。やがて大将軍塚で待っている娘にも、その話が伝わってきました。恋しい公家が、もう二度と自分のもとに帰って来ないと知った娘は、悲しさのあまり、すっかりやつれ果て、泣く泣く都へ帰って行きました。それ以後、娘が毎日峠を見上げて恋心をつのらせた谷を「恋心の谷-心谷」と呼ぶようになり、今に至っております。 首切り地蔵(佐田)
昔むかし、戦国時代と呼ばれ、全国の武将たちがあちらこちらで軍を起こして勢力争いを繰り広げた時代がありました。これはそんな時代もそうそう終りに近づいたころ、久畑に往む大地主に実際に起きたお話です。 武将たちは、戦などに多額の経費が必要であったため、領民に多くの年貢をかけて税金として納めさせましたので、領民の暮らし向きは一向によくならず、いつも貧しい生活を強いられておりました。 そんなある夕のこと、出石藩主の領地高調査が行われることになり、久畑村に住んでいた大地主の茶屋四郎兵衛は、桑畑の桑の木一本残らず調べ上げるとの藩主よりの通告を受け、たいへん心を痛めておりました。四郎兵衛は小作人たちの暮らしにあえぐ様をまのあたりにしており、これ以上の年貢をかけることなど、とてもできないと思っていたからです。そこで四郎兵衛は、何とか少しでも税金を逃がれる方法はないものかと考え、あることを思いつきました。 これは桑の木を根元から切ってしまい、その切株に土をかけて隠してしまおうというものでした。桑の木は、たいへん成長が早いので、根元から切っても春になれば新しい芽が出て、数年もすればすっかり大きな木に成長するのです。 さっそく四郎兵衛は検地の行われる前に、小作人たちに桑の木を切り倒させました。その日は雪が降っており、切株は土をかける間もほとんどないくらい、激しく降りしきる雪に次々と覆い隠されていきましたので、四郎兵衛は、これなら大丈夫だろう、見破られることもなかろうと、高をくくっておりました。 そして、いよいよ検地の行われる当日を迎えました。その日は朝から太陽が照りつけ、暖かくたいへんよいお天気になりました。切株をすっぽりと覆い隠していた雪は、じりじりと照りつける太陽の熱に、少しずつ解け始め、畑のあちらこちらで、株の頭を見せ始めてきました。四郎兵衛はあわてました。が、時すでに遅し。四郎兵衛の苦肉の作は、検地の役人に見破られてしまったのです。 「やい、四郎兵衛、これは一体、どういうことじゃ!切株もまだ新しいが、お前は我々の目をごまかす気か!」 「どっ、どうかお許し下さいませ。」 四郎兵衛は両手をつき、土下座してただ、ひたすらあやまり続けましたが、 「だまれ、だまれ!よくもお上を騙しおったな。ええい!見せしめに打ち首じゃ!」 そう言うと役人は四郎兵衛を佐田科の福井野の山麓に引張って行き、打ち首の処刑に科してしまいました。 たいへんむごい出来事ですが、当時は権力者に楯突くことなど、決して許されることではなかったのです。四郎兵衛の家族は、お上のあまりにひどい仕打ちに寝込んでしまい、その後、茶屋は絶えてしまいました。 ところで、四郎兵衛が処刑された地では、不思議なことが起きていました。春になってもなぜかそこだけは、草木一本として生えてこないのです。小作人たちは、四郎兵衛の怨念かも知れないと思い、その他に、供養のための地蔵尊を建てました。 その地蔵尊は、「首切地蔵」と呼ばれ、現在に至っております。 佐田の小字一覧『兵庫県小字名集Ⅱ但馬編』【佐田】(さだ) 庄堺(しょうざかい)、立石(たていし)、ヲソ谷(おそだに)、川原田(かわらだ)、ホウリウ谷(ほうりうだに)、ヒヤケ田(ひやけだ)、ドウ々(どうどう)、谷口(たにぐち)、棚田(たなだ)、福井野(ふくいの)、貝尻(かいじり)、吉成寺(きちじょうじ)、細田(ほそだ)、石原(いしはら)、岡ノ森(おかのもり)、津原(つはら)、カモンドウ(かもんどう)、登り立(のぼりたて)、下坪(したつぼ)、ソウツカイ(そうつかい)、青イ坂(あおいざこ)、中間ヶ市(なかまがいち)、山ノ下(やまのした)、亀谷(かめだに)、下岡花(しもおかばな)、下石原(しもいしはら)、小亀谷(こかめだに)、イノヲ(いのお)、平地(ひらち)、東坂(ひがしさこ)、高畑(たかはた)、クラカケ(くらかけ)、トウビガス(とうびがす)、サイノ谷(さいのたに)、ダンノ谷(だんのたに)、心谷(こころだに)、長坂(ながさか)、ヤブガ谷(やぶがたに)、寺坂(てらさか)、カモノ谷(かものたに)、大谷(おおたに)、アンノ坂(あんのさか)、井口(いぐち)、ヲゾ谷(おぞたに) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||