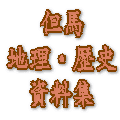 |
後(うしろ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後の概要《後の概要》 久畑から出石川の上流側、小坂峠側へ入った最初の集落。正保(1644-48)頃成立の国絵図に村名がみえる。 後村は、江戸期~明治22年の村。但馬国出石郡のうち。山名氏政滅亡後天正13年まで青木勘兵衛、同年から前野長康が領した。文禄4年からは出石藩領。明治22年高橋村の大字となる。 後は、明治22年~現在の大字名。はじめ高橋村、昭和31年からは但東町の大字。平成17(2005)年より豊岡市の大字となる。 《後の人口・世帯数》 25・11 《後の主な社寺など》 昭和60年圃場整備中に後天神遺跡から縄文初期の楕円文土器片・石鏃・石匙などが出土し、古墳時代の竪穴式住居跡も完全な形で発見されたという。  右の山の上に鎮座、下から見えるが、行かなかった。かつて霊代が盗難にあい、このとき下総国にあるとの託宣があり、これを再度勧請したと伝える。享保3年(1718)と弘化2年(1845)に本殿を再建(兵庫県神社誌)、享和3年(1803)には神像・観音像を再造した。同社境内は中世の城跡と伝え、古鏡・鉛玉などが発掘されている。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 後の主な歴史記録後の伝説『但東町の民話と伝説』二の宮さま(後)
昔むかし、久畑から夜久野に行く街道沿いに、「二ノ宮さま」と呼ばれ、村人達のよりどころとなっている神社がありました。 そのご神体は、たいそう手の込んだ彫刻が施されており、とても立派なものでしたので、村人達は火の用心の神様である「二ノ宮さん」を、いつも大切に祀っておりました。 そんなある朝のこと、食事の前に「二ノ宮さま」参りを日課としている村の長老が、その朝も杖をつきながら神社にやってきて、おっと驚きました。 「こりゃ、どげんしたんじゃ!扉がめげとるがな!あっ、ない!ご神体が盗まれとるぞ!」 びっくりした長老は、よぼよぼの体のどこからそんな大声が出たのか、とにかく天と地がひっくり返るほどのありったけの声で、 「たいへんじゃあ-!どろぼうじゃあ-!」と叫んでおりました。 長老のただならぬ叫び声を聞いた村人達はみな驚いて外に飛び出すと、神社に向かって一目散に走り、さきけどの大声で腰のぬけた長老の指さす壊された扉を見て、 「たいへんじゃ!ご神体が盗まれとるぞ!」 「ほんに、二ノ宮さまがあらへん!」 「だれがこぎゃあなひどいことを!」 「二ノ宮さまがなあなったら、今夜から火が心配で、安心して眠らりゃあせんぞ!」 みんな口ぐちに叫びました。ご神体がないとなると、一日たりとも安心して過ごせないのです。村人達は壊された扉の前で、途方にくれました。 しばらくして、何やらじっと考えていた長老が、みんなにある提案をしました。 「みな、どうじゃろ。ご神体があまりに立派なものだったんで、盗まれたんじゃ。それにこの街道沿いは、どこのだれともわがらん者も多ぜい通る。神社は村の中を通らにゃ行けんあの山腹に移し、銅鏡を二ノ宮さまの代わりにして、今までと同じように大切にお祀りすりゃ、きっと火から守っておくれると思うが、みな、どうじゃろうな?」 「そりゃ、ええ考えじゃ。」と村人達は、この案に大賛成で、さっそく神社は銅鏡のご神体と共に村の山腹に移されました。 このことがあってから何日か経ったある夜のこと、昼間の畑仕事ですっかり疲れた長老は、夕食を済ませると早ばやと床に着いてぐっすりと寝入っておりました。 「これ、長老や、起きてくれ!わしじゃ、二ノ宮じゃ。これ、長老や!。」 自分を呼ぶ声に目を覚ました長老は、盗まれたご神体が枕元に立っているので驚いて、 「あっ、二ノ宮さま!ほんとに二ノ宮さまじゃ!よう帰っておくれんさった。心配しとりましたが、ご無事で何よりでした。」 「いや、わしは帰ってきたのではない。わしのいる所は常陸の国とやらで、とっても遠いところなんじゃ。二度と帰れんじゃろ。だがいつもお前たちに大切にしてもらったことは一日だって忘れてはおらんぞ。こんな遠くからだが、今後もお前たちの村から火が出ないよう、ずっと守ってやるぞ。わしのせめてものお礼じゃ。」 そうお告げになるとご神体はスーと消えてしまいました。 あくる日、長老はさっそく村人達を集め、この不思議なでき事を話しました。みんな二ノ宮さまが元気でいることを喜び、今まで以上に神社を大切にお祀りしました。 その後、この村では、火事になりかけるとどこからともなく「火事だあ!火事だあ!」と不思議な大声が聞こえたり、重い病で寝たきりの人が、その時だけ起きて火を消したりして、数百年来、一度として大火になったことはありません。 二ノ宮神社は後部落にあり、むかしこの神社があったあたりは、今でも「二ノ宮」の字で呼ばれております。 後の小字一覧『兵庫県小字名集Ⅱ但馬編』【後】(うしろ) 川原(かわら)、岸ノ下(きしのした)、家ノ下(いえのした)、新井谷(にいたに)、安田(やすだ)、五升代(ごじょうだい)、水ノ手(みずのて)、天神(てんじん)、枕木谷(まくらぎだに)、向山(むこうやま)、枕木(まくらぎ)、棒谷(ぼうだに)、奥山(おくやま)、畑谷(はただに) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||