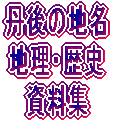 |
平田(ひらた)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平田の概要《平田の概要》 佐濃谷川下流西岸の「久美浜温泉」があるあたりである。 平田村は、江戸期~明治22年の村。はじめ宮津藩領、寛文6年幕府領、同9年宮津藩領、延宝8年幕府領、天和元年宮津藩領、元禄10年幕府領、宝暦13年但馬出石藩領、天保6年からは幕府領。明治元年久美浜県、同4年豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年田村の大字。 平田は、明治22年~現在の大字。はじめ田村、昭和30年からは久美浜町の大字。平成16年から京丹後市の大字。 《平田の人口・世帯数》 253・73 《主な社寺など》  『京都府熊野郡誌』 〈 祭神=軻偶突智命。 由緒=当社は元小字宮ノ谷に鎮座ありしが、文化の頃現地に移転せりといひ伝ふ。而して維新前は八代龍王と唱へしが、維新後八代神社と改称せり。社殿は享和二年十一月の再建にして拝殿は大正九年の建築に係る。 氏子戸数=七十三戸。  『京都府熊野郡誌』 〈 日蓮宗妙顕寺末 本尊=妙法蓮華経宝塔多宝如来釈迦如来。 由緒=当山の開基を按ずるに、成就院日相師は葦原村妙泉寺三世の住職たりしが、当村の信徒特に師を請じ一寺を建立して妙長寺といふ、時に明暦二丙申年五月なりき、宝暦年間偶々火を失し、堂宇悉く鳥有に帰す、天明四年当寺十五代の住職晴開院日道師本堂庫裡を再建し益々殷賑を図れりといふ。 『京都府熊野郡誌』 〈 一乗寺は天和二年の「丹後国寺社帳」に臨済宗寺院として記されている。 《交通》 《産業》 ♨ 久美浜温泉  昭和48年大阪市の山田六郎氏は、下和田に50゜C余の温泉を掘り当てた、久美浜温泉としてにぎわっている。 「100人入れるという大露天風呂は丹後随一の規模です・薬草風呂・ジェット風呂・泡風呂・打たせ湯・内風呂もあります」とのこと。 三分から平田に通じる府道わきにある。周辺一帯は昭和初期の不況時代に裏山を開いて果樹園をつくった。二十一世紀のいまは京都府の「二十世紀梨」の豊かな中心地となっている。  地域を豊かにしていくとはこうした事業であって、米軍基地などは将来に禍根を残すだけのもの、何一つ富は残すまい。 平田の主な歴史記録『丹哥府志』 〈 【法栄山妙長寺】(法華宗) 【萱谷山一乗寺】 一乗寺の後山を萱ケ岡といふ、其上に白岩氏の城墟あり、今白岩氏の子孫残る。昔金麻呂親王夷賊退治の頃竹野浦より伊根浦へ舟にのらせ給ふ、陸に上りて其舟を見させ給へば当に舟水のいらんとする處に蓋く蛤吸付居たり、故を以て其時随従の者子孫に至る迄蛤は食まじと誓ひしとかや、其子孫なりとて此村に蛤を喰ざるものあり、伊根浦にも平田といふ處あり爰にも蛤を喰ざるものあり、其舟の付し處なりといふ。 『京都府熊野郡誌』 〈 字平田は往古小字菅谷附近に七戸の住民ありしが、白岩与左衛門の祖先現今の平田に移住せしを始とし、暫時移住し来り、子孫繁栄して現今の部落をなせりといふ。されば現今にても七軒百姓といへる家筋あり、皆旧家にして一般に尊敬せらる。 平田の小字一覧平田(ひらた) 日光寺 志ケノ下 加悦地 溝田 加悦前 坪ノ内 加悦ケ谷 立道 加悦屋敷 大門 養老 神田ケ鼻 上大門 加悦ケ鼻 大茶園 加悦ケ岡 引藪 屋敷裏 葉割 中田イ 赤梨子 才垣 熊田 加悦ケ谷口 ヲテヲロカ ヲロカ 小柳 弥治郎谷 主ケ谷 岩谷口 赤梨 岩谷 折坂 家ノ上 立長 湯田 樫ケ谷 鍛冶屋敷 ヲテジ 宮ノ下 上宮ノ下 大清水 砂畑 家ノ浦 家ノ前 折坂地 道東 手水垣 家ノ下 北谷 段墓 稲葉 上ミ地 戸鼻 脇ノ下 石クロ 六反田 松葉 掛田 大木元 下半田 下川原 三百分 川原 堂ノ前 大ノ田 場市 越地 鉄峠 吉ノ界 桜ケ岡 向町 堂ノ奥 堂ノ上 茨谷 前田 角田 池尻 奥茨谷 アタ町 宮ノ先 宮ノ口 宮ノ尾 堂分 奥神田 寺ノヲテ 宮ノ谷 上ノ段 家ノ向 寺ノ下 下モ地 家ノ脇 家ノ北 狭間 下稲木 岡稲木 稲木 四反田 和田 茶円 戸井口 大池 下和田 竹乗 不動岡 池ノナル 寺ノ界 別惣 下ノ谷 岡垣 不動ノ下 シイ田 ミゾ田 池ノ成 カナガ花 カヤガ谷 熊作山 中尾 ジヤジヤガ谷 大成 クラ越 十四ケ谷 兼ケ尾 岩谷奥 ミイガテイ 松尾 モロガ谷 惣カン山 ガマガ谷 一本松 コエジノ奥 一木松 カナ峠 ヲスノカリユフ アタマチ アナクロ谷 ドウブン ヲカンダ 土井口 才ノ神 コモリ山 古城 下山 カヤ屋敷 木+室ケ谷口 屋敷浦 加悦覆 柏ケ鼻 三ノ堤 石風呂 半田 丸町 家ノ西 捨四ケ谷 松尾上リ口 志ノケノ下 中田イ 惣作山 同名の伊根湾奥の平田と関係がありそうだし、また「加悦」の小字も見られる。「加悦」という小字は三分にもある、たぶんその両地にまたがる地ではないのかと考えるが、私には正確にはわからないのだが、丹後海賊の根拠地とかいわれる。 『宮津市史』には、 〈 中世の物流を担った地域の廻船業者は、政治的状況によっては海軍力として働くこともあり、敵対する勢力からは海賊と呼ばれた。大永七年(一五二七)に丹後の海賊が蜂起して若狭の浦々を襲い、資材を奪って放火を働いたため、要港の西津・小浜では乱杭・逆茂木を作って防いでいる。この時、若狭武田氏は越前の朝倉氏の援軍を仰いで加佐郡に出兵しており、この海賊行為を働いた勢力は加佐郡の沿岸を根拠にしていた(九八三)。加佐郡は永正十四年(一五一七)ごろに武田氏に割譲されたが、一色方の残党の反乱が頻繁に起こっており、この海賊行為もその一つであったと考えられる。また天文九年には丹後の海賊が越前を襲った報復として、越前の船五百艘が加佐郡を襲っている(一○○○)。 その後、元亀元年(一五七○)には丹後の海賊が但馬の海賊と結び、当時、毛利氏の領国だった出雲国・隠岐島の沿岸を荒している(一○五八-六七)。これは毛利氏によって領国を追われた尼子氏の復興を期する尼子勝久が但馬・丹後の勢力と結んで起こした戦闘行為であり、のちに織田信長と連携することになる。この時の丹後海賊がどこの勢力を指していたかについては、久美湊に近い平田の集落に「加悦」の地名が多く残っており、ここは細川藤孝宛て織田信長黒印状にその名が見える加悦観十郎の根拠地であった可能性が高い。加悦観十郎は出雲と伯耆の国境で毛利方の水軍と戦い、多数の首を討ち取った武将の一人であった。但馬の勢力と連携して動いたこの時の丹後海賊は久美湊近辺を根拠とし、加悦観十郎は水軍の長であったと考えられる。 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『京都府熊野郡誌』 『久美浜町史』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2014 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||