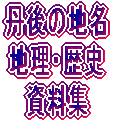 |
丸山(まるやま)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸山の概要《丸山の概要》 女布の川向かいの集落で、もと女布から移り住んだと伝えられている。 丸山村は、江戸期~明治22年の村。はじめ宮津藩領、寛文6年幕府領、同9年宮津藩領、延宝8年幕府領、天和元年宮津藩領、享保2年からは幕府領。同20年より久美浜代官所の管下。 寛永年間に宮津藩の年貢取立てが厳しかったため、丸山18軒の百姓が4年間逃散した。永留村の野村佐右衛門は4年分83石を宮津藩に上納し、寛永6年、次男を丸山に別居させ、村人を呼び戻して丸山村を再興したと伝えている。明治元年久美浜県、同4年豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年下佐濃村の大字となる。 丸山は、明治22年~現在の大字名。はじめ下佐濃村、昭和26年佐濃村、同33年からは久美浜町の大字。平成16年から京丹後市の大字。 《丸山の人口・世帯数》 114・37 《主な社寺など》  府道20号線(永留網野線)の佐濃谷川に架かる丸山橋↑から西向き。左手(上手)の山々に古墳や遺蹟がある。  丸山の地名のように当地は古墳が多い。 (『京丹後市の考古資料』より→) 「倭国大乱」の証拠ではのウワサある、弥生墳墓も見られる。 邪馬台国は意外に近いのかも… 豊谷墳墓群 堤谷古墳群 堤谷窯跡群 豊谷遺跡 《交通》 《産業》 丸山の主な歴史記録『丹哥府志』 〈 『京都府熊野郡誌』 〈 『久美浜町誌』 〈 丸山の「野村家(大家)文書」には野村家の先祖のことが詳しく書かれている。 そのなかに丸山の逃散を語るものがある。 本祖野村佐右ヱ門は丹後国熊野郡永留村の内、本谷に住む。(中略)高祖の佐右ヱ門は元来理非に明かるく親切だった。大庄屋をうけたまわること数代にも及んでいた。その頃宮津御公儀は、高十二万石。京極丹後守殿は御身分にも似ず慈悲心がなく、我欲のみつのられたが、諸役人に申しつけ、御年貢も御用金の名を以て取りたてがことのほか厳しく、百姓の困難は例えるに言葉の無い有様だった。 (丸山)十八軒の百姓たちは、生地に住めなくなって、先祖よりの家もあとに見て転住、四ヶ年は掛金年貢も不納の有様だった。このようなわけで御公儀も困られ、御評議された。 このようなときに、祖先佐右ヱ門は生来慈悲の心が厚い人だったので、これを見て気の毒に思い、四ヶ年分八十三石を宮津藩に上納した。殿は、この義心を感じられ、高八十三石の御免状一本、□の御高札並に馬一疋、苗字、表門をさし許された。 佐右ヱ門には二人の男の子があったから、その二男を寛永六年丸山村へ別家し、以前(丸山に)住人でいた百姓達を呼びもどし再び丸山村を再興した。こうして、宮津表へ御年貢の上納も滞りなく行ったという。 「野村家文書」によれば本祖野村佐右ヱ門は慶長三年(一五九八)日蓮宗に改宗し、自分一人の力で本谷に宗覚山妙久寺を建立している。野村家の先祖は室町時代丹後の守護であって一色氏と関係があり、若狭より来任したと言われており、後に豪農となった。それにしても自分一人で一寺を建立するくらいだから、相当な力をもっていたのであろう。 本祖佐右ヱ門に対して高祖佐右ヱ門と記されているように代々佐右ヱ門を襲名している。 丸山家逃散の時期はいつごろであろうか。二男が丸山に別家したのが寛永六年(一六二九)とすれば、寛永元年か二年ごろに始まったと考えてよいであろう。田辺城にいて十二万三千百余石の知行を持つ京極丹後守高知が元和八年(一六一三)に死去すると、その遺命により長男京極丹後守高広が七万八千百余石を分けられて、宮津に築城を始めた。寛永二年城郭がほぼでき上がり丹後守高広は宮津に移住するのであるが、年貢・御用金の取り立てが厳しくて領民が苦しんだのは、宮津城建設と深い関係があったと思われる。 丸山村は女布より移り住んだ比較的寂しい村であり、佐濃谷川の洪水の被害を受けやすく、生活の条件が悪かったから、領主の取立てがあまりにひどいと田畑を捨て、家を捨てて逃げることになる。それにしてもたった一八戸ばかりの逃散でも領主は頭をかかえる。野村佐右ヱ門の年貢代納によってほっとする。領主は封建支配の秩序が保たれないことを最も恐れたのであろう。 『久美浜町史・史料編』 〈 字丸山小字豊谷に所在する。 遺跡は佐野谷川左岸の西から東へ伸びる丘陵上に立地し、堤谷古墳群A一号墳・豊谷経塚の下層で検出された。 木棺墓の一号墓と方形周溝墓状の二号墓からなる。一号墓は長さ二・三メートル、幅一・五メートルの墓壙に長さ一・九メートル、幅一・一メートルの木棺を納めていた。木棺の中からは石鎌二二点が出土し、墓壙上かと思われる地点から破断した打製石剣(石槍の可能性もある)が出土した。石鍬は先端を欠損したもの、もしくは先端のみのものが含まれ、体内に打ち込まれた可能性を示唆している。二号墓は三方を溝によって区画された方形周溝墓である。南辺には溝が存在しないため南北の規模は明らかではないが、東西の一辺は五メートルを測る。この区画の中央部に長さ二・六メートル、幅一・八メートルの墓壙を掘り、長さ一・八メートル、幅一・一メートルの木棺を納めていた。棺内からは何も出土しなかったが、墳丘の北部から溝の北側にかけて弥生中期の土器片が出土した。これらの出土品から豊谷墳墓群は弥生中期初頭、畿内第Ⅱ様式併行の時期であると推定されている。 『京丹後市の考古資料』(図も。1号墓の埋葬施設と石鏃の出土状況) 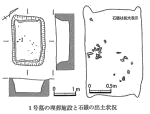 〈 所在地:久美浜町丸山小字豊谷 立地:佐濃谷川中流域左岸丘陵上 時代:弥生時代中期前葉 調査年次:1991年(府教委) 現状:消滅(国営農地) 遺物保管:丹後郷士資料館 文献:C081 遺構 豊谷墳墓群は、丘陵上に築かれた2基の弥生時代の墳墓である。1号墓は、眼下に佐濃谷川流城を望む標高62mの丘陵頂部に位置する。堤谷Al号墳(126)が同じ場所に築かれるため墳形については不明な点が多い。埋葬施設の北側で見っかった土坑を区画溝と考えた場合は、一辺5mほどの方形の墳丘が復元できる。表土掘削中に、打製石剣が出士している。埋葬施設は、長辺2・3m、短辺1・5m、検出面から墓壙底までの深さ0・7mを測る。墓壙底の形状から1・9m×1・1mの組み合わせ木棺が据えられていたことがわかる。墓壙底から22点の石鏃が出土した。出上状況は図で示した。 2号墓は、1号墓から東へ40mほど下った標高56mの地点に位置する。墳丘上には、平女時代後期の経塚遺構〔139豊谷遺跡)が築かれている。墳丘は丘陵側に尾根を切断する全長6・5m、最大幅1・5m、深さ0.8mの溝が掘削されている。丘陵先端側には幅0・4m、深さ0・4mの溝が、「コ」の字形に配置されていたものと考えられる。この溝内および墳丘から弥生土器の細片が出土している。埋葬施設は、溝に囲まれた一辺4m程度の墳丘中央部に築かれている。墓壙は、長辺2・6m.短辺1・8m、検出面からの深さ0・7mを測り、1・8×1・1m規模の木棺を収めていた。棺内からの出土遺物はない。 遺物 表士掘削中に出土した打製石剣(33)は、基部側約2分の1を欠損し、現存長8・7cm、幅3.4cm、最大厚1・Ocmを測る。無斑晶安山岩製である。二次調整も丁寧な逸品である。石鏃は、計22点出土した。先端部を欠損したもの、先端部のみのもの、二つに割れているものを含む。折先端部の欠損、先端部のみの出土などは、人骨との衝撃時に発生したことが考えられ、人体に打ち込まれた可能性がある。小さく、軽量のものが多いが、形状、重量ともにばらつきが大きく、石材は、無班晶安山岩、流紋岩、砂岩と多種多様である。2号墓では、墳丘上および溝内から弥生土器の小片が出土した。甕の口縁部に刻み目を持ち、壺や甕の頸部及び体部に櫛描直線文、廉状文が見られる。壺底部の形状も含めて概ね中期前葉(畿内第Ⅱ様式並行期)に属するものと考えられる。 意義 丹後地域では、弥生時代前期末に扇谷遺跡の隣の丘陵の七尾遺跡(50)で一辺およそ10mを測る2基の台状墓が見つかっている。当墳墓群は、墳丘区画が一辺5m未満と極めて規模の小さな墳墓である。埋葬施設は、1基ずつである。1号墓では、折損した打製石剣、多数の石鏃の出土など戦いに関する被葬者が想定される。久美浜町と隣接する豊岡市では、前期末から中期前葉にかけての山の上の方形周溝墓群が検出されている。ここでも埋葬施設は1基もしくは2基で、やはり複数の鉄鏃が出土しており、共通性が高い。中期中葉になると、居住域に隣接して、奈具墳墓群(6)や寺岡遺跡(与謝野町)や奈具岡遺跡の貼石墓群(6)など長方形墳墓が営まれるようになるが、当墳墓群はそれ以前の丘陵上の墳墓の具体相を示す数少ない資料である。 『久美浜町史・史料編』 〈 字丸山に所在する。 古墳群は佐野谷川中流域左岸の丘陵上に立地する。古墳群の立地する丘陵は小さな谷を挟んで二筋あり、南東側の尾根上に立地する支群をA支群、北西側の尾根上に立地する支群をB支群と呼ぶ。 A-一号墳は長さ一八メートル、幅一六メートルの長方形の方墳である。弥生時代中期の豊谷一号墓と墓域が重複しており、豊谷一号墓に伴う溝と見られる遺構を一部破壊している。 墳頂部には主軸を墳丘の主軸に揃えた長さ八・五メートル、幅二・六メートルの第一主体部と、長さ二・八メートル、幅 〇・九メートルを測る第二主体部が設けられている。第一主体部は長さ五・九メートルもある長大な組合式箱形木棺で、内部は四室に区分されていた。この内西副室には竪櫛、玉類、刀子が、東主室には大刀、刀子、鉄斧、直刃鎌、東副室には鉄斧が副葬されていた。第二主体部には副葬品は見られない。この古墳の時期は竪櫛、直刃鎌が副葬されるが曲刃鎌が副葬されない点から古墳時代中期前葉であると考えられる。 B-一号墳は直径二〇メートルの円墳である。墳頂部には箱形木棺を直葬した二段墓壙の主体部を一基検出した。棺内には二重口縁壷を転用した土器枕がニヵ所に置かれ、南側の土器枕の北東側に鞘入りでハバキが残存する刀子が一点副葬されていた。この古墳の時期は二重口縁壺が布留二式に属することから古墳時代前期後半であると考えられる。 B-I三号墳は一辺一〇メートルの方墳である。墳頂部から箱形木棺を直葬した主体部が二基検出された。墓壙一には長さ二メートル、幅三〇センチの長方形にベンガラと見られる赤色顔料が検出され、土層断面の観察からもこの範囲が木棺であると考えられる。棺内からは鉄鏃約一〇本が一束となって出土した。この古墳の時期は鉄鏃が長頸鏃で、主体部が木棺直葬であることから、古墳時代中期末~後期前半と考えられる。 B-五号墳は地滑りによって墳形が崩れているが、長軸二〇メートルの楕円形墳であったと考えられる。墳頂部には箱形木棺を直葬した、二段墓壙(東側は三段)の墓壙一、同じく箱形木棺を直葬した二段墓壙の墓壙二が設けられていた。また墓壙一の埋葬後、墓壙二が埋葬される以前に木柱が一基立てられていたと見られる。墓壙一棺内には鼓形土器転用の土器枕が置かれ、ヤリガンナ一点が副葬されていた。また墓壙上には土師器複合口縁壺、小型丸底壺などが供献されていた。この古墳の時期は出土した土器が布留二式に属すことから、古墳時代前期後半であると考えられる。 B-7号墳は長さ一ニメートル、幅一〇メートルの長楕円形を呈する円墳で、墳頂部には割竹形もしくは舟底状木棺を直葬した一段墓壙の主体部を一基設けていた。墓壙内の木棺裏込土上から鉄剣一振が出土した。 B-一〇号墳は長さ一ニメートル、幅九メートルの長方形を呈する方墳で、墳頂部に一段墓壙の主体部一基、南北の区画溝内に溝内埋葬がそれぞれ一基ずつ設けられていた。墓壙上には小型器台、鼓形器台、高坏が供献されていた。古墳の時期は出土した土器から古墳時代前期末と考えられる。 B-一一号墳は削平により規模が不明なものの、長方形の方墳である。墳頂部に三基と西側墳裾部に一基の主体部を設ける。この内墓壙三は墓壙二に隣接する土器棺墓で、二重口縁壷を棺身に用いる。この壺は擬口縁の稜が鋭く、布留二式でも古く位置づけられる。古墳の時期はこの二重口縁壺から古墳時代前期後葉に位置づけられる。 『京丹後市の考古資料』 〈 所在地:久美浜町丸山小字豊谷 立地:佐濃谷川中流域左岸丘陵上 時代:古墳時代前期~中期 調査年次:1989、1990年(府教委) 1988、1991年(府センター) 現状:24基のうち13基が消滅(国営農地) 遺物保管:丹後郷土資料館、市教委 文献:CO81、C091 遺構 堤谷古墳群は、佐濃谷川右岸中流域の標高55~62mの丘陵上に位置する総数24基からなる古墳群である。東の尾根上に位置するA支群9基と西の尾根上に位置するB支群15基から構成される。この内、A支群の丘陵頂部に位置する2基(1号墳、2号墳)とB支群11基が調査されている。 A支群は、中期に、B支群は主に前期に属する。ここでは、調査例の少ない中期のA1号墳について述ぺる。A1号墳は、佐濃谷川を望む標高62mの丘陵頂部に位置する一辺18mの方墳であり、A支群最大規模を測る。墳丘は、地山整形による盛土をもたない、墳丘裾部の不明瞭なものである。埋葬施設は、墳頂部中央部から中心埋葬施設が、その南側から寄り添うように小型の埋葬施設が検出された。中心埋葬施設は、主軸をほぼ東西にとる長大な二段墓壙を持つ。墓壙の規模は、上段で8・5X2・5m、下段で6・9×1・4mを測る。墓壙底には、全長5・9mを測る長大な組み合わせ式木棺が置かれていた。組み合わせ式木棺は、長い側板を短い小口で挟むもので、木棺内は、さらに3つの仕切り板で4つに区画されていた。棺内の区画を便宜上西から第1区画、第2区画、第3区画、第4区画とする。第1区画は、全長O・9mを測り、仕切り板に接して、竪櫛2、勾玉1、臼玉49および鉄刀子(18)が出士した。第2区画は4区画の内最も大きく、全長2・1mを測る。主たる埋葬区画と考えられ、第1区画との仕切り板から0・5mの位置から漆皮膜が出土した。第3区画は、長さ1・7mを測り、鉄刀1、鉄刀子1、大小の鉄鎌各1および鉄斧が出土した。第4区画からは鉄斧(21)が出土した。小型の埋葬施設は、2・8×0・9mを測る木棺墓である。 遣物 墳頂部表士直下から土師器片が出土している。中心埋葬施設棺内からは、鉄製品と装身具が出土した。 意義 丹後地城では、古墳時代前期末から中期にかけて、棺内を区画した長大な組み合わせ式木棺が、日ノ内古墳(与謝野町)、八坂神社西古墳(26)、構谷2号墳(23)など20m前後の方墳および円墳に採用されている。当古墳もその一例を示すものであるが、礫床がないこと、被葬者が一人であることなどは新しい要素であろう。築造時期は、5世紀前葉から中葉に位置づけられる。 『京丹後市の考古資料』 〈 所在地;久美浜町丸山小字堤谷 立地:佐濃谷川中流域左岸丘陵上 時代:飛鳥時代~奈良時代 調査年次:1991年(府教委) 現状:消滅(国営農地) 遺物保管:丹後郷土資料館 文献:C089 遺構 堤谷窯跡群は、南向き丘陵斜面の尾根線に近い斜面上方、標高およそ60mの地点から検出された3基の窖窯と灰原からなる。 1号窯は、全長6・9m、床面最大幅1・6m、傾斜角31度を測る地下式の窖窯で、7世紀前半から中葉にかけて須恵器を焼成した後、8世紀初頭に補修を行って再び須恵器を焼成している。補修にあたっては、壁や天井を修理するとともに床面には、7世紀前半の須恵器の杯身.杯蓋を床面に塗り込んで焼台としていた。 3号窯は1号窯にやや遅れる7世紀中葉に操業された全長4・5m、傾斜角27度の窖窯である。8世紀に天井部を除去して焼土坑として利用されている。 最も遅くに築かれた2号窯は、8世紀前葉に営まれた焼成部に段を持つ半地下式の窖窯である。全長5・7m、床面最大幅1・3m、傾斜角32度を測る。瓦と須恵器を焼成しているが、矢田八幡神社所蔵資料にも正格子叩きの平瓦と行基葺き式の丸瓦があり、同時期の瓦窯が存在する可能性が高い。最終操業は瓦のみの焼成である。 遺物 コンテナに130箱分の須恵器と瓦が出土した。遺物の帰属時期は、Ⅰ期〔7世紀前葉から中葉)とⅡ期(8世紀初頭から前葉)に分けることができる。1号窯と3号窯で焼成されたⅠ期の須恵器には、小型品の紡錘車から、蓋杯、そして大型品の横瓶や甕まで各種ある。杯底部、杯蓋天井部はヘラ切り不調整のものであり、湯舟坂2号墳(148)奥壁付近で出土したヘラ切り後ヘラケズリを行っている資料に後続する。 1号窯と2号窯で焼成されたⅡ期の須恵器は、杯蓋内面にかえりをもつ8世紀初頭のものから杯Bに法最の分化が認められる8世紀前葉のものまでが含まれる。 Ⅰ期同様、杯、皿、壺、甕など多くの器種が見られる。 2号窯出士の瓦は、軒丸瓦、軒平瓦、鬼板、丸瓦、平瓦、熨斗瓦、隅切瓦と道具瓦が各種そろっている。軒丸瓦(1、2)は、9葉の単弁蓮華文である。三宅廃寺(兵庫県器岡市)で同系譜のものが出土している。軒平瓦は、有段の顎部をもち、瓦当部は無文である。鬼板は、高さ20㎝、幅24㎝と小振りのものである。鬼板を支えるための捧状土製品も出土している。丸瓦は行基葺きの1点を除きすべて玉縁式のものである。平瓦は、桶巻き作りによるもので、裏面(凸面)に斜格格子叩きを行ったのち、3分の2を撫で消すものと、撫で消し調整を行わないものがある。なお、斜格子叩きは、すぺての平瓦(軒を含む)に同一の叩き板が使用されている。 意義 丹後半島部における古代の窯業遺跡で、発掘調査が実施されているのは、当遺跡を含め5窯跡のみである。7世紀に操業されているのは、当窯跡群と新宮窯跡(90)で、8世紀中葉には、阿婆田窯跡(91)、遠慮遺跡(34)が、そして10世紀には、名地谷窯跡(92)が操業されている。これらの状況から当窯跡は、丹後半島部最初の須恵器製作工房の一つと考えられる。 堤谷窯跡Ⅰ期にあたる7世紀前半には、堤谷1号窯跡・3号窯跡で、小型品から大型品までこの時期数多く営まれる横穴墓から出上するほぼすぺての器種が生産されている。杯身、杯蓋のヘラ切り後不調整の状況は、宝珠つまみをもっ杯蓋が出現している畿内の状況とは異なる地方窯の様相を示す資料である。 堤谷窯跡Ⅱ期にあたる8世紀前半には、1号窯が須恵器の焼成のために修理を経て操業を再開する。次いで3号窯が瓦焼成を目的として操業を開始する。白鳳期的な特徴を示す瓦が8世紀の前葉に焼成されている。この時期、丹後地域唯一の白鳳寺院である俵野廃寺が佐濃谷川の河口部からほど近い網野町木津で営まれており、当窯での瓦焼成の開始もそれと連動するものと考えられよう。なお、堤谷窯の上流にあたる横枕窯跡(135)出土資料や小桑出土とされる矢田八幡神社所蔵資料にも正格子叩きの平瓦と行基葺き式の丸瓦があり、同時期の瓦窯が存在する可能性が高い。 『久美浜町史・史料編』 〈 字丸山小字堤谷に所在する。 三基の窯跡および灰原が検出されている。窯跡は、丘陵南側斜面に築造されており、一号窯→一・三号窯→二号窯の順に操業する。また二号窯は瓦陶兼業窯である。 一号窯は全長六・九メートル・床面最大幅一・六メートルを測る地下式窯、三号窯は全長四・五メートル・床面最大幅一メートルを測るものである。また二号窯は、全長五・七メートル・床面最大幅一・三メートルを測る半地下式窯であり、 焼成室には奥行二五センチメートルほどの段が一一段設けられている。 出土遺物には、須恵器および瓦がある。須恵器は、古墳時代からの流れをくむものと律令期のものがみられる。 前者には、杯蓋・杯身・高杯・平瓶・甕などがある。一・三号窯が該当する。灰原には無遺物層を挟んでおり、その上下では杯蓋・杯身のヘラ削りの有無や法量に形式差がみられる。下層は飛鳥時代前期、上層は飛鳥時代中期の所産と思われる。また後者には、杯蓋・杯身・皿・横瓶・壷・甕などがある。一・二号窯が該当する。灰原第Ⅰ層とそれ以外では形式差がみられる。後者は奈良時代初頭~前半、前者は奈良時代前半の所産と思われる。 瓦は、二号窯から出土した軒丸瓦・軒平瓦・丸瓦・平瓦・鬼瓦・道具瓦がある。軒丸瓦(一)は単弁九葉蓮華文のものである。径一七センチ前後を測り、中房は一+五の蓮子がみられる。軒平瓦は無文のものである。平瓦は桶巻四枚作りのものであり、凸面には斜格子叩きを施す。調整手法などから二分類されている。丸瓦は一点を除き玉縁式のものであり、玉縁部は凸面側を削り出す。鬼瓦(二)は、高さ二〇センチ・最大幅二四センチを測る蓮華文のものである。中央に釘孔を有する。瓦は、二号窯の灰原第Ⅱ層と第Ⅰ層に含まれており、間に須恵器のみを焼成していた時期があるようである。出土した須恵器の年代観から、これらの瓦は奈良時代前期を下限とするものと思われる。 軒丸瓦・軒平瓦ともに同笵のものはみつかっていない。軒丸瓦は、中房の大きさが異なるが豊岡市の三宅廃寺出土のものと類似することが指摘されている。また鬼瓦は、文様が全く異なるが網野町俵野廃寺のものと釘孔を有する点や法量が類似している。 肥後弘幸氏によれぽ、同じ佐濃谷川流域の上流部に位置する字佐濃丙の矢田八幡神社には、字小桑採集の丸瓦・平瓦が所蔵されており、出土位置から瓦窯の可能性が高いという。また字小桑では、これとは別に、内容は不明ながら瓦陶兼業窯の横枕窯跡が存在する。 これらの資料から、佐濃谷川流域には、堤谷窯跡とともに複数の瓦窯があったことが推定される。これらの窯跡の供給先は不明であるが、熊野郡内において当該期の古代寺院の存在をうかがわせる資料として評価できる。 『京丹後市の考古資料』 〈 所在地:久美浜町丸山小字豊谷 立地:佐濃谷川中流域左岸丘陵上 時代:平安時代後期~鎌倉時代 調査年次:1991年(府教委) 現状:消滅(国営農地) 遺物保管:丹後郷土資料館 文献:C081 遺構 豊谷遺跡は、弥生時代中期前葉の台状墓豊谷2号墓の半坦地を利用して造られた経巻を納めたと考えられる筒形容器を埋納した土坑(以下、経塚遺構と呼ぶ)11基から構成される遺跡である。土坑の構築に伴い、盛り土を行い区画を順次東側に拡張している。土坑はいずれも、筒形容器を入れるために作られたもので、多くは主土坑と呼ぶ1m程度の穴と主土坑の側壁もしくは底部に掘り込まれる埋納土坑からなる。埋納土坑には、経巻を納めたと想定され筒形容器が1もしくは2口納められていた。筒形容器には、竹製もしくは木製の容器が推定されている2号土坑を除き、土師製の筒形容器が用いられていた。筒形容器は、石で囲われているものが多い。土坑は、10号土坑を最初に築き、順次追加されたようで、土坑の形態や埋納土坑の位置に変化が認められる。主土坑には、腐植上が堆積していた。 遺物 筒形容器以外に、筒内から、和鏡や銭貨および炭化物が、主土坑内からは土師器皿や銭貨が出上した。経典に直接関わる出土遺物はない。和鏡〔9〕は、菊花双鳥鏡で、外縁付近に2個の穴があり、懸垂鏡として使用されたことがわかる。銭貨は、10号土坑の大型の容器から1点出土した以外は、5つの主土坑内から1点もしくは3点が出土している。開元通宝、景徳元宝、煕寧元宝がある。筒形容器は形態の変化に富む。10号土坑出土品は、多くの経巻を納めたのか特に大型である。 意義 豊谷遺跡は、経典の継続埋納の可能性を示す資料であり、丹後地域の経塚の多様性を示す一例として重要な資料である。土師器容器の形状、土師器皿などから平安時代末期から鎌倉時代初頭と位置づけられる。 『久美浜町史・史料編』 〈 字丸山小字豊谷に所在する。 遺跡は、丸山集落の南側、佐濃谷川左岸の丘陵上に立地する。 発掘調査によって、一一基の土坑群(一~一一号土坑)が発見された。土坑群は、丘陵尾根先端上の平坦面に営まれており、東西六メートル、南北四メートルの範囲で検出された。 各土坑は、一メートル弱の主土坑と筒形容器を埋納する施設である埋納土坑から構成されており、二号土坑を除く各土坑からは、土師製筒形容器が出土した。報告では、容器の出土位置と土坑の断面形態をもとに、土坑群を五つに分類(A~E形態)している。以下、それに従って説明したい。 A形態は、主土坑の底から段をつけずに横穴を掘るもので、一〇号土坑が該当する。一〇号土坑は、一辺一・○メートル、深さ〇・八メートルを測る方形土坑の北西隅に、奥行〇・六メートル、幅○・九メートルの横穴を穿つものである。横穴の開口部分は一枚の大きな板石によって閉塞され、この閉塞石の前面と下部から土師器皿が出土した。横穴の奥には二点の筒形容器が埋納され、左側の一号容器内部から和鏡が一面出土した。一〇号土坑は、他の遺構との位置関係から最も早く造営されたものと考えられる。 B形態は、主土坑内から一段窪めて横穴を掘るもので、一・三・四・六号土坑が該当する。主土坑の平面形は、隅丸方形または円形を呈する。一・四・六号土坑ではそれぞれ一点の筒形容器が、三号土坑では二点の筒形容器が埋納されていた。また、六号土坑では、横穴の前面部分から開元通宝が、容器の横から土師器皿が出土した。 C形態は、主土坑の一隅を垂直に落として、主土坑中央部から一段をつけた埋納土坑内に容器を安置するものであり、七・八・一一号土坑が該当する。主土坑の平面形は、不整形な楕円である。八号土坑の主土坑内には浅い小土坑が存在し、その縁から景徳元宝と土師器小皿が出土し、筒形容器内からも炭化物に混じり銅銭が検出された。 D形態は、筒形容器を主土坑隅部に納め、主土坑と埋納土坑との境界が判然としなくなったものである。五・九号土坑が該当し、主土坑自体の規模が縮小化傾向にある。容器を囲む石組みも簡略化が進み、九号土坑では石組み自体が消失している。五号土坑では、石組み周辺から三枚の銅銭が出土した。 E形態は、二号土坑が該当し、土坑の中心部に容器を安置するものである。主土坑と埋納土坑の違いはなく、筒形容器の周辺を円礫によって固定し、この上に低いマウンドを造り、方形を意識した集石を配する。さらに、その上部に盛土を行い、方形の石組みを造る。明らかに他の土坑とは性格を異にするものと考えられる。 土坑群は、遺構の位置関係・開口方向から、次のような築造過程が復元されている。まず、豊谷二号墓の墳丘を利用して一〇号土坑が造営され、次いで東側に平坦面を拡張して一・三・四号土坑が営まれる。ほぼ連続して六号土坑も造営され、次いで一一号→七・八号土坑の順につくられる。この時期、二度目の整地を行っている可能性が高い。最後に、五→九号土坑の順に営み、造営を終了する。なお、二号土坑の造営時期は不明である。 当遺跡は、平安時代末~鎌倉時代初頭に造営されたものと考えられる。経筒および人骨が出土しなかったことから、土坑群の性格について現状では判断がつかない。しかし、これほどの数の遺構群が発掘調査によって確認されたことの意義は大きく、丹後地域において埋経遺跡・中世墳墓の事例を検討する際に、良好な資料を提供しているものといえる。 丸山の小字一覧関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『京都府熊野郡誌』 『久美浜町史』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2014 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||