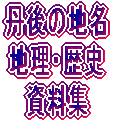 |
丹後弁(たんごべん)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹後弁の概要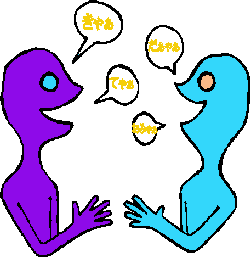 伴とし子さんがどこかで書いておられたが、舞鶴人にはもうまったくわからない。(伴さんは網野木津の出身) 何のこときゃぁな。これは生粋の奥丹人しかわからないのではなかろうか。 正解は、「貝買いかい」(貝を買いに行くかい)ということだそう。 「丹後弁を書き表す正字法はないので、「きゃぁ」としたり「きゃー」としたりするが、同じ発音である。 似ている、というのはまず耳で聞く調子が似ているということで、両方言とも特に二重母音aiがyaとなり似てると感じられる大きな要因となっている。舞鶴はこうした「きゃーきゃー言葉」はない。しかし元々の日本語には二重母音はなかったそうで、これこそがあるいは元々の日本語なのかも知れない。 イランコトするな、どえりゃーうまゃー、あっホーなん、ノソイなー、エリャーさんがオーチャクコクで、ワヤくそ、オージョウコクだぁ、とか単語も同じものがたくさん見られる。形容詞の用い方、仮定形、否定、断定の言葉など似ている所がヨーケあると言われる。 標準語というのは「山の手言葉」と言われるように、主に東京山の手に住む教養層なる者が使用する言葉を言っているので、何も普通の郷土は関係もない場所の歴史的にも関係もない言葉というか、この場所の日本語の一方言である。そこに住む人が勝手に使うのならそうすればよいが、関係もない土地の人がありがたがって自分の土地の言葉を忘れてしまわなければならないほどにありがたいものでもない。これらが今は日本の権力を握っているので今は支配者語になっているというもので、憲法解釈改悪などとナメたことを言っていると明日はひっくり返るかも知れない。 1986年の『読売新聞』に、 「わしゃは猫だ-や。名前はまだにゃ-。どこで生まれたか、じえんじぇん、うかばんわ-」(夏目漱石・吾輩は猫である)。京都府北部、丹後の高校生が「方言こそふるさと文化の原点。丹後弁を見直そう」と、この夏、祖父母から丹後弁を聞き取り調査。その成果を秋の校内文化祭で発表したところ「こんな言葉もあったんか」とか「今ごろの若いもんがなかなか感心だあ」と父母らにも好評、丹後文化見直しの一石となっている。峰山町の府立峰山高二年四組、蒲田武彦君(一六)ら四十六人。進学、就職などで都会へ出た先輩たちが、たまに帰省しても、ほとんど丹後弁を使わなくなっていることで寂しい思いをしたことなどがきっかけで、「生まれ育った丹後の方言をもっと大事にしよう」と、クラス全体の研究テーマに取り上げ、夏休みに入ってから地域ごとに十一班に分かれ各家庭の祖父母や地域のお年寄りたちから聞いたり図書館へ通ったりして調査。 私の手持ちのもっと古いものだと、『郷土と歴史32』(昭和17)に、「丹後方言を拾ふ」(黒田泰)があって、江戸期の各地の文献から単語を拾い、 結語 以上各書から丹後にて通用せるものを思ひつきに抜出したのであるが之を地方別にまとめて見ると奥羽地方十六関東地方十二中部地方二十六近畿地方六十五九州地方十六となり大体近き京坂語の影響を受けたることが最も多く遠隔の地方になるに従って其交流は少くなって居ることを知る。之の現象は一般的な傾向ではあるがその分布上各地方に大差なき浸潤を示して居ることは我が丹後方言の普遍性を物語るもので丹後人の言葉が全国的に通用せられることで比較的正しい言葉を使用してゐるのだとも云へる。更に厳密に言へば方言と称するものゝ多くが訛言であって所謂土俗語として丹後特有のものは少いといふことである。 そうした指摘はたぶん奥丹でも古くからもささやかれていたとは思われるが、誰も学問的に取り上げる者はなかったのであろう、それはそうだ、知る限りは一般に丹後と名古屋はそんなに繋がりがない、尾張弁と似ているわけがない、何をシロートが言うか、とそうしたくらいに見られていたのではなかろうか。学問は思い上がってはダメ、それは学問でも何でもない、真実の敵である、原発ゼッタイ安全・ゼッタイ事故を起こさないの大学者センセどものようなこと、このごろはゼッタイ大地震も大津波もありませんという安全神話に変わっている。学問でもわからぬことはいくらでもある、わからぬことの方がわかることよりもはるかにはるかに多い、言葉がなぜ似ているのかすらわからない、ド謙虚な者のみが真実に近づけるのかも知れない。 丹後と尾張は古代史では何かつながりありそうなことで、さっそく当サイトのHPに書いておいたのだが、それは数年前のことであった。尾張側からは丹後と似た曲があります、とかメールがきたりした。 意外な相似は府下のトピックスとなり、マスコミでも名古屋出身の女子アナが丹後に初めて取材に来て、ふるさとの言葉とよく似ているので、本当に驚きましたと話すほどになっている。 「地名」のはずのサイトだが、別に何でもアリ、とか言うのでもないが、そんな責任感から書いてみるようなことである。 尾張弁となぜ似ているか古代尾張氏と古代丹波氏の関係とか、中世の殿様の移動とかは考えられるが、何も尾張から来た者だけが丹後中世の支配者となっていたのではない、仮にそうであってもそれらは支配者の歴史である。方言は民衆語なので、支配者語とは別けて考えてみなければならない。両地方の民衆の歴史がわからないと、似ている本当の理由がわからない、しかし民衆は何もたいした遺物を残さないためにそうした過去は闇の中である。 方言学以外の分野から見てみると、 応神3年紀、十一月。処々の海人さばめきて命に従はず。則ち安曇連が祖大浜宿禰を遣して、其のさばめきを平げしむ。因りて海人の宰とす。 応神5年紀、五月。諸国に令して、海人と山守部とを定む。 こうした記事の裏にある歴史を読み取っていくより手はない。 海人と呼ぶのか倭人とよぶのか、そうした海人集団の大移動が季候変動や勢力関係などを引き金にして何波も起こった。日本国内だけの出来事でなく、中国揚子江やインドシナあたり南海の水人の大移動で、日本建国以前からの話であるが、これが九州へ渡ってきていて、安曇系は志賀海神社を拠点にやがて全国へ拡がっていく、丹後海人も尾張海人も大きくはみなこの系統になり、日本の土台のような集団である。宗像系は宗像郡に拠点を置いて全国に拡がった。中国だ韓国だ日本だと言ってるが、オマラは本当は皆同じモンなんだろう、と南米の人が言っていたが、その通りである。どこかの国にはワシはアメリカやと思っているメデテャー、ヘボイのもドエリャーおんなるが、よそから見ればまったくそう見えるのは、こうした歴史のベースがあるからであろう。そんなモンが憲法解釈変更してでも国を守るといっているが、どこの国を守ることやら、怪しいことには間違いない。(丹後弁は悪口には向かない社交的な言葉のようで、丹後人はこんなことは言わない) 海人は移住先で一部は土着するが、元々が田にくっついていないので、さらなる移動は当然のような性格であるし、水軍というか海軍なので島国の生命線を握っているし、海兵隊のように岡の奥深くにも入っていて、岡の権力をひっくり返す力を持っていた。 全国各地の安曇や宗像や海部などの地名や神社はその移動のあとで、地名が同じで言葉が似ているなら、どちらかからどちらかへ移動したといえるかも知れない。 応神紀にあるように、この海人を日本では大きくは安曇氏と呼ぶ、男はつらいよ渥美清さんとか、書き方や呼び方はいろいろある。後に権力側から海部と呼ぶが、こうした地名も各地に残されている。 方言が似ているのは丹後海人と尾張海人には特に密接な関係があるのではとも考えられる。 言葉が埋まっているわけではないが、歴史以前の記録として考古学に迫ってもらうと、 舞鶴二尾出土の二つの銅鐸のうちの一つが三遠式である。尾張も含めた、その先の三河・遠江式ということで、畿内式と別の型式とされる。銅鐸の最後で弥生の終わりころのものである。何か両地に強い繋がりがあったと推定されている。三遠式銅鐸の分布の西のはてになる。 弥生時代中期後葉における朝日遺跡とその周辺特産の土器だそうで、尾張でしか出ないと言っても大きな間違いがないもの。焼成後の壺器の腹に大きな円い穴をあけている土器で、一体どう使うのか使用方法は不明。京都府下でもわずかに出土するが、舞鶴の大川遺跡からも見つかったそうである。  たいへん珍しいもので、目の粗い籠の中に壺が入っているような形状をしている。 赤坂今井墳丘墓から出土したもの、ほかの土器と違って胎土が白く、彼の地のパレス壺の胎土のようなので、尾張からの搬入品と推定されている。 東海系と見られる土器はほかにも見られるが丹後の遺跡からは尾張地方の土器しか出てこないのではなく、そのほかの地の土器なども同じように出土するので、尾張ともこの時代に交易があった、とは言えても、両方言が似ている理由を強く証明するまでにはなりにくい。 こうした時代に丹後(福知山や綾部あたりの丹波もそうだが)、尾張と何か関係があったことは間違いはない。 丹後各地の神楽は岩滝の伊勢太神楽が伝わったもので、ほとんどがこの系統の神楽だが、「和唐内」で有名な伊根町菅野に伝わる獅子神楽だけは「尾張神楽」で、太神楽と同じものもあるが、当地だけしかないものも含まれている。 上山神社は天文23年の木札を遺存する古社で、4月25日の祭礼には神楽・太刀振・花の踊が奉納される。 舞鶴では各地の盆踊りとして古くから踊られた音頭で、今は歌詞を変えて「舞鶴音頭」などと言って踊られるが、この曲は東海地方の「吉田」から伝わったものと舞鶴では言われている。 東海の吉田の音頭と言っても古い曲が今は伝わらないのか、HPなど探してみてもわからない。 赤米が研究されている、私としては海関係の民俗が知りたいが手元には何もない。 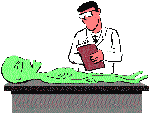 『西丹波秘境の旅』に、 丹後国は尾張系熱田海人の多住したところで、尾張国とかかわり深い。 とある。 海から言えばそうしたことかも知れないし、岡なら尾張氏も丹波氏ももともとは葛城あたりにいたのかも知れず一方が尾張にもう一方が丹後周辺へと一族郎党共々移住したのかも知れない。勘注系図を見ているとボヤーとそんな気持ちになってくる、という話であって学問的に裏付けがあるというのではない。 あくまでも、かも知れない、の話であるが、なぜ似ているか、何かいまだ知られていない歴史が隠れている、かも知れない、くらいしか言いようはない。 何でもないこれは本当のわれら国民の歴史なのだが、その解明は従来の皇国史観ではまったくムリ、学校の歴史ではムリだろう、従って市教委ではムリかも、現状あたりの解明が行政のほぼ限界かも。要するにわからないまま。 自分たちの祖先が歩んできた本当の歴史はこうした身近なところに残されていた。それが解明できないのである。こんなこともわからないとは、われらの歴史認識とはその程度のインチキに近いものと思わざるをえない。ダーダーとわけもわからず流されるだけ、われらは一体ホネのあることを勉強してきたのであろうか。 国際社会のなかでは一国の政府や市民の歴史認識の持つ重みは大きく、ますます大きくなって行く。どの分野の学問も学問のつもりならば、その真剣な見直しが迫られる。 アメリカでもその建国の精神などを若い世代に伝えることが難しくなっているそうである。見ての通りに先祖の精神はどこに忘れたのやら、しるべもなく漂流し、おいおいこれでもアメリカなのか、先祖が泣くぞ、の状態に陥っている。 どこかの国もそうならぬよう、あとは今は異端ともされる歴史学、地名学の研究者たちはじめ、良識ある市民すべてにヨーケがんばってもらうしかニャーキャ。 ワタシ的には、尾張→丹後への住民の移動(自主的プラス強制的によろう)が古代(古墳から飛鳥・奈良時代頃にかけて)に行われた。丹後に祀られる尾張系の神々、舞鶴なら高田神社の建田背命がそうだろうが、上安あたりは鉄がある、鉄資源を奪おうと何者かの侵略と地元海人の抵抗敗北の隠された過去が祭神など見ていればありそうに思われてくるが、こうした社のある周辺の地は特にその移住があったことを物語る拠点ではないのか。 しかし言葉が替わるくらいに大量に移動が行われたというまでの証拠にはならない。まだまだ大きなナゾとして残されていて、仕事は山積みのヨーケヨーケで、手もつけられないままある。 丹後弁の主な歴史記録『世界大百科事典』 〈 阿曇・住吉系はしばらく北九州海域を根拠地とし、のち、瀬戸内海中心にその沿岸と島々、さらに鳴門海峡を出て紀州沿岸を回り、深く伊勢湾に入り込み伊勢海人として一大中心点を構成し、さらに外洋に出て東海道沿岸から伊豆半島ならびに七島の島々に拠点をつくった。それより房総半島から常陸沿岸にかけて分布した。彼らは航海に長じ、漁労をも兼ねる海人集団とみられる。 これに対し、宗像系海人は、もっぱら手づかみ漁、弓射漁、刺突漁など潜水漁を得意とした。本拠を筑前宗像郡鐘ヶ崎に置き、筑後、肥前、壱岐、対馬、豊後の沿岸に進出、さらに日本海側では向津具半島の大浦、出雲半島と東進、但馬、丹波、丹後から若狭湾に入り、なお能登半島、越中、越後、佐渡に渡り、羽後の男鹿半島に及んだ。両系統とも、なかには河川を統上し内陸部へ進み陸化したものもあった。 日本の海人は元々は南方系だが、その拠点社(志賀海神社・宗像大社)がどちらも北九州にあるように、その主勢力は南方・鹿児島の方から来たのでなく、朝鮮経由の北からやってきたものと思われる。すでに中国や朝鮮半島で北方系文化と混淆していて複合文化なので、どこまでが元々の南方系文化なのかを見分けるのはかなり難しい。 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『丹後・東海地方のことばと文化』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2015 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||