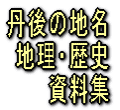 |
高津江(たかつえ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高津江の概要《高津江の概要》 高津江は由良川下流域の左岸に位置し、福知山市大江町の東北端で舞鶴市地頭に接する。 山間に人家や田畠が散在する。 高津江村は江戸期〜明治22年の村名。高津江は明治22年〜現在の大字名。はじめ有路下村、昭和26年からは加佐郡大江町の大字、平成18年からは福知山市大江町の大字。 《高津江の人口・世帯数》134・47 《主な社寺など》 高津江遺跡(由良川の川底から縄文式土器・土師器・須恵器が出土し、縄文−古墳時代の遺跡とされる) 小字岡には高吉神社(祭神高皇産霊尊・三河・高津江の氏神) 竃神社 明見神社 檀那寺は北有路の曹洞宗光明寺 《交通》 国道175号 《産業》 江戸時代から北原村・二俣村とともに和紙製造が盛ん、明治以降も大江山鬼障子紙として京阪方面へ出荷されたという。 高津江の主な歴史記録《丹後国加佐郡寺社町在旧起》〈 《丹後国加佐郡旧語集》 〈 高津江村 高百四拾五石三斗四升 内四斗 万定引 七石御用捨高 高吉明神 三河 高津江ノ氏神 判官宮 荒神 《丹哥府志》 〈 【高吉明神】 【荒川五郎八城墟】 【付録】(判官の宮、愛宕社、奉賀森外に観音堂、地蔵堂、庚申堂 《加佐郡誌》 〈 《大江町誌》 〈 明治中ごろ、宮津街道開通後は、町並図にあるように、馬車中継所と人力車夫溜場が置かれている。明治三十年代、鳥取より舞鶴に達する街道(根来経由)開削の際、その最後に高津江から根来道に出る道が、明治四十年に開削され、河守上地区と高津江港間は荷車や人力車の通れる道となった。大正八年の郡道指定の際も、三河経由を抑えて、高津江より国道を分岐する「舞鶴・河守線」として、郡道に指定されている。明治から大正初めにかけての高津江の繁盛ぶりは、町並図によっても感じられる。明治初年九九戸を数え、製紙業に従事する者その半ばを超えたことなど、既に述べた。今は五○戸弱で商店も二、三戸である。 高津江渡しは旧田辺への街道近くに在り、港はすぐ上流のくぼみにあったと伝えられる。集落の奥の方に「御門跡」とよぶ所があり、古くよりの元伊勢参道の名残りと伝える。 三河地内にまたがった瓢箪型の長池は、大正初めに野々森突角を除去した土砂で埋め立てられて耕地となり、高津江に売り渡された。(この項多くを高橋知一の資料提供による) 高津江 現墓地の下方左岸川沿いに台地があって野々森明神が祀られ、境内には大欅が生え、一帯は竹林におおわれていた。この祠は洪水のため、大川神社前まで流れて留ったが、これが現在の大川神社御旅所であると地元では云い伝えている。 この台地からの排土は、国道寄りの長池(東西三一メート化 南北一○三メートル)の埋立てに使われ、耕地が造成された。 高津江の小字高津江 松山 石ケ町 前田 堂ノ上 大張谷 コスカ谷 藤ノ志垣 砂取 岡 下谷 森ケ谷 角ノ谷 中江 関連情報 ↑175号線沿いのもう舞鶴の手前、ここの「かしわ餅」はおいしく、舞鶴でも有名です。 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『大江町誌』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||