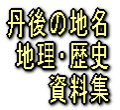 |
笠水神社
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠水神社の概要《笠水神社の概要》  西舞鶴の市街地からだと、南へ国道二十七号を進み、鉄道宮津線と立体交差する舞鶴陸橋の西側にある。陸橋へ登らずに側道を進み、くるっと回った所にちょっとした森があり、そこに鎮座する。式内社でもなくあまり目立たないが、舞鶴を代表するいかにも舞鶴らしい、そして加佐郡らしい神社である。 一般には「かさみず」と呼ばれているが、丹後風土記には「笠水」に「宇介美都=うけみず」の訓がついている。どちらが正しいのかは判断できない。 社前を流れる小川を700mばかり遡れば「真名井の清水」=笠水である。これがこの社の名の起こりで、この泉を神格化したものと思われる。 古くはこのあたりは池内川、真倉川、高野川がこのあたりで合流し、三川の水を受ける海辺だったという。本来は真名井の泉に近いその西側に鎮座あったと記される。 祭神は、笠水彦神、笠水姫神の二柱で、丹後海部氏の祖神とされる。 現在は公文名地区の氏神で、旧神嘗祭(十月十七日)に近い日曜日が秋祭の日。三年前から大阪の御堂筋祭にヒントを得て、和紙をピンク色に染めた花みこしをかつぎ、今年は子供花みこしも出した。 「舞鶴史話」によると、明治二年、田辺藩の藩籍奉還のとき、田辺の名は全国あちこちにあるので、新地名として城の美称の「舞鶴」と並んで、この「笠水」も候補にあげられたが、茨城の「笠間」とまぎらわしいためボツになったとも伝わる。なお下に位置する円満寺村は始め笠水村と呼ばれたという。 笠水神社の主な歴史記録《丹後風土記残欠》〈 《室尾山観音寺神名帳》 〈 あるいは笠売明神とも。 《丹後国加佐郡寺社町在旧起》 〈 慶徳山公国寺、桂林寺末曹洞宗、笠水明神、九社の内、伊佐津、公文名両村の氏神。 《丹後国加佐郡旧語集》 〈 公文名村伊佐津村氏神。七月六日夜祭。神楽相撲あり 《丹哥府志》 〈 《加佐郡誌》 〈 《舞鶴史話》(昭和29年) 〈 軍港談設置以来一路発展の途をたどり来つたわが舞鶴市の市名は明治初年以後の改称で、それまでは田辺と称したことは周知の通りであります。しかし誰が舞鶴の名を選定したのか、又いつから舞鶴と改めたのかは従来漠然としていましたが、舞鶴出身の老画伯藤山鶴城氏によってこの間の消息が判明しました。同氏の話によりますと舞鶴の名附親は舞鶴市明倫小学校の一初代校長だった河村真六翁で、翁が少壮江戸藩邸に在勤していた時田辺は紀伊にもあり、山城にもあって紛わしいので改称するよう大政官より沙汰があり、藩邸ではその候補名を河村翁に諮問しました。そこで河村翁は同僚幸山順吉氏と相謀り「笠水」「舞鶴」の二名称をもって奉答しました。「笠水」というのは現在舞鶴市字公文名にある笠水神社にゆかりのある名であり、舞藤は旧田辺域の城名であります。丁度その時故片山淳吉氏が来邸したので河村翁は「この二つはどうぢや。」と前記の二地名を示すと、片山氏は「マヒヅル」は訓ではおいらんの名のようだ、音で「ブカク」というか、おれは笠水をとるといったということであります。その後官辺で評議の結果片山氏がおいらんの名のようだといった舞鶴にきまったのでありますが、なぜ笠水がとられなかったかというとこうであります。当時牧野氏と同姓の牧野貞寧氏が常陸の笠間藩知事であったので、岡辺を笠水とすると大へん又紛わしくなるので、舞鶴にきまったというのであります。又いつから舞鶴と改称したかについては著者の調査によるととの如くであります。 『牧野弼成氏が亡父誠成氏の遣領をもらうために東京へ出発、参向したのが明沿三年六月十七日で、同二十日藩知事に任ぜられ「同時に朝旨あり以後〃田辺〃を〃舞麓〃と改められる」とありますから舞鶴と改称したのは前記の通り明治二年の六月三十日と考えられます。江戸が東京となったのは同年九月八日でありますから舞鶴の改称の方が東京より二ヶ月あまり早いわけであります。』 『舞鶴市内神社資料集』所収「神社旧辞録」 〈 風土記には七日市の真名井清水西辺に祠在りと見ゆ。この神名の示すとおり加佐の神泉を神格化した産土神である。 往古は伊佐津及び公文名二村の氏神とある。寺記にも載。 「舞鶴史話」は、京極高知の伊佐津川瀬替前は池内川は七日市、公文名の東を流れて淡島神社と笠水神社との中間を流れ、真倉川は十倉、京田と七日市の間を北流して笠水神社の南で高野川に合流してその辺一帯を沼にして、今の円隆寺の東方を浸しつ云々 これでみるとこの神社境域は、恰かも川中嶋の景観を呈していたようだ。 *京都地名探訪 5* *舞鶴とカサ 高橋 聡子 *笠水神社の地域に「笠氏」の存在*(京都新聞020926)に、 〈 昨年、笠水神社の南西に位置する女布遺跡で七世紀後半の大規模な倉庫群跡が確認され、地方官衙もしくは豪族の邸に付随する施設跡と推測されている。そこで豪族笠氏が笠水神社のかかわる地域を本拠として加佐郡一帯を治めていたとは考えられないものか。古くは海が入り込み潟を成していた思われるこの地から浦入への行き来も容易である。浦入では、中央政府あるいは丹後国府の管理下で製塩のみならず鍛冶生産も行われていた。女布では式内社日原神社の他に金峰神社を祀り、その奥の院に女布の語源となった祢布社がある。ニフは丹生(にゅう)であり、かつてこの地で水銀を採掘していたと考えられるのである。 カサを冠する加佐郡と笠氏、さらに東の若狭(ワカサ)という語について目下考えているところである。 (舞鶴市文化財保護委員) 『中筋のむかしと今』 〈 荒野に夕方が訪れた。じりーと焼付けられた草木が、ほろりとして休むころ、涼しい夕風が、サラサラ吹き出す。草木はびーと動いた。 「流石丹後じゃ荒野ばかり」一人の武者修行者が一人言を言いながら、ガサガサ通りかかった。 「ああのどが乾いた。此処らで一服」とやわらかそうな草の上にこしを下ろした。笠をかたわらに置き、あちこちを見ながら汗ばんだからだを拭うた。しばらくは身うごきもしないで、茜さす西の空をうっとりながめて居たが、よほど疲れたと見え、其のままうとうととねむってしまった。そして夢を見た。次の様な夢だった。 「ああのどが乾いた、水を飲みたい」何か急に思い付いた様に手早く杖を持って地面へさした。とそこからは水がチョロチョロ湧き出た。水は夕焼けにてらされて金の水の様に赤くうつって流れた。武士は大変よろこんだ。乾いたのどを水はグルグルと云って通った。 ……やがて武士は目を覚ました。目を見張ったが、唯真暗だった。無数の星がきらきら、光って居た。そして月見草が数かぎりなく咲いて居るのが星の光りで浮き出て居た。 武士はのどが乾いてしょうがなかった。…… チョロチョロ、武士は耳をすました。広い荒野の夜の静けさを破って小人の銀鈴の様な心よいひびきが、どこからともなく伝わって来る。チョロチョロチョロ。音は絶え間なくきこえて来る。天女のささやく様に甘いすんだ音で、武士はすっと立った、そうして手にした杖を力まかせに地につきつけた。 どうだろう、杖の根元からはチョロチョロチョロ心よい音を立てて湧き出たではないか。武士はそれを笠にすくって、心ゆく迄のんだ。つめたい霊水がのどを通った時、武士はひるのつかれも忘れて心よい程に、心気がのびやかになった。 夜は益々更けて行った。今は何一つ動く物はない。……東の空が白みだした頃武士は目を覚ました。まちわびて居た朝は来たのだ。武士の顔は生気に満ちて居た。見渡せばはるか向こうに鬱々とした大木がある。武士は刀を持って近よった。其の木は藤の木だった。見上げる葉末から碧玉の様な朝露が滴っている。露はキラリと朝日に映じてポタリポタリと地におちる。武士は藤の木をスラスラとけずった。白い木片が根元へばらばらと落ちた。朝日はまばゆくかがやいた。 武士はにっこり笑って木に字を彫り付けた。 「江戸より武者修行に来て、通りかかりたる者、 家紋−九曜星、名−村上九曜の星助盛。 一、この地に宮をまつれ。 一、名を笠水と名のれ。 理はわしがここへよって、水を飲みたさに杖を地につきつけ たら穴からは水がわくわくと湧いた。飲む器がないから笠で 水をすくって飲んだによる」と彫りつけ、終に其の刀を木にぐさっとさしておいた。 武士は又荒野の果てへ歩いて行った。其の後村人がここへ住む様になった。村人はこの印に気が付いて、その通りに宮を作った。これが公文のお宮の起りである。その藤も近年迄はあったが、どうしたはずみかだんだん枯れて行って、今では昔の面影は認められない。[「中筋村青年団機関誌」第一五号 大正十五年一月]).48(笠水神社の祭り(公文名) 夏祭りは八月六日に行われる夜祭りで、午後太鼓櫓・こども樽御輿を町内全域引き回し祭を盛り上げ、夕方からは境内に夜店が並ぶ。業者の店に加え町内会・愛公会の店も並び参詣者を楽しませている。また、町内会による福引き・盆踊りで祭りを一層盛り立て大変賑やかである。 秋祭りは昔は神嘗祭(十月十七日)に行われたが、祝日ではなくなったため、その前後の日曜日に行われる。神事は朝代神社宮司により午前中執り行われ、午後は太鼓櫓とこども樽御輿が町内全域を巡行し祭りを盛り上げている。なお、昭和六十年の秋祭りに新調し巡行させた「花御輿」を懐かしみ、その復活を望む声もあがっている。 [堀江昭雄] 笠水神社境内に鎮座されている「三社」の現状に到った経緯 公文名町内にはへ永年「三社」と称する古い祠が、笠水神社の西方に位置する茶臼山の山頂に鎮座されていました。 町内では毎年初夏に三社参道の整備・清掃とともに例祭を執り行ってまいりました。 しかし 町内一般にはこの「三社」がどのようなご祭神であられるのか定かでないままに時を経てきたのでした。 これらのことは一般公文名住民、特に近年町内へ転宅されてきた人達には全く不案内であり、そのうえ三社に登拝するための参道は山道で、日常人通りが皆無に近い等の理由から、年一回の例祭行事当日以外は参拝する人達も皆無の状況でありました。 このように、年々その祠もいたんで時の経過とともに、ただ形骸化の一途を辿る状況となりつつありました。(嵯峨根作一氏著「笠水神社誌」参照) しかし毎年実施される初夏の例祭を執り行う役に当たってこられた町内役員や有志の方達は、この状況を憂い「昔時から公文名地域に居住して来られた諸先輩方が、ご加護を願い、精神的な支えとして『笠水神社』と同じく護持し続けられた『三社』の現状がこのままでよいのか、時代が変わったから、新しく地域住民となられた方が増加したから、最近の人達は考えが変わってきているから等の理由で、簡単に忘却し、放置してしまって良いものであろうか。一日も早く町内の総力を挙げて昔時の状態に復元すべきだ。」との献言が町内会の集合の都度毎回のように発せられたものでありました。 その甲斐があってか、ようやく平成十年に至り町内会総会での決議として「三社の復元」の総意を得、予算化されることとなり、大きく実現にむかって一歩前進することとなりました。 このことを担当した神社係は町内役員ともども如何にして町内会の意志を実現すべきかと苦慮したのでありましたが、幸い『笠水神社』代表責任役員である朝代神社の西村宮司様のご指導により、一路実現に向かい大きく進捗をはかることができました。 まず御鎮座になっている 「三社」御三神の確認をいたすことより始めました。永年放置されていた御霊の資料を整理させていただき、改めて宮司様・神社係・町内会役員会で慎重な審議の結果「三社」を構成される御三神は、伏見稲荷大社・愛宕神社・八坂神社とご確認をいただきました。 そして各神社の本社へそれぞれ選任者が参拝し御神璽をいただき公文名町内へ勧請いたすことのお許しと分霊をいただくことを決定しました。 これより公文名では伏見稲荷大神を「稲荷社」、愛宕神社を「愛宕社」、八坂神社を「八坂社」と称すべしと宮司様より決められました。 同時に「三社」のご鎮座になる場所について町内で種々協議(平成十一年春総会)されました結果、「三社」は茶臼山より降りていただき『笠水神社』境内にご鎮座いただくことが以後の参拝・維持・管理にも最適との結論のもと、現位置にご遷座いただくこととなったのであります。 諸事計画通り進行いたしまして、平成十一年七月八日地鎮祭が行われました。そして公文名町内の当面する一大懸念であった「三社問題」のエビローグは、平成十一年九月二十五日(大安・吉日)二十三時。朝代神社西村宮司様により、町内会長を始めとする全町内会の役員や有志者多数ご参列のもと、厳粛に「鎮座祭」が執り行われました。 永い間の公文名町内が「三社」について数多くの意見が出されていた課題はようやくここに解渓し、これより「三社」の祭典行事はすべて『笠水神社』の祭典行事とともに執り行われることとなったのであります。 [山下源太郎] 『舞鶴市民新聞』(.050902) 〈 「笠水神社」(公文名) 二つの川の中を抜ける道があるので中筋。その中心地に公文書を作る所があって公文名の地名。この地区には多くの水路や湧き水があり、真名井の清水は田辺城の「御水道」と呼ばれた。そこで〃水〃に因んだ「笠水(かさみず)神社」へ−。 由来は一人の武者修行者が通りかかり笠を置いて一服。そのまま眠って夢を見た…喉が渇き水が飲みたい! 地面を杖で叩くとチョロチョロと水の音。武士は笠で水をすくい、心ゆくまで飲んだ。この地に宮を祀れ。名を笠水と名のれ」と藤の木に彫って旅立った…とか。 丹後風土記には「宇介美都(うけみず)」の訓が振られ、また真清水の湧く所から「真名井」とも記す。昔は池内川、真倉川、高野川の合流を受ける海辺でもあった。故に祭神も笠水彦神と笠水姫神で海浜族の海部直が祖神・現社殿は天保十一年(一八四〇)、境内の欅一本で建てられ、公文名、伊佐津の両村と水の恵みで栄えた紙すき屋の協力で建立されたという(「中筋のむかしと今」による)。 平成十一年九月、社殿右側には稲荷社、愛宕社、八坂社の三社が復元ざれ鎮座。夏祭りは八月六日、秋は十月七日前後に太鼓櫓や御輿が出て盛大に行われる。 また、明治二年、新行政区の藩名として、「舞鶴」と共に「笠水」の名も候補に上げられたほどの、藩を代表する神社なのである。 〃水〃は万物の命を育む…されど「水は方円器に随う」とも言われる。水を大切に! 笠水彦・笠水姫祭神の笠水彦・笠水姫を見ておこう。笠水姫は何も所伝がないが、本来は彼女こそがこの清水の女神と思われる。『勘注系図』では、三世孫倭宿祢命の子で、四世孫が笠水彦命。注文に、 母は 父の倭宿祢命は亦名を天御影命で、東舞鶴森の弥加宜神社(大森神社)の祭神、一つ目の鍜冶神。母の豊水富命は伊加里姫のことで、伊加里姫神社(現在は京田に祀られている)に祀られている祭神、水銀の女神である。嫁さんがここの現地の笠水女命ということになる。 子が笠津彦命すなわち青葉山西山頂に祀られている神様ということである。 以上は勘注系図によれば一応こうだということであるが、しかし笠水彦命は本当はかなり難しものらしく、火明命又は彦火火出見命の異名としたり、異名、否、原名は、火明命であり、又、彦火火出見命と伝えられるとしたり、天火明命又は瓊瓊杵尊を意味するとしたりするようでもある。 なかなかに一筋縄ではいかない祭神で、系図のどこに位置するのかもいろいろ伝わるそうである。海部氏も悩むという神様で、これは古代史の秘密、金属精錬と深くかかわる神様のようである。 何かほかに記録がないかと探るが、見当たらない。伝説をいくつか(『中筋のむかしと今』より)この中にあるいは笠水彦がいるかも… 〈 「昔、ここら辺に大飢饉があって、真倉の者の食う物が無くなって、飢え死する言うんで、村人を救うために、東舞鶴の弥加宜神社の稗三俵と真倉の大森神社の御神体とを交換したんやそーな。」 いま弥加宜神社は「大森神社」の方が知られているし、稗蔵もあるという。 [「わが郷土まぐら」] 一本松の大男 新婚早々の若い夫婦が親類へ行き、夜遅く帰宅することになった。堤防が街道になっていて、右側の山裾を川が流れ、その左側に数枚の田があり、鉄道の線路があり、また山になる。「山から山へ竿が届くようなところ」と悪口を言われた程で、もちろん人家は四キロ近くない、さみしい道である。 風が山の雑木をゆする音、川が流れる音のほかは気味悪いくらい静かで、月明りがほんのりしていた。一本松の近くまで来た。 一本松というのは、昔、八百比丘尼という尼さんが、どうしても死ねないので、松の枝を逆さまに挿して、「これが根付いたら、どうぞ死なせて下さい。」と、祈って挿した枝が不思議と根付いて大きくなったという、いわれのある松の木で根元には地蔵さまかしら、祭ってあったような気がする。 ここが丁度、このさみしい道の中頃になるのか、よく一服をするのに、この松陰が利用されていた。 その一木松に大きな大男(大入道)が裸で腕組みをしてもたれていたのである。これを見たとたん二人は腰も抜けんばかりに驚いたが、目と目で合図を交わし、そっと堤防の裾へ下りて、その下を這うようにして通り過ぎた。といっても、全く生きた心地はしなかった。そして、また堤防道へ上り、手をつないで一目散に走った。やっと村中まで来た時、二人は異口同音に「大きかったなあ」と息を弾ませ座り込んだそうな。 一本松辺りには、よく大入道が出て、「相撲とろかい、相撲とろかい」と言うたげな。大男に化けていたのは狸だったということだ。 河童の話 舞鶴に鉄道が出来た頃、はじめて線路工夫として鉄道へ入った青年がいた。その仕事の一つに巡回といって、夜、梅迫の方から来る者と、舞鶴の方から来る者とが途中で出会って、無事故を確かめ合う仕事があった。この仕事が嫌で辞めていく者が多かったという。中には日本刀をたずさえて恐る恐る歩いた人、お嫁さんに来てもらって二人で歩いた人もあったらしい。 青年は、独身だったし、ガキ大将だったらしく、当番がくると一人で歩いた。ある夜、山崎の鉄橋にさしかかると、バシャと大きな音がして、誰かが落ちたらしい。〃今ごろ誰が、こんな所に?〃と透かして見ると、また、黒いかたまりが五つほど見えた。一歩・二歩と鉄橋を渡りかけると、バシャバシャという音とともに黒いかたまりが川の中へ落ちていった。この時ばかりは、いかな青年も寒気を催したそうだ。 両方が山、そして川だけが流れている、シーンと静まりかえった夜中に、水泳でもあるまいし、きっと、昔はたくさんいたという河童だっただろうと言っていた。 大蛇に毒を吹きかけられた話 村に言語障害の青年がいた。不幸にも生まれつきものの言えない彼は、毎日、山へ行って柴を二束作ってこなければ、ご飯が食べさせてもらえぬという気の毒な境遇だった。毎日、柴を刈りに行くので、だんだんと雑木も無くなり、ずうーつと奥まで出かけねば手の届くところに無くなっていた。 ある日のこと、日もとっぷり暮れる頃、二束の柴を背負って帰ったが、ひどく疲れた様子だった。翌朝、目を覚ますと随分と顔がはれていた。家の人もあわれに思ったのか、「今日は、一日休んでよい。」と許可した。 めったに、こんな休みは当たらない彼にとっては、どんなにうれしかったことか。近所を遊び歩いていた。「今日は山へ行かんでもよいのか」と手まねでたずねると、「ずうーっと、山の奥まで行って柴を刈っていたら、太い長いものが首をもたげて、襲い掛かってきたので、すわ大変と一生懸命逃げて、しばらく隠れているとやがて向こうへ行ったので、また、さっきの場所へ行き二束を完成させて帰ったのだと、手まねで教えてくれた。その目は開いていないくらいボンボンにはれ上がっていた。 そして、その翌日、彼は静かに死んだ。村人はうわばみ(大蛇)に毒を吹きかけられたのだろうと、彼の死を悼んだそうな。 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||