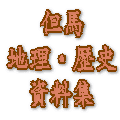 |
畑山(はたやま)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畑山の概要《畑山の概要》 太田川の南岸にあり、当地で同川に赤花川が注ぐ。北東は中山。集落は下畑山・中畑山・畑森・日和坂に分れる。 畑山村は、江戸期~明治22年の村。但馬国出石郡。山名氏政滅亡後天正13年まで青木勘兵衛、同年から前野長康が領した。文禄4年出石藩領、寛文6年からは旗本(倉見)小出氏知行。旗本小出英本は出石藩主小出吉重の弟にあたる。 寺院は、松源寺・海門庵・小林庵・宝城院の廃寺跡が見られる。畑森にある玄通庵は出石郡西国26番札所。明治22年資母村の大字となる。 畑山は、明治22年~現在の大字名。はじめ資母村、昭和31年からは但東町の大字。平成17年より豊岡市の大字となる。 《畑山の人口・世帯数》 309・76 《畑山の主な社寺など》   日出神社の先、少し登ったところの道縁にある。横穴石室のよう、径12mの円墳という、道路に削られ損壊しているが、天井石のスキマらしきところから中が少し見える、刀剣・土器などが出土したという。この周辺にもう少し古墳があるそうダス。  中畑山の日出神社は多遅摩比多訶を祀り、「延喜式」神名帳にみえる出石郡の「日出神社」に比定説される。ただし南尾の日出神社とする説もある。 当社本殿(室町末期)は国重文。三間社流造の柿葺、手挟・蟇股には室町時代末期の初材を残している。 案内板に、 重要文化財
日出神社本殿 文化財の指定 本殿は室町時代末期の様式技法をよく伝えているとして、昭和38年に兵庫県指定文化財となり、昭和45年6月に国指定の重要文化財となった。国の文化財保護審議会において。「日出神社本殿は庇部分に後世の改造部分が多いが、手挟、蟇股など細部は当初材を残し、兵庫県における室町時代末期の三間社流造本殿の一例として保存すべきものと考える」と評価されている。 建造物の概説 本殿の建築は三間社流造という。建物は構造上円柱で囲んだ区画を身舎といい、その全面を庇という。身舎は内・外陣に区画されており、外陣正面開放、内陣正面は幣軸構で板扉を建てている。庇は一面の浜床で正面の柱間は身舎同様に開放で、建物の両側面および背面は板壁、正・側面の三方には縁がある。構造からみると浜床が見世棚造風であり、身舎正面の柱間が開放であることなどは、この建物特有の形式として稀少価値がある。柱上の組物は身舎が舟肘木で妻組も豕叉首の簡素なものであり、庇は出三つ斗に手挟を組み、中備には蟇股を置き、これらの彫刻に室町時代末期の特色を見ることができる。軒廻りは二軒で本繁垂木、破風板の曲線は桁の辺りで折れたような強い曲率を描いて形式の古さを表しているが、妻飾りの猪目懸魚は輪郭に火焔形の尖頭を付けた珍しい意匠である。屋根はこけら葺で箱棟の鬼板は江戸時代中期の修理の際のものであるが、この鬼板が取り付けられる以前の本殿屋根は野地の納まりなどから推測して茅葺であったかも知れない。 沿 革 日出神社は但馬神話で出石を中心とする但馬地方を治めた天日槍の四世「多遅摩比多訶」を祭神とする。神社の創立は明らかでないが、延喜式に但馬国出石郡の小社と記された式内社である。現本殿の建立は、建築の様式技法から考察して室町時代末期の16世紀初頭と考えられ、その後、宝永元年(1704)、享保11年(1726)、明治21年(1888)に修理したことが棟札によって知られる。解体修理は昭和48年10月に着手し、翌昭和49年11月に工事を完了している。構造形式は旧規を踏襲し、後世改変された箇所は資料にもとづいて復旧し、覆屋も撤去して当初の姿に修復された。 但東町教育委員会 平成14年3月  境内に恒良親王(聖護院宮静尊法親王)旧跡地の碑がある。後醍醐天皇の皇子聖護院宮静尊法親王は元弘の乱後但馬に配流になり、守護太田守延に預けられたとされる。周辺には旗振山・しろ山・仏清城・黒木御所・お池など親王にまつわるという地名が残る。 『資母村誌』 日出神社
畑山村字宮本に在り、式内社にして現今村社なり祭神但馬日多訶。 新羅王子天日槍泊多遲摩国即留其國而娶多遲摩之俣尾之女名前津見生子多遲摩母呂須玖(諸杉御社祭神)此之子多遲摩斐泥(比遲神社祭神)此之子多遲摩比那良岐此之子多遲摩毛理(中嶋神社祭神)次多遲摩比多訶多遲摩比多訶娶其姪由良良美生子葛城之高額比賣命(此者息長帯比賣命之御祖)『古事記』 日出神社資母郷畑山に坐す。『式社考』 畑山村字宮本日出大明神。『神社啓蒙』 創立年不詳享保十一年八月十一日再建、明治六年十月村社格加列。 神體封箱之金幤なり。 土人傳説百年程前鎧着之御神體なりしも、精神病者盗出し赤花圭計酒屋之門前にて玩弄せしを人神なりとて制止せず、爾来紛失し後石地蔵を以て神體とせしを、明治三年佐治氏神體改之際、現今の金幣に改めたり。 境内攝社若宮大明神稲荷大明神秋葉大明神 一額 日出神社天眼書 一床下柱銘記 享保十一歳丙午八月吉祥 一札 日指大明神奉建立御拝、享保十一年丙午天八月十一日、守護小出主膳樣御代官彌兵衛御手代大村茂兵衛、宮本氏子中大工平井九左衛門永井文左衛門加藤仁平 裏 日指大明神奉建立御拝子孫繁昌祈祷。 一札 日指大明神寶永元年申之四月十一日守護小出主膳御代官河井彌兵衛伊藤又左衛門御手代坪内茂兵衛大工宇須井源右衛門 裏 當社及破損氏子中茂すいび仕可致力無之節操仕□□百日計り御座候て皿之木引手間へまいりやしないに仕色々と精を出し如此之破損いたし候以後如此可有者也 寶永元年申四月十一日但馬國出石郡太田谷畑山村宮本筆取羽尻平左衛門 一札 奉遷日出神社明治三庚午年九月四目 裹 村中安全畑山村庄屋永井和平年寄今井幸左衛門同苗淺右衛門百姓代永井三郎左衛門丹後久美谷神社大宮司佐治從五位藤原朝臣正□□拝一札 奉營繕日出神社御神殿一宇(一天泰平社頭光榮今上天皇 寶祚萬年)祠掌黒田廣照 袤 御遷宮明治二十一年十月十五日同村総代永井三郎左衛門 一鰐口 奉掛日出大明神正徳六年申三月日 但州出石郡太田庄畑山村ノ内宮本観音講中。(小林大師堂にあり) 一高麗狗 石製一封 一竹帙 長八尺桐箱入、箱蓋銘今上皇帝御即位清涼殿御掛御簾、取次京都新椹木町甲 斐厨屋六兵衛女房但州出石郡宮本 一鳥居 明治三十二年建立 一燈寵一封 文化六年九月、一對天保二年九月 境内坪數 百八十一坪外に二畝二十五歩、明治三十八年五月編入 氏子數 二十九戸 祭日 十三日陰暦九月中午日なりしが文化十二年九月十三日改む。『今井文書』 恒良親王謫居跡境内に奉遷すとの口碑あり現今御池等の跡を存す其他日和坂日 落谷等之字あり、神社に關係せる歟。(太田氏並に古蹟参照) 『但東町誌』 現在旧合橋村南尾字日殿滝にある日出神社について、「兵庫県神社誌」下巻は、祭神を「多遅麻日多訶神由良止美神」としており、これはこの神社の古木札の名と一致していることによっても知られる。世継記は日足命としており「但馬秘鍵抄」は「日出神社日出故名在仁徳天皇御宇六七年四月一八日。出石県主石部臣天日足命を祀る」としている。また「但馬式社考」は、日出神社は多遅麻日多訶神としている。但馬秘鍵抄は貞観五年(八六三)に選上され、但馬風土記に次いで古く、国司文書中では最古のものとされている。このように、南尾在日出神社は、但馬秘鍵抄に登録されている点と、但馬故事記但馬世継記に埴野郷の三社の中に加えられて居る点が重要視される。選進された当初に於て、何れも畑山村日出神社日足命祭祀するとあり、南尾在も日出神社日足命を祭祀するとあり、何れも石部臣之がそれを祭ったとある。「神社誌」では、南尾の日出神社は多遅麻日多訶由良止美を祭るとあり、神社東方山上に日多訶の古墳多遅麻日多訶命之陵とあり、西方に由良止美墳墓地ありと伝う。畑山の日出神社も多遅麻日多訶を祭るとあり、祭神の移動が行われていることが知られる。
雄畧帝二年(四五八)石部臣の子埴野臣出石県守となす埴野村は、その所領である。石部臣を出石丘に祀り、石部神社と云った。 たぶん日出は比遅と同意味であろう。新羅神社の意味であろう。祭神は特に個人ではなく、自分らの祖先を祀るものか。  『資母村誌』 岡野神社
畑山字日和坂村社祭神少彦名神 『古事記』曰大國主神、坐出雲之御大之御前村、自浪穗、乗天之羅摩船而、内剥蛾皮、剥爲衣服有歸來神。爾雖問其名不答、且雖問所從之諸神、皆白不知、爾多邇具久白言、此者久延毘吉必知之、即召久延毘古、問時、答白此者神産巣日神之御子少名毘古那神、故爾白上於神産巣日御祖命者、答告此者實我子也、於子之中、自我手俣久岐斯子也、故與汝葦原色許男命、爲兄弟而作堅其國、故自爾大穴牟遅與少彦名二柱神、神並作堅此國、然後其少名毘古那神者、渡于常世國也。 『日本書紀』曰、大已貴命、與少彦名命戮力一心經營天下復爲顕見蒼生及畜産、則定其療病之方又爲攘鳥獣昆虫之?異則定其禁厭之法、是以百姓至今、咸蒙恩頼、嘗大己貴命謂少彦名命、曰吾等所造之国豈謂善成之乎、少彦名命對曰或有所成或有不成是淡也蓋有幽深之政焉其後少彦名命行至熊野御碕、遂適常世郷矣(以下略) 神體 衣冠束幣の立像 鏡臺銘 奉納御鏡臺、文化元年甲子十二月三十日。 施主 今井甚兵衛妻 創立年不詳 正徳三年、享保九年、文政十一年再建、明治六年十月村社格加列。 一札 奉建立岡野宮大明神氏子般昌祈處 享保九年辰之三月二日畑山村六郎兵衛 一札 奉再建岡野大明神社 于時文政十一戊子孟秋天下泰平郷中安全但馬出石郡上郷久畑庄栗尾村大工棟梁三宅義右衛門、同國同郡下郷太田庄畑山邑永井六左衛門、小出規太郎殿御代官河合丹次義政、河合牧太義成、今井三平義連 一札 奉建立岡野宮大明神氏子般昌祈處 正徳三巳正月吉日御代官小出岩之丞樣御領分御代官河内彌兵衛様伊藤又兵衛様 一札 岡野宮大明神遷宮朝日和泉謹攸 文政十一歳戊子九月吉日 一鰐口銘 岡野宮大明神、但馬出石郡太田庄畑山村今井藤右衛門寄進。享保七寅年十一月十一日 境内社 稲荷神社琴平神社 一燈龍一基 安政四年丁巳仲多一對享保二年子戌八月如意日 境内坪數 百二十六坪 氏子數 四十五戸 祭日 十月十三日陰暦九月二十一日なりしが、文化十二年九月十三日改。『今井文書』 附記 合橋村唐川及三原に岡神社ありて祭神少彦名命なり當社と関係あらん乎  下畑山の御影(みかげ)神社(水影神社)は天明元年(1781)に本殿を造立し、文化13年(1816)に再建(棟札)。 『資母村誌』 御影神社
舞鶴の弥加宜神社と同じで、畑山村字宮ノ下村社祭神月読神伊弉諾尊曰吾欲生御宙之珍子乃以左手持白銅鏡則有化出之神、是謂大日霎尊、一書云月弓尊、月夜見尊、月読尊其光彩亞日可以配月而治故亦送之干天。『日本書紀』伊邪那岐命洗左御目時、所成神名天照大御神、次洗右御目時所成神、名月讃命、伊那那岐命詔月読命汝命者、所知夜之食國矣事依也(『日本書紀』『古事記』)月讃尊伊弊諾尊の子母は、伊奘冊尊二尊が國土經營の後、天下の主たる者を生まんと、まづ日の神を生み次に月の神を生む光彩日に亞ぐ、故に日に配して高天原を治めしむ、記の一書に伊弉諾尊左手に白銅鏡を持ち大日霎尊を生み右手に白銅鏡をもちて月読尊を生むとあり古事記には伊弉諾尊禊の時左目を洗ひて天照太神を右目を洗ひて月讃尊を生むとあり紀紀共に天照太神に次ぎて尊き神たるを傳へたるを見れば蓋し勢力ありし神なるべし。 創立年不詳 天明元年九月上屋再建、明治六年十月村社格加列。 神體 衣冠束帯の坐像一躯外に立像一體あり。 一札 奉造立御影大明神御寶前所 天明元辛丑年九月如意日OO王天中天、加陵頻伽聲、哀愍衆生者、我等會敬禮畑山 村氏本當人九右衛門。(外三十一名) 一札 奉鎭祭水影大明神正遷宮 朝日和泉文化十三年丙子十月吉日、出石博労町町子謹修 一額 御影宮前妙心海門書文政九丙戊 一額 御影大明神一道叟敬書 安永七戊年正月吉祥日奉納御寳前大工當邑永井七郎兵衛 一鳥居 明治四十年九月建立 一燈寵一封 寛政十二年庚申歳天保五年午二月 一石段 明治二十一年九月 一鰐口銘 奉納御影宮安政二卯氏子中。(現今観音堂にあり) 境内社 秋葉明神若宮大明神稲荷大明神猿田彦命。 境内坪數 百五坪 氏子撒 四十戸 祭日 十月十三日陰暦九月七日なりしが文化十二年九月十三日改む。『今井文書』 參考 古事記傳云彦坐王は淡海の天之御影神の女息長水依姫を娶りて生みませるを以て丹波彦多々須道之字斯王と申す崇神天皇の御世に四道將軍の一人にて丹波道に遣はさる然れば此彌加宜神社は此王の外祖神を祀りしならん(丹後加佐郡彌加宜神社傳)當社にも関係あるにや附して後考を俟つ姓氏録山直、天御影命十一世山代根子之後也)  日和坂バス停の向かいに旧庄屋屋敷があり、ひょうご住宅百選の1つ。倉見領の大庄屋を勤めた今井家住宅は宝永六年修理の墨書が残り、江戸初期の豪農家屋の特色を残している。橋本閑雪・今井雨香などの襖・敷物があり、頼山陽も訪れた樹齢350年という杉のある庭園がある。 敷地内の概要
一、家屋 寛永六年(一六二九)頃の建築で家は民俗学的に珍しい箱棟尾根であった。 一、茶室 龍吟庵(利休型)昭和五十五年 大工棟梁上垣正男により建築 一、神仏 天満宮 正徳三年(一七一四)建立し昭和五十一年大修理 稲荷神社 文政十三年(一八三〇)建立し昭和十年建替 石地蔵 宝暦元年(一七五〇)建立 一、庭 木 銀木犀、杉、紅葉、薮椿等(樹令三百年以上) 其の他百余品種の庭木が散在している。 一、滞在された名士 享保十二年 海門大和尚 文化十三年 頼山陽先生 明治時代 橋本関雪先生 《交通》 《産業》    今井住宅の少し先、使われなくなった2.4ヘクタールの田畑を「たんとう花公園」と名付け、地域の人たちがチューリップを植えて有料で開放している。およそ200種類50万本の色とりどりのチューリップが咲く。 《姓氏・人物》 畑山の主な歴史記録畑山の伝説畑山の小字一覧関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||