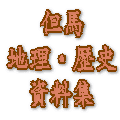 |
口藤(くちふじ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口藤の概要《口藤の概要》 集落は太田川北岸の谷間、出石・宮津道(丹後道)に沿って発達。古くは北東の中藤森村、南東の奥藤森村と合せ藤森村と称して一村であったが、寛文6年(1666)の検地の際に村切を行ってそれぞれ一村となったという(資母村誌)。 口藤ケ森は、明治22年~大正6年の資母村の大字名。大正6年口藤となる。 口藤は大正6年~現在の大字名。はじめ資母村、昭和31年からは但東町の大字。平成17年より豊岡市の大字となる。 口藤・中藤・奥藤は、それぞれ口 ヒジは当地の北に連なる丹後の比治山(磯砂山)や久次(咋石)山のクシと同じ意味と思われ、比治真名井神社、 久士布流岳のクシフルと同じ意味で、大ソフル神社の意味であろうか。豊受大神降臨とかは後の伝説で、もともとは当地住民らの祖神が天降ったとされた地に祀られたのではなかろうか。 《口藤の人口・世帯数》 63・22 《口藤の主な社寺など》  口藤集落へ入ると「延喜式内 比遅神社」の石柱と燈籠がある。本殿はまだまだ先である。  ずっと山奥で、人よりも熊の領域にある。:境内は広いがこうした人が寄り付かない所では荒れてしまう。社名から見ても、ずいぶんと古い元初の神社であろう、記紀や延喜式などが忘れてしまった遙かな過去を窺えるかも。このあたりを開いた日槍さんの一族が祀ったものと思われる。 『資母村誌』 比遲神社
口藤村字山姥にあり。式内社にして現今村社なり。祭神多遅摩比泥命天津兒屋根神。 古事記 天之日矛、聞其妻遁、仍渡来、將到難波之間、其波之神塞以不入、故更遷泊多遅摩國即留其國而、娶多遅摩之俣尾之女名前津見生子多遅摩母呂須玖、此之子多遅摩斐泥 然るに神社啓蒙神祗志料の説は然らず。 神社啓蒙 藤ヶ森鎭坐丹後丹波郡比治麻那爲神社と同神社なり後の山を比治山又は「いさなご」山又葦占山或は眞名井と云ふ一山四名あり伊勢外宮の本つ宮なり藤ヶ森は比治が森なり。 神祇志料亦同 蓋豊宇賀乃賣神を祀る初豊字迦乃賣神常に攝津稲荷山に居て厨膳を為り給ひしが後故ありて丹波國比遅の麻奈韋に遷り給ふと 相殿神天兒屋根の命は中臣の祖にて藤原氏の祖神なり。 本履別に羽倉信義の書を蔵す、其文左之如し。 正一位稻荷五社大明神安鎮の事 右本宮之?(竹+斬)祕而不他宗之所知故不許容易修封□□也雖然但馬國出石郡平野口藤ヶ森村中執事(徳右衛門要助)常崇敬當社殊于他且今般請安鎮本宮之神霊同謹而大祀式修封之奉勸遷厳重神寳神鏡於其請齊場年々永奉無怠祭祀□□尊信者可爲其所其家繁柴安全長久幸福之鎮護者也 明治二年己巳年八月豊日正官御殿預從五位上行攝津于之□□信義(印) 右文書之箱書に羽倉攝津守とあり。 右文は明治初年火災に罹り神體燒失せし故徳右衛門要助なるもの伏見稲荷祠官羽倉攝津守に依頼し御霊を授けられしなり前後綜合し祭神に疑念を生す要は豐宇賀命は稲荷社之本體にして本社俗に稲荷と稱せしに依るならん 境内社稲荷神社祭神保食神 一札維持亨和元暦辛酉八月令辰天下泰平国家安全 一札丹後板並別八幡社司毛呂下野□□庄屋嘉左術門(外二名)丹後宮津萬町鍛冶次右術門 奉再營正一位稲荷額持国天王増長天王廣目天王多門天王丹後岩屋住大工 一石段 天保五年仲秋二川 一鈴 明治二年正月吉日岩破平右衛門 創立年不詳明治元年本殿家根替之際火を失し燒失せり。同年八月再建、明治六年村颱格加列、明治四十二年五月春日社合祀、大正四年十月二十五日、物饌幣帛料供進社となる。 境内坪數 三百二坪 祭典 祭日十月一日。 『但東町誌』 比遅神社 祭神 味散公命 (「但馬世継記」延長三年(925)四月)
村社 鎮座地 資母村口藤字山姥 〔特選神名牒〕 口藤ヶ森村字山穂(出石郡資母村大字口藤ヶ森) 〔神祇志料〕 今丹後但馬の界比治山の麓藤が森村にあり 祭神 多遅摩比泥神 *天津兒屋根神 由緒 創立年月不詳なれども延喜式の制小社に列し明治元年社殿を再建せり同六年十月村社に列同四十二年春日神社を合祀せり 〔延喜式 巻十 神名式下〕 但馬國一百卅一座 大十八座 小一百十三座 出石郡廿三座 大九座 小十四座 比遲紳社 〔特選神名牒〕 比遲神社 祭神 豊宇加之賣神 〔神祗志料〕比遲神社 山姥稲荷と云(神社明細帳道志流倍○按藤森神社轉森は比治訛也) 盖豊宇迦乃賣神を祭る初豊宇加乃賣神常に攝津稻椋山に居て厨膳を爲り給ひしが後故ありて丹波國比遲の麻奈韋に還り給ふ(摂津風土記)即是也 〔神社調書〕明治元年辰八月再建 明治四十一年九月同村無格社春日神社合祀の義許可同四十二年五月廿四日合祀濟 〔神饌幣帛料供進神社指定年月〕大正四年十月二十五日 境内 三百二坪 官有地 榮造物 本殿 萱葺入母屋造四坪 幣殿 瓦葺入母屋造六坪 拝殿 萱葺入母屋造四坪三合二勺。○調書ニハナシ 境内神社 稲荷神社(保食神) 祭日 例祭 十月一日 〔神祗志料〕凡其祭八月 日を用ふ(豊岡縣式社取調帳) 賓物及貴重品 一本殿棟札 享和元年建立か 氏子 五十戸 『大日本地名辞書』 藤森(ふじがもり)。今資母村の大字なり、中山の北東にして、丹後への通路にあたる、延喜式比遅(ヒヂ)神社あり、神祇志料云、此社今山姥稲荷と云ひ、蓋豊宇加能売命を祭る、丹後中郡の比治真井神社に近き地なれば、其因由なきに非ず。
補【比遅ヒヂ神社】○神祇志料、今、丹後・但馬の界比治山の麓藤が森村にあり、山姥稲荷と云ふ(神社明細帳・神社道志流倍)按に、藤森は比治森の転訛なり、 蓋豊宇迦之売神を祭る、初豊宇賀之売神常に摂津稲椋山に居て厨膳を為し給ひしが、後故ありて丹波国比遅の麻奈韋に遷り給ふ(摂津風土記)  比遅神社参道より金蔵山(453.6m)を望む。どこから見てもこの姿をしている。山頂からは天橋立が見えるという。 同名の寺院が今、中山にあるが、その寺院でなく、過去にこの金蔵山にあった山岳仏教時代の大寺院である。大寺院だけでなく、その防衛に巨大な城郭も築かれたが、森蘭丸に焼かれたとか、やがて滅んだという。  中山の金蔵寺にある笠塔婆。もともとは金蔵山の頂上にあった。古金蔵寺のもので、正和4(1315)の銘がある。(下の『資母村誌』に説明がある)  『但東町誌』に 『但東町誌』に「口絵写眞 懸仏(かけぼとけ) 説明 旧金蔵寺の鎭守白山妙理権現の本地仏十一面観世音像を鍍金した銅の円板上に槌出しにして作り、左右に蓮華を取りつけている。円板が薄いので裏板がつけてあり、その左右上方に紐を通寸釣手耳があり、製作年代は室町時代のもの。もと加悦町の西光寺の所蔵であったが、明治維新以後所有者が転々と変り、現在は臨済宗妙心寺派加悦吉祥寺の所有となっている。金蔵山の数少ない遺品の貴重な一つである。」とある。 『資母村誌』 古金蔵寺
是れ古時の金蔵寺なり。現今のものとは全く異るにより敢て分ち記す。 1、宗旨 古時の金蔵寺は宗旨詳ならす。一般に眞言宗なりしと信ぜられ、諸記録亦此點一致す。元より確證有るに非るも今暫く之に從ふ。 2、山號 古時は金蔵山金蔵寺なりと云ふも、予は從はず。現今の瑞雲山と云ふもの古時より是ならん。抑金藏と云ふは雲の名なり。佛祖統紀三十に曰く賢劫初成時光音天窓中布金色雲注矢洪雨云々。 原人論自註頌に曰く金蔵雲布及三千界云々。 瑞雲と云ひ金蔵と云ふ、首尾相應す。古人據て以て名くる所以あり。 3、遺跡 中山瀧谷山上陵夷せる地域一帯は遺跡なり。地名に「仁王曲り」「地臓坂」「山本坊跡」等あり。又古井池尚存す。 4、遺物 一、高三尺餘、三寸角の石柱あり。其面に記して曰く 正和二二年乙卯十月十八日願主沙彌蓮意 (註)正和二二年とは正和四年也。四の音死に通ずゐを忌みて二二と重ねたり。此例少きにあらず。正和四年は紀元一千九百七十五年。花園天皇の御宇也。尚此に石柱と云ひしが、墓標にもあらず、頂上の面滑かなれば、燈籠の臺にてもあるべき歟。 二、五輸塔三基。何れも空輸を闕くと雖も、極めて雄なるもの也。 三、板牌無数。板牌は處々に発見さる。計ふるに勝へず。 四、逆修塔。三基あり。何れも自然石にして、其面には彌陀三尊の種字、及僧俗の戒名多数を刻せり。(古蹟の條參詳) 五、木佛像一。十一面観世音菩薩なり。丈一尺八寸。永濱宇平(丹後の史家著書多し)大正十五年十一月二十七日発行の橋立新聞に記して曰く尚金藏寺の遺物に一尺八寸の木像十一面観音像があって、今の金藏禪寺に保存されてゐるが、面貌り一種犯すべからざる瑞相と各部の勁健なる手法とは、之を平安末期に擬すべきか、遲くも鎌倉初期を降ゐまじ云々 六、佛具。茶湯器なるべし。碗五箇、臺亦五箇あり。銅なるも金を鍍金せり。 由緒 金藏寺に傳ふる由緒なるものに曰く 弘仁年間空海上人諸國遍歴の際金藏山に瑞雲靉靆たるを望みわけ登り給ふに南に當り一巨石あり坐して禪定を修し給ふ遂に止りて一寺を建立し瑞雲山金藏寺と名け給へり七堂伽藍の跡現在す古は眞言宗にして境内八丁四方寺領三千石を有せしも元龜年間織田氏の爲に討落され爾來衰微せり云々 又元金藏寺の支院にして現在加悦町西光寺にて明治十七年京都府廳へ進逹せる寺院明細書に曰く 陽成院の御宇元慶四年但馬國出石郡中山金藏山上に創立あり御朱印高二千石の地領(寺領か)の塔中(塔頭か)なりし所永祿十一辰年兵燹に罹り焼失其後二十四年を經て人皇百十一代後陽成院の御宇文祿元年に至り現地へ引越し開基良眞上人再 建以來現住職慈雲迄十八世連績す。と。此外當山の由緒に関する文献未だ現れず。 癈絶の原因 山本助太夫蔵「山本氏由来書」に曰く 抑山本氏の祖は金藏山に山本坊と云ひて山の東側に家屋敷あり古より眞言宗にて大ぐわらん處赤花より奥藤迄山の根回り寺領にて凡そ二千石の取締代官数百年の間相勤め居候に比は永祿十一辰四月四日大勢攻来り思不寄事なれば寺々騷動し弱き者は逃げ隠れ早落行くもあり若き僧俗相戦し炉四日五日と兩日燒討せられ僧俗不殘討死す此證金蔵山大石塚に刻り付有り云々 大石塚とは前記三基の逆修塔なり。此に於て塚か逆修塔かの一大疑問に逢着す。塚とせば金蔵寺没落の年月日は永祿十一年四月五日に断定することを得るも、塔には明かに逆修と刻せり。參考として逆修の字解をなせば 逆修とは佛数の術語なるは勿論にして、逆(アラカジ)め吾死後の佛事を修することを云ふ也。又預修、豫修に作る。詳細は灌頂随願往生十力淨土經に就て見るべし。謠曲丹後物語に「御逆修とも成り候ふべし」とあり。我國史乗に現れたるは百錬抄に「正暦五年十月二日関白道隆於東三條行逆修怫事」と云ふを始見となすと云ふ。永濱宇平曰丹後地方諸處の逆修塔は永禄を最も多しとなすと。謂ふに應仁以来天下紛乱朝に存し夕に歿し、佛經に所謂「如露亦如電」を如實に目撃して、我死後の佛事を生前に修するの風盛なりしならん。 已に是れ逆修と云ふ。然らば金藏寺の没落は塔面の年月以後ならずんばあらず。 永濱宇平曰く 縁城寺年代記に曰く 乙酉大永五 與謝郡岩屋雲巌寺兵燹に罹る夏七月 宮津日記上の卷に曰く 元祿十三年に聞く與謝郡雲巌寺炎上に百七十二年前の由(予曰く元禄十三年より百七十二年前は享禄元年にして大永八年に當る)但馬國藤ヶ森の近邊寺領にて有之候を但馬の城土押領致すべしとて二年の間度々攻来る云々 此等に依りて雲巌寺が大永の比但馬より攻略されしことを知る。而して遂に雲巌寺を滅亡せしめたるは金蔵寺なることなしや。金藏山は禅山凡て要塞に仕立てあり、即山上横に幾段の削りたる平地を作り、山腹竪に幾條の土壘石堡を築き、壕を穿ちたるは南北朝より戰國時代に亘れる各地通有の山嶽城を成せり。惟ふに全盛時代には幾多の山武士、僧兵等が據て以て金城湯池と恃みしならん。雲巌と金蔵は山の表裏に位置し、各僧兵を蕾へて領地を爭ひ。遂に雲巌を亡ししに非るなきや。 金藏山要塞の構造より見るも北方の敵を防ぐべき設備なり。而して又金藏山の滅亡せしは、雲巌の復讐戰なるか或は他の寺院より攻略されしならん。 と。以上之を要するに、金藏山は所謂山岳佛教時代の創建にして、數百年の間儼存せし名藍なり。支院には西光寺、壽福院、多寳院あり、坊に山本坊、杉本坊、松本坊等あり。其没落せしは逆修塔に刻されし永禄十一年四月五日以後なり。敵の何者なるやに至りては暗中摸索の感ある耳。永濱宇平の説は大いに參考すべし。但し雲巌の復讐戰としては、大永五年より永禄十一年迄四十三年の間隔ありて年代の餘りに遠きものあり。資母村一般の古老は織田信長の臣森蘭丸に討たれたりと信ず。又參考すべし。 金蔵寺と寂室禪師 人物傳正燈國師の條を參詳すべし。 白山権現 古来より金蔵山上に鎭坐し、稻の害虫驅除に靈驗ありと信ぜらる。白山権現とは是れ本地垂跡説の最先蹤泰澄()が賀州白山比咩神社祭神を十一面観音の権りに化現せしものなりと唱へ、白山妙理権現と稱せしに始まれり『元享釋書』。 即當山のものも同社より奉請せしこと明なり。 (附説)七堂伽藍 金蔵寺、栗丹寺、園城寺、其他古蹟に七堂伽藍は殆ど梅に鶯竹に虎の如く附物として人口に膾炙せり。その悉く七堂伽藍を具備せしや否は予等の知る所に非るは勿論なるも、只參考として、七堂伽藍が如何に結構雄大なるものなるやを知らしめんとす。 伽藍とは梵語僧伽藍摩()の略にして衆園と訳し寺院の通稱なり。七堂とは何に據り定めしや詳ならず。又異説も有り。大體として眞言七堂と禪宗七堂とあり。後者は今記せず。眞言七堂とは 一、金堂-佛像を安置奉祀す。俗に曰ふ本堂に當れり。金色燦爛たるを以て云ふ。具には金色堂と云ふ。 二、講堂-佛典を講する所也。 三、塔-佛舎利を奉安す。 四、経蔵-一切経蔵也。 五、鐘楼 六、中門 七、大門-南大門とも云ふ。 『但東町誌』 山岳仏教と金蔵山金蔵寺
このようにみてくると、史実の少ない中世の但東町の歴史に、今はない幻の寺院金蔵山金蔵寺の遺跡が浮び上がってくる。旧「資母村誌」はこれを廃絶寺として、若干の口碑や由来記や古文書、遺跡を発掘している。まずこの寺を訪れた僧の記録からみよう。 すなわち校補『但馬考』一四〇頁に、 「南朝後村上帝の興国元年(一三三八)北朝歴応三年の頃、寂室和尚入但、出石郡金蔵寺に寓すること一年」 とあり、当時の文章が残されている。「資母村誌」の伝える金蔵山の金蔵寺(現存の金蔵寺と異る)の由緒として記するところによれば、 「弘仁年間(八一〇~一八)空海上人諸国遍歴の際金蔵山に瑞雲あいたいたるを望み、分け入りで登り給うに南に当り一巨石あり(現存)、坐して禅定を修し給う。遂に止りで一寺を建立し、瑞雲山金蔵寺と名付け給えり。七堂伽藍の跡現存す。古は真言宗として境内八丁四方、寺領三千石を有せしも、元亀年間(一五七〇~七二)織田氏のため討落されたり」と。 その空海が但東町に来り、金蔵山上に瑞雲を見たという由緒の記事は、前述「養父郡誌」や、「十二所村史」が伝える新宮山満福寺の寺歴の記事と余りにもよく似ている。およそ開山寺歴の由緒とはこのようなものと思える。問題はこの当時空海が但馬に来たかどうかである。平安時代の初期を占める弘仁期(八一〇~二三)の文化は、仏教美術として密教美術が勃興し、不動明王像等の傑作が現われると同時に、新しい天台宗、真言宗が勢を得、また仏教と固有の民族宗教との習合が進められた時代であった。そして天台と真言とは、相争って僻地の開発と布教に力を入れた時代であった。金蔵寺の支院で現在加悦西光寺が、明治一七年(一八八四)京都府庁へ進達せる寺院明細書によれば、 「陽成院の御宇元慶四年(八八〇)但馬国出石郡金蔵山上に創立あり、御朱印高二千石の寺領」 とあり、これによれば空海の没年が八五五年であるので、没後二五年の事に属する。もしこれらの記事にして誤なしとすれば、空海は四〇才台の頃但東町に来り、山上に寺院建立の計画を樹で、没後二五年の八八〇年寺院を創出したことになる。このような山上に大きな寺院を建てるためには、前の新宮山満福寺の場合もそうであるが、金蔵寺由緒の伝える「七堂伽藍の跡現存す」(「資母村誌」一六八頁)はやや表現が大に失する嫌いがないでもない。既に「資母村誌」の編者が記述しているように、真言宗の七堂伽藍すなわち「真言七堂」とは、金堂・講堂・塔・経蔵・鐘楼・中門・大門等の七大建造物を云い、「境内八丁四方」とあるも山上のことでもあり、到底そのような建造物を平面に配列する余地はなかったと思われる。もっとも群馬県の榛名神社等のように、谷間の狹い箇所に大きな建造物が建築、配置されている例もあるが、その配列の距離と山上の面積とを比較しても、七堂伽藍は無理のように思える。現存している旧跡にみるような「大規模の寺院しという意味であろう。ただ寺領二千石又は三千石といい、僧兵多数を擁していたとすれば、相当の僧坊を必要としたことは想像されねばならない。 以下現存の記録と追跡により、この幻の寺院に関する史実を再現に努めてみよう。 【注】 伽藍とは梵語僧伽藍摩(Samg harama)の略称で、衆園と訳し、寺院をいう。七堂とは何により 定められたかは明らかでないが異説もある。真言七堂と禅宗七堂とがある。真言七堂とは一、金堂-仏像を安置奉祀する。俗に本堂ともいう。詳しくは金色堂という。金色燦爛としているため。 二、講堂-仏典を講義するところ。 三、塔-仏舎利を奉安する。 四、経蔵-一切の経蔵。 五、鐘楼 六、中門 七、大門-南大門ともいう。 その配置は法隆寺形式によれば左の通り。 … 金蔵山金蔵寺の由緒と遺跡 山本助太夫文書の「瑞雲山金蔵寺」現存の中山にある金蔵寺と区別する意味で、金蔵山頂にあった古金蔵寺の遺跡についてみれば次のようである。 金蔵寺山は但東町の西北部にあり、丹後の加悦町、野田川町に接する県境(但馬国と丹後国の国境)にあり、但東町側より見れば古樹繁茂せる時は、山頂はどこから見ても円形に見える。近時古樹伐採され山容は、若干狭まっているが、ほぼ円形の山頂をなしている。但東町内からは虫生又は中山瀧谷を経て山頂に達する途あり、奥藤、奥赤より山頂に達する途もある。山頂の一番高い所には白山権元を祭る小祠あり、その下に明治初期に改築された観音堂あり、また山頂の尾根に沿ってゆくと金蔵山金蔵寺由緒に、空海上人が坐して禅定を修されたという巨岩がある。それ程高い山ではないが、遙か天の橋立を遠望することができる。風光明媚で、昔山を歩いて往来した交通の要所にある。山頂に達するに最も近い山道は、虫生より棚原を経て上る途であり、その裏側にある奥藤より山頂に達する途もある。しかし最も平坦であるのは中山より瀧谷を経て登る途で、恐らく往時の正道はこの途でなかったかと思われる。現在云い伝えられている地名に「仁王曲り」「地蔵坂」「山本坊跡」等がある。往時僧兵等の屯していた坊跡の名が地名となったものと思われる。しかし最も近い途は虫生より上る途で、往時の日常の通行跡はこの途と思われ、寂室和尚が五〇余霜月遊んだという田原(棚原)部落あり、「庵屋敷」があって東光菴跡がある。 山頂はかなり平坦部があり、今は四季涌水とはいえぬが古井池がある。したがって山頂ではあるが水の調達には余り不自由でない。このような地の利を踏査して寺院僧坊の経営を考えたのは、やはりかなりの名僧か賢僧・偉人であろう事は想像に難くない。 平坦な山中が寺院跡で、古い石垣のあとが見られ、それらの分布よりして、相当規模の寺院があったものと思われる。そこに現に散在し、拾蒐されたもので旧「資母村誌」が調査した遺物は次のようなものである。 1、石柱 高さ三尺余(一m)三寸角 「正和四年(一三一五)乙卯十月十八日、願主沙弥蓮意」とあり、願主の名は明らかであるが、その形は墓標でもなく頂部の面が滑かである。燈龍の台柱でないかとみられている。(現在は金蔵寺にあり) 2、七重層塔一基(屋根二層及び九輪を欠く、外残缺二基)、空輪はないがかなり大きい。村誌は「極めて雄なるもの也」としている。 3、板牌無数、処々に発見される。 4、逆修塔三基、自然石でその面に弥陀三尊の種字と次の戒名が誌まれる。 大法師祐、權少都定重、同隆権律師舌 一基 (梵字)権少僧都賢恵、盛順、菩提永開通明 常金、妙秀、妙心、道心、道善、佑心 一基 (梵字)権大僧都(以下不明) 一基 永禄十一戊辰年四月五日施主各人存逆修 この三基が残っている。永禄一一年(一五六八)は、永禄元年加悦西光寺に真言宗金蔵寺が引越し、良真上人が再建された年より数えて二四年前で、この年金蔵寺が兵火にあって焼失という事は、各記録共みな一致し、元亀説もある。なお「逆修」は預修ともいい、死後に修せらるべき七七日の斎を、預め生前において修し、また生前に戒名をつけるものを云う。「随願往生十方浄土経」に「逆修の功徳の無量」を説いている。また「預修盛衰記」三に「入道祖国は福原にて逆修行われける」等とあり。この年は金蔵寺焼打ちの年であるので、山本氏由来書にもあるように「此証金蔵山大石塚」に「逆修」として刻み付けたのではなかろうか。なお永浜宇平氏(京都府中郡の人・故人)の調査によれば、丹後地方の逆修塔は「永禄」に最も多いといわれている。 5、木仏像一体 いわゆる十一面観世音菩薩これである。丈一尺八寸、平安末期仏教芸術の盛んなりし頃の作品と見られ、弘仁期の密教美術に見られる仏像に比して、この頃は比較的明るい日本人らしい容姿のものが多くなっているのが特徴といわれている。 6、仏具 碗十四個 当時の茶湯器とみられており、銅製で鍍金の跡が残っている。(金蔵寺蔵) 由来大石塚に刻み付けとあり、その遺跡・遺物があることからして何かが現存せしことは明らかである。しかしこれらの寺も、城と同じく存在していたとすれば多数の地元の住民とくに農民の労力や、当時の著名の寺院大工、宮師等が動員され、かなりの日時をかけて完成したものと思われる。これらの記事はないが、それを想像するに難くないものと思われる。町史や郷土史の任務の一つは、これらについての断片的な古文書や口碑、由来と、現存する遺跡や遺物を考證し、一つのまとまった史実に再現してみることで、その誤りや史料・推理の不足は、後日に訂正さるべきであるといえる。 2、寂室和尚と金蔵寺 既に「但馬考」も記しているように、中世の文学、宗教とその頃の但東町の有様を知るものとして寂室和尚の、但東町金蔵寺假寓の記事は注目に価する。 寂室円応禅師は諱を元光という。作州(岡山県)の人で正応三年(一二八八)五月一五日に生る。一五才の時江州(滋賀県)田上に至り、そこの僧の紹介により鎌倉に至り約翁に師事し、仏門に入る。当時中国支那の名僧天目山中峯和尚の名を聞き、後醍醐帝の元応二年(一三二〇)渡支、中峯の他古林・情拙・霊石等の大和尚の教をうけ、嘉歴元年(一三二六)帰朝、日本国各地を歴訪し、山陽・山陰・近畿の諸国の寺に半年あるいは一年止って、専ら聖胎長養すと。(「資母村誌」二二八頁)元弘の乱のあった元弘元年(一三三一)年には、但東町では太田判官が亀ケ城を築いた年である。その「但馬太田文」にも金蔵寺山領の記事がないから、その頃は開墾私領の山項の寺領であったかも知れない。太田氏の但馬太田文は弘安八年(一二八五)のことであるから、その頃は寺領として公認されていなかったかも知れない。しかし亀ケ城構築後九年の興国元年(一三四〇)寂室和尚が金蔵寺に来り、一年寓居し思索と作詩にふけっていることから見ても、金蔵寺は既にこのような名僧の寄寓しうる寺として存在していたことは明らかである。 その寄寓中寂室和尚は次の文章を残している。 寂室録金蔵山壁に二首書いて曰く 「借二此閨房一恰一年、嶺雲渓月伴古禅、明朝欲下厳前路、又向何山石上眠。 風攪飛泉送冷声、前峰日上竹窓明、老来殊覚山中好、死在巌根骨亦清。」 又備前要侍者予に偕て但之金蔵山に寓すという詩もある。(「校補但馬考」四二六頁) 生れたのが正応三年であるから、興国元年は彼が五一才の時のことであるといえる。 また寂室録によれば寂室和尚は金蔵寺の西麓の渓間にある虫生の田原に遊んだとして次の詩がある。 「九月一三日遊田原村、投宿茆舎、同来諸弟皆曲肱就寝、独開窓観月、聊写老懐耳。 戊子季秋将半日。田原村裏宿烟蘿。看来五○余霜月。幽興不如今夜多。」(「寂室録」) その他金蔵寺山上の作として次の文章がある。 「備前要侍者偕予寓但之金蔵山冬?千春忽一日辞往京師俚語以成?別云子伴病夫金峯索莫対雪擁爐口辺生 ?三玄三要瀬商量 四句百非渾?却 今朝又遂春雲掃帝郷 何日相逢共看山月白」 春夏秋変化多く、冬は雪が埋って爐辺に雪景色を楽しんだ中世の但東町の風光が、この寂室和尚の詩文によって知ることができる。 寂室録は更にその上巻六丁で 「戊子姑洗之未夫出遊而帰云々」 とあり南北朝の正平三年(貞和四年一三四八)から翌年の秋まで金蔵山に在ったことが知られる。禅師五九才の時のことである。 興国三年金蔵寺に来てからこの年まで、帝郷に帰ったことはあったが、かなり長い年月を金蔵寺山と田原村に遊び、作詩と寺院建立の想を練った寂室和尚は、その後正平一五年(延文五年)に佐々木氏頼と奥の島と雷渓の地に永源寺を創建し、正平二二年(一三六七)七八才で永眠した。 興国四年(康永二年一三四三)には前述養父郡の満福寺の碑が立てられた記録があり、一三五二年には「但馬風土記」がなり、宝徳四年(一三五二)には「太田文」が写されている。しかし、満福寺のように、のちの住職が寺歴を残していないこともあって、最盛期の金蔵寺山金蔵寺に関する記録は今のところ何も残されていない。 しかし但馬太田文には出ていないが、その後の隆盛は山岳仏教としての山地の開拓と他領の押領により山武士・僧兵を擁して寺領を二千石、ないし三千石を維持していた事は前述山本文書でも知られる。山本坊跡あり、杉本坊、松本坊があったといわれ、時に他の寺領等の押領を試みた事はその頃の山寺として容易に想像される。最も近い丹後野田川町岩屋の雲巌寺も相当な寺領をもっていたが、大永八年(一五二八)の頃、攻撃された記録を残している。例えば「縁城寺年代記」は、 「乙酉大永五(一五二五)与謝郡岩屋雲巌寺、兵火に羅る夏七月」 とあるは恐らく金蔵寺山僧兵によるものであろうし、「宮津日記・上の巻」に曰く、 「与謝郡炎上は、大永七~八年の頃(元禄一三年より一七二年前)の由にて、但馬国藤ケ森の近辺寺領にて有之候を、但馬城主押領改すべしとて二年の間度々攻来る」云々(「資母村誌」) 岩屋村の伝える口碑では城主ではなく、これは金蔵山金蔵寺の僧兵であって、絶えず攻めたり攻められたりしていたと伝えている。(「岩屋村誌」) この時代の文書や記録はどこかに残っているはずである。かって「三河内村誌」の編者が、金蔵寺山に関する古文書を持っているともらした事があった。恐らくこの頃の文書でないかと思われる。本町史編纂のためその遺族を訪ねてみたが、その編者は他界され、その文書の所在も知れなかった。 3、金蔵寺領の滅亡とその遺蹟 現在中山にある金蔵寺は、臨済宗であり、古い金蔵寺山金蔵寺とは別のものと見られ、一応廃絶寺院となっている。しかし口碑や由緒記によるまでもなく、元慶年間に開山されたといい、寂室禅師の寄寓及びそれらの文章といい、山頂に残る壮大な遺蹟・遺物といい、古くから残っている地名といい、中世に古い金蔵山金蔵寺が存在したことは疑い得ない。もし西光寺明細書の元慶四年を金蔵寺の創立年とし、永禄一一年に兵火により滅亡したとすれば、七四八年間また元亀年間織田氏によって討落されたとすれば、七五二年間、金蔵寺は真言の法燈を守っていたことになる。その間逆修塔にも見られるように、法燈を守った名僧がこの地に骨を埋めているのである。これがどうして亡びたであろうか。その間の由緒や文書についてみよう。 「資母村作誌」の伝える由緒記は 「元亀年間(一五七〇~七二)織田氏のために討落され爾来衰微せり」と。 また西光寺の明細書は、 「永禄一一辰年兵火に罹り焼失」云々。 また山本助太夫「山本氏由来書」は、 「永禄十一年辰四月四日大勢攻来り、思不寄事なれば寺々騒動し、弱き者は逃げ隠れ、早落ちゆくもあり、若き僧俗相戦しが、四日五日と両日焼討せられ、僧俗討死す。この證金蔵山大石塚に刻み付有り」と記されている。大石塚とは逆修塔なりと資母村誌はのべている。山上の寺院が何故繁栄したかは住民や地方豪族の信仰はもとより、開拓山地が寺領として私有が許され、あるいは黙認された事によるものといえる。その社寺領も亦、時の支配者・豪族に貢物を送り、その祖先一族を祀り、回向して支配者から更に寺領や山を寄進されるよう、政治的支配との癒着に努めた。しかし山上の生産物のない処で僧侶を養い、寺院を維持するためには、他領を押領し、山林や村落を住民共寺領に治める必要があった。寺院の特権を背景とした僧兵などはそのため必要で、天台宗などはそれが繁栄の原因となっていた。 このようにして中世は戦乱相次ぎ、戦死者を葬るための新しい宗派も起り、寺院は充実され、寺院領の勢力は、時として地頭や御家人の勢力を上廻るものがあった。 この間領国大名の統一が行われ、織豊時代に入って天下の統一のためには、諸国大名小名の他このような独立国家の形をもっている寺領を統一し、それを拒むものは平定する必要があった。 「但馬史」は天正年間からの織田・豊臣の数次に亘る但馬征伐の様子を詳細に記述しているが、これら織豊勢力による但馬の統一は、当然僧兵のこもる金蔵山金蔵寺の平定に及んだものと思われる。山本文書の示す通り、永禄一一年の攻撃は急であったため、寺院と古文書は焼失し、有力な僧も討死したものと思われる。 口碑記説によれば攻め已した武将は織田信長の臣森蘭丸ともいわれているが、年代は元亀年間とも永禄年間ともいう。金蔵山金蔵寺に残る逆修等には永禄一一年(一五六八)と記録されているが、数次の但馬征伐により、僧等は寺領が征服の運命にある事を予知し、逆修塔を残しだのかも知れない。ともあれ、この年は信長が足利義昭を奉じて京都に入り、諸国の関所を撤廃した年であり、元亀年間といえばその二年後の一五七〇年で、信長・家康等相次いで入京し、皇居の工事を行い、長島一向一揆等、仏教徒の反乱に対し、徹底的な征伐を行った年代である。この意味では岩屋の雲巌寺や、他の寺領によって攻略されたのでなく、織出・豊臣の全国平定の事業として、その軍によって滅亡されたと見るべきである。もし織田氏がそれを滅ぼさなかったとしても、秀吉は但馬征伐で彼に反抗した人達は、徹底的にやっつけた(「神美村誌」)といわれているから、秀吉が天正年間に入って攻略したのかも知れない。前記「十二所村史」の新宮山満福寺も、「降って天正中秀吉の此国に來り、亦兵火の為に焼かる。唯存するところのものは本堂一宇及び本浄院一院のみ、其余大悲の尊像易産の秘符亦幸に甚災を免る」(二〇頁)と寺歴は書き残しており、村史も「秀吉の但馬征めの戦火により、古文書の如きものは現存していない」と記している。金蔵寺の最後もほぼ同じであったと思える。ただ金蔵寺の場合は八丁四方に亘る遺跡と、古碑だけが残っている。いずれにしてもそれは、山陰の山奥に残された中世以降の寺領荘園の最後であったとみるべきであろう。 しかし真言の法燈は消えなかった。祖先をこの寺により葬った地元の壇家は、支院西光寺に集り、一時赤花字寺岡に移った。今でもここに二〇数戸の壇家がある。支院西光寺は金蔵山金蔵寺焼失後、赤花から加悦町字後野に移り、焼失後二四年のちの文禄三年(一五九二)良真上人が西光寺を興し今日に至っている。加悦後野の西光寺は、入口にその標札を掲げているし、古い山門は、その後改築はあったとしても古いその当時の面影を残している。惜しい事に鐘は戦時中供出してしまい、鐘銘から昔を忍ぶことは許されなくなっている。 金蔵山上の金蔵寺はその後徳川時代となり、「荒艸漫々野鹿群嶺猿抱子者年尚矣三四歳」という状態にあったが、明暦四年(一六五八)肥後国泰睛寺興山犬禅師がこの山に来て古刹の中絶せるとなげき再興したが、鎌倉仏教として開祖栄西が建久六年(一一九五)に開宗した臨済宗の寺として初めて禅風を吹き込んだ。また嗣席炎雪禅師、次に守玲祖傳、次に義範がこれを継ぎ、膏油の田二〇石余を買い付け、また金蔵山の山峯が嶮岨で交通に利便でないので、明和元年三月二一日に寺を中山の山添の地に移した。 (金蔵寺由緒「資母村誌」一一二~三頁) 宗派は変わったがその法燈は今の金藏寺に受継がれているといってよい。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 口藤の主な歴史記録口藤の伝説口藤の小字一覧関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||