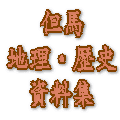 |
虫生(むしう・むしゅう)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虫生の概要《虫生の概要》 太田川の北岸にあって、出石・宮津道(丹後道)が通る。古くは中山村のうちであったが、寛永19年(1642)に同村の 虫生村は、江戸期~明治22年の村名。但馬国出石郡のうち。寛永19年中山村から分村して成立した。出石藩領。鎮守は式内社の安牟加神社。明治22年資母村の大字となる。 虫生は、明治22年~現在の大字名。はじめ資母村、昭和31年からは但東町の大字。平成17年より豊岡市の大字となる。 ムシウという地名、あちこちに見られるが、死骸を埋めるところ、それは山裾であるが、そこをムショという。ムショには普通詣らない。詣るところはラントという。そうした地名かも知れない。 《虫生の人口・世帯数》 50・23 《虫生の主な社寺など》  丹後街道(県道2)沿い北側に鎮座。古くは  本殿↑もさることながら、当社は歌舞伎舞台↓が有名。このあたりの神社の境内は立派な舞台がたいていは併設されている(農村歌舞伎舞台は資母地区に5、高橋地区に8、合橋地区に8の計21残存)。その中でも当社の舞台は最上級のものという。文久元年(1861)以前に建てられたという。 豊岡は演劇の町、あそこに立派な演劇学校を建てたい、先生その設計をしてくれませんか、それよりも廃校があちこちにあるでないですか、あれを使ってはどうでしょう、とか聞いた(安藤忠雄氏の話)、前の知事さんの時代だが、どうして言うのか知らなかったが、これでガッテン。これら農村舞台こそがその源流なのであろう。 舞台床面が低い、これなら見やすいだろう。舞鶴に残っている舞堂は床面が高い、背丈ほどもあって、当時の農民なら背伸びしても床面は見えまい、どうやって見たのだろう。  案内板がある。 兵庫県指定文化財
安牟加神社 農村歌舞伎舞台 農村歌舞伎舞台は近世から近代にかけて、庶民の厚い共感に支えられた文化施設だった。 農村へ歌舞伎が浸透しはじめるのは江戸時代初期で、十八世紀に入ると地芝居が農村でも上演されはじめる。寛政十一年(一七九九)江戸幕府は芝居禁止令を出し、「神事祭礼の際とか虫送り・風祭りなどの名目で芝居・見世物のようなことを催して見物人を集め、金銭を費やしているのでそのようなことは一切してはならない」とし歌舞伎関係者の入村や遊芸・歌舞伎・浄瑠璃・踊り類も厳しく禁止した。 地芝居を催す主体は基本的に村の青年組織である場合が多く、この若者たちが次第に禁令を犯して芝居を強行するようになっていく。但馬では関宮町葛畑座、日高町堀の手邊座、但東町の虫生座などが知られている。 かつて但馬地方は農村歌舞伎が盛んで、どこの地区にもこの舞台があったが、現在では舞台の老朽化に伴い急激に減少している。町内では十八棟の農村歌舞伎舞台が現存しているが、最盛期にはその倍近い四十棟弱であったと推測される。 本町では江戸時代末期から明治時代にかけて盛んに建てられ、神社の境内などで地方廻りの役者一座や農民自身が歌舞伎などを上演して大人気を博していたようである。 本農村歌舞伎舞台は「撥転がし」や「遠見機構」、「上段舞台」などさまざまな仕掛けが工夫されており、文化財的にも但馬地方に残る歌舞伎舞台の代表的なものとして貴重なものである。 舞台の構造 ●桁行/6665㎜ ●梁間/4490㎜ ●軒高/4415㎜ ●軒の出/1210㎜ ●屋根勾配/0・50 ●瓦葺(本来は茅葺) ●舞台の高さ/約790㎜ 常設の上段舞台 ●桁行/3120㎜ ●梁間/1705㎜ ●高さ/450㎜ ※前面框に障子か襖の溝が二本彫られている。 遠見機構 上段舞台の背面に蔀戸のように上下二つ折になっている。遠見と呼ばれる芝居の背景が提げられる装置であるが、借景として正面に東里ヶ岳全体が美しく見られるよう配慮されている。 撥転がし 舞台の床が前方観客に向かって緩傾斜し、観客に演劇効果を考慮したものである。 墨書痕 文久元年仲夏二五日若狭藩中石井某 建立時期 舞台壁面に残る墨書痕から文久元年(1861)以前と考えられる。 平成15年3月 但東町教育委員会 系列は舞堂との呼称があることや建築様式などからみて舞堂系に属するという。構造上注目すべき点は舞台床面の傾斜だという。能舞台にみられる撥ころがしと同じような造りで、舞台の床面が観客席の方へ向けて少し傾斜している。観客が見やすいようにと工夫された構造で、全国的にもまれな装置といわれるそう。  床が傾けてあるといっても、ほんのワズカである。言われないと気付かない程度。太鼓を叩く丸いバチが転がる程度の傾斜だそう。ペットボトルが転がるか、やってみないと、持ち合わせがなく、試せず。 これくらいの傾きなら、どこにでもありそうなことで、ワシの家は、床にボールを置くと、コロコロ転がっていきよるデ とか聞く話である。 その歌舞伎はいつ消えたものかわからないが、この舞台で秋の祭りに奉納される大古踊りは、ささばやしともいわれ、しんぶち(新発意)と〆太鼓の子供たち3人で踊るという。 『但東町誌』 虫生の太鼓おどりとささ囃しの歌
安牟加神社祭礼も一〇月八日、仐鉾を先頭に老若男女の氏子が、屋台に大太鼓をつみ、これに小太鼓を前腰につけた少年三人を乗せ、一同県道を行列し神社に参拝する。拝殿では三人の少年が、おどり保存会二〇余人の歌に合わせて約二〇分間、典雅に舞う。服装は紅白の鉢巻と同じたすきをあやどり、黒木綿和服袴に白足袋をはく。この祭礼は何年ごろからの伝統であろうか、父子孫とつづいて太鼓おどりをつとめた家系もみられる。 歌の一節 やんかん鎌倉の御所のお庭に植えたる唐松 やん唐松の一の小枝に御所のお鷹が巣をかけた やん片羽がやぜぜの紅梅紫の やんあら美事鷹の巣下し恋する姫に見せばや (後略) 当社は「延喜式」神名帳にみえる出石郡の「阿牟加神社」に比定される。豊岡市森尾の阿牟加神社とする説もある。 『豊岡市史』 「論社」とは、式社調査によって式内社と確定するについて論の分かれた神社をいう。『校補但馬考』は論社の起因として、流行神の合祀や社号のみだりな変改の他、分霊奉祀の結果、主社枝社の別が不明になった場合などを示唆している。
いずれにせよ延喜式(延長五年〔九二七〕完成)以来の年月と習合の実態が式内社の索定をあいまいにしてしまったものである(表82)。 市内の論社については、既に上巻に一部を記述した。ここでは、新資料によって森尾地区の阿牟加神社を取り上げる。 阿牟加神社は延喜式には「出石郡、阿牟加神社」とだけあるが、郡内には出石郡虫生村(但東町)と出石郡森尾村(豊岡市)に併立していて、『大日本史・神祇誌十七』は「虫生村」とし、『但馬式社考』は「安美郷大内庄森尾村」としている。 兵庫県豊岡市森尾の安牟加神社の祭神は、 天湯河板挙命(現在)、天穂日命(伊能忠敬測量日誌(文化11年〔1814〕)当地に測量のため立寄ったときの記述)、天穂日命(但馬神社深秘考(明治2年〔1765 〕 )、 物部十千根命(国司文書、城崎郡・気多郡・出石郡各故事記(平安時代の著とされる)、天湯河板挙命(伝承、特選神名牒、神祇志料による) 阿牟加荒神(江戸時代までの習合神号) 結局は虫生村の阿牟加神社が式内と決定され、森尾側の反論が相次ぐこととなったものである。 明治七年(一八七四)九月に森尾村から豊岡県にあてた陳情によると、二年八月に久美浜県式社内外検廻のため朝来郡竹田町の神官・荒尾近江と出石藩少属・橋本八郎兵衛が検社、森尾村の阿牟加神社を式内社と認め、翌三年三月には出石藩から式内社として保逞し標識などを立てるよう指示されたという。 七年に至り、虫生村氏神"箱ノ宮"が式内阿牟加神社と認められ、森尾村阿牛加神社は式外と心得るよう沙汰された。"箱ノ宮"は出石藩時代も式内と称していたが証拠はなく、検廻神官や橋本に潜称することの不当性を説諭されたほどである、と森尾村は激しく式社不認定措置に抗議した。 八年一月に森尾村は、同じく式社認定を奥野村の大生部兵主神社と争った三宅村(安美郷戸主大生部兵土神社)と連名で、両社ともに式社として両村に鎮座したことを立証する文書を人手したとして認定の再考を願い出た。 式社認定は流動的であったらしい。二十八年には兵庫県訓令二十号によって、森尾村は再び阿牟加神社の式内認定を願い出たが、却下された。 森尾村の場合、神社のある谷一帯を「阿牟加谷」と呼ぶのに対し、虫生村側は「あむか側」「あむか杉」の名がある上、「阿牟加神社」と記した鰐口があったと言い伝えている。問題は祭神で『神祇考証』では天穂日命、『新撰姓氏録』に「奄我」は天穂日命の後とあるのに、森尾村の場合は天湯河板挙を祭るとされた点て虫生村に一歩を譲ったのではないかと考えられている。『校補但馬考』は森尾村阿牟加神社の祭神が鳥取部の祖・天湯河板挙である場合、「あむか」は「網加=安美郷」であろうと推論している。 『資母村誌』 安牟加神社
虫生村字筥の宮に在り、式内社にして現今村社なり、祭神天穂日命。 素盞鳴尊乞取天照大神髻髮及腕所纏八坂瓊之五百箇御統灌於天眞名井?然咀嚼而吹棄氣噴之狭霧所生神號日正哉吾勝克速日天、忍穂耳尊次天穂日命(是出雲臣土師連等祖也)『日本書紀』 皇祖高皇産靈尊欲立皇孫天津彦々火瓊々杵尊以爲葦原中國之主召集八十諸神而問之曰天穂日命是神之傑也即以天瓊日命往平之然此神佞媚於大已貴神比及三年尚不報聞云々。『日本書紀、古事記參取』 出雲宿稱出雲入間宿稱神門臣土師宿稱菅原朝臣秋篠朝臣大枝朝臣山直石津連民直贄土師連以上天穂日命より出づ。『姓氏鋒』 天穂日命天照大神忍穂耳命を降し給はんとする時、國土未騷乱す仍て此命を遣はし平定せんと大穂日命大國主命に媚び復命せざる事三年遂に若日子を代らしむ、後大国主歸順し天日隅宮にかくれ、此命をして祈の事を司らしむ。 神體封箱の御魂なり 創立年不詳、亨保十六年九月二十三日再建、明治六年十月村社加列、明治四十二年上の宮神明社合祀。 境内攝社稲荷神社、祭神保食神三柱神社、保食神、稚皇産霊神、蒼稽魂神、上宮事解男神、神明社大日霎貴紳(天照大神)木像古神體あり。 一札 再建阿牟加神社享保十六年辛亥九月二十三日大工出石八木町大工七右術門 一鰐口 正保年中記銘のものありしも、神佛區別之時取除き後紛失せりと 一燈寵 寛政九年六月 境内坪數 百四十八坪外に一反一畝八歩、明治三十八年五月編入。 氏子數 八十五戸。 祭日 十月十四日祭禮として傘鉾あり。 本社古来より角力之行事は神慮に叶はずとて行はず、蓋、祭神天穂日命は土師の祖野見宿禰と同系なればなり。 奄我神社丹波天田郡奄我村にあり、聖大明神と云ふ、蓋天穂日命を祀る、土人但馬阿牟加神社傳説なりとて、寳龜四年壬辰九月丹波天田郡奄我神社、盜供祭物を喰ひ社中に斃れたるを以て本社を距る事凡十丈許の地に更に社を建て之れを移す(『續日本紀』寶龜四年九月記)以て本社と関係を有するならんも由緒不明なり、但傳説のみ今は口碑に存す。 『但東町誌』 安牟加神社 祭神 物部十千根命 (「但馬世継記」延長三年(925)四月)
安牟加とはナニか 出石郡には2社あり、「室尾山観音寺神名帳」の「熊野郡八十四前」にも、 正三位 丹波天田郡式内社に こうした名の社は全国探しても、この周辺だけにしかなく、解明は難しい。 《交通》 《産業》 『資母村史』 鑛坑の跡 西野々村字本谷にあり、金屋の字を存し愛宕山裏に金屑石多く出づ太田村にも金屋、吹屋、イモヂカエ、トギダ等の字を存す、往昔鉱石發掘し鍛練せしものならん虫生村字向金山坂野字轟にも鑛坑あり。 《姓氏・人物》 虫生の主な歴史記録虫生の伝説虫生の小字一覧関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||