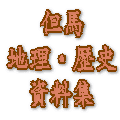 |
中藤(なかふじ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中藤の概要《中藤の概要》 丹後からだと野田川上流にある岩屋峠(↓)を越えて、但馬に入った最初の集落である。丹後の続きのような場所にあるが、円山川に注ぐ出石川支流太田川最上流域になり、但馬の水系である。 今年は藤の花が綺麗、岩屋トンネルにも垂れ下がっていた。  この県道2号(宮津養父)線、出石宮津線、俗称・出石街道、丹後街道は、かつての西国33箇所霊場の参詣道で、27番書写山円教寺(姫路市)から28番成相寺へ、ずいぶんと長い道の一部であった。また当地で出石・宮津道から分岐南下し、奥藤森村を経て加悦奥峠を越えて与謝郡加悦奥村に至る道も通じており、地内の出石・宮津道沿いには「左なりあい道 右かや道」と記された道標(↓)が残る。  白い車が走って行く方向に成相寺がある。あと15キロほどである。 右ヘ行けば奥藤を経て、加悦の縮緬街道へ出る。 古くは口藤森村・奥藤森村と一村で 但馬に行くのなら、ぜひ鴻の鳥に会いたいと願っていたのだが、それは何とも簡単にすぐに実現した。  その三角の道標を写していると、近くの電柱の上に大きな鳥影が舞った。見ればコウノトリだ、コウノトリの出迎えだ。 その三角の道標を写していると、近くの電柱の上に大きな鳥影が舞った。見ればコウノトリだ、コウノトリの出迎えだ。オマエはそこでナニをしておる 古い道しるべを写しております そんなつまらぬ物を写してどうする 趣味です 写すのなら美しいワタシを写しなさい 剥製しか残されていない絶滅状態から、よくここまで回復させたもの。拍手! あと一つは牛。 これからはチョっと長いレンズを持って行くことにしよう。 《中藤の人口・世帯数》 66・28 《中藤の主な社寺など》  玉宗寺の隣に鎮座。 『資母村誌』 八幡神社
中藤字八幡山。 村社にして祭神誉田別神 誉田別第十五代應仁天皇御名誉田別尊又は大鞆別命胎中天皇とも稱す。仲哀天皇の第四皇子にして母は神功皇后なり。仲哀天皇の九年十二月筑紫に生れ給ふ。時に仲哀天皇既に崩じ天皇尚幼稚なるを以て神功皇后攝政し皇太子とす。皇后崩後年七十一にして始めて即位す。五年諸国に海人部、山部を定め山海の政を整ふ。 當時三韓征服之後なりしかば韓土之人來り投するもの多く、技藝學術を輸入せること尠なからず。卯十四年には百済より縫衣女を、十五年には良馬を貢し翌年王仁來朝、論語千字文等を献じ二十年には漢の靈帝の孫たる阿知使主十七縣の民を率ゐて來朝せる等我邦文明史上に於て注意すべき史實甚だ多し。四十一年二月崩す。壽百十一(古事記百三十となす)河内國惠我藻伏崗陵に葬むる。 元明天皇和銅五年豊前國宇佐に祀り、八幡大神宮と號し、清和天皇は山城國男山石清水社を創め、共に歴朝の崇拝頗る厚し。『大日本史』 神體 衣冠束帯の坐像 創立 年不詳、寶暦十二年八月再建、文化十二年三月十五日上屋再建、明治三十三年九月十五日再築、明治六年十月村社格加列。 一札 奉上棟八幡宮上屋再建立文化十二亥歳三月十五日村内安全祈所。 境内社 稲荷大明神元文五歳十月八日玉宗禪寺現住良因修造の札あり。 一鰐口銘 奉掛八幡宮、但馬國出石郡太田谷中藤ヶ森村、貞享三年丙寅九月吉日庄屋善太夫女。 一燈籠一對 寛政八年八月吉日 境内坪數 九十三坪外に四畝二十二歩明治三十八年五月編入 氏子數 四十五戸 祭日 九月廿八日 本社と丹後大成八幡社と開係ある歟。 又本社と云ひ阿蘇社と云ひ、九州に関係あるは一考すべきなり。 『但東町誌』 中藤の太鼓おどりとささ囃し
中藤、八幡神社の祭礼も同じく行われて昭和に及んでいたが、戦後取りやめられたまま今日に至っている。囃しの歌い方やおどりは虫生と同じであったが、歌詞はちがっていた。  『資母村誌』 阿蘇神社 中藤村字阿蘇
名から見ればこの社は古い、日槍さん一族が開拓した地に祀ったもの、比遅神社のシ、阿蘇神社のソは新羅の意味で、新羅(加耶)神社の意味であろう。祭神 阿蘇津日凝神 『日本書紀』景行天皇十八年六月の條に、丙子阿蘇國に到る其國郊原曠遠人居を見ず、天皇曰是國人有る哉と時に二神あり曰阿蘇都彦、阿蘇津媛忽化して人となる、曰く吾二人あり何ぞ人無き哉と故に其國を號して阿蘇と云ふ。 神體 封箱 創立年不詳 文政九年上屋再建、大正十一年上屋再建拝殿新築。 坪數 四百四十一坪 本屋は往古九州より勘請せしとの口碑あり。  八幡神社の隣にある。まるで要塞のような石垣。この裏山には中世の山城跡があるので、そうした関係ではなかろうか、八幡神社も同様と思われる。街道を挟んだ南側のやまにも城がある。丹後街道押さえる軍事上の要地であったのであろう。 『資母村誌』 玉宗寺
資母村寺院明細帳に曰く 出石郡資母村之内中藤ヶ森村字宮ノ下 曹洞宗吉祥寺末 玉宗寺 一、本尊 聖観音 一、由緒 不詳 一、本堂 桁行五間三尺 梁行四間三尺 一、庫裏 桁行七間三尺 梁行四間 一、鐘楼堂 方一間 一、土蔵 桁行二間半 梁行二間 一、廊下 桁行二間 梁行二間 一、境内地 二百八十八坪内() 一、檀徒 六百七十二人 一、境内 佛堂一宇 禪堂 本尊 如意輸観音 由緒 不詳 建物桁行三間 梁行三間三尺 1、山號並本尊に孰て 玉宗寺は永平寺派に屬し三等法地なり。山號は現に寶珠山と云ふ。?佐大和尚開闢の寺に寶珠山と呼べるもの合橋に如意寺あり。高橋に樂音寺あり。當寺は元禄享保の頃は藤林山と呼べる如し。古器、古佛像等には藤林山と記せるものあり。 私に謂へらく二世南谷天宗和尚再興の時迄は藤林山玉窓寺と云ひしにあらざるなきや。本尊は聖観世音菩薩にして脇立は阿難尊者迦葉尊者なり。 別に又聖観世音菩薩の像(傳惠心僧都作)有りて舊本尊と稱す。新舊兩本尊は何れの年代に、又何の理由によりて換へたるやは分明ならず。但舊本尊は江外和尚の時安置されしこと明確なり。而して當寺最古の過去帳を閲するに 高岳宗榮居士 延享四年十一月六日。 永盛院哲叟道賢居士 享保二年十一月三十日。 純善院節操貞義大姉 享保二年 月三十日。 此諸霊位當山本尊施主也云々 江外和尚は元禄四年に示寂せり。然らば、享保、延享等は皆元禄以後なるが故に、新 本尊を安置せる年代は略推知せらる。 2、由緒 文祿四乙永年祖道和尚の開創にして、寛永十五戊寅年迄平院なりしが、同年三月十日に至り良因和尚公稱し、慶安元戊子年梵唱山吉祥寺三世祐山?佐大和尚始て法地を開闢し伽藍を再建して教化開發に盡せり。由って祐山大和尚を開山となす。 右は當寺に傳ふる由緒なり。然るに良因和尚は示寂の年月は不詳なるも、寛永時代の人にあらず。現に本堂前に塔ありて 表 三界萬靈等 右側 寶暦三癸酉九月十八日 現住良因記 と云へり。寛永と寶暦は百餘年を距つ。況んや左の文書あり。 乍恐差上申一札之事 一、但馬國出石郡藤森村玉宗寺儀ハ 山和尚開闢而寛文八年三月公儀載帳仕候處相違無御座候右ニ付此度了因僧法 地ニ仕度奉願上勿論伽藍並寺徳且檀家等別紙書上之通り少茂相違無御座候得 共永ゝ法地相績可仕儀ニ奉存候云々 明和三年三月 以上を綜合すれば寺傳の由緒外に、胸底に湧出し来るもの有るを覚ゆ。 3、歴代及沿革 開基 一山祖道禪師 寛永八年三月十三日 師は何許の人なるや詳ならす。與謝郡四辻寶泉寺も師を開祖となせり。 開山 祐山?佐大和尚 慶安二年三月五日。 師に就ては人物傳を參考すべし。 二世 中興南谷天宗大和尚 寶暦五年二月二十六日。 三世 太然覚聞大和尚 寛政三年九月二十八日。 四世 雷義玄黙大和尚 天明四年十二月二日。 五世 黄梅□定大和尚 同年十月十九日。 六世 萬奇太林大和尚 天明七年二月十八日。 七世 賢外徹明大和尚 寛政四年六月十三日。 略 4、洪鐘其他 … 『但東町誌』 宝珠山 玉宗寺 (中藤)
曹洞宗 永平寺派 吉祥寺末 本尊 聖觀音 由緒 不詳 本堂 桁行五間三尺 梁行四間三尺 庫裏 桁行七間三尺 梁行四間 鐘褸堂 方一間 土蔵 桁行二間半 梁行二間 廊下 桁行二間 梁行二間 境内地 二百八十八坪… 擅徙 六百七十二人 境内 佛堂一宇 祠堂 本尊 如意輪觀音 由緒 不詳 建物 桁行三間 梁行三間三尺 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 中藤の主な歴史記録中藤の伝説中藤の小字一覧関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||