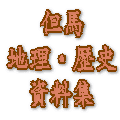 |
奥藤(おくふじ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥藤の概要《奥藤の概要》 中藤で出石・宮津道から分れ、加悦奥峠を越えて与謝郡加悦奥へ至る道が通る。これが古代の官道といわれる。 古くは北西の口藤森村・中藤森村と一村で藤森村と称していたが、寛文6年(1666)に村切をしてそれぞれ一村となった。 奥藤は、大正6年~現在の大字名で、明治22年資母村の大字、昭和31年からは但東町の大字。平成17年より豊岡市の大字となる。もとは資母村奥藤ヶ森。 《奥藤の人口・世帯数》 57・22 《奥藤の主な社寺など》 太田川流域の資母地区では、奥藤遺跡など、隣接する丹後地方と共通の特徴をもった土器片が出土し、密接な交流があったことを示している、という。 『資母村誌』 奥藤古墳 多寳院北方山上にあり、既に發掘の厄に遇ひしも石槨存し奥行二間間口五尺の圓墳なり、遺物等未だ發見せざるも奈良朝前のものなるが如し。
 奥宮神社には寛文13年と文政2年(1819)の修復棟札が残る。郷土芸能に大刀振りがある。 『資母村誌』 須賀神社 奥藤村字山内に在り。
祭神は保食神 相殿に稚皇霊神、蒼稽魂神。 保食神は蓋し豊受神、又は豊宇気毘賣神也 『日本書紀』曰天照太神在於天上曰聞葦原中國有保食神宜爾月夜見就候之、月夜見尊受勅而降、已到于保食神許、保食神丸廻首嚮國則自口出飯又嚮海則鰭廣鰭狭亦自口出、又嚮山、則毛?毛柔亦自口出、夫品物悉備貯之百机而饗之。是時月夜見尊忿然作色曰、穢矣、鄙矣、寧可以口吐之物敢養我乎、迺拔劍撃殺、然後復命具言其事、時天照太神怒甚之、曰汝是惡神、不須相見乃與月夜見尊、一日一夜隔離而往、是後天照太神復遣天熊人、往看之、是時保食神實已死矣、唯有其神之頂化爲牛馬、顱上生粟、眉上生蠶、眼中生稗、腹中生稻陰生麦及大豆小豆、天熊人恐取持去而奉進之、干時天照太神喜之曰、是物則顯蒼生、可食而活之也、乃以粟稗麥豆、爲陸田種子、以稻爲水田種子、又因定天邑君、即以其稻種、始植于天狹田及長田、其秋垂穂八握莫了然甚快也、又口裏含蠶、便得抽絲、自此始有養蠶之道焉、保食神、此云宇気母知能加微、顕見蒼生此宇都志枳阿烏比等久佐『古事記』伊邪那岐、伊那那美、生和久産巣日神、此神之子謂豊宇気毘賣神。(以下同書紀)但本書作大気津比賣神 『資母村誌』は昭和9年発行なので、その当時は山内という集落があったのだろうが、今は地図にもない。たぶんとっくの昔に廃村になったのでなかろうか。村の西に金蔵寺山があるが、その東山中にあっのではなかろうか。 『但東町誌』 奥藤山内の萱堂と観音祭
このように中世における金藏山金蔵寺の記録は、その後全く消滅してしまった。庶民が文字による記録を残さなかった中世の特質ともいえるが、その中にあって民間信仰による祭祀行事は、一つは父祖伝来の信仰に基く口述口碑により、二つには庶民の日常生活と結びついた年間生活行事、とくに民間信仰を基礎とした慰楽、レクリエーション行事として伝承されている。奥藤の「佐古文書」によれば、現に奥藤山内にある萱堂は「中世金藏山に七堂伽藍のあった当時の遺物で、伽藍廃滅後山から下され、須賀神社境内に移されていたものを明治初年(?)現地に再建したものと伝えられている」とされている。金蔵寺の滅亡は一五六九年の永禄一二年とされている。明治元年は一八六八年である。その間正に三〇〇年間、この木造建築物がどのように保存され、修繕されてきたかは知る由もないが、建築物としては残存しうる事は他に例は多い。しかし佐古文書は「その構造は堅牢であって、明治四〇年(一九宅)の大暴風雨の際、突風のため全部吹飛ばされ、道路下に転落し『真逆様』(まっさかさま)に倒れたが、構造に破損なく、完全にもとに復したという。その後昭和四五年山内に道路改修があり道路敷地となったため堂を撤去し、元公民館跡の現在地に移建した」と記録されている。 この萱堂では毎年旧盆八月一七日に「観音祭り」が行われ、山内地区の老人が集り、念仏を奉唱した。またこの日は部落親戚を招いて夕食を楽しむこととなっていたが、いつの日か、老人もいなくなり、この観音祭りも廃止となった」といわれている。しかしこの萱堂だけは今も残って中世金蔵山の唯一つの遺跡となり、四〇〇年の歴史の生ける証物となっていることが、佐古文書で伝えられているのである。中世の但東町史を物語る数少い建物といえよう。  文化2年(1805)銘のある庚申塚。 但東町域は80基の石造庚申塔が確認されている。うち河本・佐々木・佐田・久畑・大河内・赤花に残る庚申塔はいずれも高さ1-1・5メートルの板状の石に庚申像が浮出るように彫刻され、その塔には屋根も構築してあって、手厚く信仰されていた様を今に伝える。 《交通》 《産業》 出石鼻緒 強くて美しいことで知られる出石鼻緒は当村で作られていたとされる。当地の佐古家に残された文書によれば棕櫚の荒を哂して純白に仕上げるためには昼も夜もなく、夜業は深夜に及んだという。 『但東町誌』 藩下の副業奨励
出石藩はその産業振興政策として各種の副業を奨励したことは「校補但馬考」にも記されているが、その一つに「出石鼻緒」の製作があった。これらの副業は管下に奨励されたが、「佐古文書」によるとこの下駄の鼻緒の製作は奥藤の極楽の協同事業として行われ、その製品は、明治中期頃まで出石町で販売されたといわれている。このような農家の副業は、手間の多い、純朴な農山村の人々によって行われ、冬期等の藁仕事に加えて行われたものと思われる。それが奥藤部落のような、丹後国境の山村で守り継がれてきたという記録の中に、上からの藩の命令や奨励事項を忠実に、親から子へ伝えて来た山村の善良さと素朴さを窺い知ることができる。 「その鼻緒製作は、棕櫚(しゅろ)の荒を漂して純白に仕上げ、明治の中頃は出石町内の各店に販売され、名産のひとつとして流行したが、極楽では出水重吉一家を中心に昼も夜も製作し、夜業は深夜に及んだ。そのおやつとして、どの家からも里芋(さといも)を栽培して、それにあてたという。その慣習が今も残ってか、里芋づくりは家庭消費以上に増植し、昔を物語るものになっている」 (「佐古文書」) その下駄も鼻緒も今は過去の思い出となってしまったが、雨や雪の多い但東町で下駄は重要な庶民の履物で、そのぬれて切れ易い鼻緒をしゅろで作ることが奨励されたのである。 《姓氏・人物》 奥藤の主な歴史記録奥藤の伝説奥藤の小字一覧関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||