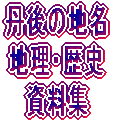s{^ÓS{næ s{^ÓS{næ
s{^Óì¬âê¬
|V´§Ïõ|
åÈà̾¯
i¶ìnæj
 q¶iqb̶ìj q¶iqb̶ìj
 r
[hW]äiò´Ïj r
[hW]äiò´Ïj
 Ò̼« Ò̼«
 V´§·òiqbÌj V´§·òiqbÌj
 mbÌÝi´§¼¨j mbÌÝi´§¼¨j
 mbÌÖ mbÌÖ
 ôù´ ôù´
 V´§ÏõD V´§ÏõD
 ú{OiFV´§ ú{OiFV´§
 é´ é´
 ´§¾_ ´§¾_
i{næj
 Oãê{E³É¨EâÄ_Ð Oãê{E³É¨EâÄ_Ð
 ^¼ä_Ð ^¼ä_Ð
 P¼ö P¼ö
 ¼28ÔDF¬ ¼28ÔDF¬

 ½y¿Ù ½y¿Ù
 ª¬ ª¬
|
qt½ÌTv
 @ua¼´vOã^ÓSµ½ÌPÂBR{ÌPÍugçV£B @ua¼´vOã^ÓSµ½ÌPÂBR{ÌPÍugçV£B
uOãyLví¶ÌVÖ§ðÉÍA¬Î¢Æ éB
VÖ§
OãÌÌyLÉHÍAäoÓÌSBSÆÌkÌ÷ÌûɬÎÌ¢ èBÌ¢ÌCÉ·å«ÈéO èB·³ÍêçñSùãäAL³Í½éÍãäȺA½éÍ\äÈãAùäȺÈèBæðVÌ֧ƼïAãðvuÌlƼÃBR]ÓÍA¶Ýܵµå_AÉËÞ|½AVÉÊÐsÅܳÞƵÄAÖðìè§Ä½ÜЫBÌAVÌÖ§Æ]ЫB_ÌäQܹéÔɻ굫B¹¿vuõÜ·±Æð~ݽÜЫBÌAvuõÌlÆ]ЫBðÔÉvuÆ]ÖèBæèÌCðäoÓÌCÆ]ÐA¼ÌCð¢hÌCÆ]ÓB¥ÌñÊÌCÉAGÌLZßèBAA¸ÍRµB |
qt½ÍA{Ãs{næ©çâê¬Éܽªé¢hCðÍÞnÉäè³êÄ¢éB
ãÌ{ÌnªÜÜêAÃãÌ{ª Á½Æ³êéªAC^[ÌnÌãiÞÇúújÉÍAnÉÍÈ©Á½Æ©çêéLqÅ éBSÆÌÊu©ç¬Î¢ðྵAnÉ Á½Æ³êéåÉiÞÌE±Å éjÉ¢ÄͽàLªÈ¢Bàµ{Éåɪ Á½ÌÅ êÎAuSÆÌkÌ÷ÌûɬÎÌ¢ èvÆ¢Á½«û͵ȢŠë¤A¬ÎÌ¢ÍåÉÌ éƱëÆL·Ìª©RÅ ë¤BÌOãåÉÍ¢¸±É Á½ÌÅ ë¤B
µºÁÄA¶¡4N(1188)ÁðL·é{âÄ_ЫàoyoÉuìè
ñåú{RA¹Oã@^ÓSqt½aKºiºªjvÆ©¦éB
uOãc vÉÍ
ê@qu½@µ¬liñSÜ\Zàà
@@ê¬@@@@@@@@@@@óèLÐ
@@ê½Sª\à@@@@@§«
@@ê¬ñiã\à@@@@i¶º
@@µiñS\Zà@@@@¬gOǶqå
@@O¬ZiñSµ\à@@ÀǪY
@@ñ¬Sª\à@@@@@@K
@@l½l\à@@@@@@@³ºn
^ÓS
ê@qu½_c@ãiSùà@@³»n |
óèLÐA¡ÈÇ{ÉÖWÌ éynÅ é±Æ𦴵ĢéB
uú{nuÈvÍu{EªEjRE¬¼EìEå_EɪE]KEïgìEaKEâ`E|Øvð³µAuåú{n¼«vÍu¡gúEâêºE{º¥ÈèvƵĢéB
{nVÆÄÎê½næÍAàÁÆL©Á½ÌÅÍÈ¢©ÆÍl¦Ä¢éBãÌúu½ÍÙÚmÀÉÜñÅ¢½©àmêÈ¢B
 @»Ý̱ÌnÅÍAnVÌâÌÍÝçê¸Aw³ÌÅ_Æåa©ì̳xÍA @»Ý̱ÌnÅÍAnVÌâÌÍÝçê¸Aw³ÌÅ_Æåa©ì̳xÍA
| aºNÈ~̬ÎÆ¢¤n¼ÍASYp¹çêA»¡ÜÅⶵÄ͢ȢÌÅ ÁÄAí¸©ÉA¬Î(nCV)Æ¢¤©ª ÁÄA»Ì¢Ì¼Ì̼cèð¯ßÄ¢éÉ߬ȢÌÅ éB |
db ð©éÆAÎTª]KÉ6A¬ÎTª]KEïgìÉ7AÑTÍ{ÃÈÇÉ3¬ÙÇfÚ³êÄ¢éB
uºöRϹ_¼ vÌ^ÓSZ\ªOÉA
]ñÊ@qtäþ_
]ñÊ@qtP¾_ |
ª©¦éªAµ©µ¡Í»ñÈ_ÐÍÈ¢µAÇ±É Á½Ì©às¾Å éB
]Ëú̶£ÉͬÎʸÌL੦éB
mRså]¬VcàÉÑ_Ъ éB
{Ãsg©ÉuÑèvÌ¢¼ª éBúJÌúg_ЫàÐÉu¬Ñ_Ðvª éB
nV½ÍenÉ©¦éªAßÅÍOgVcSqt½A¯½Sqt½ª éB
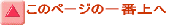
nVÌê¹
 @åÏdvÈynÉt¯çê½AåÏdvÈðjIÓ¡ðÂnVÆ¢¤Ããn¼B»ÌӡͽÈ̾ë¤B @åÏdvÈynÉt¯çê½AåÏdvÈðjIÓ¡ðÂnVÆ¢¤Ããn¼B»ÌӡͽÈ̾ë¤B
±±ÉѪ Á½©ç|A»ñÈÈPȨêÅÍÈ¢æ¤Å éB
µ©µLèÆÉÍæwª·Åɾ¢½¢Íð¢Ä¢ÄÍêéÌÅ»êÉ]ÁÄ©ÄÝæ¤B
OãÉ¢ÄÍNàܾ誯ĢȢæ¤Å éA±ñÈÊ¢ðjðÙÁĨ¢Ä½ð×·éÆ¢¤Ì¾ë¤©A±¤µ½îbÌgݪ誯çêÈ¢ÆAÀÛÍ×੦ȢÌÄÍȩ뤩BàĸÉƪ¾뤩A»¤µ½ ÜèÉRE߬骽yjânûjÉÍæ©çêéAVEg¾©çµ©½àȢ̾ªA»Ì¹ÉУè߬éAàÜßÄÌbÅ éªARbPCƾ¤©î¯È¢Æ¾¤©A³íÈÙ©Ì¢E©ç©êÎ}KÉ੦é±Æ¾ë¤Æv¤B
î¯È¢©ªÌpðRRÉu«ÈªçA¨¾¯ÍÍé©YpÌÞûÖÆÁ½n¼Ì¨êé¢EÖÆX¯ÄÝæ¤B
^JiV^Jt
 @qt½ÌkA^ÓSɪ¬ÉuvÌn¼ª éBɪYÌM®Ì¿ÀÔAêÔèOAüèû¤Å éB±Ì¯¶Ìn¼ÍSÉà¢Â©©çêéBǤ¢¤Ó¡Ìà̾뤩B @qt½ÌkA^ÓSɪ¬ÉuvÌn¼ª éBɪYÌM®Ì¿ÀÔAêÔèOAüèû¤Å éB±Ì¯¶Ìn¼ÍSÉà¢Â©©çêéBǤ¢¤Ó¡Ìà̾뤩B

±ñÈÉÓOȱÌnÌðjªÐÁ»èÆc³êÄ¢éBM®ÆuâJjΩèÌæ¤É¾íêÄ¢éªAàÆàÆÍ»¤µ½nÅÍÈ©Á½Bu^ÛCÌ¢vÅࢽŠéªAà¤êx¨³ç¢ðµÄ¨±¤B
wdyLxÌKÛS
ã⦪Eºâ¦ªEËÃEUc
@F¡ÌVcÌÝ¢AF¡AªdAZ¾ÁÞuEí¾ÁÞuÌñlAåc̺ÌäoxÌnð¿ÐÄAcð¤èª©ÞÆéABlAUðÈ¿ÄAHÌį̈ð×ЫB±±ÉAUÜêÄ׿«B±ÌÈÉAÞèy¿µ|ÍA¦¿ËÃÆåj¯AOÌ⦿µ|ÍA¦¿ã⦪ƼïAãÌ⦿µ|ÍA¦¿ºâ¦ªÆ¢ÐA×ÌU¿µ|ÍA¦¿UcÆ¢ÓB |
Zí̾ÁÞuÆA±±ÅÍ\LªÙÈéÆ¢¦Í¯¶ðjðêéàÌÆvíêéB^JiVÆÍ^JṯƾÆgìTÍ·ÅÉ©êÄ¢éBtÆÍSṯÆÅAÌz»SWcÅ éB
^x̺͡ɧPHs´æÅ éªA¯¶æ¤ÉÁ²SÌ^ÛC( Rðz·Æ½Squ½¾Á½Æv¤)àAÌìÉ é{Ãs{Và½ÔñAܾmFūĢȢªA°ç¯¶ðjðÂàÌƪūéB
»ÌåcÌ¢ÆÍA
åcÌ¢@yÍÌãÈèB
åcÆÌÓÈÍAÌAàÌAØæèxèÄAnßAIÉ̼ÌSÌåc̺Éè«B´ÌãAªêÄAÛÃÌOÌêüÌSÌåc̺ÉÚèè«B´ªAKÛÌSÌåc̺ÉJè¯èB¥ÍA{ÌIÉÌÌåcðȿļÆ਷ÈèB |
^JƼæéÌÍúnÆvíêAÍ»¤µ½àÁÆàúÌØ©çÌnn»SZpWcÌ_n¾ÆvíêéB
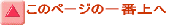
nVCiVÖt
 @dÌ^x̼ÍKÛìÆÑcì̬_ÅA»ÌÑcìðPOLΩèkÁ½ªÑc̢ŠéBwa¼´xÌKÛSÑc½B¡ÌºÉ§PHsÑc¬Å éªA @dÌ^x̼ÍKÛìÆÑcì̬_ÅA»ÌÑcìðPOLΩèkÁ½ªÑc̢ŠéBwa¼´xÌKÛSÑc½B¡ÌºÉ§PHsÑc¬Å éªA
udyLvÉÍA
| ÑcÌ¢@{̼ÍkÞuÈèByÍ̺ÈèBkÞuÆÌÓÈÍAÉaÌå_AèßܵµAäuð|ÉAĽÜÓÉAɾÌ÷¶Ð«BÌA¼ðkÞuÆÌÓB |
¾mÉnVÍCiV¾Æ©êÄ¢éBÑcTÍOgɽ¢ªA»êͳÍCiVƾÁ½Æ©êÄ¢éBCiVªnVÉ]æaµ½æ¤Å éBCiVÆÍÖt¾ÆgìS͢ĢéB^JtÍìâCÌ»SðÌWµÄ¢½æ¤¾ªA±ÌãÌÖtÍâÎðÓ¢ÄSðìéæ¤ÉÈÁÄ¢Á½Ì©àmêÈ¢B
nVÆÍÖtÌ]æaÆ©égìÌÓOÈàªÅà몢ÆÍ©Ä¢éBOã̱ÌüÓÍtΩèÅ éB
õOÖS潪wa¼´xÉ©¦éB
aC´Cà³ÍÖÊöÅ éBßÉÍaCTà éªA é¢Í»¤µ½±Æ©àmêÈ¢B
ζÍCiVÆÇÞÌÅ éªAC\EÆàÇßéBXãSζ½ÍC\EÆ©C\ÇÞªA{ÍCiVÈÌ©àmêÈ¢B
»¤Æ·éV´§Ìé´
ÌC\ªÜ½µÄàCÉÈéB൩·éÆCAiVÌ´
¾Á½©àmêÈ¢B
^ÓS®àÐE¢m]C\(ÎÎÉR)_ÐB
uºöRϹ_¼ vÌ^ÓSA]ñÊé¾_B
±êçÌC\Í é¢ÍCAiVÅ Á½©àmêÈ¢B
³ÄAwOF{uxÉ»¡[¢Lª éB
§Îº(¹®Ì)
y ¶©ÜÌz{Ã{uÉIc½hìºÉ µ©lÆ¢Ó µ©ÜÌÎÍ|Èçñ©Æ^ð¶µÄL¹èB³êǧκ µ©Æ¢ÓëРèA°çÍ|Èé×µB µ©Í µ©Ü̪êÈèA¡ ¶âÆ¢ÓÍñÈèB
y µ©ÌÐz( µ©Ín̼ÈèA µ©ÜÌÉ éÐÈè)
µ©ÌÐͽðÕéâºlàµç¸A³êÇ¿ç~Ð̼Èêκ·ÉÝÄàðJ«qÝòêÎÃãÌ©ÉÄë¸ èA¥æèOÜ\¬ÎʽðÕèÄæèºðÎÆ¢ÓÆÃVÉ«µ©à½êÌÐÈéðµç¸A¡¸ðqÝÄÄÐÈéðµéAÜ\¬ÎʽÍOã¹å½Ì·ÈèAOã¹å½ÉÜ èF¢³êÄ@ÜÆÈéAÜ\¬ÎʽÍælÜåHàùüPÌqÈèAZð¬ÎʽƢÓA^ÓÂÀ¬Î¢æèvðòéAíðÜ\ú«F¸Æ¢Ó^ÓÜ\úÌ¢æèvðòéAÜ\¬ÎʸÉÍ^ÓîYæèvðòéAæÁÄÜ\¬ÎʽðÕéÈèB
yTRCz(ÕÏ@)
yåRáz(´@) |

OãÅÍV´§É®Ïõ¼ÉÈÁÄ«½AɪY¾ªAÏõ¾¯ÅÈA¼nÉÍàÆàÆ[¢ÖWª Á½ÆvíêéBTÆÄÎêÄ¢éªA§ÎÍXÖÇÌÓè©çAáECÌ ½èÜÅð¾¤æ¤Å éBCÓÍM®ª±Æ±ëÅ éB
æÌÆÍYð²ñ¾ÎݤÉÈéªA±±ÉÜ\¬ÎʸªâJçêÄ¢½BC^eÆ¢¤Ìàܽ»¡ø©êéAÉBÈÇÆà©êA_÷c@ÌãÉnµ½èGè_ÆvíêéA»êÆnV(Öt)ªÌµÄ¢éBÞÍOg¹åÌ·ÅAZÍqt½É¢½Æ¢¤ÌÅ éBÀÌZí©Ç¤©ÍmçʪA¼nÌÖWÍ»ñÈàñÈñ¾ÆM¶çêÄ«½æ¤Å éB
u ¶©Üvu µ©vÌAVÍAiVÌ©àmêÈ¢ªAñåÏõ¼Ì¢hCàɪYà³XÍSÌY¾Æ;ÁÄ«½AǤâçÜ·Ü·»Ìæ¤É©¦Ä«½B»¤ÈçÎAɪÆÍDÈ̾뤩B
ڵͱÌnÅÄÑæèã°½¢B
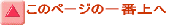
AiVt
 @dÌÑcìð³çÉà¤POLΩèkÁÄÝæ¤B»±Íळ¾SÀx¬ÉÈèAyLÉæêÎA³ÑStÌ¢B @dÌÑcìð³çÉà¤POLΩèkÁÄÝæ¤B»±Íळ¾SÀx¬ÉÈèAyLÉæêÎA³ÑStÌ¢B
wa¼´xÌÀu½(d³¾S)BAiVÆ©AVÆÇÜêÄ¢éªAì̼àtìÉÏí黤ŠéB»µÄ¡ÍÀuÌWª éBAWÆ¡ÍÄñÅ¢éªAAiVÅ éBAiVÍtASṯÆÅ éB
AiVÍEÆaƵÄÚ¾¯ÅÈA^^ð¥Þ½ßÉ«àÉßéA»Ì½ßÉwÆ©É«Aa«Æà©êéµAêÉæÁÄÍÎÆà©êéB
ìcì¬lÒÉÎ_Ъ èA»Ì×ÌãRcÉÍê³_Ðà éBNiVNiVNtÆvíêéAÚµÍA»Ìy[WÜÅMªiñÅ©çɵ½¢B
PÉtÆÄÎêéÌÍVµ¢ãÌ椾ªA»ÌtÆ~_ÐâJ_ÐÍÖWª 軤ÅAâê¬|ØÉÍOÖ_Ъ èA±êàtªâJÁ½àÌ©ÆvíêéBâÄ_ÐÕ_ÍêÎ_ÐÕ_ÆÀͯÌÆ¢íêéB±êçàÚµÍãÙÇæèã°½¢B
nVÌÖW·éynÍÍ©ÈèL¢ÍÍÉܽªÁÄ¢½æ¤Évíêéí¯ÅAOãÃãjÌSIÈêÅ Á½ÆvíêéªA»ÌSÍÇ±É Á½Ì¾ë¤BqtPEqtF_ÐÌnÈ̾ªA»êç͸íêÄ¡Íà¤í©çÈ¢B
âêâjRÌ ½èÆÍáÉñÅ¢é̾ªA
nu¿ÍA
Ââ_ÐÝñjRºêWâJñr¬Îʽê
Æl¦Ä¢é椾ªAjRª¦ªS©àmêÈ¢B
nii~ÆAiVཀྵÖWª é©àmêÈ¢B
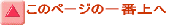
qt½ÌåÈðj¿
wOãLx
| ¬ÎʸBú{LmVcælÌÜåHàùüPÌäqr¬ÎʸƢÓÜ\̬ÎʸB |
wOF{ux
y ¶©ÜÌz{Ã{uÉIc½hìºÉ µ©lÆ¢Ó µ©ÜÌÎÍ|Èçñ©Æ^ð¶µÄL¹èB³êǧκ µ©Æ¢ÓëРèA°çÍ|Èé×µB µ©Í µ©Ü̪êÈèA¡ ¶âÆ¢ÓÍñÈèB
y µ©ÌÐz( µ©Ín̼ÈèA µ©ÜÌÉ éÐÈè)
µ©ÌÐͽðÕéâºlàµç¸A³êÇ¿ç~Ð̼Èêκ·ÉÝÄàðJ«qÝòêÎÃãÌ©ÉÄë¸ èA¥æèOÜ\¬ÎʽðÕèÄæèºðÎÆ¢ÓÆÃVÉ«µ©à½êÌÐÈéðµç¸A¡¸ðqÝÄÄÐÈéðµéAÜ\¬ÎʽÍOã¹å½Ì·ÈèAOã¹å½ÉÜ èF¢³êÄ@ÜÆÈéAÜ\¬ÎʽÍælÜåHàùüPÌqÈèAZð¬ÎʽƢÓA^ÓÂÀ¬Î¢æèvðòéAíðÜ\ú«F¸Æ¢Ó^ÓÜ\úÌ¢æèvðòéAÜ\¬ÎʸÉÍ^ÓîYæèvðòéAæÁÄÜ\¬ÎʽðÕéÈèB |
wåú{n¼«x
| yqt½za¼´A^ÓSqt½B¡gúAâêºA{º¥ÈèA¦V´§ÌlüÉÂéAyLí¶É¬ÎÊÔ¼¢ÉìéBcªc |
w^ÓSx
qt½
@yLí¶ÉäoÓSXÆk÷ûL¬Î¢]XÆ éª¬ÎAqt¯¶Bnu¿ÉÍiñ{AªAjRA¬¼AìAå_AɪA]KAïgìAaKAâëA|ØWêà¨ñýæêâJTâÄ_ÐÝñå_ºêâJñZgO_êÌñ{Bêm{êAØÏ_ÐÝñ|غ{JêâJñÜ\Ò_êÂâ_ÐÝñjRºêWâJñr¬ÎʽêçAÓvZNOãÉHÛnªã¡î´AÉH©ñcÚ^êÆ èAɪÍúu½ÉĽÌnæÉ ç´é;©ÈéàA´Ì¼Ìº¢ÍÙÏÈ«ª@¦¿¡{ºAâë¬ÌnæÈèB |
wÁ²Sx
| å»ÌVÈOɯé{SÉ¢ÄÍAL^Ì¥·×«àÌ«ªÌÉA¡ÍBðãÌÌiðñL·éÉ~ßÄuB¬Îʽ@¯ã(mVcÌäã) |
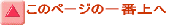
ÖAîñ




|
 ¿ÒÌgbvÖ ¿ÒÌgbvÖ
 OãÌn¼Ö OãÌn¼Ö
¿ÒÌõø
|