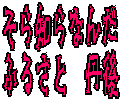 |
和泉式部
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
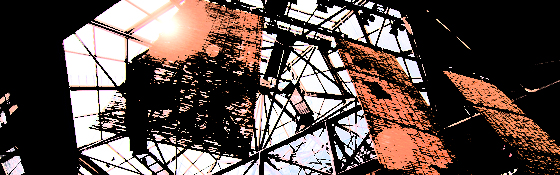 放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 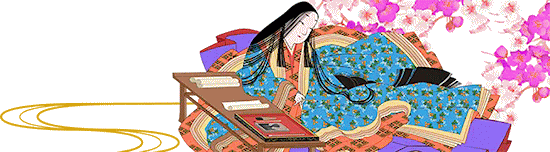 百人一首 56番 あらざらむ この世の外の思ひ出に 今ひとたびの 逢ふこともがな 「あらざらむ」は、「此の世にはいないだろう」、「死んでしまうだろう」の意味。 「この世の 「逢ふこともがな」は、お逢いしたいの意味。 死ぬ前に、冥土への思い出に、もう一度お逢いしたいですね という歌。 和泉式部(いずみしきぶ)夫(二十歳ばかりの年上・再婚)の藤原保昌が丹後守となったのは寛仁2年(1020)くらいで、万寿2年(1025)には大和守となっている。この5、6年の間は和泉式部も丹後にいたのであろう、彼女は40歳中~50歳くらいだったと思われる。この時代だけを取り上げてみる。(和泉式部の生年は、諸説あって、天延2(974)~天元2(979)くらいと見られている。 明治・大正時代の平均寿命は44歳前後、平安時代中期、貴族の推定平均寿命は、男性が50歳、女性が40歳くらいだったという。今ならまだ若い世代だろうが、当時は棺桶に両足を突っ込んだ状態の年齢だろうか) 夫は藤原道長の 和泉式部は通称で、最初の夫(橘道貞)が和泉守であったところから、こう呼ばれている、本名は不明。 李夫人・楊貴妃や小野小町と並び称される美女とされ(『平治物語』)、一条天皇中宮彰子の文化サロンの「四天王」(紫式部、和泉式部、赤染衛門、伊勢大輔)の一人、日本を代表する女流歌人、千年が過ぎても彼女達を超えるような人物は多くはいない、そんな恋多き超才女にとっては、丹後の田舎生活は超たいくつな物足りないものでなかっただろうか。 57めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半の月かな(紫式部) 59やすらはで 寝なましものを さ夜ふけて 傾くまでの 月を見しかな(赤染衛門) 61いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな (伊勢大輔) 一条天皇は二后あって、もう一方の中宮定子のサロンには清少納言がいる。(一条天皇は6歳か7歳で即位。だからその奥様もその年齢で、おひな様かままごと遊びのような世界であろうか。彰子は道長の娘、定子は道隆の娘。道隆は道長の兄だから、彰子と定子は 62夜をこめて 鳥の空音は はかるとも よに逢阪の 関はゆるさじ(清少納言) 日本史上にも希有な百花繚乱の黄金期の文化環境から、いきなり丹後へ移ることとなるが、花の都からの都落ちといっても、ものすごい格差で、月とスッポン以上、何とも落ちぶれたはてたものだの感が強かったかも知れない。旗手歌人としてやって行けるかどうか。道長だってそれくらいは知っていようが、保昌は一の家臣だし、都に置いておけば、またぞろ…とか、ナニかあったのか、ありそうだったのかも知れない。  はななみのさととしきけば物うきに 君ひきわたせあまのはしだて 「はななみの里」という地名、平安期にはあったのであろう、今はない。天文7年(1538)の『丹後御檀家帳』に「いたなみ」と見えるところのことで、今もそう呼ぶ天橋立北岸の「板列」のこと、ここでは夫の赴任先・丹後国府があった場所の地名である。 『丹後旧事記』 花浪の里。花浪は庄名なり板竝板列庄など書也里にはあらず日置の郷より西の方府中七ケ村岩滝の地迄を云ふ。…
花波の里などと聞くも物憂く気が進まない、行きたくはないので、あなたワタシを天橋立まで連れて行って、引き渡して下さいな。といった意味。 -和泉式部の簡単な伝記- 2人の間にはまもなく小式部内侍が生まれる、10歳ばかり年長の夫にはあきたりないものがあったものか5年ほどで離婚。  式部と恋愛の関係にあった人物は、ほかにも数人あって、小式部内侍のほかに、敦道親王との間に栄覚という子があったという。 丹後の伝承  和泉式部は、不思議な伝説の人で、全国ほうぼうに伝説があり、墓があったりする。紫式部も清少納言も、これにはとても及ばない、人気の高い、あこがれの女性であったものか、小野小町か和泉式部か、伝説の多い人である。 丹後は実際に4、5年くらいは住んでいたので、伝説があってもナニも不思議ではないが、たいていはずっと後世の書(江戸期後期)に取り上げられたものなので、史実としての真偽のほどは確かではないものもある。 『丹後旧事記』(其白堂信佶(田中新吉)著、天明年中(1781~89)成立)や『丹哥府志』(小林玄章著、天保年中(1830~44)成立などであるが、もう800年ほども後の書である。 『丹哥府志』 ◎山中村(皆原村の次是より新宮村へ出て加佐郡漆原へ出る)
どうせ退屈ならいっそうのこと、もっとも退屈な場所に住んでみるか、とそう思ったのかも知れない。【和泉式部の庵跡】和泉式部は越前守大江雅致の女なり、和泉守道貞の妻となる、よって和泉式部といふ。和歌を善くす。女子一人あり小式部といふ。道貞の没後上東門院に仕ふ(歌遷伝)、既にして亦藤原の保昌の妻となる(袋双紙)。先是性空上人といふもの播州の書写山に居る世を挙て之を崇信す。式部歌を作て之に贈る、其歌に曰「くらきよりくらき道にそいりぬへきはるかにしらせ川の端の月」、世の人情妙とす。(新古今和歌集)詞葉和歌集に云ふ。後保昌忘られて侍る頃兼房卿訪ひければよめる 人しれず物思ふことは習ふにも 花に別りぬ春しなけれは 又云ふ。前保昌に具して丹後に居りけるに忍びて物いひ来せる男の許えいひ遣しける 我のみや思ひこせんあしきなく 人は行衛もしらぬ物故  丹後旧記云。藤原の保昌丹後の守となる頃和泉式部保昌に随ひ丹後に来る。保昌既に任国終て再び都に帰る其後和泉式部は与謝郡山中村といふ處に庵を結び、之に居て老を慰めける。保昌の次に兼房卿丹後守となる、折々和泉式部の草庵を訪ひ和歌の物語などありしとぞ。今其庵の跡に浅黄桜あり、俗に式部桜といふ。 【和泉式部の墓】(庵跡の東出図)和泉式部の墓といふもの處々に建ちたれども多くは是式部の和歌塚なり。吾丹後に於ても又三ケ處に在り一は鶏塚なり、一は桜山なり、蓋其風操の名高きを以て好事のもの之を為せり。其終焉の地はいずれの處や詳ならず、今居住の地を以て考る時は京師と丹後の両所に定る。又細に其両處を考るに和泉式部の卒せしは正暦三年なり、保昌と倶に丹後に来るは是より前僅に四、五年保昌四年の任国終て後式部は丹後に留る、之を以て観る時は式部終焉の地丹後と為して可なり。 式部は山中の里に住み、夫のいる府中へ通ったともいわれる。 その道中に伝説が多い。 『丹哥府志』 【和泉式部産湯の滝】(飛石より西へ入る) 和泉式部山中の草庵より兼房卿の許へまゐらせける途中、婦人の産に臨むを見る、よって和泉式部扶て之を産しめ其産む所の児を此滝の流に洗ふ。其頃観世音菩薩の出現して産婦を扶け玉ふといひしが三とせ斗過て後実は和泉式部にてぞありけると聞ゆ、是以此滝を和泉式部産湯の滝といふ。(土人の説)》【和泉式部産湯の滝】(飛石より西へ入る)
和泉式部山中の草庵より兼房卿の許へまゐらせける途中、婦人の産に臨むを見る、よって和泉式部扶て之を産しめ其産む所の児を此滝の流に洗ふ。其頃観世音菩薩の出現して産婦を扶け玉ふといひしが三とせ斗過て後実は和泉式部にてぞありけると聞ゆ、是以此滝を和泉式部産湯の滝といふ。(土人の説)  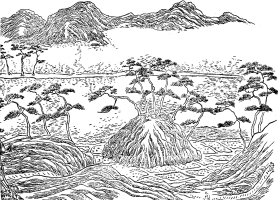  『丹哥府志』 【鶏塚】(しらぬ坂の下、出図)
巡国志云。丹後守公基朝臣一国巡見の時日置の郷金剛心院において数多の宝器一覧ありける中に、和泉式部の書捨らし反古多し、よって其一紙を乞ふて泪の磯に埋め為に三重の塔を建て名付て鶏塚といふ、其書捨られし反古の歌にいふ いつしかと待ける人に一聲も 聞せる鶏のうき別かな (和泉式部) 既にして金剛心院に供養の歌合せあり、後拾遺和歌集云公基朝臣丹後の守にて侍る時国にて歌合せし侍りけるによめる 鹿の音に秋を知る哉高砂の 尾の上の松はみとりなれとも (源頼家朝臣) 其後いつの頃や年暦詳ならざれ共、風波の為に橋立の景色多く損せし事あり、是時泪ケ磯にある鶏塚も砂に埋りける。明応の頃智恩寺より其塚をほり出して之を文珠堂の傍にたつる、今の歌塚是なりといふ。忠興の懐中日記云。慶長のはじめ中院通勝卿田辺の配處より橋立にまゐられて父藤孝に告給ひけるは、元泪の磯にありし和泉式部の和歌塚今文珠堂の傍にあるは口惜き事なり、殊更歌も千載集にありと思へば早く本の地へうつし玉へ、和泉式部亡世の誉れ捨置べき事にあらずやと返し返しすすめられける、歌人の心筋なる處遂に忘れ侍らすといふ。  和泉式部歌塚と伝える鎌倉期の石造宝篋印塔があり、明応頃、山門より600メートルほど南にある鶏塚から掘り出したという。 和泉式部歌塚と伝える鎌倉期の石造宝篋印塔があり、明応頃、山門より600メートルほど南にある鶏塚から掘り出したという。案内板 宮津市指定有形丈化財(建造物)
石造宝篋印塔(鎌倉時代) 宮津市字文珠 智恩寺 この石塔はいつのころからか和泉式部の歌塚と伝えられている。『丹哥府志』によれば、丹後守藤原公基が日置金剛心院において、和泉式部が書捨てた和歌を持ち帰り、なみだの磯(涙が磯)に埋めて鶏塚と呼んだという。その反古の一首が、 いつしかと待ちける人に一声も 聞せる鶏のうき別れかな その後明応(一四九〇~一五〇一)のころ、砂に埋まった塚を掘り出して文珠堂の傍らに建てたのが今の 歌塚であるという。 彼女が丹後に下って詠んだ歌のいくつかは知られているが、前記の歌が丹後において詠まれたものかは分からない。丹後において各処の和泉式部伝説のあるなかで、これもそのひとつとしてうけとればよい。 塔は堂々として基礎の格狭間や、塔身の薬研彫の四方仏の種子、笠石四隅の突起等に時代的な特徴がみられる。 宮津市教育委員会  『丹後旧事記』 磯清水(濃松の内橋立明神の御手洗をいふ)。
衆妙集 橋立の松の下なる磯清水 都なりせは君も汲見ん 和泉式部 『丹哥府志』 【【磯清水】(明神の傍)
碑文云。丹後国天橋磯辺有二井池一清水湧出蓋在二海中一而別有二一派之源一乎、古来以爲二勝区一。呼曰二磯清水一舊談有レ言和泉式部和歌曰、橋立濃松濃下奈留磯清水都奈利勢波君毛汲末志云々式部従二藤原保昌一来二当国一界其所二傳称一非レ無レ縁也。今応清水混海鹹而尋其水路新構二幹欄一以成二界限一永使下二勝区之名一垂二於不朽一而考古之人無中弁尋之疑上延宝六丙午年当国宮津城主大江姓尚長建 弘文院林学士撰 愚按ずるに衆妙集に此歌を玄旨法印の歌となせり、いづれか是なるをしらず。 『衆妙集』は、細川幽斎の和歌集。飛鳥井雅章 編。寛文11年(1671)に跋文。 まつ人はゆきとまりつつあぢきなく としのみこゆるよさのおほ山 和泉式部が丹後で詠んだ歌も多い。 小式部内侍 和泉式部の娘だけあって(父は橘道貞)、少女の頃から和歌や色恋に秀でていたという。年齢に合わず、今の小学生の年齢だから、それにしても上手にたくさん作るので、これはたぶん、母の和泉式部が代作しているのではないかと一部では疑う人もあったという。 和泉式部の娘だけあって(父は橘道貞)、少女の頃から和歌や色恋に秀でていたという。年齢に合わず、今の小学生の年齢だから、それにしても上手にたくさん作るので、これはたぶん、母の和泉式部が代作しているのではないかと一部では疑う人もあったという。藤原定頼という人も疑い、 「丹後に使わした人は戻られましたか」とか、いらぬ声かけをしたという。 それに即答、彼の目の前でサラサラとしたためたのが、 60大江山 いく野の道の 遠ければまだふみもみず 天の橋立(小式部内侍) 遠い丹後の母の手紙は見ておりません(代作はしてもらっていません)。  ガ~ン。タコもイカもびっくら、なななな、なんと。定頼は仰天、返事の声も出ず、ただオロオロワナワナ、ててて、天才じゃなもとか逃げ帰ったという。 この時小式部は12~3歳。超有名なこのうたは小6~中1くらいの少女のものである。 そんな少女がこんな歌を即興で歌うのだから、定頼ばかりでなく話を聞いた人はみな、ウッソーと腰抜かした。 これ以来小式部内侍は歌よみの世界で母にも勝ると覚えめでたかったという。 小式部内侍は産婦死のようで、25~6歳で母よりも早くに亡くなった。自分の才能を受け継いだ娘の夭逝に式部の落胆は大きかった。 『和泉式部』(山中裕) 小式部内侍は和泉式部の娘だけあって、和歌に秀でていた。少女のころから歌を多く作っており、母の和泉式部が代作するのではないかという疑いもかけられているほどであった。代作を疑っていた藤原定頼(公任の男)は、小式部の局の前を通り過ぎ、「丹後へつかはしける人はまいりたるにや」
といったという。小式部は、 御簾よりなかばいでゝ、直衣の袖をひかへて、 大江山いくのゝ道の遠ければ まだふみもみずあまのはしだて と、よみかけゝり (『古今著聞集』五) とある。すなわち、母の文などは見ておりません、代作などしてもらったことはございません、とはっきりと答えた。よびかけた定頼は、 「こはいかに」とばかりいひて、返しにも及ばず、袖をひきはなちてにげられにけり。小式部、これより歌よみの世おぼえいできにけり。(同右) と見える。このとき小式部は十二-三歳であったと推定されている。
|
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
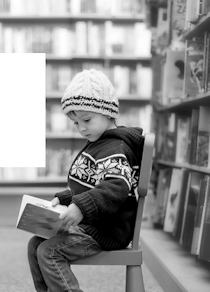






 音の玉手箱
音の玉手箱