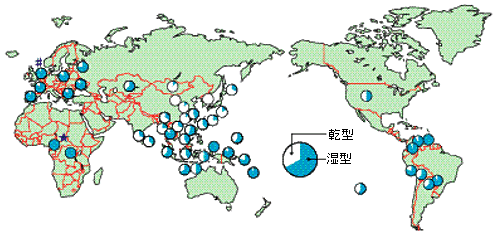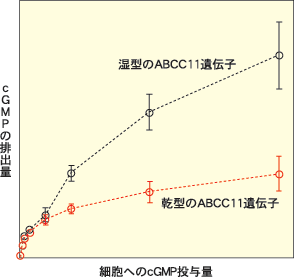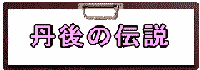丹後の伝説:22集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥生渡来人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二重構造モデルすでに述べたように、日本人に北東アジア的特徴が多いのは、渡来集団の影響が相当に強かったことを示すものだろう。さらにいえば、渡来人の数は〝無視しうる程度″どころでなく、想像以上に多かったと考えなければ説明がつかない。 現在、日本人集団の形成史は大きな見直しを迫られている。それは単に私どもの人類学的研究の成果によるばかりでなく、あいつぐ考古学の新発見や、さまざまな遺伝子の研究などに負うところが大きい。これらの成果を含めて説明するためには、どのようなモデルが考えられるだろうか。 まず、日本の旧石器時代人や縄文人は、かつて東南アジアに住んでいた古いタイプのアジア人集団-原アジア人-をルーツにもつということが問題の出発点となる。縄文人は一万年もの長期間にわたって日本列島に生活し、温暖な気候に育まれて独特の文化を成熟させた。気候が冷涼化するにつれて北東アジアの集団が渡来してきたが、おそらく彼らも、もともとは縄文人と同じルーツをもつ集団だったのだろう。異なる点は、長い期間にわたって極端な寒冷地に住んだために寒冷適応をとげ、その祖先集団とは著しい違いを示すようになったことである。 大陸から日本列島への渡来は、おそらく縄文末期から始まったのだろうが、弥生時代になって急に増加し、以後、七世紀までのほぼ一〇〇〇年にわたって続いた。渡来集団はまず北部九州や本州の日本海沿岸部に到着し、渡来人の数が増すにつれて小さなクニグ二を作り始めた。さらに彼らは東進して近畿地方に至り、クニグこの間の抗争を経てついに統一政府、つまり朝廷が樹立された。 その後朝廷は積極的に大陸から学者、技術者などを迎え、近畿地方は渡来人の中心になった。また土着の縄文系集団を〝同化″するため北に南にと遠征軍を派遣し、一部の地方には政府の出先機関も設置された。渡来系の遺伝子はこのようにして徐々に拡散したが、縄文系と渡来系との混血は近畿から離れるにつれて薄くなる。現代にもみられる日本人の地域性は、両集団の混血の濃淡によって説明される。混血がほとんど、あるいはわずかしか起こらなかった北海道と南西諸島に縄文系の特徴を濃厚に残す集団が住んでいることも同じ論理によって説明することができる。 以上が私の考えている日本人形成史の概要だが、日本人集団の主な構成要素を縄文系と渡来系の二つと考えることから、「二重構造モデル」といってよいかと思われる。実はこのモデルで説明できるのは人間ばかりでなく、人間の共生動物ともいえる日本犬や野生のバツカネズミの遺伝子分布にも当てはまる。 麻布大学の田名部雄一教授(家畜遺伝学)が日本犬のDNA配列を調べたところ、北海道犬(アイヌ犬)と沖縄の琉球犬がよく似ているばかりでなく、ともに東南アジアのイヌと同系であることがわかった。また本州の大部分に分布する秋田犬、甲斐犬、柴犬などは北東アジア系のイヌと共通の遺伝子をもつので、そのルーツと分布地域は日本人集団とほとんど同じパターンを示すといってよさそうである。 一方、総合研究大学院大学の森脇和郎教授(遺伝学)が日本産の野生ハツカネズミのDNA配列を調べた結果では、本州の大部分に分布するネズミは北東アジア系だが、北海道・本州北部・南西諸島のネズミは東南アジア系ということがわかった。しかも東南アジア系のネズミは、とくに島嶼部に分布する系統に近いといわれるので、氷河時代にはスンダランドに住んでいた集団という可能性が高い。 イヌもネズミも人間と緑の深い動物である。イヌはおそらく三万年以上前に家畜化され、人間の忠実な伴侶としてつねに行動をともにしてきた。またネズミは家畜ではないものの、人間-というより、人間の食料とともに移動する。 田名部、森脇両氏の研究から想像されることは以下のようなシナリオである。 縄文人の祖先にあたる集団が東南アジア系のイヌを、そして渡来人たちが北東アジア系のイヌをつれて日本列島にやってきたのだろう。同時に、〝招かれざる客″のような格好でハツカネズミも東南アジアや北東アジアから移動し、人間集団と似たような地域に分布するようになったと考えられるのである。 さらに、京都大学の日沼頼夫名誉教授(ウイルス学)らの研究によると、ATLV-2というウイルスの保有者の分布パターンも同じモデルで説明できそうである。このウイルスの保有者はアイヌ系や南部九州・奄美・沖縄地方の人びとに比較的多く、その他の地方には-一部の地域を除いてー少ないといわれる。このような分布から、日沼氏は日本人をATLV-2の保有者群と非保有者群とにわけ、前者が縄文系、後者が渡来系の集団に相当するのではないか、と考えている。 このほか、私の専門ではないが日本文化にかかわるさまざまな疑問も、このモデルで考えると理解しやすいことが多いのではないかと思える。すでにふれた日本文化の地域性、たとえば東日本・西日本の文化の違いなども、〝文化の二重構造″という文脈で考えれば新しい視点が開けるようにも思われるのだが……。 さらに問題を掘り下げていくと… 人口増加モデル縄文時代から初期歴史時代にかけての人口については、国立民族学博物館の小山修三教授が遺跡の数とその規模に基づいてコンピューター・シミュレーションを行った研究がある(一四〇ページの表参照-引用者注・略)。その結果をみると、縄文時代中期の人口は約二十六万人だったが、後期になると約十六万人、晩期には約七万五千人と激減した。その主な理由は気候の寒冷化で、食糧資源の確保が難しくなったためだろう。 ところが弥生時代になると、人口は急激な増加に転じる。この傾向は特に西日本で著しい。小山氏の推定値でみると、縄文時代全体を通して人口増加率(年率)は一部の例外を除いて〇・二パーセント以下、またはマイナス成長だが、縄文晩期から弥生時代にかけての増加率は東日本で〇・二パーセント前後、西日本では〇・三パーセントから〇・四パーセントほどに達した。その結果、弥生時代の全国の人口は約六十万人、古墳時代には五百四十万人になったと推定される。 弥生時代に大陸から新しい文化が導入されたことはよく知られているが、特に重要な変化は発達した稲作技術が入ってきたことである(後述するように、単なる稲作なら、ひょっとするともう少し早く入ってきたかもしれない)。このため、日本の社会は縄文時代の狩猟採集段階から農業段階へと進歩し、人口増加率も急速に高くなったと想像される。とはいえ、縄文時代末期(ここでは縄文晩期の数値を代用)から古墳時代にいたる千年たらずの間に七万五千人から五百四十万人に増加したとすれば、その年増加率は〇・四パーセント以上となり、この時代としては異常な高率と考えざるをえない。 初期段階の農耕民がどれほどの人口増加率を示すかというデータは、何人かの人口学者によって研究されている。例えばC・マッケヴェディとR・ジョーンズによると、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、アメリカのさまざまな地域で推定した結果、平均して〇・〇四パーセントという値が得られている。この中で最高値を示すイングランドでも約〇・一パーセントで、〇・四パーセントという日本の数字は異常に高い。 そうすると、小山氏の推定がほぼ正しいとみる限り、日本では何か特殊な原因があったのだろうと想像される。そこで、本書ですでに述べた理由から、「特殊な原因」とは渡来者の流入ではなかったかと思いあたる。つまり、弥生時代以後に次から次へと渡来者がやってきたとすれば、人口の自然増加に加えて、渡来者と彼らの子孫の数がプラスされることになり、全体としての人口増加率を押し上げることになっただろう。このような考え方をモデル化すると次のようになる。 (一)大量の渡来者がきた時代を弥生時代の開始期(紀元前三世紀)から初期歴史時代(紀元七世紀)までの約千年間と考える。 (二)この期間の人口増加率(年率)を初期農耕民のデータから、安全を考えて、やや高めの〇・二パーセントとする。 (三)小山氏の推定値から、弥生時代開始期の人口を七万五千八百人、八世紀初めの人口を五百三十九万九千八百人とする。 (四)初期人口が年率〇・二パーセントの割合で千年間にわたってⅩまで増加したとすれば、Ⅹと七世紀初めの推定人口との差は、その間に渡来した人数の関数になるはずである。 (五)ただし渡来した人々も子どもを産み、人口増加に影響を及ぼすことを計算に入れる必要がある。 以上のモデルを数式化してシミュレーションを行うわけだが、初期値として使う人口(小山氏の推定値)も人口増加率(マッケヴェディとジョーンズによる推定値)もかなり誤差を含むと思われるので、安全を考えていろいろと異なる数値を使うことにした。具体的には、初期人口として縄文末期ばかりでなく、これよりかなり多い縄文中期の推定人口を使い、また人口増加率として〇・二パーセントから〇・四パーセントまでの種々の値を使って計算した。 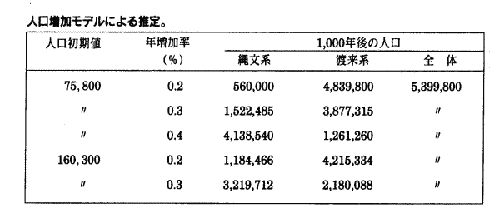 その結果は上の表に示す通りだが、これは驚くべき数字である。計算した私自身が驚いたくらいだから、この結果を論文で読んだ人はもっと驚いたに違いない。表の中で渡来音数が最も多くなる推定では、千年間の渡来人口が約百五十万、七世紀初めの時期での縄文系と渡来系の人口の割合は一対八・六となる。人口増加率を〇・四パーセントとしても渡来人口は九万四千人余りとなり、これを縄文末期の人口七万五千強と比べると、「渡来者の影響は無視できる程度」どころではないことになる。 ここでお断りしておきたいことは、私がこのシミュレーションを行った理由は渡来者の数そのものを知るためではなく、渡来者の影響を「無視できる程度」の一言でかたづけようとする学界の傾向に対して、なんらかの客観的な判断基準を示そうとしたからにほかならない。また論文にもそのことを明瞭に書いてある。 ところが一九八七年にこの論文を公表して以来、「埴原の百万人渡来説」と呼ばれて数字だけが一人歩きし始め、いろいろな批判が寄せられた。批判されることはありがたいのだが、この研究の目的を誤解し、その一部だけが批判の対象にされることは心外である。特に一部の高名な考古学者たちが原論文をほとんど読みもせず、単に「百万人」という数字にこだわって批判らしきことをいっているのは、研究者の態度として理解に苦しむところである。 頭骨小進化モデル頭骨に限ったことではないが、動物は時間とともに大なり小なり進化する。人間も例外ではなく、比較的短い期間にも微小な進化をするが、このような進化は特に「小進化」といわれる。 日本人の場合は、先輩たちの努力によって縄文時代から現代まで、それぞれの時代の骨が収集されており、小進化のありさまをみるにはまことに都合がよい。そして今までの研究で、縄文時代から古墳時代にかけての頭骨の小進化の傾向がよく分かっている。そこで、小進化の進みかたから渡来人の影響をみることはできないだろうか。 実は、この時代の小進化には二つの傾向がみられるのである。一つは縄文人がほとんどそのまま小進化したと思われる例であり、他は渡来者の影響によって、小進化がやや違った方向に進んだと思われる例である。 ここで注意しなければならないことは、このような二つの傾向を比較する時、あまり離れた地域では環境の差の影響が強く出てしまう恐れがあることだ。したがって、なるべく接近した地域で比較しなければならない。 この条件に合う例は、北九州と南九州だろう。北九州は弥生時代以来、渡来系の人が濃厚に住んだ地域であり、これに対して南九州は渡来者の影響をほとんど受けていないと思われる。そこで、縄文末期から古墳時代にかけての小進化を、この二つの地域の集団に基づいて比較することにした。この場合のモデルは、次の通りである。 (一)まず、渡来者の影響がほとんどないと思われる西北九州の弥生人と、南九州の古墳人の頭骨計測値を基準値とする。つまり、もし渡来者との混血がないとすれば、この二つの集団の違いが小進化の程度(小進化率)を示すことになる。 (二)これに対して中国地方や近畿地方の古墳人は、南九州の古墳人と大きく異なる特徴を示す。その理由は、彼らが渡来者と混血しながら小進化したためと考えられる。 (三)西北九州の弥生人を縄文系集団の代表、また山口県土井ケ浜遺跡の弥生人を渡来系集団の代表と考えれば、この両者から古墳人にいたる小進化率の差から、各地の古墳人がどの程度の混血をしたかということが分かるはずである。 実際には、混血率を変えながら小進化の程度を計算し、その結果と実際の古墳人とを比較すればよい。いい換えれば、計算によって仮想の混血集団をつくり、さらにそれを計算によって小進化させ、その結果を現実の古墳人集団と比較するのである。そして現実の集団に最も近い仮想集団の混血率をみればよい。 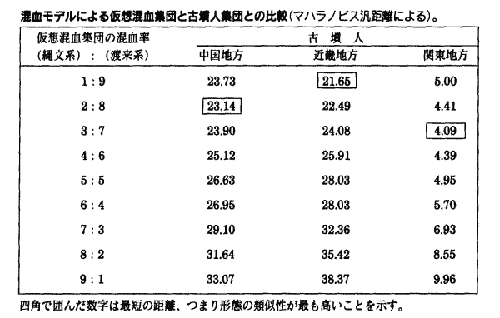 上の表は、このようなシミュレーションの結果を示したものである。これをみると、西日本全体、中国、近畿の古墳集団は、それぞれ混血率二対八、および一対九の仮想混血集団に最も近い。つまりこれらの古墳人は、縄文系二または一、渡来系八または九という割合で混血したと考えられる。これに対して関東の古墳集団では混血率がやや低く、縄文系三に対して渡来系七の割合で混血したと推定される。 これらの結果は、人口増加モデルで増加率を〇・二パーセントないし〇・三パーセントとした時の計算によく一致する。したがって二つの全く異なるモデルによって、ほぼ一致した結果が得られたということになる。 このほか、例えば国際日本文化研究センターの尾本恵市教授が計算した遺伝子の割合からみると、現代日本人(本土人)では東南アジア系(縄文系)と北アジア系(渡来系)の割合がほぼ二対八になるという。さらに東京都老人総合研究所の鈴木隆雄部長は、弥生時代に入ってきたと思われる結核の罹患率からみて、大量の渡来者を想定しなければその後の人口維持や、まして急激な人口増加は考えられないとしている。 いずれにしても、弥生時代以後に日本に入ってきた渡来音数は、今まで想像されていたよりはるかに多く、土着の縄文系集団に与えた影響はきわめて強かったと考えざるをえない。「渡来人の影響は無視できる程度」といっていたかつての説は、日本人単一民族説の文脈で考えられた先入観に過ぎなかったともいえるだろう。  世界一寒い所にいたのであるから、それは当然である。胴体は長いが手足が短いのでカッコウが悪い。上着はMやLでもズボンのサイズはSである、それでも長すぎる(国際サイズならいかに足が短いかがよくわかる)。 寒いところは体が大きくなる、縄文人よりも背が高い。顔がのっぺらで凹凸がなく体毛が少ない。目が細く一重瞼。ほお骨が飛び出している、冷たい外気を暖めるために上あごの骨が大きくなって、左右にエラが出てさらに上下にも大きくなり顔が馬面になる。前後にも大きくなり、前歯が鼻先より先に出たりする。縄文人は丸顔、渡来人は馬面である。 熱いよりも寒い方が体に合っているように感じられる。だいたい隣の人や自分を見てみれば、こうした寒冷地の特徴がある。これらはみな寒冷適応である。 もともと猿は熱帯の生き物であり、しかも温暖な日本に悠久の昔から住んでいたのなら、こんな体に極端に進化する必要がないはずのものである。われわれは温暖のこの地に住む者としてはどうやらかなり変わった体つきをしている。どうも古くからの日本人ではなさそうである。インベーダーの子孫かも知れないと思う。 丸顔の馬面の人はどうか。そんなのがいるのかと思われるかも知れないが、お父さんが馬面でお母さんが丸顔だとこんな子が生まれる。どう見ても馬面だし、どう見ても丸顔なのである。自然の産み出すものは不思議な事があるものである。同居できないものが同居している。馬は丸顔といったハナシがあるそうだが、それかも知れない。日本人はだいたいがこんな感じの顔をしていることになる。渡来系の血の方が多いから、ちょっと馬面系の丸顔。鏡に己が顔を写しトクとご覧あれ。 上の写真は丹後町の古代の里資料館に展示してある縄文人(左)と弥生人(右)。この展示はもう一つよくわからないが、少し違うのだと言いたいのだろうか。縄文人が古来からの日本人。弥生人というのが渡来人らしい、新しい日本人である。その両者の混血児がわれわれだといわれる。混血の割合は西高東低で日本海に面する丹後あたりだと9割は渡来系でなかろうか。  日本人の祖先の一方は縄文人であるが、彼らは東南アジア系で、ふるさとはそのあたり、スンダランドと呼ばれる現在は海没しているが、氷河期にはそこは陸地であった。このあたりでなかろうかと言われる。ここが日本人の一方のふるさとである。そういえば何となく顔立ちが似ているように思われる。 さてもう一方のふるさとは、渡来系弥生人の故郷であるが、そこはどこなのだろう。 渡来系弥生人の系統すでに述べたように、縄文人が東南アジア系、現代の本土人が北アジア系の集団と同じグループに分類されるナゾに直面した私は、それを解くカギが弥生人に隠されているのではないかと考え始めた。 まず注目したのは、「彼らの本当の故郷はどこか?」という問題だった。前記のように、金関は中国の中南部をその候補としてあげた。しかし土井ケ浜や三津永田のデータをよく検討すると、むしろ中国北部の集団に近い点もある。そこで私は比較のため、まずアジア大陸のさまざまな集団の頭骨計測値を集め、これらを数量分類学の方法で比較した。 統計学的分析の結果とくに注目される点は、土井ケ浜人がシベリアやモンゴルの集団と現代日本人(本土人)とのほぼ中間に位置していること、また土井ケ浜人が予想以上に北アジアの集団に近いことである(図7)。この結果からみると、渡来系弥生人の祖先はやはり北アジアの極寒の地ということになりそうに思える。 そこで私はさらに集団の数を増し、また生物学的距離ばかりでなく、因子分析、主成分分析、判別分析などの統計モデルを使って分析を続けたが、大筋としてはほとんど同じ結果となった。 また計測とは別に、頭骨の形態小変異(ある特徴の有無による個人差)の出現頻度を比較したオッセンハーグ(一九八六年)は、シベリア-近畿-関東-北海道(アイヌ)-縄文人の順に形態学的勾配がみられ、シベリアの特徴は東日本よりも西日本に強いことを証明した。さらに百々幸雄・石田肇(一九八八年)はオッセンハーグより多数の形態小変異について分析し、渡来系弥生人は北アジア人や現代日本人と同じグループに分類されるが、アイヌと縄文人は別のグループに分類されることを明らかにした。このことから、彼らは日本人の起源に関する移行説は採用できず、北アジア人が大量に渡来したことを認めざるをえないと結論した。 しかし一つ気になるのは、金関の中・南部中国説である。そこで今度は中国の新石器時代人のデータを集中的に集め、やや詳しい統計学的比較を行った。その結果は、渡来系弥生人はやはりシベリア地方の集団にもっとも近く、ついで韓国人や中国北部の新石器時代人に近い。これに対して中国南部の新石器時代人は縄文人や在来系弥生人の方に近く、渡来系弥生人とはやや遠い関係にあることがわかった。 最近、埴原恒彦(一九九四年)は頭骨計測値から計算される六種の示数によって五四集団の比較を行った。その結果も同様に、渡来系弥生人は北アジアの集団に近く、中国南部の新石器時代人や東南アジア人とは離れることを示している。 これらの分析からみると、金関の中・南部中国説にはやや無理があるように思える。もっとも当時は比較データが少なかったのだから、金関がこのように推論せざるをえなかった事情もわかる。私自身いつも感じることだが、情報不足でつらい思いをするのは研究者の宿命かもしれない。 もう一つ気にかかる点は、「渡来人の集団は男性が主体で、おそらく在来集団から妻をめとった……」という金関の言葉である。 のちの話になるが、小片丘彦や韓国の金鎮晶(一九八八年)は韓国・釜山の近くにある礼安里(エアンリ)古墳の人骨を調査した。朝鮮半島の人骨資料は日本人研究にとってとくに重要である。そこで試みに礼安里と土井ケ浜のデータを比較してみたところ、これらは実によく似ていることがわかった。とくに注目される点は、女性の頭骨がーわずか一例に過ぎないがー瓜二つといってよいほどよく似ていることである。 この結果をみると、渡来人たちは男性ばかりでなく、女性を伴って日本列島にやって来たのではないかと想像される。また土井ケ浜人と縄文人との計測値を比較しても、土井ケ浜人の女性がとくに縄文人女性に近いという結果は出てこない。 この点について中橋孝博(一九八九年)は、主成分分析や判別関数を使ってさらに詳しく分析した。その結果によると、渡来系弥生人の遺跡では縄文系と渡来系との個体が混在しており、いずれも一〇~二〇%程度が縄文系の個体となっている。またこの混在率は男性より女性の方が高いというが、その差はわずかでしかない。したがって、渡来人の男性のすべてが在来系弥生人の女性を〝現地妻″にしたとはいい切れないように思える。 土井ケ浜などの遺跡が渡来人のコロニーだったとしても、ある程度の時間がたてば在来系が混入するのはむしろ当然かもしれない。しかしそうであったとしても、渡来人たちが男性だけでやって来たとは思えない。地図を開くまでもなく、朝鮮半島と九州や山口県は一衣帯水の地であり、舟で簡単に往復できたに違いない。そうすると、男性だけの集団が日本列島に定住するようになったとは考えにくい話である。 日本人が中国人の子孫というなら認められるが、朝鮮人の子孫では絶対にないと、なぜかそう根拠もなく思い込んでおられる美しい国の人々は実に多い。上の氏の文章をもし抵抗なくここまで読めたらなら、そうしたわけのわからぬ偏見からかなり自由な人でしょう。 はたして本当にそうした多くの日本人の思い込みが本当に正しいかとうか、さらに学問は切り込んでいく。 二重構造の成立ここで人間に日を移そう。この時代に朝鮮半島南部に住み、日本列島に渡来した人々はどんな民族だったのだろうか。 当時の朝鮮半島から中国東北部にかけてはたくさんの民族が住んでいた。なかでも日本列島への渡来人と関係が深いのは、おそらく中国東北部の森林地帯に住み、やがて朝鮮半島に南下したツングース系の人々だったといわれる。また紀元前三世紀ころから、古朝鮮は西方の漠族の攻撃を受けるようになり、さらに紀元前二〇七年に秦が亡びて漠が起こったときには、中国から多くの避難民や亡命者たちが古朝鮮に入ってきた。 このような抗争はその後も絶えず、三一三年に高句寛の攻撃によって楽浪郡が消滅するまで、実に四〇〇年以上にわたって朝鮮半島は動乱に明け暮れたのである。 このような朝鮮半島の歴史から考えると、弥生時代に日本列島に渡来した集団の大部分は、もともとツングース系の人々だったということになる。また同時に、中国との動乱によって移住してきた漠族系の人もいくぶんかは混じっていたかもしれない。 弥生人についてはもう一つの問題がある。それは、金関丈夫が渡来系弥生人の影響を局地的なものと考え、鈴木尚もそれを強調している点である。 この主張を検討するためには、弥生時代ばかりでなく、その後の日本人の小進化を明らかにしなくてはならない。そこでこの間題は次章以下にゆずり、ここでは次の点だけを指摘しておこう。 すでに述べたように、渡来系弥生人は北部九州や山口県の西端地域で集中的に発見される。しかし中国地方の他の地域や近畿地方、さらには関東地方においてさえ、時として渡来系の特徴をもつ人骨が発見されることがある。たとえば奈良県の唐古・鍵遺跡で一九八五(昭和六〇)年に発見された人骨や、鈴木が「古墳人に近い」とした神奈川県三浦市の人骨は、渡来系弥生人の特徴を多分にもっているのである。 これらの証拠を考え合わせると、渡来系弥生人は意外に早く移動したように思える。しかしそれは大きな集団としてではなく、家族程度の単位だったかもしれない。またこれらの人たちが、必ずしも北部九州あたりに上陸したグループの一員だったとは限らない。もしかすると中国地方や、さらに東方の日本海沿岸に上陸した人たちだったかもしれないのである。 -以上みてきたように、人類学的に弥生時代の重要な点は、渡来系・在来系(縄文系)の二種の集団が日本列島に住むようになったことで、前者は主として北部九州を中心とする地方に、後者はその他の地方に分布していた。したがって日本列島に住む集団は、弥生時代から「二重構造」を示すようになったのである。 大陸-主として朝鮮半島-からの渡来は、縄文時代の後期または晩期から始まったという可能性が高いが、弥生時代になるとその数を増し、北部九州やその周辺で渡来人のコロニーが作られた。『魏志倭人伝』にみえる邪馬台国の場所はまだはっきりしないようだが、いずれにしても数を増した渡来人たちは小さなクニ(部族国家)を作り、「倭国乱ル」(『魏志倭人伝』)とあるように、それぞれが勢力を競いあったのではないかと思われる。 大陸からの渡来の原因としては、まず気候の冷涼化があげられる。気温が下がると北方民族の南下が起こり、種々の民族摩擦を生じ、それが中国や朝鮮半島の動乱の原因となり、さらに古代のボートピープルを生んだのではないかと想像される。 文化の面をみると、水稲耕作の技術や金属器の伝来が重要視される。しかしこのほか、渡来人がもっていた政治的能力も無視できない。彼らはもともと騎馬民族の後裔であり、大集団で行動し、ときには戦闘集団としてその威力を発揮した。それを可能にしたのが社会の指導原理としての政治力であり、クニの形成能力だった。 これに対して在来系の人々は血縁集団の単位で生活し、自給自足を原則としてグループを維持していたから、とくに強力な政治システムを必要とはしなかったであろう。 田中琢(一九九一年)の考えによると、本州における国の成立と王者の出現という歴史過程が始まったのは四世紀中ごろから後半にかけての時期だったという。その背景には渡来人たちに特有の社会システム、つまり代々にわたって大陸でつちかわれた政治的土壌が大きな力となっていたに違いない。 …つまり、丹後王国というけれども、いったい人口、食糧の特徴ですね。そういうものはどういうふうに考えているのか。それから農耕面積はどれだけであったか。こういうご質問をいただいております。これはまことに困った質問で、人口何万ぐらいであったと、はっきり言えないのですが、奈良時代以後ならかなりはっきり出ます。これは郷の数もわかりますし、一つの郷に何人ぐらい住んでいたという全国平均も出ますから、簡単に出ますこれは……。ただそれ以前は、人類学者の間でも渡来人口をどのぐらいとみるか、弥生時代を通して百万程度しかなかったであろうという説もあるけれども、少なくとも二、三百万は来たのではないかとか、そういう説が出始めておりますのであまり簡単には言えない。しかし少なくとも人口密度は太平洋岸よりも日本海域のほうがはるかに上だったろうという意見は強くなっておりますね。その程度のことしか言えませんがお許し願いたいと思います。…
耳アカの話になって、「私はタレ耳なんよ」とヨメはんが言う。「耳アカが垂れるヤツかい。それは日本人は少ないよ。たぶん10パーセントくらいだったと思うけど、それは古い縄文人なんだ。私はカサカサ耳で、これは間違いなく渡来人。人類全体ではタレミミが多く、カサカサミミは少ないグループだから、これは出身地がすぐわかる。」 ヨメはんの話では、タレミミの場合は、耳アカがいつの間にか本人も気が付かない間に垂れて外へ出ていることがあるそうで、気をつけてないといけないのだそうである。 両者の混血児の私の息子もタレミミだそうである。カサカサ耳は劣勢遺伝だそうで、両親ともカサカサ耳でなければ、カサカサ耳の子は産まれない。混血児はタレ耳になるそうである。あと何千年もすれば日本人は全員タレミミになる。 現在カサカサ耳ということは先祖には一人の縄文人も混じっていなかったということになる。さて日本にはカサカサ耳を持つ純血種のマルマル渡来人がいかに色濃く分布しているか。見てみよう。 耳あか地図・西日本、東より乾いた人多い・高校生作成
耳あかで日本人のルーツを探れ――。耳あかには湿ったタイプと乾いたタイプがあるが、全国の高校生が協力して、日本人に多い乾いたタイプを作る遺伝子の頻度を全国調査した〃耳あか遺伝子地図〃を作成した。 古代日本人の移動経路などの解明につながる成果と期待される。 この研究は、文部科学省が全国101校を選び、理数教育を支援しているスーパーサイエンスハイスクール(SSH)のうち、32道府県42校が連携組織を作って実施。各校につき20~50人程度計771人の生徒のつめを試料として集め、長崎県立長崎西高の生徒らが長崎大の協力を得て、つめの細胞からDNAを取り出して耳あかの遺伝子を分析した。 28道府県のデータをまとめた結果、乾いた耳あかを作る遺伝子は、西日本にやや多い傾向がみられた。新川詔夫・北海道医療大学教授らの研究では、縄文時代から日本にいた人々は湿ったタイプを作る遺伝子を持ち、乾いたタイプの遺伝子は弥生時代以降に大陸から渡来した人々が持ち込んだとされており、今回の結果と合致している。来年夏には、都道府県別の完全な地図完成を目指す。データがない県については、今後もSSH以外の高校にも協力を依頼する方針だ。 都内で15日開かれた日本人類遺伝学会で発表した長崎西高の山田賢輔君は「一つの遺伝子で日本人の起源が分かるのは驚きだった」と話している。 遺伝子で異なる「耳あか」、高校生が渡来後の経路追う 2007年09月17日01時15分
耳あかにはネバネバとカサカサの2タイプがあり、特定の遺伝子の違いで決まる。この遺伝子が地域ごとにどうなっているか調べる研究を全国42高校の生徒が進めており、代表して長崎県立長崎西高校の生徒が15日、東京・新宿で開かれた日本人類遺伝学会で、これまでの結果を発表した。 研究は、文部科学省が高度な科学教育に取り組む「スーパーサイエンスハイスクール」に指定している同高の生物部が、長崎大学の協力を得て2年前に始めた。 呼びかけに応じた他のスーパーサイエンスハイスクールも参加し、各校50人の生徒・職員から指のつめを集めることを目指す。現在は入手できた分から順次、DNAを取り出して解析中だ。 カサカサタイプの起源はロシア・バイカル湖付近とされ、日本には、約2000~3000年前に渡来した人たちが広めたと考えられている。このタイプの遺伝子頻度を調べて地図に示すことで、大陸から来た人たちの移動経路がわかるのではないかと期待する。今までのところ西日本に多い傾向がみられるという。 発表した同高3年の山田賢輔さんは「たった一つの遺伝子で、何千年も前の歴史がわかることに驚いた」と述べた。指導にあたった新川詔夫・長崎大名誉教授は「この地図が教科書に載ることを目標に研究を完成してほしい」と話している。 耳あか遺伝子に地域差、長崎の高校生が学会発表
耳あかが湿っているか、乾燥しているかは遺伝子のタイプで決まるが、どちらの型の人が多いかは地域によって微妙に違う――。 長崎県の高校生らが、全国の高校生から集めたつめのDNA分析を基に 、長崎大と共同でこんな研究結果をまとめ、東京で開催中の日本人類遺伝学会で 15日発表した。 研究に取り組んだのは県立長崎西高3年の山田賢輔君(18)ら。 耳あかは、両親の双方から特定の変異がある耳あか遺伝子を受け継ぐと乾燥型になる。 過去の研究から、古くから日本にいた縄文人は変異がなく湿っていたとみられるが、大陸から渡来した弥生人は乾燥型だったとされ、現代の日本人は約8割が乾燥型といわれる。 山田君らは、地域による違いがあるのかを調べようと計画。 長崎西高は理数教育に重点を置く「スーパー・サイエンス・ハイスクール」の指定を文部科学省から受けており、全国のスーパー高校に協力を呼び掛けた。 これまでに28道府県の32校から計771人分の高校生のつめを集め、長崎大で遺伝子の型を分析してもらった。〔共同〕(22:42) 耳あか遺伝子に地域差 高校生が学会で発表
9月16日16時42分配信 産経新聞 耳あかが乾燥している弥生人タイプの人は西日本に多いが、地域によって微妙に異なる-。長崎県立長崎西高の生徒らが、全国の高校生から集めたつめのDNA分析をもとに、こんな研究結果をまとめ、東京都内で行われた日本人類遺伝学会で15日、研究成果を発表した。高校生が一線の研究者と同じ舞台で、学会発表を行うのは珍しい。 研究テーマは「耳あか型対立遺伝子の全国地図作製の研究」で、長崎大の研究者のアドバイスを受けて実施。日本に古代から住み、湿った耳あかを持つ縄文系日本人と、乾燥した耳あかを持つ渡来系の弥生人の国内における分布を、つめから取れるDNAで調査するという内容。 長崎西高は理数教育に重点を置く「スーパー・サイエンス・ハイスクール」(SSH)の指定を文部科学省から受けている。研究では、SSHに指定されている32道府県42校の生徒から、つめを集めた。 その結果、弥生系の乾燥型の比率は岐阜や京都、愛媛、大分など西日本地域で高かったことが判明した。ただ、三重や島根など西日本地域の一部では乾燥型の比率が低く、今回の調査で、渡来してきた弥生人の移動経路がさらに詳しく分かるのではと期待される。 同校の生徒は今後も調査を続ける考えで、「いつか『遺伝子地図』を完成させたい」「日本人のルーツについてもっと学びたい」と話していた。 【科学】耳あか研究で長崎西高生物部に学会特別賞
:2007/09/13(木) 長崎西高が特別賞 日本人類遺伝学会で研究発表 長崎市竹の久保町の長崎西高(廣田勲校長、九百五十五人)の生物部が中心になって取り組む 「全国スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の共同による耳あか型対立遺伝子の全国地図作成の研究」が、 日本人類遺伝学会の特別賞に決まった。十五日に東京で開かれる同学会の大会で、生徒たちが研究発表し、表彰される。 同校は、文部科学省が高校を対象に科学を軸にした教育を支援するSSH事業で、昨年から全国四十一の高校と 共同研究。長崎大の協力を受け、生物部員ら約二十人が実験に取り組んでいる。 耳あかは乾、湿型の二種類があり、長崎大は昨年、そのタイプを決定する遺伝子を発見。世界の大多数の民族は湿型で、 乾型は東北アジア特有。日本人は両方があり、乾型は大陸からの渡来人、湿型は元来の日本人に由来するとされる。 研究は古代日本における渡来人の移住経路の解明が目的。全国の参加校の生徒が提出したつめのDNAを分析し、 乾型遺伝子の頻度を解析。現在、二十八都道府県を調査。データを分布地図にした結果、乾型遺伝子の頻度の高い地域 が西日本に多い傾向が示された。渡来人の人骨が西日本で多く発掘されている学説を裏付けるという。 [長崎新聞](9月13日 PM1:42) 長崎西高が人類遺伝学会特別賞 耳あか遺伝子を研究
耳あか型対立遺伝子の研究に取り組む長崎西高の生徒たち=長崎市竹の久保町、長崎西高 長崎市竹の久保町の長崎西高(廣田勲校長、九百五十五人)の生物部が中心になって取り組む「全国スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の共同による耳あか型対立遺伝子の全国地図作成の研究」が、日本人類遺伝学会の特別賞に決まった。十五日に東京で開かれる同学会の大会で、生徒たちが研究発表し、表彰される。 同校は、文部科学省が高校を対象に科学を軸にした教育を支援するSSH事業で、昨年から全国四十一の高校と共同研究。長崎大の協力を受け、生物部員ら約二十人が実験に取り組んでいる。 耳あかは乾、湿型の二種類があり、長崎大は昨年、そのタイプを決定する遺伝子を発見。世界の大多数の民族は湿型で、乾型は東北アジア特有。日本人は両方があり、乾型は大陸からの渡来人、湿型は元来の日本人に由来するとされる。 研究は古代日本における渡来人の移住経路の解明が目的。全国の参加校の生徒が提出したつめのDNAを分析し、乾型遺伝子の頻度を解析。現在、二十八都道府県を調査。データを分布地図にした結果、乾型遺伝子の頻度の高い地域が西日本に多い傾向が示された。渡来人の人骨が西日本で多く発掘されている学説を裏付けるという。 学会では、山田賢輔君(18)=三年=、北嶋玲那さん(16)=二年=が会員と同じ一般演題で発表する。二人は「結果が集まって形になる研究の楽しさを知った。全国のみんなの代表として発表する」と抱負。生物部顧問の長嶋哲也教諭(48)は「地道な研究の成果。達成感があり、いろんなことに対する自信につながると思う」と話している。 耳あか:“乾湿型”分布をつめで解明 全国の高校生ら協力
毎日 耳あかがぱさぱさした「乾型」か、ネットリした「湿型」かを特定する初の遺伝子分布地図を作成するため、全国の高校生が、自らのつめを試料に取り組んでいる。乾型は東アジアに多いことが知られているが、この調査で西日本ほど乾型の割合が高い傾向がみられた。日本人の祖先の移動経路の解明に役立つと期待される。東京都内で開催中の日本人類遺伝学会で15日、中間報告された。 研究の中心となっているのは、理科教育などを重点的に行う「スーパーサイエンスハイスクール」の長崎県立長崎西高。他の高校に呼びかけ、32道府県の42校が参加した。各校の生徒や職員が匿名で提供したつめのDNAを解析した。 その結果、乾型の割合の全国平均は90%で、最も高いのが京都府の98%、低いのが栃木県の79%と分かった。割合が高いほど色が淡くなるように都道府県を濃淡表示すると、東より西の方が色が淡くなる様子が浮かび上がった。 京都府は、日本の心臓、千年のミヤコ、そここそがまるっきりの渡来人100パーセントの地。 さて一体日本とは何なのだろう。歴史学とは何だったのだろう。 しかしこの調査結果はほとんどの「歴史学者」が無視することだろう。ごくごくごくわずかの真摯な学者だけが注目することであろう。 気をおとすなよ高校生たち。日本とは今はそんな国だ。 乾型耳あか型遺伝子全国分布 長崎西高生が研究発表
長崎新聞 長崎市竹の久保町の長崎西高(廣田勲校長、九百五十七人)は、長崎大医学部の協力で、全国における乾型耳あか型遺伝子の分布地図の作製に取り組んでおり、二十四日、同市茂里町の長崎ブリックホールで、研究成果を発表した。乾型耳あか型が、古代日本における大陸からの渡来人(弥生人)の遺伝子に由来することから、その移動、移住経路を明らかにする。 人間の耳あか型は乾、湿型の二種類があり、長崎大は昨年、タイプを決定する遺伝子を発見。世界の大多数の民族は湿型で、乾型は東北アジア特有。日本人のうち、乾型は弥生人、湿型は元来の日本人(縄文人)に由来するとされる。 (中略) 長崎西高三年、生物部の山田賢輔部長(18)が研究結果を報告。今年六月までに二十八都道府県を調査し、乾型遺伝子の頻度の高い地域が九州北部から東北へと帯状に延びていることを発表。弥生人が九州北部から日本を縦断するように移動したという学説を裏付けるデータを示した。 今後、全都道府県のサンプルを解析し、結果を九月の日本人類遺伝学会で発表する予定。遺伝学と日本史の融合研究として注目されている。 一番下にアドレスが書かれている、しかしここからはまず入れません。申し訳もないが、便宜のため引かせてもらいました。
|
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『モリ地名と金属伝承』(谷有二・2000) …これを連想させる記事が二〇〇〇年一月一〇日の朝日新聞朝刊に出ていた。酒の強い人が北海道・東北・九州・沖縄に集中していることが、筑波大社会医学系の原田勝二・助教授らの調査でわかったという。現在の日本人は縄文人と弥生人の特徴を兼ね備えているが、縄文人には酒に強い体質の遺伝子形型を持つ人が多かったと考えられる。酒に弱い遺伝子型は弥生時代に海外から近畿、中部に多く移り住んだとされる北方系の弥生人によってもたらされたのではないかという。つまり、弥生系の人々が、入って来て、従来、生活していた縄文系の人々を、南北に押しやったとも考えられる。
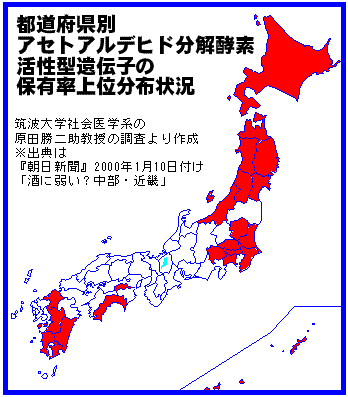 専門的には下のHPなど参考に。 いつだったか、確か青森県の青年団だったと記憶する、バス貸し切りでやって来る、さあ到着したぞ、と見ているとまずバスの床下にある荷物箱から出されるのはお酒の、一升瓶を20本くらいを1パッケージに梱包した大きな木枠である。私はこんな物は見たこともなかった。何だったか昼間の用も終わり、夜も更けかけてくると賑やかそうにやっているグループがあちこちに出来る。さて今宵はちょっとここへでももぐりこむかときめて、2、30人ばかりの見知らぬグループへ入れてもらうことにした。どうそどうぞここへ入って下さい、と席を空けてくれて、さあどうぞと、差し出してくれたのは、トンブリ茶碗、そこへお酒を溢れるばかりついでくれる。女子団員があまりいないもので男で悪いですが、さあ舞鶴の団長さん呑んで下さい。えらい所へきてしまったわい。と気が付いたがもう遅い。 2、30人が車座に座ってワイワイやっているのだが、見れば、先のドンブリが3個ばかり回っている。これは御存知だと思うが、自分が呑んで空にになったら右へ回す。回し飲み。早く呑まなければ次のトンブリが左から回ってくるという仕掛けである。特別の茶碗があることもあってそれは下に穴があいている、指で押さえていないと酒が漏れてしまう、これはどこへも置けず、飲み干す以外には手がない。 京都は渡来人だから、京都の青年団は強くはない。まず日本酒は飲まない、せいぜいビールみくらい。あまり回し飲みもしない。 彼らにタップリの酒をいただきながら、二つのことを学んだ、一つは、東北は酒に強いということ、二つは問題は共通しているということであった。京都と青森では何か別世界のように考えるかも知れないが、地域社会がかかえる問題はまったくうり二つだということ、まったくピッタリと同じ、金太郎アメのようにどこで切っても同じ顔が見えたのであった。 しかし彼らは酒飲んで乱れるようなことは決してないので、日本風に考えてはならない。渡来人末裔は特に酒には充分すぎるほどに気をつけて下さい。 篠田氏の書から引用させてもらうと-。(分布図も) …ところで私たちのなかには、ほんのわずかなお酒を飲んだだけでも真っ赤になったり、すぐに気持ちが悪くなる下戸の人もいれば、いくら飲んでも顔色一つ変わらない酒豪もいます。実はその違いは、体のなかでALDH2酵素が正常に働くか否かにかかっているのです。ALDH2をコードしている遺伝子は、ヒトの第一二番染色体にあります。この酵素の四八七番目のアミノ酸は正常型ではグルタミン酸ですが、このグルタミン酸がリジンというアミノ酸に置き換わっている人がいます。DNA配列で言うと、グルタミン酸をコードするGAAという配列の先頭のGがAに変化して、リジンをコードするAAAになっているのです。このDNAが一か所で置き換わっただけで、ALDH2はアセトアルデヒドを酢酸に分解する能力をなくしてしまいます。お酒の強い人は正常型の、弱い人はこの変異型の酵素を持っているのです。
余談ですが、この遺伝子は両親から受け継ぐのですから、正確に言うと私たちのなかには、正常型のALDH2をセットで持っている人と、一つ持つ人、まったく持たない人の三つのタイプがあることになります。そうなると、一つだけ持っている人は、お酒の強さに関して言えば、ちょうど中間の能力を持つと考えたくなりますが、事情はちょっと複雑です。実はALDH2は、この遺伝子から作られるタンパク質のユニットが四つ合体して機能していますので、そのなかに一つでも変異型を持っていると正常に働きません。ですから四ユニットすべてが正常型で構成されるのは確率的には一六分の一になってしまうのです。つまり正常型の遺伝子を一つ持っている人のアセトアルデヒド分解能力は、二つ持つ人に比べると約六%ということになります。 ここまでは、私たちが日常生活で気がつく「体質の違い」といったものが、遺伝子に基礎を置いているというお話です。一般にはこのようなことがわかってくると、ではALDH2が体内でどのように働くのか、あるいは変異型ではどうして正常の機能を失うのか、といったことを研究するのが普通です。しかし、それではこの変異型の遺伝子の分布はどうなっているのだろう、というところに注目するとテーマは俄然人類学の分野のものになります。 遺伝子の分布からヒトの移動を考える 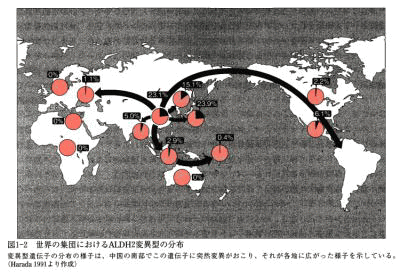 図1-2は世界の各集団におけるこの変異型遺伝子と正常型の頻度を示したものです。変異型は中国南部を中心とした極東アジアの地域に多く、そこから離れると徐々に保有率が低下していくことがわかります。ヨーロッパやアフリカの人々には、変異型の遺伝子を持つ人はほとんどいません。 周りを見わたせば、必ず何人かのお酒が飲めない人を発見できる私たちからすれば、これはずいぶん奇妙な状況です。中国に行くと北京のような北部の都市で宴席に出されるのがアルコール度数の高い蒸留酒であることが多いのに、上海などでは紹興酒のような醸造酒であることが多いのも、この遺伝子の分布に一致しているように思えます。実際、中国人と話をすると、南の人間は酒に弱いと言います。変異型遺伝子の分布状態を経験的に理解しているのでしょう。 このような分布状態は、変異型が中国南部で発生し、その後ヒトの移動にともなって周辺の地域に広がっていったと考えるとうまく説明できます。実際には、ある遺伝子の変異型について現在最大の人口を抱えているところが、単純にその変異型の発生した地域と考えるのには問題があるのですが、現時点でのデータから推定すると、この拡散のシナリオがもっとも無理がないと考えられます。さらにアメリカ大陸の先住民のなかにも若干ですがこの変異型が見られることから、その誕生の時期は、彼らがベーリング海峡をわたって新大陸に進出したと考えられている今から二万年前よりもさらに前のことだと推察されるのですが、残念ながら時期に関してはこれ以上の情報はありません。 それでは中国南部に次ぐ変異塑人口を持つ日本の分布はどうなっているのでしょう。そこには、日本人の成立に関する理論と一致する面白い現象が見て取れます。日本人全体では、正常型を二つ持つ人が五六%、一つの人が三八%、変異型二つの人が四%存在すると言われていますが、日本における分布を県別にみてみると、地域的な偏りがあることがわかります。変異型は近畿地方を中心とした日本の中部地域に多く、正常型は東北と南九州、四国の太平洋側に多いのです。後の章でくわしくふれますが、日本人の成立に関しては在来の縄文人が住む日本列島に、水田稲作を携えた渡来系弥生人が大陸からやってきて、両者が混血して現代に続く日本人が形成されたという、いわゆる二重構造論が主流です。この理論によれば、北海道や東北と沖縄や九州の南部には、縄文人の系統を引き継ぐ人たちが主に居住しており、九州北部から近幾地方には渡来系の弥生人の特徴を色濃く持つ人々が住んでいると考えられています。ここで変異型の遺伝子を日本に持ち込んだ人が渡来系の弥生人だと考えると、この遺伝子の分布が二重構造理論によく合うことがわかります。 実際に変異型遺伝子の分布が二重構造論にのっとったものであるかを検証するためには、縄文人と弥生人のALDH2遺伝子を直接解析することが必要ですから、現在の技術水準では不可能です。 しかしながら、変異型遺伝子の故郷が、水田稲作の源郷の地と重なっていることを考えると、この説はなかなか魅力的です。今後の研究の進展を待ちたいと思います。 私たちの体は祖先から受け継がれた遺伝子をもとにできあがっています。お酒に弱い人に関して言えば、少なくとも祖先の一人はこの中国南部に由来していることになります。お酒が飲めないと、ときとして宴席で肩身の狭い思いをすることがありますが、そう考えると、少なくとも自分の祖先の一人が住んでいた場所を教えてくれる、この変異型にも感謝したくなります。しかし、世界でも希なほど下戸の多い日本で、重要なことをお酒の席で決める傾向があるのはどうしてなのでしょうか。不思議な気がします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|