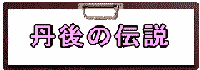丹後の伝説:23集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹後の鬼伝説 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川上名號 一名蟻巻名號 親鸞上人筆此名號の来由は元丹後国與謝郡世屋木子村護念寺山の奥に平家の残党矢野氏兄弟なるもの一族を引連れ何れの頃よりか隠れ住みしに初めの程は更に知る者なし、或時其下僕里の村居へ出て塩を買ふ其様怪しげなるに依りて里人跡を慕ひて付け行き遂に其隠れ家を窺ひ知り縣官に訴ふ。官庁より軍士を遣しこれを攻めけるに一族悉く討れ矢野氏兄弟は髻(モトドリ)を切って僧となる、兄を教念弟を祐念と號し木子村に出て庵室を結ひ住けるに、其頃村中疫癘流行し老少死亡する者数を知らず兄弟坐ながら是を見るに忍びす京師に出て親鸞上人に謁し除病の符を請ふ、上人憐んで紺紙金泥十字の名號を書して両僧に賜ふ。兄弟急ぎ木子村に帰り此名號を家々に播し戴かしむるに悪病悉く消除す、故に一村の人民名號の霊験に帰依して崇敬の餘り古より祠り来る二社の氏神を廃せんとす、或は神祠必ず廃すべからかと云者ありて論議やまず所詮氏神と名號との奇特を試みんとて神體と名號とを急流の中へ投す、此所を今に一二淵と云ふ、然るに名號は川上へ流れ上る事四五町許、諸人奇瑞あらたなるを驚き感じて是を取上げ見れば数萬の蟻名號を囲繞して相ケイ持するが如し、故に蟻巻の名號とも名づく。彼氏神の神幣は流れに従ひて竹野郡宇川の庄に至る、此地上山村 一曰上野村一曰平村 に古より四社明神あり当社の別当深識と云者彼二社の神幣の流れ寄るを見て拾ひ上げ、四社明神に合せ祭りて六社明神と號す、今の上野大明神是れなり。拾ひ上げし時は承久三年辛巳年九月朔日、即四社明神の祭日也。此名號照応元年故ありて当寺(引用者注−宮津市金屋谷・仏性寺)に納め永く什物とす。以上縁起略取 【なべ淵】(木子村より谷へ下る凡三四丁)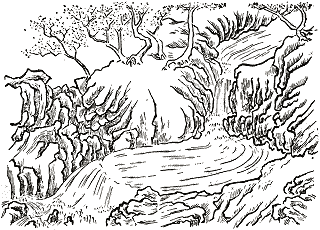 教念、祐念既に僧となりと後、疫邪流行して一村の人伝染せざるはなく死亡する者半に過ぐ、於是教念、祐念京都に上り親鸞上人へ其由を審に語り除病の妙符を請ふ、親鸞上人為に紺紙金泥十字の名號を二僧に授与す、教念、祐念兄弟是を以て丹後に帰り家々に授く、其功徳のありけるにや一郷の疫癘頓に除きぬ、故を以て一郷の人々其名號の霊験に帰依して甚是を崇敬す、元より一向専念の宗門なれば其宗意に従ひて古より祭り来る氏神の社をも毀たんとす、中には社は毀つべからずといふものあり、論議二途に分れて決しがたく遂に其霊験を試みんとて神体と名號を流に投ず(此處をなべ淵といふ岩に名號を刻して村人毎に礼拝す)然るに其名號は水流に遡り独り神体のみ流れ下る、於是諸々の人々其奇瑞に驚き恭して取揚げければ数万の蟻其名號を取巻き恰も警持するが如し、是木子駒倉の二村皆一向宗門となる所以なり、其名號を蟻巻の名號と称す、一に川上の名號ともいふ、今仏性寺に納む。竹野郡宇川の庄に元四社大明神あり、其別当深蟻といふもの二社の神体川に流る(木子駒倉の川宇川の庄に流る)を拾ひて四社大明神に合せ祭る、今上野に在る六社大明神是なり、事は承永三年九月朔日にあり即ち六社大明神の祭日なり。
一、鬼形の仮面 二 (出図)
 寺記曰。嘉暦三年十二月二月一老夫老婆を携へ偶然として寺に来り投宿を乞ふ、元より何の人なるを知らず蓋廻国の者と見へたり、宜基上人其老て寒気に向ひ猶搓行するを憐み懇に之を留る、遂に寺に留る凡四五十日其人となり皆質朴にしてよく寺の助となる、以是寺檀共に是を喜びぬ。一日上人留守を老夫に托して他に出たり、是夜は為に帰らじと約せしが、思の外早く用を済し、いまだ夜半にならざる前寺に帰る。老人夫婦は既に熟睡して会て上人の帰るを知らず、其顔色蓋人間にあらず各一角あり、上人之を見て怪むといへども敢て其熟睡を覚さず、ひそかに室に入りしが翌朝に至て二人のもの別を告げ将に去らんとす。上人強て之を留れど肯せず、其夜現せし二人の異相を自から刻み上人に捧げて去る。今ある所の鬼形の仮面是なり。毎年正月十三日は鬼面開帳の日なり、常には人に示さず、之を出せば必ず雨降るよって請雨に是を用ゆ極めて験ありといふ。 【鬼石】(海辺) 鬼石といふは石の状鬼に似たりといふにあらず、鬼の持ちたる石といふ所以なり、蓋国分寺に留りし二鬼寺より帰り去る時此石を持てなげたりとて、其手の跡今に存すと語り傳ふ。 護国山 国分寺 在與謝郡府中国分村
 真言宗古義派 成相寺末 本尊金銅薬師如来 開山行基菩薩 寺記曰。人皇四十五代聖武天皇天平十三年建立ニシテ而行基菩薩之草創也云々。 天橋記曰、凡毎州国分寺を置るゝ事天平九年なり、相傳ふ当寺本尊を盗人奪ひ去て他国に往き鎚を以て砕かんとす、其鎚の音丹後国分に帰らんと聞ゆ、盗人驚て返し奉るとなり今に鎚の痕あり。嘉歴年中宣基上人再興す上人は東寺の亮明なりと云、供養法事の図あり、勅使など有りけるよし傳へ侍る、今田間に古の伽藍柱礎の跡残れり。 … 鬼面二ツ 外ニ 上人面一 毘沙門面一 古記曰、当寺に一角の鬼の面二あり、常は秘して猥りに開かず、是を出す時は究めて風雨俄に起るなり、夏日旱天には郷民此面を仰ぎ雨乞を爲すに大雨必ず降るなり、毎年疋月十三日於二寺内一開帳す。相傳へて云ふ宣基上人の時嘉暦三年十二月二日何国ともなく老人夫婦来りて上人に仕ふ、老夫は山野に出て耕作薪水を供す老婦は内に在て食饌を供す夫婦昼夜奉事する事数月也、上人怪みて毎々其来所を問へども更に語らず。一日土人他に行かんとして留守を夫婦に属し、明日ならでは帰るまじとて出行しに、其夜夫婦の者上人の留守を安じて互に酒を酌て覚へず酔臥す、上人は思の外に用事を早く仕舞て他に一宿す可き所を其夜に直に帰り、方丈に入て見れば夫婦酔臥してあり、灯の影に見れば其顔色異形の相を顕らはす人間の顔にあらず、上人大に驚き怪むし雖彼等が日頃の労事を思て是を咎めず、翌朝に至て夫婦の者上人夜中に帰来て、酔臥の貌を見し事を恥けるにや、二人共に啼泣して暇を乞ひ永く去らん事を願ふ、上人懇に止むれども留らず、其夜顕わせし二人の異相を手自ら彫刻して上人に奉り、二人共に辞し去て行方を知らず、時に嘉暦四年正月廿三日なりとぞ、今の什物の面即ち之れなり。 鬼石 堂寺の近辺にあり、右の両鬼立去る時に擲し石なりと俗に云傳ふ、鬼の手痕とてくぼみあり。  【国分寺】村の又国分と云。本尊金銅の薬師、開山行基菩薩。凡毎州国分寺を置るる事天平九年也。相伝盗人本尊を盗み他国に行鎚を以て破らんとす。鎚音丹後国分に帰らんと聞ゆ驚て返し奉ると也。今に鎚の跡あり。嘉暦年中宣基上人再興上人は東大寺の亮明也と云。供養法事の図あり、勅使なと有けるよし伝へ侍る。今田間に伽藍の柱礎残れり、寺に鬼の面あり。霊異のこととも委く記しかたし真言宗にて成相寺に属る。
毘沙門天面 一面 字国分 国分寺
木造彩色 長三二・五センチ 平安時代(十二世紀) 宮津市指定文化財 仏教の法会の際には、仏の世界の諸菩薩、諸天に扮し、礼拝供養のために、堂塔や仏像のまわりを歩き巡る儀式である行道(ぎょうどう)が行われることがあった。そのために用いられるのが行道面である。  この面は、忿怒形で、天冠上に火炎状の文様の中に宝珠を表しており、毘沙門天と考えられ、十二天面の一部であったかと考えられる。建武元年(一三三四)の丹後国分寺再興を記録した『再興縁起』に行道の記録があり、これがその際にも用いられたことが推定される。 ヒノキの一材から彫り出され、比較的面奥の浅い形制をとっている。仏像と同様の表現をとるが、忿怒の表情は誇張を抑え、静かな威厳を保っている。また内部のモデリングに微妙な抑揚をもち、頬の膨らんだ表現には力強さがある。天冠台や髪際の彫り口は精緻で、全体に的確な彫技を示し、優れた作域を示している。 この面は、裏面に「金光明寺・修正□□」の墨書があり、これが追記であることから、ある時期から年初の除災法会である修正会(しゅじょうえ)で用いられたことが知られる。法隆寺西円堂の修二会(しゅにえ)では、三鬼が暴れているところに、毘沙門天が登場してこれらを追い払うという追儺(ついな)の例があり、これもそのような用い方をされたものであろう。 追儺面 三面 字国分 国分寺 木造彩色 長 三五・八五 二九・八 二三・五センチ 室町時代(十五世紀) 宮津市指定文化財 当寺の修正会に用いられていたと考えられる面で、男、女の鬼面と宣基上人と伝える面とからなる。鬼面二面は、一角を含んで一材(材不明)から厚手に彫出され、白で下地を作ったのち、彩色を施していたものとみられ、父鬼に一部朱色が残っている。太い鋸歯形の眉(先端欠失)や、中央に穿孔のある球形に表された目、大きな鼻の作り出す相貌には誇張が目立っているが、下唇を噛んだり、口をへしめたりした表情には諧謔味も感じられる。口の両脇に穿孔があり、可動式の牙が取り付けられていたかとも考えられるが、類例が知られずその意味は不明である。  全体に彫技に優れ、鼻から口にかけての滑らかな彫り口にはみるべきものがある。 伝宣基上人面も一材から彫り出されるが、こちらは幾分薄手である。この面も伝承にかかわらず、鬼神系の面とみられ、細まった顎や開けた口の作り出す表情には、一種の不気味さがある。鬼面と一具の制作ではないであろうが、これも追儺面と考えられる。これらの制作時期は、同類の作品との比較から室町時代かと考えられるが、全体の整った形態には古風なところがあり、国分寺復興の南北朝期にさかのぼる可能性を保留しておきたい。 寺蔵の『国分寺略縁起』の紙背の『当寺之霊宝鬼面之起』は、嘉暦三年(一三二八)十二月に宣基上人のもとに仏道修行に訪れた二人の男(実は鬼)が、その本形を現すことを請う上人に対し、残して行ったものと伝えている。 その伝説はともかく、法隆寺西円堂には、毘沙門天が三鬼を追う追儺の例があり、これらは中世に南都との関係が深かった国分寺の追儺の行事を示す遺品として貴重であろう。
鬼の牙
新宮 井上保 むかし、むかし、新宮に、どえらい力持ちがおったげな。青鬼や赤鬼の、力くらべがあって、その時に新宮の力持ちも、力くらべに行っただって。そうして、青鬼をいっぺんにやっつけただって、そうしたら赤鬼が怒って、 「今度はわしの番だ出てこい」 いうて、新宮の力持ちに飛びかかってきただって、二人連れ上になり下になり、力くらべしとったげなが、赤鬼がとうとう負けてしまったんだって。そうして、 「あんたには負けたで、何でも好きな物をもっていけ」いうたで、 「そんならお前の牙をくれ」いうて赤鬼の牙を引きぬいただって、そいて、『その牙を、村の者に見せたろう』思って、持ってもどって村の上までもどってきたら、川で婆さんが洗濯しとって、 「お前は今日、鬼と力くらべに行ったげながどうだった」いうもんだで、 「そりゃ、鬼よりわしの方が強かった。見てくれ、これが鬼の牙だ」いうて、取ってきた鬼の牙を婆さんに見せた。そうしたら、 「ちょっと見せてくれの」いうて、手に取って見とったげなが、ちょっと、口を開けて、ガタガタッと合せて、 「ああ、よう合う」いうで、いいして見せただげなが、見るもも恐しい鬼婆になって、空高く舞い上り、奥山の方へ帰って行ったそうだが、鬼が姿をかえて、牙を取リ返しにきとっただって、それから、鬼婆ができただって、悪い婆さんはあっても、鬼爺いはおらんそうです。
木子の吉原の牛鬼が化かす
五十河 田上惣一郎 木子(宮津市)にはこんな諾がある。 木子の吉原の丸山いう田のあたりには、牛鬼という者がおって、人を化かすいうことだ。昔、あるとき内山の市さんいう者が、雪のよう降る日に、そこを通ったそうな。吹雪が、ビュウビュウ吹くので、前も後も見えんようになってしまったが、又杖いうもんをつきながら、一生懸命雪道を歩いとったら、急に道がようなった。『はてな、変だな、こんなはずはない。ひょっとしたら、自分が同じ所を、ぐるぐる回っとったかわからん』思って、又杖をそこにてんと立て、ひと歩きしてみたら、やっぱりそうだった。自今が立てた又杖の所へもどってきたそうな。 それで、『こりゃ牛鬼に化かされとった』と思って、こんどは、しっかり道を見きわめてもどったそうな。 現在はもう誰もいないのではないのかと思う。
鬼を一口
是安 吉岡 ちい あるお寺に和尚さんとお小僧さんが住んでおりました。ある日、秋のことです。お小僧さんが、 「和尚さん、栗拾いに行って来ます」と言って 袋を持ってお寺を出ました。 だんだん奥へ入って、だんだん、だんだん、奥へ入っていきますと、はるか向こうに女の子が、かわいい女の子が、橋がありまして、その橋のらんかんにもたれて おいでおいでをしているんです。お小僧さんは走ってその女の子のところへ行きますと、女の子が、 「お小僧さん、わたしのところへ来なさい。栗もたくさんあるし、遊ぼう」言うて その女の子はお小僧さんを連れて、わが家に連れてきました。すると、ずっと奥に、ずーっと奥へ行きますと、大きな大ちなお家があって そして、その庭に栗の木がいっぱいあるんです。そして栗もなっとるんです。そしてお小僧さんは喜んで 栗を袋にいっぱいもらって、帰ろうと思ったら、 「遊んでいけ」と。遊んでいけということで、その女の子と遊んとったんです。 おもちゃやら、いろんなもん出してもらって、時間のたつのも忘れて遊んでおったんですけど、ふと気がつくと、もう日暮れ近うなってるんです。 「そろそろ帰らんと和尚さんが心配するから、帰る」言いますと、お婆さんとその女の子と住んどったんです、その家に。するとその女の子と、お婆さんも出てきて、 「もっと遊んでいきなさい。ごちそうもするし」言うて とめるんです。そうするとにわか雨が降ってきて、 「困ったなあ。雨が降ってきたし、雨がやむまで遊ぼうかなあ」と言って、まあ遊んとったわけですけど、雨はやまないんです、何時間たっても。そのうち夜になってしまって、 「しかたがない。お婆さんとこで遅うなって、泊まっていきなさい」いうて言うんです。ほして、ごちそうよばれて、三人やすんだわけです。 ほして、夜なかにふと目がさめると、雨だれが、 「顔見ろ、顔見ろ」言うて、雨だれが落ちとるんです。「おかしいなあ、誰の顔見るんだろう」と思って、横に寝ている女の子とお婆さんの顔見たら、鬼だったんです。鬼の子と鬼のお婆さんと。びっくりしてしまって、その鬼も目えさまして、 「顔見たかあ」言うて、こわい顔してにらみつけるんです。 「いや、顔は見らへん。おしっこに行きたいで、おしっこにやらしてくれ」言うて。 「ばんなら逃げるといかんから、その、縄でくくってやる」言うて、縄でくくられて、そしておしっこに行ったんです。でも、どうしてその縄といたんか、縄をといて、ちょっと知恵を出して、そこらに何かないかなあ思ったら、木があったもんで 木をくくりつけて、いちもくさんにお寺へ帰っていったんです。 こちらではお婆さんが、 「まだかあ、まだかあ」言うて、あんまり長いもんだで綱をたぐりよせたら、木がひっつけてある。それで怒って 金棒持ってあとを追いかけていくんです。お小僧さんももう走って そうとう奥から走るんですで、 もう死にものぐるいて走って、ようやくお寺へ帰って、 お寺の入ロをガラガラッと開けて、 急いで戸棚の中へ隠れたんです。 そのとき和尚さんはお餅を焼いとった、いろりで。和尚さんに帰ったとも言わんと、戸棚の中へ隠れたんです。すぐあとから鬼が金棒持って入ってきて、 「おい和尚、いま小僧がここへ来た」言うたんです。そしたら和尚さんが、 「小僧はいま帰ってきたけど、あれはわしの小僧だで おまえにはただではやれん」 「そんなら、どうしたらくれる」言うたち、 「世界で一番大きなものに化けてみろ」。ほしたらその鬼が、 「よし、そんなら化けてやる」言うて、すーっと消えて、ものすごい大きな大入道ですか、そんなんに化けたんです。 「みごとだなあ」言うて和尚さんは見上げて、ほしたらまたすーっと消えて、また鬼になって。 「なかなかりっぱな化けぶりだ。もうひとつ化けてくれ、そしたら小僧をやる」言うて。ほして、てしょう(小皿)を、 「このてしょうに、しょう油に化けてくれ」 「まあ、よし、簡単なことだ」言うので また鬼はしょう油に化けたんです。お餅焼いて食べとったで、そのお餅にそのしょう油つけて食べて、鬼婆を食べた坊主いうんです。
鬼のツボ (舞鶴市小橋)
今の村の墓は、浜の小学校の裏山の浜側の砂丘によって作られた山をあがった横にあるが、昔は浜にはなかった。 源の頼光さんが四天王寺をお供に、大江山酒呑童子という鬼の大将を鬼ごろしという酒をのませて殺した。その手下の鬼があちこちに逃げたそうや、その中の九匹が逃げて逃げてこの小橋まで逃げこんだ。いかつい顔に大きな体で頭の毛がぼうぼうだった、村の娘子はもちろん村人はえらいこっちゃと大さわぎした。生かしておけば食べ殺されるかも知れぬと、村人は相談した。村の庄屋の家に招き娘たちに酌をさせ、山海の珍味を食べさせ、地酒をのませた。鬼どもは大いに食べ酒をのんだ、今までのつかれが出たのか、みんな赤い顔や青い顔してぐうぐうねてしもた、村人たちは力をあわせて竹やりや、くわ、かま、いのししとりのやりを持ち、鬼を次から次に殺した。「ぎゃー」と大きな□をあけ立ちあがるものもあった。血がとび、苦しさに肉をかき乱す鬼もあった。しかし一匹の鬼がとっとと走り浜辺の方に走っていった。村人たちは驚いて、やりやかまを持って追いかけた、酒とつかれでこの鬼も砂べでぐったりたおれてしまった。村の若い力のあるもの四、五人がそろりそろりと近ずき、竹でつついたがびくともしない、それでいのししつきのやりで体をぐさーとさした、血がくじらのしおふくようにとびあがった。鬼は立ちあがり、こっちをじっとにらみつけた、村人はびっくりして体をふせた、こわごわ顔をあげたら鬼はひざをついたまま、両手を砂浜について動かなかった。村人はかわいそうになって、鬼の霊をなぐさめるため浜に墓をつくった。この浜を「九鬼が浜」という。それから村人は自分の家の墓もここに作るようになった。 ここには鬼のツボという穴がある。 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||